チベット高地における血中酸素飽和度について
〜日本人旅行者およびチベット人の興味深い測定結果〜

長嶺胃腸科内科外科医院 長嶺 信夫
はじめに
長距離を走るマラソン選手がオリンピック前に 高地トレーニングをすることは良く知られている。
大気中の酸素含有比率は高地においても平地 と同じ21 %であるが、高地では気圧が低く、 それに比例して大気中の酸素分圧も低い。高度 5,000m では気圧は540.2 ヘクトパスカル(hPa) しかなく、空気中の酸素分圧は53 %である。 すなわち、海抜0 m での大気中酸素濃度を 100 %とすると、5,000m の高地では、平地の 約半分の酸素濃度でしかない(表1)。
表1.標高と気温・気圧・酸素分圧(理科年表平成18 年版を改変)
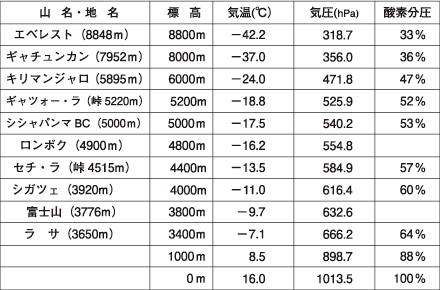
筆者はこの度、チベット高地を訪問すること ができた。その際、旅行日程の9 日目に、標高 4,900m に位置するロンボク在のホテル(絨布 寺賓館)でツアー参加者、ガイド、運転手およ び現地のホテル従業員(チベット人)、総勢17 人の血中酸素飽和度(以後、酸素飽和度と略)、 脈拍数を測定し、興味深い結果を得たので若干 の考察を加え報告する(写真1)。

写真1.4,900m の高地に建つロンボクのホテル(絨布寺賓館)。
手前の動物は登山者の荷物を運ぶヤク。
測定方法および結果
測定場所:標高4,900m に位置するロンボクのホテル・絨布寺賓館
測定日時: 2011 年5 月24 日、午後7 時前後、夕食前。
測定機器:パルスオキシメーター機器製作社・NONIN、型式・Onyx1、モデル9,500.
被験者:日本人7 人(ガイド1、ツアー客6)、チベット人9 人(ガイド2、運転手1、ホテル従業員6)、漢民族1 人(運転手)の17 人。
測定項目:酸素飽和度、脈拍数。ほかに喫煙の有無を問診した。
測定結果:測定値は表2 のとおりで、症例4、5、6 の日本人が酸素飽和度60 %代 で低値であったが、他の日本人と現 地チベット人の酸素飽和度に差はみ られなかった。また、喫煙の有無に よる差もなかった。
表2.チベット高地(4,900 m)における血中酸素飽和度・脈拍
2011 年5 月24 日ロンボクのホテル(絨布寺賓館)にて測定
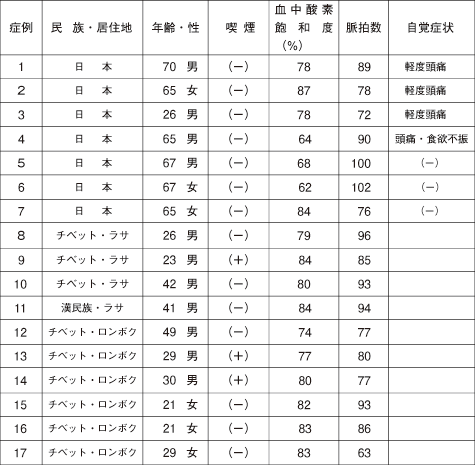
考察
今回のチベット旅行ではニンティ(林芝・標 高2,980m)から最高5,220m のギャツォー・ ラ(峠)に至る高地を12 日間の行程で旅行し、 チベット自治区内のニンティ(2,980m)、ラサ (3,650m)、オールドティンリー(4,390m)、シ ェーカル(4,300m)、ロンボク(4,900m)、シ ガツェ(3,920m)に宿泊した。
旅行日程の9 日目に今回のツアーにおける最 高高度の宿泊地であるチョモランマ・ベースキ ャンプ(5,150m)に近い標高4,900m に位置す るロンボクのホテル(絨布寺賓館)で夕食前に 17 人の酸素飽和度及び脈拍数を測定した。ま た喫煙の有無が測定結果に影響する可能性があ るため、喫煙の有無もあわせて調査した。被験 者の既往歴に関しては調査せず、機器の関係か ら末梢血の赤血球数の測定も実施しなかった。
高地においては大気中の酸素分圧が低いた め、呼吸回数を増やすとともに、体内では血中 の赤血球数を増加させることで対応していると いわれている。すなわち、高地で常時生活して いる人達は、末梢血中の赤血球数が多く、その 分、血中酸素濃度が高いと考えられている。今 回は被験者の末梢血中の赤血球数の測定はでき なかったが、酸素飽和度の測定結果は意外な数 値を示した。
まず、興味深いのは、一部を除いて、ツアー に参加した日本人と現地のガイドやホテル従業 員間で測定結果にほとんど差がみられなかった ことである。
旅行社はツアー客に事前に医師による診断書 の提出を義務付けるとともに、現地において、 健康管理上、毎日パルスオキシメーター(血中 酸素飽和度測定器)で脈拍数や酸素飽和度を測 定し、客観的に高山病の症状を判断している。
今回ツアーを企画した旅行社では、
1.酸素飽和度が69 %以下の数値になった場合
―酸素の供給を開始。
2.酸素飽和度が64 %以下の数値になった場合
―即座に最寄の病院にて入院治療、酸素吸
入。ということになっていた。
今回のツアー客は旅行開始時7 人であった が、バスに乗車してニンティ(標高2,980m) からセチ・ラ(峠、4,515m)、ミラ・ラ(峠、 5,020m)をへてラサ(3,650m)に到着した日 から、60 代の女性客1 人が、食欲不振、不眠、 疲労感を訴え、翌日(日程5 日目)の観光日程 を中止した。日程6 日目には旅行を継続するこ とができず、ラサから成都、北京経由で日本に 帰還した。ラサ到着時点での女性の酸素飽和度 は80 %、脈拍数は84 回で、測定結果自体はそ れほど悪い数値ではなかったが、当日までの強 行日程や睡眠不足で体調をこわしたものと思わ れた。
残りの6 人のツアー客は旅行を続行したので あるが、症例4 ( 6 5 歳、男性) はラサ (3,650m)からカンパ・ラ(峠、4,749m〕、カ ロ・ラ(峠、5 , 0 4 5 m )、ツォー・ラ(峠、 4,500m)、ギャツォー・ラ(峠、5,220m)を 経由してオールドティンリー(4,390m)ヘ向 かう途中から、頭痛を訴えた。酸素飽和度は 67 %を示し、移動中の4 輪駆動車の中で、酸 素吸入を実施した。同症例は日程9 日目のロン ボクでも酸素飽和度は64 %の低値を示し、脈 拍数90 回で激しい頭痛(ガンガン)および食 欲不振を訴え、酸素吸入を実施している。
症例6(67 歳、女性)は5 月24 日のロンボク(高度4,900m)での夕食前の測定では酸素 飽和度62 %、脈拍数102 回で無症状であった が、翌朝25 日午前7 時には酸素飽和度は57 % に低下し、脈拍数103 回の数値で食欲不振と不 眠を訴えていた。
症例2(65 歳、女性)はロンボクで軽度の頭 痛を訴え、就寝時に横になると、激しい咳を訴 えた。上半身を高くした状態で寝かせると症状 は軽減した。同症例は軽度の睡眠時無呼吸症候 群の疾患があるため、高山病予防を兼ね、日程 4 日目のラサ滞在中から、炭酸脱水酵素抑制剤 のダイアモックス(250mg)1 錠を毎日服用さ せた。5 月24 日朝の酸素飽和度は90 %、脈拍 数は98 回、午後7 時の酸素飽和度87 %、脈拍 数78 回で、客観的データは全症例中で最も良 好であった。薬剤の効果で換気量が増大し、血 中酸素量が増加したことが考えられた。症例2 以外にダイアモックスを服用したものはいない。
症例3 ( 2 6 歳) は日本人登山ガイドで 6,000m 級の登山経験者である。
ところで、高山病初期の症状として、頭痛 (頭重感)、不眠、食欲不振、吐き気、放屁、手 足のむくみ、胸部圧迫感などがあり、中期の症 状として、頭痛(鉄の輪をはめて締め付けられ るような痛み―症例4)、発熱、下痢、尿量減 少、足の浮腫、嘔吐、咳(夜、横になると咳が とまらない―症例2)、脈拍増加、意欲減退な どがある。
重症の高山病になると、肺水腫や脳浮腫を生 じ生命の危険がある。ちなみに、今年も私たち がチベットに入国する直前の5 月12 日、第1 回 植村直己冒険賞を受賞した登山家の尾崎隆さん (58 歳)がエベレスト頂上直下で高山病のため 遭難死している。
ロンボクにおける測定時にホテルのチベット 人従業員(症例13)に1 回目の測定後ホテル の周りを小走り(これ以上の運動は無理)した あと、再度測定したところ、酸素飽和度が 77 %から65 %に落ち、脈拍数が80 から130 に増加した。チベット人でも現地での行動は息 苦しいとのことであった。
ホテルは3 階建てで、ツアー客の寝室は1 階 にあり、食堂やテラス、トイレは2 階にあった ので、宿泊人は階段を上がるとき、ゆっくり、 休みながら上がっていた。また、2 階のテラス から見るチョモランマ(エベレスト)の眺望は 格別であったので、シャッターチャンスを逃が さないため、急いでカメラの望遠レンズや三脚 を部屋に取りに行く際、息せき切って階段の上 り下りをしたものである(写真2)。

写真2.ロンボクのホテルから見たチョモランマ(エベレスト)。
現地のチベット人従業員の酸素飽和度を測定 する時、予想したのは「チベット人の酸素飽和 度が平地で生活してきた日本人ツアー客の酸素 飽和度よりかなり高く、少なくても80 %代後 半では」ということであった。しかし予想に反 して、チベット人で酸素飽和度が85 %を越す 人はなく、一部の症例を除いて両者に差がみら れなかったことに驚いている。
また、同じ環境下で酸素飽和度を測定した日 本人で、症例1(70 歳、筆者、酸素飽和度 78 %)や症例2(65 歳、同87 %)、症例7(65 歳、同78 %)が高値を示したのに対し、特記 すべき疾患を有していない同年代の症例4(65 歳、同64 %)、症例5(67 歳、同68 %)、症例 6(67 歳、同62 %)が低値を示した。同じ年 代層でありながら、血中酸素飽和度にこのよう な差がでたことに驚いている。この数値をどう 解釈すべきかわからない。今回は測定結果を公 表することに徹し、読者に今後の研究資料を提 供することにしたい。
おわりに
チベット高地を旅行し、標高4,900m のホテ ルで現地ホテル従業員を含む17 人の血中酸素 飽和度および脈拍数を測定した。予想に反し て、日本人ツアー客と現地チベット人では測定 値に大きな差はみられなかった。
広報委員会からのコメント
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター
當銘 正彦
長嶺信夫先生には度々、本誌へ興味尽きない投稿を頂き、感謝に堪えません。今回もチベットへの 訪問を単なる旅行記としてではなく、山岳地に居住する人体の低酸素症に対する医学的興味を追求さ れています。日本人観光客7 人とチベット在住10 人において、年齢、性別、喫煙の有無、血中酸素飽 和度、脈拍数、そして自覚症等々で丁寧な比較検討をされています。そして酸素飽和度の低下と自覚 症状の有無が必ずしも相関しないこと、また日本人観光客とチベット住人との間に、さ程の酸素飽和 度の違いが見られないことに気づかれ、素朴な驚きを示されています。
臨床家としての長嶺先生の着眼点の鋭さに感服するところです。ところが酸素飽和度に関しては、 “両者間で相当に違うだろう”という問題設定には疑問を感じました。酸素密度の低い高地に居住す るヒトの環境適応は、赤血球の数を増やして単位血液当たりの酸素含有量を増大させる方向で発揮さ れるものであり、それ自体は酸素飽和度には反映されない数値だからです。Hb と酸素の結合度合い を示す酸素飽和度を決定するのはあくまでも環境の酸素分圧であり、これは観光客も現地人も等しい 条件にいる訳ですから、各固体の有する酸素取り込み能力(A-aDO2)に大差がなければ、赤血球の 数とは関係なく同等の数値を示してくる筈です。従って、長嶺先生の調査された結果は当然の帰結で あり、特に驚くことではないものと考え、コメントさせていただきました。とは言え、実際に日本人 観光客の酸素飽和度の平均値を算出すると74.4 %で、現地住民の平均値80.6 %と比較すると明らか な低め傾向を示しています。しかしこれについては、ヒトの正常動脈血酸素分圧は経年的に約0.3 torr/年づつ低下して行きますので、日本人観光客の平均年齢が60.7 才で、現地住人は31.1 才である ことを加味しますと、充分に納得できる結果であると考えます。
以上、長嶺先生の貴重なフィールドワークを拝見して、呼吸生理学的な観点より、コメントを書か せて頂きました。