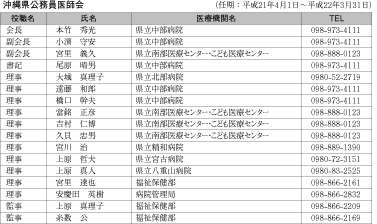琉球大学医学部脳神経外科学分野教授 石内 勝吾 先生

| P R O F I L E | |
|---|---|
| 昭和60年3 月 |
群馬大学医学部医学科卒業 |
| 昭和60年4 月 | 群馬大学医学部脳神経外科入局(主任 大江千広教授) |
| 平成2 年7 月 | 群馬大学医学部病理第一研究生(主任 中里洋一教授) |
| 平成10 年1 月 | 医学博士「中枢性神経細胞腫の分化能に関する研究」 |
| 平成11年1 月 | 科学技術振興事業団「脳を知る」(CREST)研究員(〜平成15 年まで) 研究課題「グリアとグリアの腫瘍におけるグルタミン酸受容体の解析」 |
| 平成11年7 月 | 群馬大学医学部脳神経外科助手 |
| 平成14年9 月 | 群馬大学医学部脳神経外科講師 群馬大学医学部脳神経外科外来医長 |
| 平成16年10月 | 21 世紀COE「加速器テクノロジーによる医学生物学研究」 分担研究員 研究 課題「神経膠芽腫の浸潤性増殖に対する重粒子線の作用機序に関する研究」 |
| 平成18年10月 | 21 世紀COE「加速器テクノロジーによる医学生物学研究」事業推進担当者 研究課題「癌の浸潤性増殖機構に対する重粒子線の作用機序に関する研究」 |
| 平成19年1 月 | 厚生労働省重粒子線がん治療中枢神経腫瘍臨床研究班員 |
| 平成19年7 月 |
独立法人放射線医学総合研究所 重粒 子線治療ネットワーク会議 計画部会 中枢神経分科会委員 |
| 平成21年6 月1 日 | 琉球大学医学部脳神経外科教授 受賞歴 |
| 平成4 年 | 時実利彦記念脳研究基金 |
| 平成14年 | 第1 回群馬大学付属病院GCP (Good Clinical Practice)賞 |
| 平成15年 | 第11 回日本脳腫瘍学会「星野賞」受賞 専門分野 |
| 専門分野 脳腫瘍の外科的治療、化学療法、分子標的療法、腫瘍放射線生物学 癌のシグナル伝達路の解析 |
|
医療情報の共有化や治療の 選定など患者さんにとって 最適な治療ができる環境を 会員の皆さんと維持したい と考えています。
Q1.この度は、琉球大学医学部脳神経外科分 野教授就任おめでとうございます。沖縄に 赴任されてのご感想をお聞かせいただけま すでしょうか。
初代六川二郎教授(1975 〜 1997)、2 代吉 井與志彦教授(1997 〜 2009)の後を受けて 2009 年6 月に着任しました。
「脳科学を基盤とする脳神経外科学の発展」 を目標に教室運営を行う所存です。
皆様どうぞよろしくお願い申し上げます。
赴任後、慌しく1 ヶ月が過ぎました。自分が 働いている研究室や病棟また琉球大学医学部 附属病院の手術室からもエメラルドグリーンの 海が見えることに最近気づきました。沖縄の海 は関東の海のように潮のにおいがしないので判 りませんでした。前任地群馬県の前橋は海なし 県であり、沖縄の豊かな自然に魅力を感じてい ます。
琉球王国という独自の文化の栄えた土地であ り、その精神の本質を学びたいと思います。と りわけ高齢者の前向きな姿勢には驚かされまし た。沖縄に来て週2 例ずつ関連病院から紹介さ れた患者さんの脳腫瘍の手術を行っています。 中には80 歳をすぎた方もいて脳外科の手術の 適応年齢は、本土の高齢者より10 〜 15 歳高い のではないでしょうか。
最近の神経科学の研究で、ヒトの脳細胞は一生涯に渡り神経新生を行い老後も進化すること が判明しましたが、沖縄の高齢者を見るとまさ にそれを証明していると思われる方がいて大変 興味深いと感じています。
Q2.本県では脳神経外科医が不足し、特に離 島地域においては深刻な問題となっていま す。このような状況のなかで琉球大学脳神 経外科の果たす役割は大きいと思いますが、 離島医療、県下の脳神経外科医療への抱負 をお聞かせ下さい。
琉球大学医学部脳神経外科は地域医療への貢 献と地域医療との調和を目指します。亜熱帯・ 島嶼環境などその地理的特性から、離島医療は 本県の大きな問題であると認識しています。現 在山口大学、福岡大学など他県の協力を得るこ とで離島の脳神経外科医療が成り立っているこ とを認識しなければなりません。背景には医師 の偏在化などの社会的問題もあり解決は容易で はありませんが、沖縄県の考え、琉球大学とし ての立場、地域基幹病院の意向を踏まえながら 離島医療問題の本質を明確にすることから解決 策を探りたいと考えます。
沖縄県医師会医学会脳神経外科会の中に四金 会という脳神経外科医の学術集会があります。 県下の脳外科医が年4 回集まるわけで会員の皆 さんと知り合いになり協力して沖縄県の地域医 療の向上に貢献したいと思います。車で30 分 もかからない地域で皆さん活動していますの で、顔見知りとなり、調和を崩さず融和しなが ら医療を推進したいと思います。先日県医師会 館で世話人会が開かれました。公式な学術集会 とは別に、2 ヶ月に一度、大学と基幹病院で交 互に症例検討会を行うことが決まりました。普 段から島中の脳外科医が知り合い、情報交換を 密にすることで医療情報の共有化や治療の選定 など患者さんにとって最適な治療ができる環境 を会員の皆さんと維持したいと考えています。
また、忙しい日常診療に埋没しないで島の中 で治療したことを論文として記載し世界に発信 する習慣を作ることも重要と思います。
Q3.脳神経外科の領域は変性疾患治療からイ ンターベンションまで革新的な治療法開発 が行われています。このため、脳神経外科 に興味を持つ若い医師も多いと思います。 これらの医師を脳外科に取り込む良いアイ ディアがございましたらお聞かせ下さい。
脳神経外科学の主要疾患は脳腫瘍と脳血管障 害です。
脳腫瘍の中でとりわけ悪性の神経膠芽腫は現 行の治療では5 年生存を得られず革新的な治療 法の開発が望まれています。重粒子線や分子標 的療法などの臨床治験が今後活発になると思わ れます。神経膠芽腫は「がんの中のがん」とい われる疾患ですので、この病気に対する治療法 の開発はすべてのがん治療に大きなインパクト を与えるはずです。我々はこの課題を解決すべ く研究中です。
脳血管障害は適応に応じて手術と非観血的な 血管内治療などが行われています。とりわけ血管 内治療は患者さんへの負担が少なく、治療道具 の開発が目覚しく今後の発展に期待が持てます。
変性疾患を含む神経疾患では、パーキンソン 病や痴呆症の原因であるアルツマイマー病をは じめ、多発性硬化症、アミロイド血管炎などが 重要です。これ等の疾患は本質的には脳機能を 正常に保つための神経再生・新生機構の異常で あり、正常な脳の発生、老化の仕組みの解明が その根本治療の確立に必要です。
脳神経外科は神経科学の一分野でありとりわ け脳科学の魅力を若者に伝えることで脳神経外 科学の発展に貢献するような人材が出てくるこ とを期待しています。
Q4.県医師会に対するご意見、ご要望があり ましたらお聞かせください。
広報活動、学術集会への支援など県医師会の 果たす役割は多大かと思います。
大学の方も積極的に講演活動、啓蒙活動を行 う準備がありますので、どうか今後ともよろし くお願い申しあげます。
Q5.先生の座右の銘、日頃の健康法やご趣味 などをお聞かせ下さい。
脚下照顧
御実家が禅寺の高校の担任から教わりまし た。禅寺では門のところに脚下照顧とかかれた 札が掲げられているそうです。
常に自分自身を見つめなおし不備な面を整備 し将来に備えて勉強することが大切と考えてい ます。また、自分の判断に客観性があるか、自 分のことより周りのことを優先して考えている かをいつも自問しております。
日ごろの健康法
特別なことは行っていませんが、タバコはす わず、機会飲酒で普段は飲みません。野菜、果 物、魚を食べ肉類を多食しない。お茶や水分を 十分摂取し、成人病を予防しています。
趣味は読書。吾を忘れてもめり込む物語性の 強いものもよく、Nature やScience などの国 際誌の最新論文を読むのも面白い。最近は飛行 機に乗ることが多くなり、邪魔されずに読書で きる最善の時間となっています。
この度は、お忙しい中インタビューにご回答 いただき、誠に有難うございました。
インタービューアー:広報委員 鈴木幹男
お知らせ
8 月号に掲載しました報告「各地区医師会役員決定」の沖縄県公務員医師会役員欄(33 ページ)に 誤りがありましたので、お詫び申しあげ、下記のとおり改めて掲載いたします。