��19�ꌧ��t������J�u���@��炮���N���������Ȃ�
�`���f�Ă���[���イ�`

�����@�ʈ�@�C

����7 ��25 ���i�y�j�A�p�V�t�B�b�N�z�e���� ��ɂ����āA�W�L���J�u�����J�Òv���܂����B
���ꌧ�̓��茒�f��f����26 ���ƌ����ė� ���͂���܂��A���{������{���N�f���̍� ���������ݎ�f���𗎂Ƃ������ߑ��ΓI�Ȕ� �r������ƑS��23 �ʂƂȂ�܂��B��f���S�� ���[�X�g�̃��b�e���͕ԏ�ł��܂���������� �ی��҂̐ϋɓI�Ȏ�f�����̌Ăт����ƁA���� ����t��������Ă���W���_��ɂ���Ďs�� �������茒�f�Ɏ��g�݂₷�����𐮂��Ă� ��Ƃ��������傫�ȗv�����Ǝv���܂��B��N ��ꂩ��t�܂ŁA���茒�f�̏W���_��Ɋւ��� �͉��x���Ïʂɏ��グ�܂����B���ꌧ��t�� �����ǂƈꏏ�ɁA���ꂱ���݂̃L���L���ɂނ� ���Ȓ�����c�����x���蔲���A���̓x�Ɂu�� �̏W���_����ǂ̂悤�Ȍ`�ł���邱�Ƃ��ł� �����X�͋����Ă����I�v�Ɨ�܂������� ���Ƃ��W���_��܂ő������܂����B
��������ē��茒�f�Ɋւ��Ă̌������J �u�����J�Â��鎖���ł��A���S���ʂł����B�� ���ɗǎ��ȓ��茒�f����邽�߂ɗl�X�ȗ� ��́A�����̐l����ςȓw�͂����Ă��܂��B�� ���̊W�@�ւ����茒�f�Ƃ����v���W�F�N�g�� ����ꓬ���Ȃ���ꏏ�Ɋ��������Ă��܂��B�� ���ʖڂ��A�Ǝv���Ă���̈ꓥ��A������ ���߂Ȃ��C�����̑�����w�т܂����B
�������J�u���ɏW�܂��������̌��������Ȃ� ��v���܂����B�ΊO�L��̂��̗l�Ȋ�������� �����̑��ɔ��z�̍��{������ׂ����ƁB���ꌧ ��t��͌����Ɣ��ɕ��ނƂ����p��������� ���Ƃ��Č������J�u���͂���ׂ����Ǝv���� �����B
�u���̏��^
�{���ɂ����錒�N�̌���
�`���f��f�ւ̈���́A���Ȃ��̌��N�ւ̑傫�Ȉ���`

���ꌧ�����ی�����Ð��x���v����
���@���J
���a52 �N�@������w�ی��w������
���a52 �N�@�����֓���
���a59 �N�@�����ی����Ζ�
�ȍ~�A�R�U�A�ΐ�ی����A�{���ŋΖ�
����19 �N�@�����ی�����Ð��x���v����
1 �����̌��N�̌���ɂ���
�{���ɂ����錧���̌��N�Ɋ֘A����́A �ǂ̂悤�ɂȂ��Ă���̂ł��傤�B
�����N���������Ȃ�Ƃ��Čւ�邱�ƁA�i �j ���́A���ʁA�ւ�Ȃ�����
- �E�����̕��ώ��������{��i�������A�L�ї� �͑S����������Ă���B�j
- �E�q�ǂ��̏o���������{��i�������A��̏d ���o�����͔��ɍ����B�j
- �E���炢�̖����~�}��Ò̐����\�z ����Ă��邱��
���ۑ�ƂȂ��Ă��邱��
- �E�j���̕��ώ������S��26 �ʁi����17 �N�� 25 �ʁj�ɓ]��
- �E�j���Ƃ��얞��^�{���b�N�V���h���[�� �Y���҂����ɑ����B
- �E���A�a�̎��S���́A�j���Ƃ��S���ꍂ���A ���A�a�t�ǂŐl�H���͂Ɉڍs����l����� �ɑ����B
- �E���f��f�������ɒႭ�A�܂��A���f�ň� ��l���o�Ă���Ë@�ւɍs���Ȃ��l���S�� �ꑽ���B
��L�̗�́A��Ȃ��̂ł����A�{���́A���N �ۑ�̌��ʂ̌���Ƃ��āA�V�l��Ô�̒��œ� �@�������S���ꍂ�����Ƃ������J�������i19 �N�Łj�Ŏw�E����Ă��܂��B���A����܂ň�� �̐����Ǝ�ȏ��o�Ȃ���A����҂�� �l�̕��X����J���d�ˑ���グ�Ă����u���ǂ� ��̓��v�́A�u���N���������Ȃ�v�̃u�����h ���őS���ɔ��M����A�ό�����������͂��� �l�X�ȕ���ɍv�����Ă��Ă���܂��B
�������Ȃ���A����́A���N�ۑ肪�܂��܂� �����Ă���ł���A������l�ЂƂ肪���N �̕ێ����i��}��Ȃ���A�q�⑷�ɂ��u���N�� �������Ȃ�v�̃u�����h���ێ��E�p�����Ă��� ���Ƃ����߂��Ă���܂��B
�Q�@����A��X�����ׂ����Ƃ͉��ł��傤�B
�{���̒j���̕��ώ������傫�ȉۑ�ƂȂ��� ���܂����A���͒j����65 �Έȏ�̕��ϗ]���́A �����S����ʂ�ۂ��Ă���A40 �őS��20 �ʂ� �}���ɒቺ���Ă��邱�Ƃ��傫�Ȗ��Ȃ̂ł��B
�܂��A���^�{���b�N�V���h���[���̊Y���҂� �\���Q�̎҂��j���Ƃ��������Ƃ́A�����K���a �̔��ǃ��X�N���������Ƃ������Ă���܂��B
���̂��Ƃ���A�����K���a�ǂ��銄���� ����40 ��ȏ�̑s�N�����̕��X�ɑ��ē��� ���f�A���f���̎�f�������}�邱�Ƃ��d �v�ȑ�ɂȂ�܂��B
����A���N�ۑ肪�����Ă��钆�ŁA�{���ɂ� ���Ă͍���������b�����Łu���N���Ǝv���Ă� ��B�v�l�����{�ꑽ���Ƃ���Ă��܂��B����́A �a�C�������Ȃ��Ă��u���炢�����Ȃ���� �ɂ��A���ł������Ă����B�v�Ǝv���Ă� ��l�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���A���Â̕��u���ɂ����@���銄������ ���A���̂��Ƃ���t��Ō�t���̉��d�J���ɔ� �Ԃ������Ă��܂��B
�u���N���������Ȃ���ێ��E�p�����邽�߂Ɂv�A�܂��A�u���炢�����Ȃ���Ò̐� ���ێ����邽�߁v�ɂ��A������l�ЂƂ肪���N �P��̌��f���āA�g�̃`�F�b�N���s���l ���ɉ������H������^���K�������邱�ƁA�� �Â��K�v�ȏꍇ�́A�d�x�ȏ�ԂɂȂ�Ȃ��悤 �ɑ����Ɏ�f���邱�Ƃ��d�v�ł��B
���̂悤�Ȃ��Ƃ܂��A��t��A���ۘA�� ��A���A�s�����ł́A�A�g��[�߂Ȃ���A���� �ւ̕��y�[���𐄐i���Ă���܂��B�܂��A���� �̑����̈�Ë@�ւ����茒�f���̋��͋@�ւƂ� ��A�u�����������̂ǂ��ł����f������ �̐��Â���v���\�z���Ă��܂����B
���f�ɂ́A�W�c���f�ƌʌ��f������܂��B
�W�c���f�́A�s�������e�n�斈�ɔN�ɂP�`�Q ��̕p�x�Ŏ��{���Ă���܂��B
�W�c���f�́A���茒�f�A�������f�A���f ���������̌��f���������Ɏ��郁���b �g������܂��B�i�s�����ɂ���ē����Ɏ� ��錒�f�̎�ނ��Ⴂ�܂��B�j
�܂��A�W�c���f�̓��ɓs���������Ȃ��� �́A�n��̓��茒�f���̋��͈�Ë@�ւŌʌ� �f�����܂��B
�ʌ��f�̈�Ë@�ւł́A�����̐f�Î��ԓ��ł�����ł��A����ɑ҂����Ԃ��Z���� ���郁���b�g������܂��B
�ʌ��f�̈�Ë@�ւ́A�����Ɂu���茒�f �ł��܂��v��u�������N�f���ł��܂��v���� �u���f�ł��܂��v���̃X�e�b�J�[���\��� �Ă��܂��̂ŁA�m�F���܂��傤�B
�u������l�ЂƂ肪�v�u����̐l�ɂ������� �āv�݂�ȂŌ��f���I�A���̂��ƂŎq�⑷�ɂ� �u���N���������Ȃ�v�̌ւ�A�ǂ����ێ��p�� ���܂��傤�I
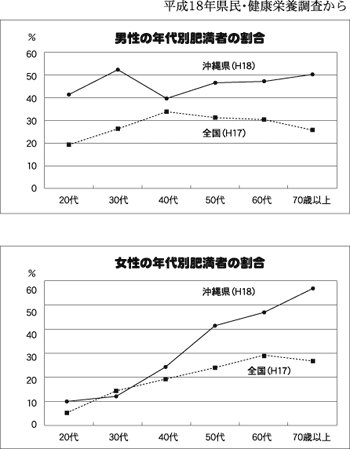
�u���N�v�̔��f�����Ȃ��͉��ł��Ă��܂����H
�`���ꌧ�̓��茒�f�́A�����t���a�̔��f���ł��܂��`

���ꌧ�������N�ی��c�̘A����Ɖے��⍲
�V���@����
���a63 �N�@�����암�a�@�Ζ�
����2 �N�@�����������
����5 �N�@���ꌧ���ۘA����Ζ�
�P�D���ꌧ�̓���
�S�����牫��̈ʒu�����Ă݂܂��傤�B
�������K���a�ɊW����f�[�^
�S�N���ɍs���鍑�������̌��ʂ����Ƃɂ� ���A�s���{���ʈ��H�X���i��ƒ����j�A�ƌv�� ���Ƃ������v�f�[�^�Ō���ƁA
- �E���H�X���̑S�����v�ŁA�n���o�[�K�[�X �܁A�o�[�E�r�A�K�[�f�����S����1 ��
- �E�������A�����͑S���ꏭ�Ȃ�
- �E�����߁A�x�[�R���A�ɂ�̏���ʂ� �S���ꑽ���A���̏���͑�3 ��
�����f
�E��N����n�܂������茒�f�̎�f���� 26 ���őS��23 �ʁi�S�����ρj
�@�������A���͌��f��f��65 ���ƍ����ڕW���f���Ă��܂��B�� �W���B���ł��Ȃ��ƁA �������Ҏx������ 10%���Z����܂��B�� �̌���Ŏ��Z���Ă� ��ƁA���ꌧ�S�̂� 19 ���~�Ƃ�������� ������[�߂Ȃ��Ƃ��� �Ȃ��Ȃ�܂��B
���̂����͒N���� ���̂ł��傤���H�c �c�����ł��B�F���� �̕ی����ɂȂ�܂��B
����Ô�Ɖ���
�E�Ȃ�ƂP�l������V�l��Ô100 ���~���Ă��܂��܂� ���B���ی����n�܂������́A78 ���~�� �����̂ŁA22 ���~�������Ă��܂��B
�E������S����R�ʂŁA��Ô�Ɖ���� �����Z����ƁA�P�l����130 ���~�������� �Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B
�����͊��Ґ�
�E���ꌧ�͓��͂��Ă�������A���� 3,886 ���őS���ő�T�ʂł��B
�@������25 �N�O��700 ���قǂł������A�N�X�E���オ��ɐL�тĂ���ł��B
����Â̂������
�E�O����f�����S���ʼn��ʂŁA���@��f���� �����B���i�͕a�@�ւ����炸�A�d�lj����� �a�@�֍s���̂ł��傤���H
�@�܂��A65 �Έȉ��̎Ⴍ���ĖS���Ȃ�� ���A�S���Œj��1 �ʁA����5 �ʂŁA������ ��̉҂��肪�S���Ȃ��Ă��܂��B
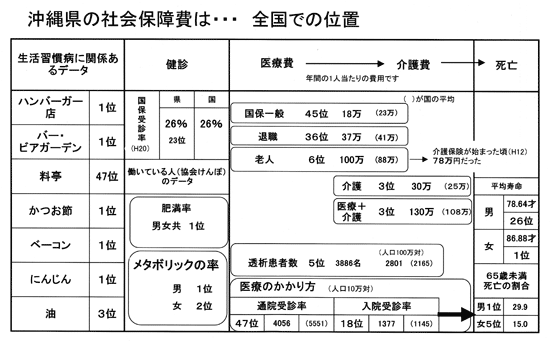
�Q�D���ꌧ�̓��茒�f
��N����n�܂�܂������茒�f�A�����m�ł��傤���H��f�����茳�ɓ͂��Ă��܂����H
�����K���a�́A�قƂ�ǂ̏ꍇ�A���o�Ǐ� �Ȃ��܂ܐi�s���܂��B���o�Ǐo���Ƃ��� �́A�a�C�����Ȃ�i�s���Ă���ł��B
���茒�f�́A�u�����̍��̐g�̂̏�Ԃ�m��v ��Ȍ����ł��B�܂����茒�f�̌������ڂ́A �S������(�W����)����Ă��܂����A���ꌧ�̓� �茒�f�́A��L�Ō��Ă���������Ԃ܂� �āA�����t���a�����f�ł��錟���i�����N���A �`�j���A�����A�_�A�A�����j���ڂ���ꍞ�݂� �����B
�t���̔\�͂��݂邽�߂ɁA��Ȏw�W�ƂȂ� �uGFR�i�t���̔\�́j�v�Ƃ������t������܂��B ����o���ĉ������B�Ƒ��ɂ��ߏ��̕��ɂ����� �ďグ�ĉ������B
�t���̔\�͂�100%����GFR100�A60%���� �Ȃ���GFR60 �ɂȂ�܂��B
���Ȃ��̐t���̔\��(GFR)�͂ǂ̒i�K�ł��� �����H���茒�f����A���f�ł��܂��B
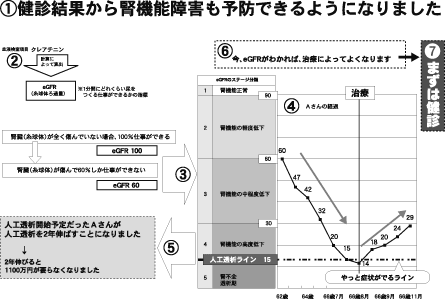
���茒�f�Ő������P

�ߔe�s��t����K���a���f�Z���^�[����
�茴�@�i�C
���a62 �N�@�H�c��w��w����w�ȑ��Ɓ@������w��w���@�]�_�o�O��
����8 �N�@�f���}�[�N�E�R�y���n�[�Q����w���w
����13 �N�@�ߔe�s��t��@�����K���a���f�Z���^�[�@������
����21 �N�@�ߔe�s��t��@�����K���a���f�Z���^�[�@����
�E���{�]�_�o�O�Ȋw�����
�E���{��t��F��Y�ƈ�
�E���{�l�ԃh�b�N�w�����
����20 �N����S���Ŏn�܂������茒�f�́A �����K���a�����������邽�߂Ɍ��N�f�f�ƕی� �w�����Z�b�g�ɂȂ��Ă���A�����K���̉��P�� �ŏI�S�[���ł��B�����K���a�Ƃ́A�D�܂����Ȃ��H�K���E�^���K���E�����K���E�i���K���E �����Ȃǂ̐����K���������Ŕ��ǂ��A�i�W���� �a�C�̌Q���w���A���������Ƃ��Đg�߂ȍ����� �ǁA�����ُ�ǁA���A�a�Ȃǂ���\�I�Ȃ��̂� ���Ă������܂��B�����̎��a�́A�d�ǂɂ� ��Ȃ��Ɩw�ǎ��o����Ȃ����߁A�\�h�I�ȑ� ���d�v�ł��B�\�h�I�ȑ�Ƃ͂܂��͐������P �ŁA��̓I�ɂ͌����A�ԐH�����炷�A�ΐH���� �Ȃ��A������ۂ�߂��Ȃ��A�����������A�E �H�[�L���O�Ȃnjy���^�����n�߂�A�։������s ����A�x�̓������A�������[���ɂƂ�A�Ȃ� ���������܂��B
�������Ȃ���A���N�J��Ԃ���Ă��������K ����ς���Ƃ������Ƃ͗e�ՂȂ��Ƃł͂���� ����B���̗��R�́A��ɂ͐����K���a���C�� ����ɂ������߁A���������P���悤�Ƃ����ӎ� ���N���Ȃ����Ƃ�����܂��B�����ɑ���ӎ� �̕ω��̒i�K�ɂ�5 �i�K����A���S���A�S ���A�������A���s���A�ێ����ɕ�����܂����A ���S�̏�Ԃɂ���l�ɂ����琶�����P�𑣂� �Ă��Ȃ��Ȃ����܂������܂���B���S���ɂ� �������Ă܂��S�������Ă��炤���ƁA �S���ɂ͕ω��@�t���邱�ƁA�������ɂ� ��̓I�������v��E�x�����邱�ƁA���s���E�� �����ɂ͎����I�Ȋ�����������ė�܂����Ƃ� �NJe�i�K�ɉ������x�����K�v�ƂȂ�܂��B���R �̓�ڂɁA����������ɐl�X�̐����K���� ���e�����y�ڂ��Ă��邱�Ƃ��������܂��B�� ���A�Z�������Ď��ԓI�Ȃ�Ƃ肪�Ȃ��ꍇ ��A�t�ɕ֗��Ȑ������������邱�Ƃ́A�^ ���s���A�ߐH�A�A���R�[���̑����A�����s���� �ǂ̍D�܂����Ȃ��K���ɂȂ���܂��B
����ł͂��̂悤�ȏŁA�������P���ӎ� ���邽�߂ɂ͂ǂ�����Ηǂ��̂ł��傤���B�� ��ɂ͓��茒�f��傢�ɗ��p���邱�Ƃł��B�� �茒�f����f���A���̌��ʂ������̐����K���� �֘A�t���ď[���ɗ������邱�Ƃ��������P�ɍ� ���傫�Ȃ��������ƂȂ�܂��B�K�v�Ȑl�ɂ͕� ���t�A�h�{�m�A�^���Ö@�m�ɂ���̓I�Ȑ��� ���P�̃A�h�o�C�X���Ȃ���邽�߁A���s���E�� �����̎����I�ȕω������҂ł��܂��B�u���f�Ă���[����[�v�̂��߂́A�܂����N�f �f��ʂ��Č��N�ɊS�������A���ȊǗ��\�͂� �������Ă����̂��ł��ߓ��ł���Ǝv���܂��B
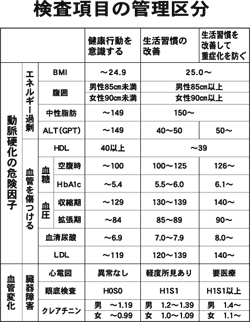
���������E�������Â̂��߂́u���f�v

�����a�@�@�\����a�@�@��
�ΐ�@���i
���a49 �N�@���R��w��w����
���{�O�Ȋw��F�����E�w����
���{�����O�Ȋw��F��w����
���{�ċz��O�Ȋw��F��w����
���{���ÔF���@�\�b�苳���
������w��w���Տ�����
�͂��߂�
�u����v�͋����Ƃ����C���[�W���������̂� ���B�������A�����͈Ⴂ�܂��B�ǂ̂悤�ȕa�C�� ���A�����̕a�C�͎���܂��B�i�s�����a�C���� �����͎̂����ł��B��w�́A�f�f�Z�p�����ËZ �p�������ɐi�����Ă���܂��B�u���f�ƌ��f�v�� ���A����i�K�ł̕a�C�̔����ɓw�߂܂��傤�B
���f�ƌ��f
�u���f�v�́A����̕a�C�����A�����Ɏ� �Â��s�����Ƃ��ړI�ł��B���f��A�X�x�X �g���f�A���A�a���f�Ȃǂ�����܂��B
�u���f�v�́A���N��Ԃ��m�F���A���N��̖� �肪�Ȃ��A�Љ��������ɍs���邩�ǂ����� ���f���܂��B�w�Z���f��A�E�����f�Ȃǂ����� �܂��B
����N��ɒB���Ă���́A���f�Ƃ����� ����ɂ�錒�f�i���N�`�F�b�N�j�̗��҂��K �v�ł��B
���f�̊�{�I�ȏ���
�i�P�j���̂���ɂȂ�l�������A�܂����S�̏d
��Ȍ����ł��邱��
�@���f�̑Ώێ҂͌��N�Ȑl�ł��B�p�x��
���Ȃ�����͌��f�̑Ώۂɂ͂Ȃ�܂���B
�i�Q�j���f�ŁA���̂���ɂ�鎀�S���m���Ɍ�
�����邱��
�@���������E�������Âɂ�莀�S����\��
�����������邱�Ƃ��ړI�ł�
�i�R�j���f���s���������@�����邱��
�@�����̐l��ΏۂƂ��āA�����Ŋȕւɍs���������@�����邱�ƁB
�i�S�j���������S�ł��邱��
�@���N�Ȑl�ɍs�������ł���A�����ǂ̉\�����Ⴂ�����@���K�v�ł��B
�i�T�j���f�̐��x����������
�@����\���̍����i�K�ŁA���m�Ɍ����邱�Ƃ̂ł��錟���@���K���Ă���B
�i�U�j�������ꂽ����̎��Ö@�����邱��
�@���ʓI�Ȏ��Ö@���m�����ꂽ���ΏۂƂȂ�܂��B
�i�V�j�����I�ɂ݂āA���f���郁���b�g���f�����b�g�����邱��
��L�̏����ŁA���炩�Ƀ����b�g���傫�� �Ɣ��f�����ƌ��f�ɓK���Ă���B
�Ȋw�I�����̂���ƍl�����錟�f���@
�i�P�j�݂���E�E�E�E�E�E�݂w����
�i�Q�j�q�{��E�E�E�E�זE�f
�i�R�j������E�E�E�E�E�E���G�f�ƃ}�����O�� �t�B�[���p
�i�S�j�x����E�E�E�E�E�E�����w���A�i���҂� �\႕��p
�i�T�j�咰����E�E�E�E�E���������A�咰�� ����
�i�U�j�̂���E�E�E�E�E�E�̉��E�B���X�E�L�� ���A����
���������ɂ��k����p
�i�P�j�݂���E�E�E�E�E�E���������S���؏�
�i�Q�j�q�{��E�E�E�E�~���؏�
�i�R�j������E�E�E�E�E�E���[�����Ö@
�i�S�j�x����E�E�E�E�E�E���o���������؏��A���؏�
�i�T�j�咰����E�E�E�E�E���������؏�
- �u����v�Ɋւ���펯�̃E�\
- �~�ǏȂ��̂Ő����͕K�v�Ȃ�
- �~����҂́u����v�͐i�s���x��
- �~��p�E���ː��E�R���܂͋���
- �~�Ɖu�Ö@�Łu����v������
- �~���N�A���f���Ă���̂ň��S
�ނ���
�Ǐ�̖��������ɕa�C�i����j�������܂� �傤�B
���������āA�u���f�v�Ɓu���f�v�ł� ���Ē����̌b�݂���ɓ���܂��傤�B
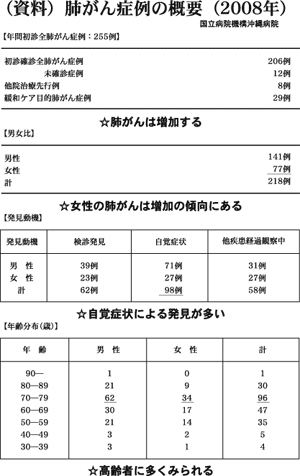
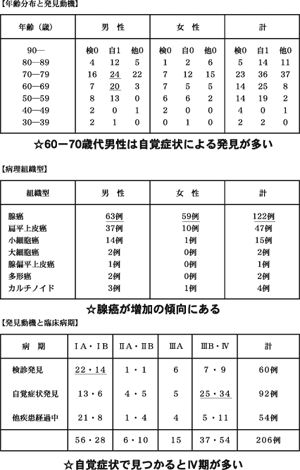
���k��`�������J�u�����I���ā`
���ʈ�����@�F�l����ꂳ�܂ł����B
�݂Ȃ���A�{���͎v���̏�͌��܂����ł� �傤���B
���������@15 ���̍u���ł͌��E������� �Ɗ����܂������A�{������@�I�ȏł��邱 �Ƃ�A���Ƃ����m��Ȃ����Ƃ������ɓ`���� �ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�Ⴆ�Γ��A�a�̖��Ȃǂ͏��߂Ēm�����l�� �����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�����͕��ώ��������{��Ƃ����Ă��܂� ���A���ۂɂ͉���̏��������A�a�ɂ�鎀�S�� �����{�ꍂ�����Ƃ�A���^�{�̖��A�V�l��� ����@��ɕ��Ă��邱�ƂȂǁA�ǂ�ǂ�m �炵�߂Ă����K�v������Ǝv���Ă���܂��B
���V�����@���x�̘b�ⓝ�v�f�[�^�͎s������ �o�����ςȂ��Ȃ̂ŁA�Z���Ɏ��m����̂ɔ�� �ɗǂ��@������Ǝv���܂��B
���茴�搶�@�������`�������������Ƃ́A�� ���K���a�Ƃ����͎̂��ȊǗ����L�[���[�h�ł� ��Ƃ������Ƃł��B���̎��ȊǗ��������邽�� �ɂ́A�����̐g�̂��ǂ��Ȃ��Ă���̂��A���� ���ǂ��Ȃ��Ă��邩�A���f���ǂ��Ȃ��Ă���� ���A���̌��f�̓��e�̂ǂ����݂Ă���̂��A�� ���ƌ����̊F����ɗ������Ă��������A������ ���ȊǗ��\�͂������ƕt���Ă����Ȃ������ �ł��Ȃ������̂��̂ł���Ƃ������Ƃ�`���� �������̂ł����A���ꂪ���܂��`��������킩 ��܂���B
���ΐ�搶�@�����͏펯�Ǝv���Ă��邱�� �ɂ��āA���͂����ł͖����Ƃ������Ƃ�b�� ���������̂ŁA����͏[���ɓ`���邱�Ƃ��o�� ���Ǝv���Ă���܂��B
�Ǐ����̂Ő������Ȃ������Ƃ����� ���ň�ۂɎc���Ă���̂��A�Ō�t����Ȃ�� ���B���̉e�������狎�N���������̂ł͂Ȃ��� �ƕ�������A�m���ɂ����������N�Ɏ��M������ ���̂Ő������Ȃ������Ƃ�����ł��ˁB�� ��1 �N�ŇV���ɂȂ��Ă��܂��Ă��ċC��t���� ���Ƃ����Ȃ��Ɗ����Ă���܂��B
���ʈ�����@�����͌������ی������牜���[ �q�����ɂ����z�������Ă���܂����A�������� �����ł��傤���B
����������

�������߂ĎQ������ �Ă��������āA�l�I �ɂ����ɕ��ɂȂ� �܂����B�Ƃ����̂́A ���������d�������Ă� �Ȃ���A��{�I�Ȓm�� ���Ȃ�������ł��ˁB �{���̍u���ł́A���ɂƂ��Ă��V���������ł� ���B����Ƃ����������@�������������āA�n ���ɍL�������ɓ`���Ă������Ƃ����Ȃ���� ���Ȃ��Ǝv���Ă���܂��B��葽���̌����ɉ� �ꌧ�̎��Ԃ⌒�f�̕K�v�������m����K�v���� ��܂����A�}�X�R�~��ʂ��đi���邱�Ƃ��ł� ��Ǝv���܂��B
�܂��A���ꌧ�͎��������N�ł���Ǝv���Ă� ��l����ԑ����Ƃ����b��A������J���[�J ���[�U��������킩��悤�ɁA�l�����ĂȂ��� ���Ƃ����v���͗ǂ����Ƃł͂���܂����A��� �ł͔얞�Ȃǂ̂����ȕ��Q���o�Ă��܂��B�� �̈ӎ����ǂ�����ĕς��Ă�����������̉ۑ� �ƌ����܂��B
����ƁA�����̐E���Ō��f�ŗv�����ƂȂ�� �����\�����ł��ˁB���̐E������f�����邱 �Ƃ��A�Ǘ��҂̋Ɩ��Ȃ̂ł����A���ꂪ�Ȃ��� ����f�Ɍ��т��Ȃ���ł��B�����̒��ł��� ��ɑ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���A��������̐E ��Ƃ݂āA�����ɑ���Ɩ������Ȃ���A���� �ی����𒆐S�Ɍ����E���̌��N�Ǘ����s���Č� �f�ɂ����т��Ă��������Ǝv���Ă��܂��B
���ʈ�����@�㌴�搶�ǂ��ł��傤���B
���㌴���ہE���N���i�ے�

�����̌��N�Â���� �w�j�i���N���i�v��j �Ƃ��āA����1 4 �N�� �u���N�����Ȃ�2 0 1 0�v �����肵�܂������A26 �ʃV���b�N�̌㌩���� �����ĉ��P���Ă��Ȃ� ���������������߁A�u���N�����Ȃ�21�v�̉��� �ł��V���ɍ�N3 ���ɍ��肳��܂����B
���̒��ɂ́A9 ��������ꍞ��ł����āA�� �̒��ɂ́u1 �����̑̏d����v��A�u����� �������ɓK�x�ȉ^���v�Ƃ������ڂ������Ă��� ���B���̑�7 ��ނ̏����ȃ��[�t���b�g����� �Ă��܂��B�茴�搶���{������������Ă����A �d�������܂�ɂ��������ă����^���w���X�ɂ� �e������Ƃ��������e���܂܂�Ă��܂��B
���̂悤�Ȕ}�̂��g���|�s�����[�V���� �A�v���[�`���s���Ă������Ƃ���ł����A�� �茒�f�ł́A������x�n�C���X�N�A�v���[�`�� �I�яo�����l�ɂǂ��ւ���Ă��������d�v�ł��B
���B�́A���N��4 �����獑�ۂƓ�������A�� �ہE���N���i�ۂƂȂ�܂������A��Ð��x���v ���Ă����Č��N�Â���Ɠ��茒�f�����܂��A �����āA�ł��邾����Â���\�h�ł��錒�N�� ����ւ����Ă��������Ǝv���Ă��܂��B
�䂪�ۂł́A���W�I�̑�������Ă��܂��B�m ����6 �K�ɕ����������ł����A�K�i����艺 �肵�Ă���܂��B���̏�ʂɉ��x���o���킵 �āA�m�����{�C�Ŏ��g��ł��邱�Ƃ������� ������̂ł�����A���B�������Ƃ��Ė{�C�Ō� ���̂��߂ɂ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ɗ����Ă��܂��B
���ʈ�����@����^�C���X�̏㌴������ �ł��傤���B
���㌴�ҏW�ǒ�

�����͌��f���e�[�} �Ƃ������ƂŁA����� �ł̐S�̕a��얞�Ȃ� �ɂ���ׂē��肪�ǂ� ���ƐS�z���Ă��܂��� ���A���ی��Ă݂�Ɛ� �����܂��Ă܂����̂ŁA��͂茧��t��̌��J �u���͂������茧���ɒ蒅���Ă��邱�Ƃ����� �Ă���܂��B
�^�C���X�Ђł́A35 �Έȏ�͂��ׂĐl�ԃh �b�N����悤�ɂȂ��Ă��܂����A�Ȃ� �l�������ł��ˁB�قƂ�ǂ��Ǘ��E�Ȃ�ł� ���A�����̊Ō�t�����w���Ń��[���𑗂��Ď� ����悤�Ɍ����Ă͂��܂����A����ł��� ����B���낢�뒮���Ă݂�ƁA�Ȃ����R�� 2 �����āA�u�ߐM�v�������ł����A��ԑ��� �̂��u�|���v�Ƃ������R����Ȃ�ł��B�� �����ł����ςȂ��ƂɂȂ邩��|���Ă����� ���Ƃ������ƂȂ�ł��ˁB���̕��X��� �s������悤�ɂ͂��Ă��܂����A���X����_ ������܂��ˁB
���ꂩ��A���f�����ȊǗ��̂��������ɂȂ� �Ƃ������b������܂������A�����̌��N�Â��� �̂��������ɂȂ�Ƃ������Ƃ����m��A �傫�Ȑ��ʂɂȂ邵�A�����Q�����ꂽ������� ���݂ŁA�u�܂��͎Ă݂��炢����v�Ƃ��� �ӂ��ɍL�܂�A�����ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B ���R��X�͎��ʂœW�J���Ă��������Ǝv���܂� ���A�����ƌy���C�����ŎĂ������ƂƁA�� ��ł��Ȃ��猒�f�͑傫�ȈӖ������Ƃ����� �Ƃ�`���Ă��������Ǝv���܂��B
���������@�s�������ő����������āA�ꐶ ����������Ă���̂ɂȂ���f����������� ���̂��킩��Ȃ��B�ꐶ��������Ă��邱�Ƃ��Z ���ɓ`����Ă��Ȃ��\��������܂����A���� �����Ȃ̂����ׂȂ��Ƃ����Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B
���̂悤�Ȃ��Ƃ���A���͍��N�����̒��� �����悤���ƌv�悵�Ă��܂��B���܂܂ŁA���� ������b�������Őu���Ă͂��܂����A���{�I�� �ł��Ȃ����A�������Ă��������ƍl���� ���܂��B
���㌴���ہE���N���i�ے��@�ʈ�搶���O�� ������Ă��܂������A�����̖�ȂǑ�R�o���� ��ƁA���҂���{�l�͈��݂����Ȃ��Ǝv���Ă� �邵�A�ׂ�̂������Ɂu���܂Ȃ��ق����� ����v�ƌ�����ƃh�N�^�[�������̐l�̌� �����Ƃ�M���Ă��܂��B�t�Ɍ����A�h�N�^�[�����e���͂����邨�����Ɍ����݂Łu�s ���ėǂ������A�s���ׂ�����v�ƌ��킹��悤 �ȓ������������Ă��������Ǝv���܂��B����� �́A�������p���[�͂����������ł���ˁB
���ʈ�����@�u�ꏏ�Ɍ��f�������܂��傤�v �Ƃ����čs���̂����C�}�[���ł���ˁB���C�} �[�����͂��Ⴆ�āA�悯���Ȃ��߉������̂� �͂Ȃ��A�{���̈Ӗ��ł̃��C�}�[�������s���� �ق����Ǝv���܂��B
���㌴���ہE���N���i�ے��@���͈��܂���� �Ȃ����ǁA��܂ł͘A��Ă�����̂��g���� ���h�̖����ł���ˁB
���ʈ�����@�������i�������ē��茒 �f�̎�f�����グ�Ă��������Ǝv���܂��B�{�� �͂��肪�Ƃ��������܂����B
�������z���������������X�̒�����A�����̕��ɃC���^�r���[�������Ă��������܂����̂ŁA���� �����牺�L�̂Ƃ���3 ���̕��̂��ӌ��E�����z���f�ڒv���܂��B
�{��̍L���ɂ����͂��������܂��āA���ɗL��������܂����B
�C���^�r���[1�j�F
�@�@�{���̍u����ɎQ������Ă̊��z�����������������B
�@�@�܂��A����̓��퐶���łǂ̂悤�Ȏ��ɋC�����悤�Ǝv���܂����B
�C���^�r���[2�j�F
�@�@��t��ւ̗v�]�����������������B
�i45 �E�j���E���c�Ɓj
1�j���߂ču����ɎQ�����܂����B�b�̓��e�͂ƂĂ��킩��Ղ������ł��B�Q���҂��݂�ƍ���҂����������N�̐l�� ���Ȃ��悤�Ɏv���܂����B
2�j�����ƎႢ�l���Q���ł���悤�ɂ��Ăق����B���f���Ăق����N��̎Q���҂����Ȃ��A�����Ɗ撣���Ăق��� �ł��B
�i71 �E�����j
1�j�����2 ��ڂ̎Q���ɂȂ�܂��B�p�l���ł̐����͂킩��₷���A��ώQ�l�ɂȂ�܂����B
2�j������A���̂悤�Ɍ��J�u�����p�����Ă������������B
�i70 �E�����j
���N�Œ�������ڕW�ɂ��Ă��܂��B�l�ԃh�b�N�̌��ʂ̐��l�ɕq���ŁA�O�N�x�Ƃ�����r���Ă��܂��B���������� �S�����Ă��܂��B
2�j�V����ʂ��Ēm��܂����B����������Ă������������Ǝv���܂��B
