��107�ꌧ��t���w���

�����@�c���@���F

��N6 ����12 ���̔N2 ��s���Ă��錧�� �w��ł��邪�A����͐V��ٗ����L�O���T�̊J �ÂƂ̌��ˍ����ŁA12 ���̒�Ⴊ1 ���ɂ��ꍞ �ޕϑ��I�Ȃ������ŁA1 ��17�A18 ���̗����� �s��ꂽ�B���͂Ƃ�����A�V��قōs���ŏ��� ����w��ł���B
����17 ���́A��w��ɐ旧���đ�64 �� ����t���ᑍ��s���A����19 �N�x�̉� ���⌧��t��E��v�̎��x���Z������ ��A��t��ق̈ړ]�ɔ����芼�̕ύX�������F ���ꂽ�B
�悸�͋ʏ�M����w���ɂ��J��錾�� �s���A����������y�m���搶�����w�� �̈��A�������A�{��̗��j�I�Ȍo�܂̊T�� �ƍ����I�Ӌ`�ɂ��ĐG����A�`���ɑ����� ����ۓI�Șb�ł������B
����̓��ʍu���́A�u���{��t��̖����ƍL ���ɂ��āv�Ƒ肵�ē��{��t���� �|���N�O�����b���ꂽ�B�u���͑傫��2 �̍\ ������Ȃ�A�O���͓���̍L�͂Ő��͓I�ȍL�� �������Љ��A������}�X�R�~�ɑ��A���� �̍l������@���ɐ��������z���邩�̓w�͂��� �p����������ƂȂ����B�㔼�͓���̈�Ð��� �ɂ��Ă̊T���ŁA���Ô����t�s���� �痈��u��Õ���v�Ƃ����[���Ȏ��Ԃ̔F�� ���A�ŋ߂ł͐��E�ɂ����X�ɐZ�����ė��Ă��� �����ɐG����A����̉��v�̓W�]�ɂ��Ă� ���҂��q�ׂ�ꂽ�B
�����ň㎖���J�҂̕\����������s���A3 �l�̉��ꌧ�m���\����39 �l�̉��ꌧ��t� �\���̕��X�����X�Ɠo�d����A����₩�Ȓ��� �������ȕ��͋C�Ői�߂�ꂽ�B�Ō�͎�҂� ��\���āA���N�̒����n���t��Ƃ��Ă̌� �тŌ��m���܂���ꂽ����i�搶�̎ӎ��Œ��߂�����ꂽ�B
�����Ō�̃v���O�����́A�Տ����C���e�[�} �Ƃ����V���|�W�E���ł���B�u���ꌧ�ɂ����� �����Տ����C�������i���j���C����ѐ��U ����܂ł̘A�g�ɂ��āv�Ƒ肵�āA��w��� ���ʏ�M���搶�ƈ�w���c���B�搶�̎i ��Ői�s�����B
�V���|�W�X�g�͌����a�@���牓���a�Y�搶�� �ˌ����ݎ}�搶�A�Q���O���[�v���璇�����N�� ���Ɣ�Ð���搶�A�����ė��傩��剮�S��� ����5 �l���o�d���Ċ���s�����B�l�X�� �_�_����Տ����C�ɓZ��镪�͂���ׂ��� �����A����̍ő�̊S���́A����Ő������� �i��ł���Տ����C�̎��т��A������������� �邽�߂ɂ͌����a�@�Q�A�Q���O���[�v�A RyuMIC ��3 �̗Տ����C�v���W�F�N�g������ �������A���ݏ����������ɓ��ꂽ�𗬂��s �����Ƃɂ���āA��芈������������������� �Ă���̂ł͂Ȃ����A���ׂ̈ɂ͌���t��̖� �����d�v�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����A�Ƃ̘_�c�ł� ��B��蕪�����ڂɒl����̂́A�����ł��� ����̗�����Â��A���̃}�O�l�b�g�z�X�s�^�� ���x����g���āA����Տ����C�̈�ɑg�ݓ� ���\���ɂ��ẮA���Ɍ����a�@�Q�ł͋� �̓I�ȃv���O�������v�悳��Ă��邪�A�Q���� RyuMIC �ɂ��Ă��\���ɎQ�����͂̉\���� ���邱�Ƃ���������A�����3 �Q�̋����s���� �傫�Ȋ��҂��q�����Ƃ��o�����B
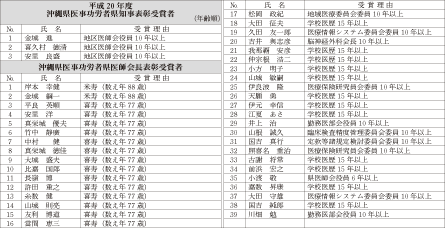
����A

��107�ꌧ��t���w���
��y�@�m��
��107 �ꌧ��t���w���̊J�Âɂ� ����A�ꌾ�����A��\���グ�܂��B
�n�߂ɁA����Җ]�̉��ꌧ��t��ق���N�v �H���A����12 ��14 ���ɗ����L�O�s�������s�� ��A�{����107 ���w���V��قŊJ�Â� ���܂����ƂS��肨�c�ѐ\���グ�܂��B
���A���̂悤�ȋL�O���ׂ��V��قł̈�w�� ����J�Âɓ���A���i��y�j�ɉh�������w�� �����̋@���^���ĉ������܂����{��M�Y ��A�ʏ�M����w����͂��߉���̊F�l�� �������\���グ�鎟��ł���܂��B
�Ȃ݂܂��Ɖ�ق̌��݂́A��Í��Y����� �ɑk�蕽��9 �N3 ���ɊJ�Â��ꂽ��c����ʼn� �ٌ��݂̕K�v��������A��É����̌� ���ψ�����ٌ��݂̕K�v����F�߂铚�\�� �o����A��ٌ��݂Ɍ����ĉs�ӌ������i�߂�� �Ă��܂����B���̌�A��ق̌��ݍ\�z�͔�É� �����玄�A�X�ɋ{���ւƎO��ɘj���E �̏d�v�ȔC���Ƃ��Ĉ����p����A���ʁA����� ��t����̋��_�ƂȂ�V��قň�w���J �Âł��邱�Ƃɑ��[���h�ӂ�\���鎟��ł� ��܂��B
����w��̗��j��U��Ԃ��Ă݂܂��ƁA 1903 �N�i����36 �N�j�̉��ꌧ���ݗ��Ɠ��� �ɍs��ꂽ�w�p���\�������w��̑O�g�ƂȂ� �Ă���A1951 �N�i���a26 �N�j�ɂ͉���Q���� �w��ݗ�����A��1 ��Q����w����J�� ���Ă���܂��B
�܂��A1952 �N�i���a27 �N�j�ɔ������ꂽ�� ���w��G����1 ��1 �����A���݂ł͖{������ ���ꂽ��47 ��3 ���ƂȂ�A��w��̍\����20 ���ȉ�Ƒ���ɘj��A����w��{���̈�w�E ��p�̔��W�E����ɉʂ��������́A���ɑ���� ���̂�����ƔF�����Ă���Ƃ���ł���܂��B
���āA�䂪���ł͏o�����̒ቺ�ƍ���Ґl�� �̑����ɂ��A���E�ɗނ��݂Ȃ������ŏ��q�� ��Љ�ւƐi�W���Ă���܂��B�o�����̒ቺ �́A�l���\���ɑ傫�ȕω��������炵�A�Y�Ƃ� �o�ς̔��W��j�Q���A��Õ���ɂ���������� �Ղ���̖�蓙�l�X�ȉe����^���Ă���� ���B�X�ɐl���\���⌻��̐����K���̕ω��͎� �a�\�������ω������A�����K���a�A���A�F�m�� �⑽�����Q�ȂǏd�NJ��҂̑����������点�� �����B���̂悤�Ȓ�����Љ�ɂ����ẮA���a �\���̕ω��ɑΉ�����݂̂Ȃ炸�A�\�h��w�A ���N���i�Ȋw�A�������a�����������҂̎Љ �A�A���Ȃǂ̕�I�ȕی���Õ����̗��_�� �\�z�Ǝ��H���d�v�ȉۑ�ƂȂ��Ă��܂��B
�܂��A���̒��N�ɘj���Ô�}����̌��ʁA ��Ò̐��͍X�Ɍ������𑝂��A�S���e�n�� �����Ĉ�t�̐�ΐ��̕s���y�ђn���Ȃ̕� �������ƂȂ�A�f�ÉȂ�a�@���������ŕ��� ��A�n���Â͐��ɕ���̊�@�ɒ��ʂ��Ă��� �܂��B
���݁A���ꌧ�ł���t�s����A��t�̉ߏd �J�����A�����a�@�̉��P���A���ۑ�̉����� �����ċ}�s�b�`�ői�߂��Ă���܂� ���A���S�E���S�Ȉ�Â���邽�߂ɂ����� �̉��P�����߂���Ƃ���ł���܂��B
�K���ɂ��A�킪���ꌧ�ɂ����Ă͈�t�s���� ������g�݂Ƃ��ď����Տ����C�̐��́A�� �w�𒆐S�Ƃ���RyuMIC �⌧���a�@�Q�A�Q�� �����3 ���C�a�@�Q�̐s�͂ɂ�薈�N150 ���� ���̌��C��������O������n���Â̊m �ۂɓw�߂��Ă���܂��B�܂��A���t�̌��C�� �����߂�}�b�`���O���ʂł��A�{����84 ���� �����Ɏ�����2 �ʂƂȂ�A�����}�b�`���O���� �L�[�v���A����A�Ⴂ��t���{���ɍ��t���čs �����߂ɂ��A���i����j���C�̃��x���A�b�v ��e���C�a�@�Q�̏�L���d�v�ȉۑ�ƂȂ� �Ă���܂��B
���̂悤�ȏ���A�{���̓��ʍu���͐V�� �ق̗������@�ɁA�V���Ȉ�t�����͍����� ���߁A���{��t���̒|���N�O�搶���� �u���{��t��̖����ƍL���ɂ��āv��q �����A�V���|�W�E���ł́u���ꌧ�ɂ����鏉�� �Տ����C�������i���j���C�y�ѐ��U����� �ł̘A�g�v�̃e�[�}�ŊJ�Â��邱�ƂɂȂ��Ă� ��܂��B������@��ɖ{���̏����Տ����C�̐� �̍X�Ȃ锭�W�ƌ���i���j���C�̏[�����}�� �邱�Ƃ����҂��Ă���܂��B
�Ō�ɁA�{��w��������݂̊w�p���� �Ɋ�^���A�Ђ��Ă͌����̕ی��E��ÁE������ ���i�ɍv�����邱�Ƃ��F�O���A�����ĐV��ق� ��t�̊w�p�����̋��_�ƂȂ�A�{���̒� ����u�n��ɍ����������͂����t��v�Â��� ���A�X�ɐ��i����邱�Ƃ�O�������A�Ƃ��܂��B
���ʍu��
�u���{��t��̖����ƍL���ɂ��āv

���{��t��
�|���@�N�O
S39.3 ��B��w��w������
S40.5 ��Гo�^
S40.4 ��B��w��w���@���`�O�Ȉ��
S43.6 ��������Z���^�[�a�@�����Z���i��t�j
S46.4 ��B��w��w��������������
S48.10 ������w�a�@���`�O�ȍu�t
S52.2 �^�P�V�}���`�O�Ȉ�@�@��
S56.6 �^�P�V�}���`�O�ȁE�O�Ȉ�@�@��
S62.10 ��Ö@�l�^�P�V�}���`�O�ȁE�O�Ȉ�@������
H15.9 ��Ö@�l���̏o��@�^�P�V�}���`�O�Ȉ�@������
H8.4 �`H16.3 �i�Ёj���{��t���c��
H10.4 �`H16.3 �i�Ёj�����s��t��
H16.4 �`H18.4 �i�Ёj��������t��
H16.4 �`H18.4 �i�Ёj���{��t���
H18.4 �`���݁i�Ёj���{��t��
�T�D���{��t��̖����͑���ɂ킽�邪�A��� ���̂ɂ��ďq�ׂ����B
1�D��̗ϗ��̕��y�E�[��
���{��t��́A2000 �N�ɐV���ȁu��̗� ���j�́v���쐬���A�{�N6 ���ɂ́A��̓I�� ��ɂ��Ắu��t�̐E�Ɨϗ��w�j�k���� �Łl�v���Ƃ�܂Ƃ߂��B
���{��t��ɂ́A�����ϗ��Ɋւ����̂� ���āA�Ή���R�c���A�Љ�ɑ��Ĉӌ��\ �����s�����߁A���̎���@�ւƂ��Đ����ϗ� ���k���ݒu���Ă���B
�����́A���V����u���x��Љ�� �����鐶���ϗ��v�Ƃ̎�����A�R�c���� ���߂��Ƃ���ł���B
2�D��w�E��ÂɊւ���m����Z�p�̔��W�� �̍v���Ǝ��Ȍ��r
���{��t��́A��w�E��ÂɊւ���m���� �Z�p�̔��W�ւ̍v���Ǝ��Ȍ��r�ɑg�D�Ƃ��� ���g��ł���B
�w�p���i��c�ł́A�����̎���u��t �̐��U����ƔF��㐧�E���㐧�v���A �R�c���͂��߂��Ƃ���ł���B
�܂��A���U���琄�i�ψ���ł́u�J���L�� �������C�ɂ������Ă̋�̓I�������v�̎� ����A�R�c���͂��߂��Ƃ���ł���B
3�D����̕����ƒc��
��16 ��5 ��l�̉���̈�ƌo�c�⏫���� ���������ׂ��A���ݕ}���̊ϓ_����l�X�� �{���i�߁A����̒c����}���Ă���B
���{��t��́A��t�����ӔC�ی����x�y�� ��t�N�����^�c���Ă���B
4�D�����
���{��t��́A�����̂��߂Ɉ��S�ň��S�A �����ėǎ��Ȉ�Â̊m�ۂɌ����āA�n���� ��S����Ò҂̗��ꂩ�琭��𗧈Ă��� �ƂƂ��ɁA���̎����Ɍ����Đ���̏�� ���鍑���ɓ��������Ă���B
���̂��߂ɁA�V���N�^���N�ł�����㑍�� �́A�f�[�^�̎��W�E���͂��s���A�G�r�f���X ���\�z����d�v�ȋ@�\���ʂ����Ă���B
���{��t��́A���{�E�s���̐R�c��E���� ��ɃG�r�f���X�Ɋ�Â��f�[�^����� ����A�ϋɓI�ɋc�_���A����ɂ́A�W�e�� ���y�э����̏�ɂ����āA����I�Ƀ��r�C�� �O������W�J���Ă���B
5�D��Ì��ꂩ��̏����W�y�яW��
�㐭�������s���ɂ́A��Ì��ꂩ��A�펞�A �������W���A�W��w�͂��d�v�ł���B
�u�㐭�����Ă̈�ÁA���ꂠ���Ă̈㐭�v�B ���{��t��́A���̊�����Ղł���B
�U�D�������щ�O�L��̌����Ƃ����
���{��t��ł́A��t����Ƃ��āA��2 �� �́u����j���[�X�v�̊��s�A���T�̒��L�҉� ���A���[�����O���X�g�u���N�}�ʐM�v���Ƌ� �ɁA�e���rCM�A�V���ӌ��L���Ȃǂ̃��f�B�A ��ʂ����L�����A�ϋɓI�����ʓI�Ɏ��{ ���Ă����B
1�D���}�̂ɂ��L��
���L�҉�́A���T���j���Ɏ��{���A�� ��20 �` 30 �Ђ̈�ʎ����A�ƊE�����̋L�҂� �S���������A���̈�Ð��x�Ɋ֘A���鐭��� �{��ɑ��A���㑍���ɂ��f�[�^�A���͎� ������ɁA����̎{��A��������s���� ����B
���L�҉�̓��e�́A��ʂ��čL�� �����ɓ͂����Ă���B�܂��A����Ɍ����� �̒��ڂ̍L��́A�u���N�}�ʐM�v�̑��A�u���� �j���[�X�v�A�u����z�[���y�[�W�v�ɂ��f�� ���A�`�B���Ă���B
�V���̈ӌ��L���ł́A6 ���Ɂu����ҁi75 �Έȏ�j�̂��߂̈�Ð��x�v�A7 ���ɂ́A�u�� ��ۏ��̔N2,200 ���~�̍팸���v���A�� �b�Z�[�W���̋������e�ŁA�����̕��c�� ���āA�����Ƌ��ɑi��������`�ōs�����B ���Ȃ�̗ǂ��������������B
�܂��A��N12 ��5 ���ɑS��5 ���Ɍf�ڂ� ���ӌ��L���u��������f�Ă���邨��҂��� �����Ȃ��v�́A�ǔ��L����܁A�L���d�ʏ܂� ��܂����B
2�D�e���r��}�̂Ƃ����L��
�e���rCM �ł́A��Õ���̊�@��i�� ��A�c�������ɑ���u�����~�}��Õҁv�A ����҂̂��߂́u�����×{�a���ҁv�������] ���A�V���̈ӌ��L���Ƃ̑�����ʂŁA�� ��̊����ɑ���S�x�A���ғx�A�M���x�� ���܂��Ă��邱�Ƃ�������ʂ��Ă킩�����B ����CM �ł́A�S���{�V�[�G�������A���̑� 48 ��CM �t�F�X�e�B�o����ACC �܂̃S�[�� �h�܂�2 �N�A���Ŏ�܂���Ƃ��������𐬂� �������B
�e���r�ԑg�́A����4 �����BS �����̒� ���ԑg�Ƃ��āu���z�r���Y�@��Â̌���I�v ����f���Ă���B���T�y�j���ߌ�6 ������� 30 ���ԑg�ŁA���j���̌ߑO10 ���ɍĕ����� ��Ă���B���ԑg�͈�Â̌���ŋN���Ă��� ���������グ�A���z�����d�h�̐�� �ŁA�����VTR �Əo����t�Ƃ̑Θb���d�� �Ȃ���A��Â̂���ׂ��p�⌒�N�̑���� �i���Ă������e�ł���B�n��g�̎������ɓ� ���铖�ԑg�ւ̐ڐG�����ǂ��B
����̉ۑ�Ƃ��āA��Â̒n��i�����~�� �邱�Ƃ�����B���ׂ̈ɂ́A�n���t� ��A���̈�ÁE��쌻��̏����A�ǂ����� �ɏW�߂Ă��邩�A�W�҂őΉ���}���Ă��� �����B
�V���|�W�E��
�u���ꌧ�ɂ����鏉���Տ����C�������i���j
���C����ѐ��U����܂ł̘A�g�ɂ��āv
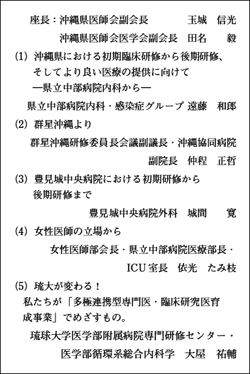
1�D���ꌧ�ɂ����鏉���Տ����C���������C�A�����Ă��ǂ���Â̒Ɍ�����
�\���������a�@���Ȃ���\

���������a�@���ȁE�����ǃO���[�v
�����@�a�Y
1�D�͂��߂�
�����a�@�̈�t�Տ����C���x��1967 �N�Ɏn �܂�A�̗p�������C�㐔��800 ������B�� �C�C����703 ���̓����������Ƃ���A���� �O�o�g�ҍ��v435 ���i62.5 ���j�����ꌧ�ɋΖ����Ă����B���̗��j�̒��ŁA���ꌧ����ѓ� �{�̈�Â̐�삯�ƂȂ��������͏��Ȃ��Ȃ��B �܂����C�����ƌĂ��悤�ɂȂ�������̗� �����C�̍����ƂȂ��Ă��邱�Ƃ͒N�����F�߂� ���ł��낤�B�������j�Ɠ`���܂��A�� �ɉ��P�𑱂��A���̃m�E�n�E���L�����J���Ă� ������y���̌��тƂ��Čւ肽���Ƃ���ł� ��B���C�㋳��͓��@�̍ŏd�v�ۑ�ł���A�� �����ł���B���X�̋��炪�w���㎩�g�𐬒��� ���A���ׂĂ̐E��̎Q�����`�[�����[�N������ ����B�`�[�����[�N���a�@�S�̂������������A ���ǎ��Ȉ�Â̒ɂȂ���B���������� �����I�Ȍ��C�a�@�������邱�Ƃ́A���ꌧ�̈� �Â̈�w�̏[���Ɋ�^���邱�ƂƂȂ�B
2�D���ꌧ�̕������Ö��Ƌ��݁@
���@�̗Տ����C���������������ő�̗��R �́A���̈�t�s���̉����ł���B���60 �N ���o�������ł�����̈�t�s���́A�`��ς��� �ǂ�����Ƒ��݂��Ă���B�����̈�t�s���͍P �퉻���A�����a�@�Ɨ�����w����̔h�������� �͏[���ł��Ă��Ȃ��B�Y�w�l�Ȉ�t�s���͌��� �k���a�@�̎Y�w�l�Ȃ̕��������炵���B�Љ� �ɖڂ�]����ƒ������̃u�����h�͎����A�� ��얞�x1 �ʂ��蒅�����B�}������Â̍Ō�� �Ԃł��錧���a�@�̌o�c�͈������A���̋@�\�� ���ɐ[���ȉe����^���n�߂Ă���B�ł͉��ꌧ �̈�Âő����ɂȂ����݂͉��ł��낤���B���� �͈ȉ���2 �_�ɏW��ł��悤�B�u���炢�v �̂Ȃ��}������Â̏[���B�����Ă��C�ɂ��� �ꂽ�D�G�Ȍ��C�オ�S������W�܂��Ă��邱�� �ł���B
3�D�����a�@�̌��C�̓���
���@�̋�����@�́A��y����y��������u�����������v����{�Ƃ��Ă���B�����邱�Ƃ͊w �Ԃ��Ƃł���B���������邱�Ƃ�g�ɂ��邱 �Ƃ́A���U�ɂ킽��w�ё�����K����g�ɂ� �邱�Ƃł���B�u�����������v�͐��U����ɂ� �s���ł���B���@�̖ڕW�Ƃ����t���́A�� ����Â�S�����Ƃ̂ł���W�F�l�����X�g�̈� ���ł���B���̂��߂ɂ́Acommon diseases �� ��葽���A��葁���A�������f�f�A���Â��A ���ɐ[���l�@����y�낪�K�v�ƂȂ�B
4�D������C��ƕa�@�@�\�ێ�
���@�̌�����C�ł́A�������C�ł͊w�ׂȂ� ��荂�x�Ȓm���ƋZ�p�̏K���A����ɂ̓��[�_ �[�Ƃ��Ă̎������v�������B������g�ɂ� �������C�C���҂ɂ́A���H�̏�ł��闣�����C ����N�ԋ`���Â����Ă���B�������C�̓W�F �l�����X�g�Ƃ��Ă̌��C�̑��d�グ�ł��邾�� �łȂ��A�����ւ̈�t�̏d�v�ȋ������ƂȂ��� ����B���Ȃ킿������C��̌����́A������� �̕s���艻�������N�����A����ɕ���ɂȂ� �邱�Ƃ��A��Î҂݂̂Ȃ炸�������m���Ă��� �Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
5�D���ꂩ��̗Տ����C
���ꌧ�ɂ�3 �̗D�ꂽ���C�V�X�e�������� ����B���݊e�V�X�e���͓Ǝ��Ɋ������A���̂� ����\���ȘA�g������Ă���Ƃ͌�����B ���ꂩ��͂��ꂼ��̓��������A���� �̌��C�ڕW�����������B���͗Տ����C�̍ŏI�� �W�́A�����b����ĂĂ��ꂽ����ւ̍v���� �l���Ă���B���̈�Ƃ��ė�����Âւ̏]�� �����������B���Ƃ����ׂĂ̌��C�V�X�e���� 3 �N�����C�オ�A�����{�Õa�@�A�������d�R�a �@�A�����Č����v�ē��a�@��2 ����������@ �O���C���s���B�͂�t����������C��͊e�a�@ �̐�͂ƂȂ�A��Έ�̕��S���y���ł���B�� ��ɕ����̌��C�オ�����Ɍ��C���s�����Ƃɂ� ��A���C�㓯�m�̐e�r�Ɨǎ��ȋ������������� ��A�V���ȃ��`�x�[�V�����̍\�z�ɖ𗧂B�� ��ɂ͊e���C�V�X�e�����҂̎��_�Ŕ�r ���A���C�ψ���Ȃǂɕ��邱�Ƃɂ��V�X �e���̕W�����ƒ�グ���͂�����B������� �̖ʔ����������������C��̈ꕔ�́A������C �I����ɗ����ł̋Ζ�����]���邾�낤�B���� �ہA�����a�@�̉@���͎��͂Ɛ��i���n�m������ ���t�����S���Čٗp���邱�Ƃ��\�ƂȂ�B
6�D���ꂩ��̉���̈��
�V��t�Տ����C���x�̌��߂͂��낢�날�邾 �낤���A���ꌧ�ɗD�G�Ȍ��C�オ�勓���ĖK�� �����Ƃ͕�����Ȃ������ł���B���̋M�d�Ȑl �ނ��A�����S���l�Ԑ��L���Ȉ�t�Ɉ�Ă�B �����Ĕނ�ƂƂ��ɁA���ł��ǂ��ł����S�� �ėǎ��Ȉ�Â����鉫�ꌧ�����B���� ����X�w����̎g���ł͂Ȃ����낤���B
2�D�Q��������

�Q�����ꌤ�C�ψ�����c���c�����ꋦ���a�@���@��
�����@���N
�Տ����C�a�@�Q�v���W�F�N�g�u
���݂́A29 ��Ë@�ցi�Ǘ��^�a�@7�A���͌^ �a�@11�A���͎{��11�j�Ō��C�v���O�����i�� �w�N��W���69�j���\�z���Ă���A117 ���̏� �����C�オ���v���O�����Ŋw��ł���B
����6 �N�ڂ̎Ⴂ�v���W�F�N�g�ł��邪�A1 �����` 5 �����܂�273 �����̎�҂����{�S�� 40 ��w���ĎQ�����A�w�O�̌��C�v���O�� ���Ƃ��Ă͑S���ōő�K�͂Ǝv����B
���C�C���҂̖�������Ō�����C���s�� �Ă���B
�S�̂�7 �����{�y�o�g�҂ł��邱�Ƃ������ŁA�����̐�߂銄����4 ���Ɣ�r�I�����B
�v���O�����̓��F�Ƃ��ẮA�����̈�Ë@�� ���Q�����邱�ƂŁA��茤�C��{�ʂ̋��炪�� �\�Ȃ��ƁA�č��i�s�b�c�o�[�O��w�B2009 �N �`�X�^���t�H�[�h��w�ɑւ��j�Ƃ̌𗬂��� ��Ȃ��ƂȂǂ���������B
���ʂȋ���s���̒��ł��A�S����肠�܂��� �˗�������Z���^�[�������f�����I�Ɏ� ���邱�Ƃ́A���C��ɂƂ��đ傫�Ȗ��͂̈� �ɂȂ��Ă���B
�Q�����ꂪ�Տ����C���ƂɎQ�������ړI�́A �u����Ђ��Ă͓��{�̖����̗ǂ��Տ��Ƃ���� ��v�i���̃R���Z�v�g�j���Ƃɂ���B������ ���āA�S�l��Â̒S����𐔑�����Ă邽�� �ɁA�W�F�l�����ȋ���ɂ��ꂩ����͂𒍂��� �s�������ƍl���Ă���B
���̂��߂ɂ��A�u�����E�ւ��n�֍s���Ă��ʗp �����t��ڕW�Ɂv���X���[�K���ɁA������C ��̒������]�����ė����ւ̔h�����n�߂��B
����́A�i�Ёj�n���ÐU������u�䂢�܁[ ��v���W�F�N�g�v���i���Ƌ��͂��āA�����ւ� ��t�x����ϋɓI�Ɏ��g��ōs�������B
���ꌧ�ɂ����鏉���Տ����C�`����i���j ���C�̃��x������A�����ė����̈�t�m�ۖ�� �ȂǁA����t��ERyuMIC �E�����a�@�Q�E�Q ��������Ɍ𗬂�[�߁A���ۑ�̑O�i�A������ ���߂Ɉ�v���͂��邱�Ƃ����������߂��Ă� ��̂ł͂Ȃ����B
3�D�L���钆���a�@�ɂ����鏉�����C����� �����C�܂�

�L���钆���a�@�O�ȁ@��Á@����
�L���钆���a�@�ɂ����錤�C���x���Љ�܂��B�L���钆���a�@�́A����15 �N�Ɉ�t�Տ� ���C�w��a�@�ƂȂ�A����16 �N�ɐV��t���C ���x���n�܂����Ƃ��ɁA���߂Č��C����� ��Ă��܂����B���シ���̐V�l������邩 ��ɂ́A��l�̈�t����l�O�ɂȂ�܂ł̃v�� �Z�X�ɐӔC�������đΉ��o����l�ɑ̐���ς� �Ă��Ă��܂��B��t����悻��l�O�ɂȂ�ɂ� ��10 �N��������ƌ����Ă��܂��B���@�ł́A �����3 �̎����ɕ����āA1�j�������C���i2 �N�j�A2�j������C���i3 �N�j�A3�j�t�F���[���i3 �N�j�Ƃ��Ĉʒu�t�����x������Ă��܂����B�� �ɂ��̓��e��������܂��B
1�j�������C���i2 �N�j�F�L���钆���a�@�͌Q�� ����v���W�F�N�g�Q���a�@�̈�Ƃ��ď����� �C���s���܂��B����ɂ��ďڂ����́A�Q���� ��v���W�F�N�g�ɂ��ĕʃV���|�W�X�g���� ���܂����A���@�Ǝ��̎p���Ƃ��ẮA���C��� �L�������O�����W���A�o�g���Ȃ�ׂ���� ���悤�ɔz�����Ă��܂��B
2�j������C���i3 �N�j�F�e�f�ÉȖ��ɕ�W�� ��B��W�f�ÉȂ͓��ȁA�O�ȁA�Y�w�l�ȁA���` �O�ȁA�����ȁB��W�̌`�Ԃ�3 �N�_��ƒP�N�x �_����B��{�I�ɂ��ꂼ��̐f�ÉȂ̐�� ����擾����̂ɕK�v�Ȍo����ςނ��Ƃ��Œ� ���̏����ł���B�f�ÉȂ��Ƃɔz������邪�A �g���͌��C�ψ���ɏ������A���C�̐i���� �������C�㓯�l������C������C�ψ�����c�� �ɓw�߂�B�܂��A3 �N�̒��ŁA�@�O���C���\ �ŐϋɓI�ɐi�߂Ă���B���ۂɉ@�O���C�̕��@ �Ƃ��ẮA�Q������v���W�F�N�g�Q���a�@�̃A ���C�A���X�AVHJ �a�@�Ԃ̃A���C�A���X�A�܂� �a�@�Ǝ��̊W�Ō𗬂��Ă���a�@�Ԃł̌� �ƂȂ�B��̓I�Ȏ���Ƃ��ẮA�O�Ȍ��C�と �ђ˕a�@�i�~�}���A�����O�ȁj�A���������C�� �����q�L�O�a�@�i�S���O�Ȗ����j�A���`�O�Ȍ� �C�と�����K���Z���^�[�i��ᇊW�j�A���Ȍ� �C�と���q�L�O�a�@�i�z��n�j�A�܂����{ �݂����łȂ��A���Ȍ��C�と�ɍ]�����f�Ï��� �����������B����ɉ@�O�������Ă��� ���C��Ƃ��ċT�c�����a�@�i�����O�ȁj���O �ȁA�܂�������w�����������C��̐g���Ō𗬂��Ă���B
3�j�t�F���[���i3 �N�j�F�P�N�x�_��A�Œ�3 �N �ԁB���@�̌��C������N3 ���Ō�����C���I�� �����t������A������C���I�����A����ɐ� �啪��Ōo����ς݂����ꍇ�ɑΉ����邽�߂� ���̐��x�����肳�ꂽ�B���@�݂̂Ȃ炸�@�O�� �C���\�ɂ��Ă��蓖�@�𑫏�ɂ����I�� �{�݂ł̌��C���\�ɂȂ�B�܂����N����̐� �x�Ȃ̂ō���[���������̂ɂȂ�悤�Ɏ��g �݂����B
�ȏ�A�L���钆���a�@�̏������C���炻�̌� �ɂ��ďq�ׂ����A�������C�Ȍ�͊�{�I�ȃv ���O�����͂��邪�A�X�ɂ��Ă̓I�[�_�[�� �C�h�ō��グ�Ă���B���N�͗����f�Â���] ���������C�オ�����̂ŁA�ɍ]�f�Ï��ŋΖ� �ƂȂ������A�L���钆���a�@�Ƃ��Ă͒n���� �܂őg�ݓ��ꂽ�v���O�������쐬���Ă������� �ƍl���Ă���B
4�D������t�̗��ꂩ��

���ꌧ��t�����t���
���������a�@������EICU ����
�ˌ��@���ݎ}
������t�ɂȂ������a50 �N�O��̏�����w ���̊����́A10 ���O��ł������B�����̎Љ� �i�o�̑����ɔ����A2000 �N�̍��Ǝ������i�� �̏�����t�̊��������߂�30 �����A2008 �N��34.5 ���Ƃ���ɑ������Ă��Ă���B2006 �N�̈�t����277,927 �l��17.2 ����������t �Ő�߂��Ă���B�o�Y�E�玙�Ȃǂňꎞ�I�� ����x�E������Ȃ�������t�̋�̓I�Ȏx ���A���ꌧ�݂̂Ȃ炸���ꂩ��̓��{�̈� �Â����E����ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B������ ���₭���̏d�含�ɋC�t���A���J�Ȃً͋}��t �m�ۑ�̗v�|�̈ꕔ�Ɂu�o�Y��玙�ł̈�t�̗��E��h���A���E�𑣂����߂ɉ@���ۈ珊�� �����ȂǏ����������₷���E������� ��B�v�ƒ����B
�������A������t����芪�������͌������B 2005 �N12 ���ɍs�Ȃ������ꌧ��������t��� ������t�ɑ���A���P�[�g�����ŁA�������� ���A�X�ߎ��Ȃ��A�V�����[���Ȃ��A�������� �����Ȃ��Ɖ����{�݂͂߂��炵���Ȃ��B�� �w�a�@�A6 �����a�@�ʼn@���ۈ�{�݂�L���Ă� ��a�@�͂Ȃ��B�u�������Ă��A��Ύq���͍�� �Ȃ��v�Ɖ������C��́A�j����t�ȏ�ɏ� ����t�Ƃ��ē��������鍢����A���������� �ł̋�a�̉������̂��낤�Ǝv���B
�y�ړI�z
����̃V���|�W�E���̃e�[�}�u���ꌧ�ɂ��� �錤�C����ѐ��U����܂ł̘A�g�ɂ��āv�� ������t�̗��ꂩ��A���ꌧ�̏�����t�̌��� �͂��A�������Ȃ̂��A�������ɂ͉��� �K�v�Ȃ̂����A�j����t���܂ޑS�Ă̈�t�̖� ��Ƃ��čl���Ă��������Ǝv���B
�y���ꌧ�̋Ζ��㌻�������z
���ꌧ��t��̍s�����Ζ��㌻�������ɂ�� �ƁA2007 �N3 �����݉��ꌧ�̋Ζ���1954 ���� �̂�����1,062 �����A���C����܂ޏ����� �t����177 ���őS�̂�16.7 �����߂Ă����B �x�E�E���E�҂�50 ���ȏ�Ɛ�������Ă��邽 �߁A������t�̐�߂銄���͑S�����݂Ǝv��� ��B�����E�o�Y�E�q��Ă��d�Ȃ�ł��낤���� 10 �N�ȓ��̏�����t��66 �����߁A����5 �N �ځA10 �N�ڂ܂ł����ꂼ��55 ���O��ł������B ����ɂ��̎����͌��C��Ƃ��Č��r��ς݁A�� ����1 �l�̈�t�Ƃ��ĐӔC�����ɏd�v�� �����ł���B
���̈�ł͓���51/������18/���_�_�o�� 14/�Y�w�l��12/�O�Ȍn12/������9/���9/�� ����8/���ː���5/���@��4/��A���3/���̑� 31 �ƂȂ��Ă����B
�y���_�z
1�D�Ζ���ł̕��S�ȓ_�F�j�����ɉߏd�J������ ���ŁA�����Ŋ��҂̉ߏ�Ȍ����ӎ��A���ҁE �Ƒ��ւ̐����őS�̂�64 �����߂Ă����B
2�D�D�P�E�o�Y�ɔ������_�F������t4 ���A �j����t12 �����Y�x�E�玙�x�ɂ̑����ɂ� �铯����t�̕��S�������Ă����B
3�D�玙�Ǝd���̗����F�A���P�[�g���ʂɂ�� �Ə�����t��53 ���i30 ���j���玙�o���� �ŁA���̂����̖�25 �����玙�Ǝd���̗��� ����E�����ł��Ȃ������Ɖ��Ă����B�� �̗��R�Ƃ��Ĉ玙�x���̐����Ȃ����ő��ŁA �����ň玙�x�ɂ����Ȃ��A�Ζ���̗����E �Ƒ��̋��͂������Ȃ��ƂȂ��Ă����B
4�D�������E��̐E�ꕜ�A������F�ċ��炪�K �v�Ɖ����̂́A�o���L�x�Ǝv����50 ��ł���30 ������A20 �` 40 ��ł͖�80 �� �O��ƂȂ��Ă����B
�y������t�����߂�x���Ƃ́z
1�D�玙�x���̐��\�a���ۈ���܂މ@��24 ���ԕۈ�A���ԊO�Ζ��E�����̖Ə��A���[�N�V�F�A�����O
2�D�Y�x�E�玙�x�ɒ��̐l����[
3�D���E�Ɍ����Ă̍ċ���
4�D�h�N�^�[�o���N
5�D��i�E�����E�Ƒ��̗���
6�D�Ǝ�����
�y���B���ł��鎖�Ƃ́z
������t���d���ƈ玙�̗����̂��߂ɂ�1�D �ۈ�{�݂��܂ޓ����E�Ƒ��̃n�[�h�ʁA�\�t�g �ʂł̈玙�x���̐��A2�D���E�Ɍ����Ă̍ċ� �炪�傫�ȉۑ�ł��鎖���ĔF��������ꂽ�B
2007 �N8 �����ꌧ��t�����t����� �����A���N��10 ���A���{��t���t�ďA�Ǝx �����ƃ}�l�[�W���[�̕ۍ�V�Q���搶�������� ��2 ����t�t�H�[�������J�Â����B�Ō�� �X���C�h�Łu���⎩���̂��t��⑼�̒N���� ���������߂�̂ł͂Ȃ��A���ꂼ�ꂪ���ꂼ�� �̖�����S���Ă��鎖�����o���āA�s������K �v������B�ǂ͌����Ă��A�����˂��������A �����邱�Ƃ��ł���B���̓���M���ċ��͂��� �����܂��傤�B�v�A���������v���B�g�߂Ƀ��[�� ���f���������A���̎����̎��ɉ���D�悳�� ��̂������߂�͎̂������g������ł���B�� �ꌧ�̏�����t�̃l�b�g���[�N���A���k���� �Ƃ��ď�����t��������ł����ɗ��Ă�K ���ł���B
5�D���傪�ς��I ���������u���ɘA�g�^�� ���E�Տ�������琬���Ɓv�ł߂������́B

������w��w�������a�@��匤�C�Z���^�[�E
��w���z�n�������Ȋw
�剮�@�S��
��w�a�@�́A�]���A��Ðl��{�����邽�߂� ����@�ցA�V������Â��J�����錤���@�ցA�n ��Ƃ̘A�g���Ƃ�Ȃ��獂�x�Ȑ���Â�� �����Ë@�ւƂ��Ă̖��������҂���A�܂��A ���̖�����S���Ă��܂����B�������A�l����\ �Z���n�߂��܂��܂Ȑ����Љ��x�̕ω��� ��A���̂��ׂĂ���������ɂ͎����Ă��܂��� �ł����B�����Ȋw�Ȃ́A�{�N�x���5 �N�ԁA�� �w���v���i���Ƃ̈�Ƃ��āu��w�a�@�A�g�^ ���x��Ðl�{�����i���Ɓv���J�n���܂����B�� ��A������w��w������ш�w�������a�@�́A ���̍�������y�їՏ������҂�{�����錤�C �v���O�����Ƃ��̎x����ړI�Ƃ����u���ɘA�g �^����E�Տ�������琬���Ɓv�����債�A�� ������܂����B��̓I�ɂ́A������w�ɐ��� �琬�̂��߂̃Z���^�[�Ɛ�C������z�u���A�� �����C��A�������C��A�w���ɂƂ��Ė��͓I�� ��含��g�ɂ��邽�߂̌��C�R�[�X���쐬�� �Ď��{���܂��B���ɉ���ŏ������C���C������ ��t�������A�p���I�ɉ���ɂ����āA����� ���̍�����Â��w�Ԃ��߂̎M�ƂȂ�v���O ������ڎw���܂��B���̎��ƂɊ܂܂��R�[�X �̓����́A���炩���ߖ������ꂽ�v���O������ ���������C���s�����ƁA��������ь��O�̐�� �a�@�⑼��w�a�@�����[�e�[�V�������āA���� �悭����ɕK�v�Ȓm���ƋZ�\��g�ɂ��A�� �ۂɐ���擾���s�����Ƃ�ڕW�Ƃ��邱�Ƃ� ���B�܂��A�D�ꂽ�w����⋳�����琬���邽�� ��Faculty Development �v���O�������s���� ���B2�j�Տ��������s�����Ƃ��ł������� �琬�̂��߁A����v���O�����̍쐬�Ƃ��̎��{ �̂��߂̎x�������ݒu���܂��B���̃v���O�� ���̒��ł́A�����v��⎎���v��̍����A�� �Ó��v�A��×ϗ��A��Ï��̎��W�@��]���@ �Ȃǂ̌����̊�{�ƂȂ鎖�����n���I�Ɋw�Ԃ� �Ƃ��ł��܂��B�܂��A�Տ��̌���ł�����on the job training �̌`�Ŏ��{���邱�ƂŁA���� ���{�ł���\�͂�g�ɂ��Ă����܂��B����� �̊w�тɂ����āA�Љ�l��w�@����Տ���w�@ ���Ƃ��ĉے����C�����邱�ƂŁA�w�ʂ̎擾�� �\�ƂȂ�܂��B�܂��A��w���v�ҁA���T�[�` �R�[�f�B�l�[�^�[�A���T�[�`�i�[�X��z�u���A �Տ������̃T�|�[�g���s���܂��B3�j��t�̐� �U�ɂ킽��L�����A�`���̉ߒ��ŁA�w�т��p�� �ł���悤�Ɏx�������Ă����܂��B������t�� �́A�o�Y�A�玙�ɂ��L�����A�����f���Ȃ��� ���ȁA���f���Ă���ꍇ�͈��S���ĕ��A�ł��� �悤�ȃT�|�[�g���s���܂��B�܂��A�����Ζ��� �̎x���₻�ꔺ���L�����A�`���ɂ�������� �̎��g�݂��l���Ă����܂��B�������́A���� ��̌v������{���邱�ƂŁA���݉��ꌧ�̈�� �E�S�̂Ŏ��g��ł���w�n��𗝉����A�n�� �������A�n��ɍv������x��t����Ă銈�� �ɁA�ϋɓI�ɍv�����čs�������Ǝv���܂��B