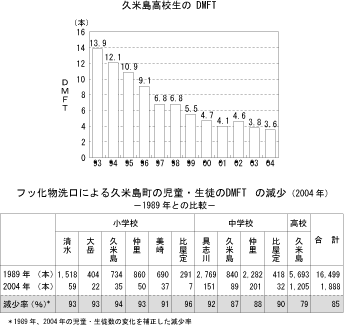歯の衛生週間(6/4〜6/10)について
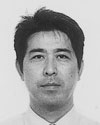
沖縄県歯科医師会地域歯科保健委員会
福里 英彦
今年も、歯の衛生週間が6月4日(月)〜6月 10日(日)まで行われます。沖縄県歯科医師会 の活動の1つとして毎年6月に行われるデンタ ルフェア−があり、今年は6月2日(土)、3日 (日)と9日(土)に各地区にて実施されます。 成人検診、小児検診、顕微鏡による口腔内細菌 の観察、小児のフッ化物洗口、栄養指導等を行 っています。
この週間は、厚生労働省、文部科学省、日本 歯科医師会などが中心となって「歯の衛生に関 する正しい知識を国民に対して普及啓発すると ともに、歯科疾患の予防に関する適切な習慣の 定着を図り、併せてその早期発見及び早期治療 等を徹底することにより歯の寿命を延ばし、も って国民の健康の保持増進に寄与することを目 的」として、1958年(昭和33年)から毎年実 施されています。すでに半世紀近い歴史があり ますが、現在の形になる以前から、6月4日を 「むし歯予防デー」としてさまざまな啓発活動 が展開されてきました。日本歯科医師会が6月 4日を「むし歯予防デー」と定めたのは1928年 (昭和3年)にさかのぼります。
昨年6月2日に厚労省は「平成17年歯科疾患 実態調査結果の概要」を発表しました。この調 査は1957年(昭和32年)から6年ごとに実施し ているもので、9回目になります。全国の満1歳 以上の男1,927人、女2,681人、計4,608人が対 象となりました。この調査結果にも、長年にわ たる地道な啓発活動の成果が徐々に現れ始めて います。
今年度の「歯の衛生週間」の重点目標は「住 民主体による8020運動の新たな展開」で、標 語は「ずっとずっといっしょがいいな自分 の歯」です。
公表された調査結果によると20歯以上を有 する人の割合は80〜84歳では21.1%となって います。これは、前回の平成11 年調査時の 13%から8ポイントの大幅な増加であり、80歳 で20歯以上を有する人の割合が初めて20%を 超えました。80歳以下の年齢層では、75〜79 歳は27.1%(前回調査時17.5%)、70〜74歳は 42.3%(前回調査時31.9%)など、40歳以上の 各年齢階級でも大幅に増加していることが明ら かになりました。一人平均現在歯数も各年齢層 とも少しずつ増加し、80歳では約10本になっ てます。
1989年に日本歯科医師会と政府が8020運動 を提唱した当初は、80歳で20歯以上の歯を有 する人は1割にも満たない(1987年調査の参考 値で7.0%)というのが実情で、あまり現実味 のない運動のように思われていた時期もありま した。しかし、今日、実際に高齢社会を迎え、 8020運動は具体的な目標と着実な成果を示す ことが出来る「新たな展開」の時期を迎えてい ると言えます。
同調査結果で見ると、1日の歯磨きの回数は、 2回磨く人が49.4%と、ほぼ半数に達していま す。3回以上も21%に増えていることがわかり ました。半面、年齢階級が上がるとともに健全 歯数が減少しており、1人平均の未処置歯数も 全年齢階級で1歯前後と前回調査からわずかし か減少していないことも指摘されました。
平成16年国民健康・栄養調査結果でも「何 でも噛んで食べることができる」人の割合は、 現在歯が20歯以上の人では約8割である一方、 19歯以下の人では約5割にすぎないことが示されるなど、メタボリックシンドローム対策の基 本である食習慣の改善においても歯の保健と健 康、噛んで食べることの重要性が改めて認識さ れつつあります。地道な活動がますます大事に なっています。
平成12年に生活習慣病予防のための国民運 動としての健康日本21が発表され、その中に 「歯の健康が」取り上げられました。平成13年 度には、その都道府県版たる「健康おきなわ 2010」が策定され、さらに平成15年3月には、 その実行計画としての沖縄県歯科保健計画が策 定されました。その中には、2010年(平成22 年)までに3歳児う蝕有病率を30%以下にする とか、12歳児のDMFT(永久歯う蝕経験歯数) を2.0本以下にするなどの目標値が書かれてい ます。本県の3歳児う蝕有病率は年々下がって いますが、全国ワースト1です。平成15年には ついに5 0 %を割り4 9 . 3 %、平成1 6 年には 48.6%になりましたが、減少率は小さく、この ままのペースで推移しますと、2010年までに 30%以下にすることは困難だと思います。
本県のう蝕有病率を大幅に下げるには、その 有効性が確立されているフッ化物の応用が重要 です。本会会員の先生が、久米島にて既にその ことを実証してくれていますので、それをいか に全県に広げていくかが課題です。現時点で は、保育施設と幼稚園を中心に活動しておりま すが、県のフッ化物洗口実態調査報告書による と、実際にフッ化物洗口を実施いているところ は、保育施設で1.7%、幼稚園で2.4%しかあり ませんでした。う蝕予防のためのフッ化物の応 用について十分理解されていない状況があると 思われるので、今後とも、県民に対しフッ化物 の応用について普及・啓発に努めなければなら ないと思います。なお、「貴施設でフッ化物洗 口をしてみたいと思いますか」の問いに、「出 来ればやってみたいと思う」と「すぐにでも始 めてみたいと思う」と回答した施設の合計は、 保育施設では61.3%、幼稚園で43.2%です。こ のような中、フッ化物洗口を希望する保育施設 や幼稚園などから依頼されたときのために、本 会は平成17年11月に「フッ化物局所応用マニ ュアル」を作製しました。
これからの歯科医療は県民にとっても歯科関 係者にとってもより満足度の高いことが求めら れます。その実現に、この地道な努力が少しで も役立つことを切に願う次第です。