第1回地区医師会長会議
常任理事 真栄田 篤彦

会場風景
去る5月10日(水)、沖縄ハーバービューホ テル(白鳳の間)において、標記会議が開催さ れたので、その概要について報告する。
【宮城会長挨拶】

開会にあたり、宮城信雄会長から挨拶があった。
地区医師会長会議は定期的に開催すべきであ ると考えている。各地区で医師会活動が活発で なければ県の医師会活動もありえないという思 いがある。県も地区も様々な問題を抱えてい る。このように一堂に会し問題点を出し論議し 解決していくためにも必要である。4月から診 療報酬が改定になり前代未聞の引き下げになっ たが、その影響がそろそろ各医療機関にも出て きていると思う。その上更に財政主導で医療費 を切りつめようという動きがある。日本の医療 制度はどうなっていくのか非常に問題が大きく なっているという気がしている。
そのような中で、長年の懸案事項であった会 館建設問題がでてきた。本日の会長会議は土地 の問題があり急遽開催しなければならなくなっ た。本来、会長会議は各地区から議題を募るが 急遽開催することになったので、本会からの提 案議題だけになっている。次回からは地区から も提案を受けたい。本日は活発なご意見と提案 をお願いしたい。
引き続き、宮城会長の進行で協議が行われた。
議 題
1)県医師会館建設用地等価交換の件
真栄田篤彦常任理事から提案理由の説明が行 われた。(提案趣旨詳細は別紙参照)
平成17年9月20日に県から等価交換地として 新たに新川の立地条件のよい土地が提案され た。県と本会で各々不動産鑑定士に依頼し、双 方の土地の鑑定を行った結果、県から示された 等価交換による本会の面積は6,858.99mlとなっ ており、現在の所有地より4,166.42ml少なくな るが、等価交換をしてよいかご協議いただきた い。県は6月に開催予定の県公有財産管理運用 委員会へ本会との等価交換について提案するこ とになっているので、本日の会長会議でご承認 いただきたい。
また、宮城会長から県有地との等価交換につ いては代議員会で承認を得ているが、実際に不 動産鑑定を行った結果、現在所有地の7割に満 たない面積となった。これでよろしいかご意見 を賜りたいと述べた。
南部の永山会長から、会館建設にあたり等価 交換を行う当初の目的は駐車場が狭い、また、 自前の会館でないから使い勝手が悪いとのこと であった。今回の等価交換先にどの程度の会館 を建て、駐車台数はどの程度かを示さなければ 協議にならないと意見があり、事務局長から説 明を行った。
会館建設準備委員会で検討された現在地の駐 車場への建設予定の会館を建てた場合、建物が 下駄履きで約767坪で駐車台数は屋外186台で 下駄履き部分には33台で合計219台となる。現 在地は120台である。
以上の説明の後、協議が行われた。駐車場に 係わる問題、また今後発生するであろう負担金 の問題等活発な意見交換が行われ、その結果、 会館の機能、規模、負担金については、今後会 館建設検討委員会を開催し検討を行い、その経 過については会長会議等で説明していくという ことになり、新川地との等価交換を行うことが 承認され、6月の代議員会に上程することにな った。
<主な意見>
○村田(公務員医師会副会長)

医学会は休日に開催されるので南部医療セン ターの駐車場(500台収容)を利用させてもらう ことを条件とするよう県に申し入れた方がよい。
●玉城副会長

同地へ建設予定の薬剤師会と小児保健協会と 互いに駐車場を共有することを考えている。逆 に南部医療センターの職員に昼間は本会の駐車 場を安くで提供してもよいと思う。
○新垣(代議員会議長)

多くの医療団体が共同で利用できるホール等 も考慮する方がよい。30〜40年先を視野にい れてお願いしたい。駐車場はあまり心配しなく てよいと思う。
○中村(宮古地区医師会長)
他の団体と共有するのは大賛成である。宮古 病院を建てる際にはいろいろな団体が建物に入 れるよう要望したいと思っているので、県医師 会が先行形態をすると進めやすい。
●真栄田常任理事
会館建設委員会を開催したい。三団体との調 整も行いたい。会館の規模、会費賦課額等以前 の答申に基づき検討していきたい。平成20年3 月完成を予定に進めていきたい。
○金城(中部地区医師会長)

等価交換先はいい場所がもらえるのか?もし 土地を買うとしたら今の評価額で買えるか?で も現在の面積を求めるには購入資金がない。
●宮城会長
本会の場所は一等地である。本会の面積が決 定した後他の団体へ売ることになる。
○山内(浦添市医師会長)
機能の問題である。駐車場は最大何台必要 か?(事務局:ピーク時は300台)
○永山(南部地区医師会長)
準備委員会では会館維持管理費は徴収する が、新たな建設負担金は徴収しないとのことで あった。これを前提にお願いしたい。土地は現 在の面積でなくて等価交換分でよい。
●宮城会長
新たな負担金は徴収しないことを前提に委員 会では検討していきたい。協同組合、国保組合 等の各事業所が負担金を出し合うことを考えて いる。
●小渡副会長

負担金を徴収せず積立金の範囲内でやってい くというのは原則と考えてほしい。必要な機能 と規模で会員としての誇りを持てる会館を建設 したいと思う。
●宮城会長
準備委員会で年間維持費は1,500万円と考え ていた。この件も含めて承認いただけるよう検 討していきたい。
○金城(中部地区医師会長)
駐車場にこだわることはない。近場の会員は タクシーを利用する方法もある。
○永山(南部地区医師会長)
準備委員会に出席していたが、新たな負担は ないとのことであった。負担があるとなるとま た会員に説明が必要になる。建設委員会を開催 して平成20年度までに建設してほしい。
●嶺井常任理事
土地の取得には負担金の徴収はしないが、維 持費として月500〜1,000円程度の負担はする とのことだった。建設については新たな負担が あると言っていた。
○金城(中部地区医師会長)
用地特別会計に拠出していない会員からは徴 収すべきと言うことだった。
●宮城会長
これまでの経緯を踏まえながら検討していき たい。稲冨会長の時に等価交換が出てきた。今 回等価交換地の面積がはっきり示されたのでそ れでよいかということである。規模、負担金に ついてはこれから検討していく。
○高里(代議員会副議長)

等価交換に賛成である。等価交換後に土地は 売ることができるか?年2回の学会のために駐 車場を広くする必要はない。土地を有効利用し て余った分売ることも考えた方がよい。
○鍛(北部地区医師会常任理事)
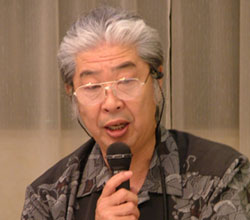
等価交換は賛成である。細かいことはこれか ら委員会でつめればよい。
○友寄(那覇市医師会長)

等価交換は賛成である。那覇市は評議員会で も会員へ周知している。土地の買い増しはしな くて良い。会館は小さくてもいいから立派な建 物にしてほしい。下駄履きでない方がよい。50 年も使うと考えると負担金は0であればよいと は思わない。維持費として月1,000円徴収する ことでよい。
○石川(国療沖縄公務員医師会長)
交通の利便性もよいから進めてほしい。
○瀧下(琉球大学医師会長)
琉大はC会員、研修医が多いから代表して賛 成とは言いにくい。負担があると少し困るが等 価交換は個人的には賛成である。
○川野(市立病院医師会長)

原則賛成である。負担金については検討させ てほしい。
●宮城会長
本日の会長会議の結論として、等価交換につ いては皆さん賛成であり承認いただけたという ことで来る6月の代議員会に上程したい。
2)沖縄県における医師確保対策について
玉城副会長から提案理由の説明が行われた。
沖縄県では、「医療対策協議会」及び「離島・ へき地医師確保対策検討調査事業(単年度事 業)」を近日中に開催し、医師確保について調 査・研究・協議を進めていくことにしている。
本会の今後の取り組み方として、各地区の現 状を踏まえた上で両協議会において、医師確保 の具体策の提案に努めていくことにしており、 例えば、琉球大学医学部に地元枠(12大学あ り)を設置していただくこと、奨学金制度(15 県で実施あり)を設けることなどについても他 県の実施状況を参考にして検討し、沖縄県や琉 球大学に要望していくことにしている。
又、先に県庁福祉保健部を訪問して、医師確 保の現状、予算、今後の事業予定等について考 えを伺った結果を会議の中で併せて報告を行い、 沖縄県が予定している調査だけでは何も解決し ないので、各地区医師会のご意見をいただき、 県の会議に反映させていきたいと提案した。
以上の提案を受けて、離島勤務のあり方や、 予算の使い方、地域枠の設置、奨学金制度につ いて意見・提案が出された。また、各地区・各 病院の実施例についても紹介があった。
これに対して、本会からは、琉大・県立病院 等調整役を担っていきたい、今回の沖縄県医療 対策協議会は、琉大からも委員が多く参加する ことになっており、沖縄県の強い意気込みを感 じており大いに期待したい。すべての科で各医 療機関の連携がとれないのか、どうやったらで きるのか、検討・提案していきたい。又、各地 域においても、地区医師会・市町村が中心にな って調整を図っていただきたいと述べた。
<主な意見>
●嶺井常任理事

県予算(4億1千万円)の具体的な使い道が わからない。
県は離島勤務を義務付けしているのか。自治 医科大学の卒業生は、義務年限9年のうち、4 年離島勤務、5年間県立病院勤務と聞いている が、その後は県職員になれないので県外に行っ てしまうことが多い。義務年限終了後の対応も きちんとやる必要がある。
● 玉城副会長
県立病院は産婦人科医師を育ててもらう、そ ういう研修医に予算を出してやることも検討し てはどうか。
●宮城会長
研修の問題についても、ある程度注文してい かなくてはならない。
○山内(浦添市医師会長)

理事会で検討したところ提案があった。1)医 師の養成も必要だが、全国に定年された先生を 募ってはどうか。2)ある期間、プライマリの研 修を(若い方とは別に)受けていただく。3)1 人で沖縄に行くのが不安なら、複数であると か、交代の工夫をしていただく。
●玉城副会長
那覇市医師会の場合、産婦人科の先生方は高 齢になると産婦人科をされない方が多い。例え ば県立病院でお産はやるとか、バックアップ体 制をとることも考えていきたい。産婦人科医師 の問題をとっかかりにしてやっていきたい。
また、県立の麻酔科医は、琉大と県立病院の 先生方で取り決めをして、必ず離島に2〜3年行 くようにしていて、うまくいっていると聞いて いる。他科についてもできないか、検討したい。
本日、北部地区で産婦人科を開業される先生 がいると聞いた、県立北部病院・医師会病院・ 自衛官医師といかに連携をとっていかれるかが 重要。各地域でも、地区医師会や市町村が本気 になって、地域の医療の体制づくりに取り組ん でいただきたい。
○石川(国療沖縄公務員医師会長)
後期研修を琉大と国立沖縄病院と宮古が連携 をとって、沖縄病院で琉大2外科の研修を受け 入れ、終わったら県立宮古病院に行くというこ とを行ってきている。多方面から検討していく。
●安里常任理事

去る2月に、臨床研修修了生の卒業後の進路 のアンケート調査を依頼した。平成16年に県内 で研修をスタートさせた研修医は140名、修了 生は135名で、沖縄県内に残ると回答したもの は94名であった。新制度以前と比べて増えた。 産婦人科4名、小児科12名である。詳細は医師 会報に報告する。
○中村(宮古地区医師会長)
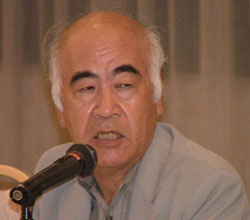
遠隔医療の予算が7,500万円となっているが、 役に立っていないと思う。実務に回していただ きたい。
地域医療対策協議会の地区医師会からの委員 が2名となっているが、北部・宮古・八重山の 3地区は入れないのか。
後輩に意見を聞くと、仕事の割りに待遇が合 わないと言っており、高度医療の現場は疲れき っている。お金で働いてくれるかどうか、これ から医師になる人に奨学金出してもどうか、や るべきではないと思う。
産婦人科、脳外科等は、市町村で予算確保し て待遇を良くするべきである。
ハワイ大学は何もならない。一人前の先生に 待遇(金銭的に)をきちんとする、行政のシス テムとして変えないと意味がない、医師の使命 感や義務で縛られるのはどうかと思う。
○金城(中部地区医師会長)
中部地区では、県立中部病院の研修医と会員 の風通しを良くし、研修医を激励するため会を 持っている。最近は管内他の研修病院の研修医 も含めている。
地区医師会と行政が、激励してあげたり、勇 気づけたりする。手かけてやると医師は動いて くれる。
県立中部病院、公務員医師の定着が悪くなっ ている。琉大は開業医に応援を出してくれるが、 県立病院はそうではない。県立病院も管理者の 指示、許可で応援出せるようお願いしたい。
○永山(南部地区医師会長)
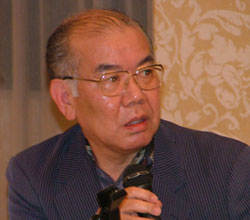
以前は、離島・北部地域の病院への産婦人科 医派遣について、琉大と県でトラブルがあった と聞いている。県医師会には、琉大や県との調 整役を努めて欲しい。
副知事にも医師不足への対応を要請したが、 研修医がたくさんいるので困らないという認識 であった。のんきな考え方であり、問題は何も 解決していない。
南部医療センターは、離島医療支援を行うと しているが、名前をつけるのであれば離島に行 ってもらいたい。県立八重山病院の産婦人科医 師配置も進んでいない。
琉大に地域枠を依頼していただきたいと主張し ているが、県はなかなか動こうとしない。県に いくら情報を入れても動こうとしなかった。県 医師会からも要請して欲しい。
○瀧下(琉球大学医師会長)

産婦人科医の件は、事実である。
H14〜H18の5年間の琉大医学部入学生の出 身高校・保護者の住所を調べてみると、北部・ 宮古・八重山の方が入学している。離島ごとの 枠を作れるのではないか。地域医療対策協議会 で話し合っていきたい。
●玉城副会長
県行政と県立病院、琉大と県立病院 上手く 行っていない。医師会は琉球大学・県行政・県 立病院の仲立ちして調整役をする。
今月、北部で産婦人科開業される方がいる。 北部地区医師会が中心になって県立北部病院・ 医師会病院・開業医が有機的に結合していけた らと思う。県医師会も一緒に調整を行う。
●真栄田常任理事

知念病院管理局長が産婦人科医会に来られ て、産婦人科医師の配置に苦慮されていること を話された。
●金城理事

30年間に亘って予算をかけたが、県立病院の 産婦人科は閉鎖の状況におかれている。県立病 院医師は必ず離島勤務を義務付けするよう県医 師会から要望していただきたい。
○村田(県公務員医師会副会長)
産婦人科医の問題は、県立病院と琉大の協力関 係が重要。麻酔科はなり手がいない科にもかかわ らず、宮古・八重山が困る状況にはなっていな い。琉大麻酔科の奥田前教授が中心となって、沖 縄県の麻酔科を支援していくことが決まったが、 内規がまだ作られてなかったので、須加原教授 が引き継いで「離島を皆で支援する、人生のどこ かで2〜3年離島に行ってもらう、その代わり帰 ってきたあと行く病院を優先させる」との内規を 作った。今は、積極的に行く人も出てきている。
琉大と県立病院が話し合い協力していけば、 産婦人科も上手くいくのではないか。
南部医療センターは、産婦人科は8人体制で、 フル回転している。帝切がほぼ毎日ある。常勤 4人、臨任2人、研修医2人、急速に育っている と思う。しかし、県立八重山病院に将来長期的 に行くつもりがあるのか、女性医師、内科から の転科、本土出身もいる。それぞれの事情があ るかもしれない。県医師会から離島に行くよう 調整して欲しい。
遠隔医療システムは、離島医師のネットワー クができており、電子会議や伝送を行っている。 毎日、中部病院の会議室から離島を結びコアレ クチャーを行っており、有効な会議であると思 っている。額が妥当であるかはわからない。
●宮城会長
県の会議は、これまで県立病院の医療の話に なってしまっている。今回の医療対策協議会 は、琉大からも委員が多く参加することになっ ており、期待したい。麻酔科・外科の例のよう にすべての科で連携がとれないのか、どうやっ たらできるのか、提案していきたい。
○石川(国療沖縄公務員医師会長)

旧国療4施設・沖縄県福祉保健部・琉大医学 部・国立病院機構九州ブロックで地域医療連絡 協議会を持っている。今回県に設置される地域 医療協議会と二つの協議会は、対策一緒なので 一つにしてもいいと思う。
3)その他
永山南部会長より、助産師養成について下記 のとおり要望があった。
助産師が殆んどいない。浦添看護学校に助産 師コースを設置していただきたいとお願いして 調整が進んでいたがだめになった。沖縄県医師 会から浦添看護学校に助産師コースを作ってい ただくよう要望していただきたい。
浦添看護学校を民間委譲にするとの話がある が、もし、将来民間委譲するにしてもコースを きちんと作っていただき形を整えたうえで行っ ていただきたい。
印象記
常任理事 真栄田 篤彦
新県医師会長のもとで、初めての地区医師会長会議であった。
宮城信雄会長挨拶の中で、比嘉国郎元会長「開かれた医師会」、稲冨洋明前会長「信頼される医 師会」という県医師会のスタンスをさらに踏み込んで「地域に根ざした活力ある医師会」の県医 師会のスタンスを表明した。県医師会の会館建設に関しては、任期中に建設を実施する旨の発言 であった。会館は「県立南部医療センター・こども医療センター」近隣の県有地に土地を確保す るべく、現在の県医師会在住の土地と等価交換をするに当たって、本会長会議で交換土地面積が 30%弱の減少を認めることで意見が一致した。6月29日の沖縄県医師会代議員会で総意を承認し た後、7月3日の「平成18年度第1回会館建設検討委員会」から本格的に会館建設に向けて協議を 行う。
次いで、沖縄県における「医療対策協議会」・「離島・へき地医師確保対策検討調査事業」等 医師確保対策について、沖縄県医師会の果たす役割が益々重要になってきた。沖縄県全体の問題 として大局的に医療を捉えて協議していく上で県医師会の参加は絶対必要であり、これからの両 協議の進展が期待される。