研修医一期生(140名)の進路について

常任理事 安里 哲好
新医師臨床研修制度が始まり、一期生が平成 18年3月末に2年間の研修を修了した。
2年間の研修期間に基礎・必須科に加え選択 科の研修と広い範囲での研修と多くの症例を経 験し、そして、新たな後期研修・専門研修にお ける自分の進路を選択し歩むことになる。
この度、沖縄県医師会地域医療臨床研修委員 会では研修後の進路、また同制度の現状を把握 することにより卒後研修における医療現場(特 に地域保健・医療)で直面する諸問題の改善に 役立てることを目的にアンケート調査を実施し た。アンケートの対象者は平成18年3月に研修 修了予定140名の研修医と単独型・管理型研修 病院の病院長・臨床研修担当責任者とし、アン ケートの一部の回収率は100%を当初から計画 し、第1回のアンケートは2月20日、第2回のア ンケートは4月4日に郵送し、その後、回答が 不十分な場合は、研修施設の研修担当責任者に 何度か電話し、5月の中頃までに終了した。そ の他、平成18年度研修医の入職状況も把握し ましたので加えて報告する。
Ⅰ)調査の概要
1.調査目的
- 1)研修医の研修後の進路。
- 2)新制度の現状を把握することによっ て卒後研修における医療現場(特に 地域保健・医療)に直面する諸問題 の改善に役立てる。
2.調査対象
- 1)単独型・管理型研修病院(15病院)
- 2)2年次研修医(140名)
3.調査内容
- 1)経年的な研修医の入職状況について
- 2)病院長・臨床研修担当責任者への2項目について
(1)研修修了医の進路について
(2)研修修了医の希望診療科目
- 研修医への16項目のアンケート調査
4.実施時期
平成18年2月20日(研修病院、研修医へ郵送)、 平成18年4月4日(研修病院へ郵送)、平成18年 5月電話での問い合わせ(研修病院研修担当責 任者へ)。
Ⅱ)調査結果
1.研修医の入職状況について
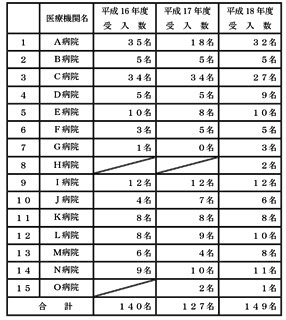
2.病院長・臨床研修担当責任者の回答2項目について
- 1)研修修了生の進路
県内へ残る方が約7割、県外へ行かれる方が約3割であった。
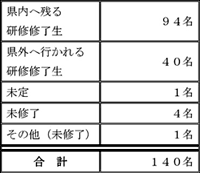
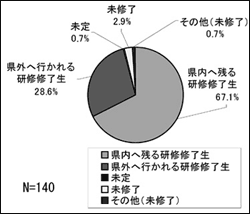
- 2)研修修了生の希望診療科目
内科が最も多く39名、次いで外科14 名、小児科12名、産業医10名、麻酔科8 名となっている。
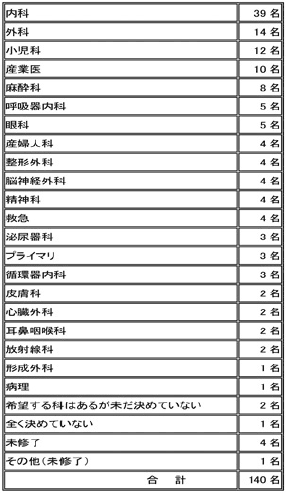
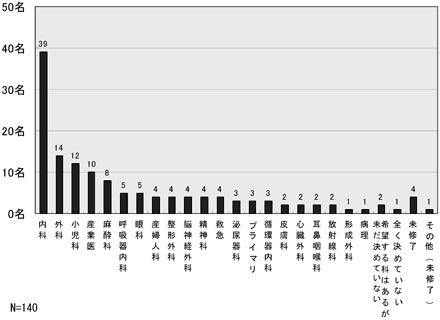
3.研修医への16項目のアンケート調査
1)回答者の概況
(1)集計対象者の内訳
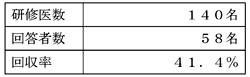
(2)性別
女性の割合は28%で、全体の約1/3を占めた。
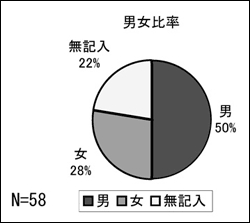
(3)出身大学別
県内出身大学が最も多い。
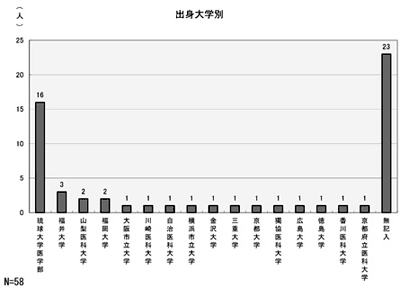
2)質問項目への回答集計結果
(1)現在、研修中の病院
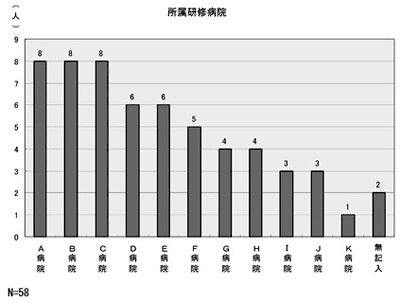
(2)研修先を選ぶ基準
主な選定基準は、カリキュラム内容の充実 (29%)、指導医の存在(24%)で合わせて、 5割超だった。
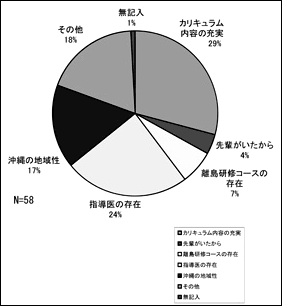
【その他の内容】
・病院・医局の雰囲気の良さ、働きやすそうかどうか
・1次〜3次救急初診を診るトレーニングができる
・群星・救急充実
・ロールモデルの存在
・これまでの実績
・症例数の豊富なところ
・出身大学
・宮城征四郎先生を尊敬していたから
・自分にとって適度な忙しさ
・奨学金制度
・指導医、先生方が充実しているとうわさで聞いた
・救急医療を実践できる
・救急医療に力を入れているから
・救急搬送数
・出身校だったから、マッチングにもれたから
・病院としての評判が良かったから
(3)研修内容・カリキュラム内容
非常に満足(16%)、ほぼ満足(63%)が約8 割を占めており、内容的には充実していると みられる。
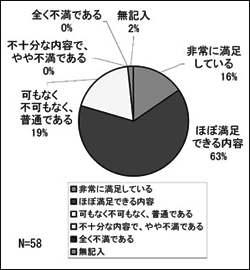
(4)スーパーローテートを経験した感想
専門分野の技術は初期研修の後に身につけれ ばよいので不安はないとの回答が65%を占めて おり、スーパーローテートを評価している。
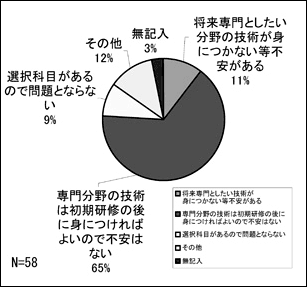
【その他の内容】
・小児科専攻なので成人を2年間診ても、その
後生かされないのではないかと思う。対象が
異なるので。
・自分の専門とする科の適・不適を事前に見極
められてよかったと思う
・意味のないところもある
・スーパーローテートよりはある程度しぼった
研修の方がいいのかも
・逆に選択の幅が狭くなって適応できない研修
医が増えると思う
・専門研修に遅れるという焦りはあるが、色々
みてみれて、経験しプラスになると思う
・今後、専門科にすすむのでその他の科の知識
・技術を身につけられたのはよかった
・一度働いた後に専門となる科を決められるの
でとても良いと思う
・専門へ進むのが遅れることに対する不安はあ
るが、やはりローテートは必要だと思うので
問題はない
・地域医療、精神科ではプログラムがまだしっ
かりしていない印象
(5)研修到達目標の達成状況の把握
8割以上が研修到達目標の達成状況を把握している。
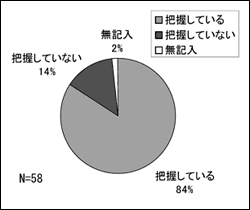
(6)指導医あるいは診療科の研修目標の設定
半数以上が、設定されているとの回答であっ たが、科によりけりとの意見が数名あった。
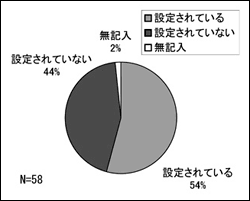
(7)指導医の指導内容に対する満足度
非常に満足(17%)、ほぼ満足(67%)で全 体的に指導内容に満足している。
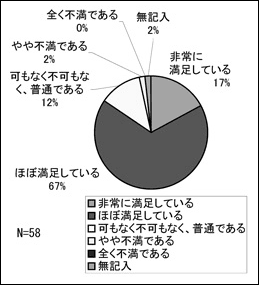
(8)指導医を評価する体制
8割以上が指導医を評価できる体制にある。
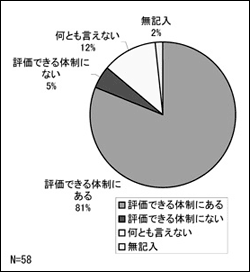
(9)主として「地域保健・医療」研修をした施設
最も多いのは診療所で59%、次いで、病院27% である。介護施設及び保健所は全体の10%だ った。
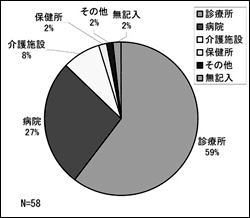
(10)質問(9)で診療所と回答した方へ、良かった 事、改善して欲しい事、その他、ご意見・ご要望等
・うちの離島研修はまともな指導医がいないの
で、まずそこからどうにかして欲しい。診療
所は、期間が短いので経過をみるには外来フ
ォローを1回くらいしか出来ず、不十分。消
化不良となる。
・急性期病院以外のあらゆる医療・介護施設や
サービスを見ることができ、医療・介護の全
体像が見渡せて良かった。
・大きな病院と異なり、検査機材などが限られ
た環境で行う医療は学ぶものは非常に大き
い。改善点は特になかった。
・熱心な指導医のもと外来診療の基本、地域医
師会の活動を学べた。2年目なのである程度
患者さんの診療をさせてもらいたかった
・開業について学べた。一人で診ることができ
なかった
・沖縄ならではの離島での研修は今後沖縄で医
師を続けるため、とても勉強になった。しか
し、研修期間の住居などは手配してもらいた
かった
・現在研修している病院とちがい、地域の病院
は非常にのんびりしていた。多くのことを吸
収したいこの時期に地域医療を研修する必要
があるのか疑問に思う
・離島研修をしたが、必要最低限の検査で診断
をつけなければならない状況は大変勉強にな
った。あとは、大病院へ紹介するタイミング
など、大病院ではできない研修ができた
・離島での日常診療がどんなものか、何が必要
なのか、などがわかった。離島研修期間の制
限が3ヶ月とあったが総合診療としてみるた
めには選択期間のうちいくらでも選べたほう
が腰をおちつけてできるため、その方がよか
った。
・往診等を通して地域を見る事ができた
・一般病院と違い、地域に密着した医療、病院
へ搬送するタイミングの難しさなど勉強にな
った
・診療所での研修期間は1〜2週間程度が適当と
思う。長すぎると時間をもてあそんでしまう。
・利点:島の医療や地域性を知ることができた
・どういった研修がいいかとか事前にプランを
ある程度立ててほしかった。
・離島・へき地の医療を経験できた事は大きな
財産となった
・非常に楽しかった。スーパーローテートした
知識が唯一使える場である
・とても有意義な研修でした
・往診があったのがよかった
・病院ではなく離島に行きたかった
・1ヶ月もいらないと思う
・先生がご多忙すぎて、教育・指導の面で少し
物足りない印象を受けた
・同病院でしか、地域医療がうけれなかった。
診療所をみたかった
・病院と掛け持ちであったため診療所研修の比
重が軽かった
・医師不足の状態でした
・地域医療の大切さが学べて良かった
・地域の中での診療所の役割を見ることができた
・相談できるオーベンが欲しかった
・のどかすぎて、初期研修には向かなかった
・沖縄にとって離島は切っても切れないもので
す。沖縄の人口の約1割の人が離島に住んでい
ることを考えれば離島医療をバックアップで
きる体制を整えていく必要があると考えます。
・本当の離島医療を実践できたことは非常に良
かった
・実際にたくさんの患者さんと接することがで
きた
・離島の診療所で、定期外来、慢性期ターミナ
ルの入院患者さん、介護医療、デイケア、救
急など総合診療を学べた
・患者さんの生活に触れる事ができた。診療所
でも救急に対応できる設備の充実を考えてほ
しい。
(11)現時点で専門分野を決めているか。また、そ の診療科。
約7割が、既に専門分野を決めており、進 路がある程度、明確化されている。
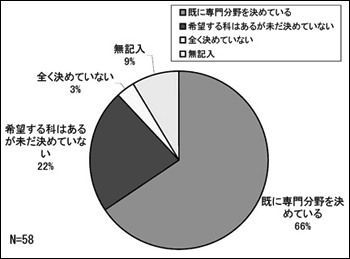
【希望診療科目別一覧】
内科が最も多いも、この時点では進路未決定者が多かった。
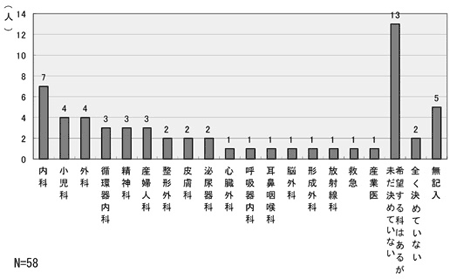
(12)研修後の進路
現在研修している臨床研修病院が最も多く24名であった。
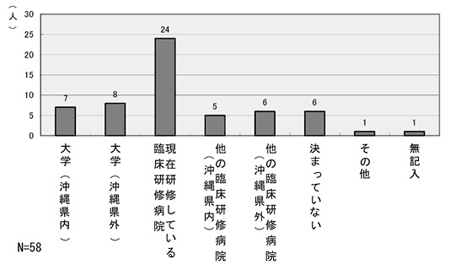
(13)沖縄の地域医療に対する興味
約7割強が、沖縄の地域医療に興味を持っ ている。
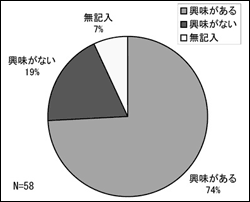
【興味があると答えた理由】
・“地域医療”という観念抜きでは急性期病院
に求められるもの、何をどこまですべきか見
えてこない。
・自分の地元なので
・若いうちに一度はいきたい
・診療所で研修し、その重要性と初期診療のお
もしろさに気付かされた
・臨床医としてその役割を求められていると思
うから
・将来的には沖縄で医療を続けていくので把握
しておきたい。
・実際に体験して楽しかった
・2年間沖縄で研修したから当然関心はある
・理想と実際のギャップがある
・何ヶ月か通してみると、何度か同じ人に会い
その人の背景・生活を通してみることができ
るから、地域特有のおもしろさ、背景が分か
ってよい。
・離島も好きだから
・離島等では、自分が技術を身につけたうえで
行くという前提で多くの症例が経験できると
考えるので
・離島(診療所)研修をし、こわさももちろん
経験したが、地域に根づいた医療の楽しさも
知ったから。また、必要性も痛感したから。
・離島医療
・離島という環境でもう一度働いてみたいと思う
・医療過疎(北部・離島)地域が多い
・離島が多く沖縄こそ地域医療の必要性を感じる
・地元出身のため
・生活習慣等まだまだ改善する点がたくさんある
・地域に密着した医療の現状を把握したい。自
分の知識・技術がどこまで通用するかためし
たい
・出身地に少しでも貢献したい
・友達は地域医療をみすえて研修しているし、
まわりがとても敏感である問題だから。(い
ずれ1人で診療所へ行くこと)
・もともと地域に根付いた開業医に興味を持っ
ており、これからはさらに予防医学が大切と
感じている為
・自分が宮古、伊良部で診療してきたため
・沖縄県出身なので
・沖縄出身であるため。離島医療を経験したため
・まだまだ人が足りない。自然がすばらしい。
(14)沖縄県内へ残りたい理由、県外へ行く理由。
(研修後の進路が決まっている方のみ)
□ 沖縄県内へ残りたい理由
・大阪出身だが、沖縄の方が暮らしやすい。派
閥もなく仕事もしやすい。
・現在の病院での研修をつづけたいため
・地元で医療を続けたい
・初期研修の内容に非常に満足しているため、
引き続き同じ病院で専門科の勉強をしたかっ
たから
・家庭がある。後期研修には案内でも良い施設
があると思う
・家族がいるから。病院の後期研修が充実して
いる
・那覇市立病院小児科の研修体制が充実してい
るため
・出身大学ということでシステムもしっていて
研修しやすい。県外病院を見学する機会がな
かった
・他県での医療も学びたい
・プライマリー、初期研修、専門にわかれすぎて
いない医療を学べる。看護師さんがやさしい。
・気候がよい、住みやすい
・当院での専門知識を深める事に希望がある。
群星プロジェクトで他病院にも行けるから。
・慣れた病院でもう少し専門をはっきりさせず
に研修したいから
・当院にて更に救急医療に関わりたい。後輩の
指導をしたい
・地域特有のものがあり、離島での医療に関わ
っていけるから自分が後期で指導を受けたい
指導医がいたから
・沖縄県が好きだから
・専門的技術を身につけるため
・なんとなく
・出身地で医療をしたい
・出身大学、研修をしたから
・外科研修を行う上で非常に良い病院であると
思うため
・県外にも研修先があるから
・将来のため
・実家が診療所なので、将来、沖縄に密着した
医療をしていきたい
・家族がいるし、地域性が好きだから
・私的な事情
・大学の義務
・自分の地元である沖縄の医療を活性化したい
から
・沖縄県で医療を行っていきたいから
・専門が決まっておらず、もうしばらく今の病
院でローテートしながら専門科を決めたいと
思ったから
・内地の病院よりも教育に対して熱心である。
Generalを大切と考えるDr.が多い。県立中
部が見本となって他病院も教育に関して頑張
っている。
・後期研修に充分対応できる体制がある
・今働いている病院が気に入っているから
・身体上の理由
・とくに理由なし
・基本的な研修を積むには良い環境と思う
□ 県外へ行く理由
・さらに専門領域をみがくには県外も必要と思う
・将来、地域の人に還元できるような技術と知
識を身につけたいため
・内地の医療も見ておきたい
・専門科で指導医、環境が整っているから
・県外出身者であるから。専門研修目的で希望
している病院がたまたま県外だったから
・親の体調が悪い
・地元に帰らなければならないから
・他県との地理的なつながりがないので、患者
数、疾患の種類が限られる
・昔住んでいたところ
・結婚する為
・実家があるため
・地元に帰る。専門研修を行いたい病院がある
(15)いわゆる後期研修(専門研修)へ望むこと。
約6割の方が、後期研修への要望を抱いて いる。
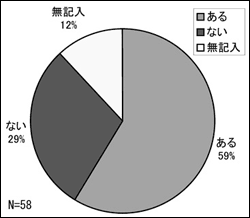
【後期研修(専門研修)へ望むこと】
・しっかりと教育してほしい。と同時に普通の
人のように休みもほしい。人間らしい生活を
したい。
・充実した指導内容、後期研修の数年が終わる
頃には、ある程度1人前の仕事ができるよう
でなければ後期研修の意義はない
・充実した研修内容
・自分は小児科希望なので、一般的な疾患を診
療できるようになりたい。その後専門性につ
いても考えていきたい。
・立場を明確にしてほしい、1年目と同等のポ
ジションなら遅い
・十分な指導体制
・その他の科へ進む可能性もあるので、そのベ
ースを築きたい。他の病院との風通しをよく
してほしい
・多くの症例を診たい(診せて欲しい)
・手術を多くしたい、専門医がとれるように
・研修機関同士の交流をしてもらいたい
・専門的なものだけではなく、あらゆる場面に
対応できるように多くの症例を経験させてほ
しい
・なるべくなら枠組みカリキュラムがしっかり
していないほうがよい。自由度が高いほうが
よい。
・認定施設である方が残りやすい
・専門に特化せず幅広く多くのことを学びたい
・内科・一般的な研修を望む。
・何年でここまでできるなどのはっきりしたこ
とを責任もって示してほしい。
・初期研修の延長と考えないで欲しい。きちん
とした役割の確立。
・早く専門研修をしたい
・専門技術の修得
・充実した指導
・希望する科をローテするなど
・早く専門知識を身につける様サポートして欲
しい
・より専門的技術知識と経験の習得
・技術的な事をしっかり身に付けたい
・まだ始まったばかりではあるが、内容がはっ
きりしない点の改善
・県立だけではなく、民間にも教育システムを
作る。
・専門分野に偏りすぎない研修
・県外、海外への交流をもっと盛んにしてほしい。
(16)その他、ご意見・要望等。
(医師会に対するご意見等でも構いません)
・あまりに上級医のフォローがありすぎると責
任感がなくなってしまい伸びないと思うが、
あまりに放りっぱなしだと事故につながる。
バランスが大事だと思う。中部での研修はそ
こそこバランスはとれていたと思うが、やは
り今後対象を小児にしようとしている私が成
人を2年間みて何が残るのか、どんなメリッ
トがあったのか今は分からない。変なクセを
覚えてしまったようでその点からは、ストレ
ート研修の方が良いと思った。
・離島医療をバックアップできる体制を是非作
って頂きたい。
・琉大では、特に色々な病院を研修する事が出
来、メリットではありますが、どこへ行って
も一人である事を感じ、最後の方では、多少
研修が苦痛と感じる事がありました。私とし
ては2年が限界だと感じました。研修医の精
神的サポートをするセンターなどがあると良
いと思います。
・研修の宣伝と中身が伴わないことがある
・研修医は医師会費などはらわなくても県医師
会の発表ができるようにしてほしい
・医師、看護師ともに患者数(重症度)に対し
て人数が少なく、みな過労気味である。長く
続けられる環境にない
・スーパーローテートは有意義であるが、全く
行く気のない科や将来関係ない科に1ヶ月と
研修するのは苦痛である。2週間など減らす
か、研修する科をしぼってもよいのかもしれ
ない。(研修先の指導体制によっては、全く
無駄になってしまうことがある)
Ⅲ)考察
研修医の県下の単独型・管理型研修病院への 入職状況は平成15年度81名に比べ平成16〜18 年度は46〜68名増加している。沖縄県は卒後 研修に関しては全国的に人気があるという現状 を示しており、熱心な指導医のもとに充実した 研修とその評価が行われんことを期待し、今後 とも現在の状況が継続して欲しいものだ。
さて、研修修了後の進路については、多くの 若い医師が県下で後期研修・専門研修を受け、 地域(離島・僻地も含め)で必要とされている 専門領域を選択し進んで行って欲しいと切に希 望するも、実際の希望診療科はどのような配置 になっているかについての関心が高いのと同時 に、地域医療にとってはとても重要な問題であ る。研修医140名中94名(67.1%)が県内に残 ることになっているが、未定・未修了者が5名 おり今後さらに増える可能性もあり、また、県 外から後期研修・専門研修を当県で希望する人 数については十分に把握していないが何人かい ると思われる。今年度の傾向が継続されれば、 10年後には、人口10万あたりの医師の最も充 実した県の一つになる可能性があるも、そのこ とは必ずしも医師の地域偏在や診療科偏在の解 決と直結するとは言いがたいし、実働医師数 (女医の増加や医師の高齢化等)と乖離するこ ともありうるが、医師総数が増すことは次のス テップの大きな飛躍と考える。
希望診療科を分析すると、小児科は140名中 12名(8.6%)、麻酔科は8名(5.7%)、産婦人科 は4名(2.9%)、脳神経外科は4名(2.9%)、放 射線科は2名(1.4%)、病理1名(0.7%)であ った(その内の約67.1%が県内に残ることにな る。一方、140名より未修了者等を除くと比率 が高くなる)。厚労省の平成18年5月の中間報 告(対象者: 2,154 名)によれば、小児科は 8.4%、麻酔科は6.4%、産婦人科は4.8%、脳神 経外科は1.7%、放射線科は3.1%、病理は0.5% であった。小児科や麻酔科は今年の傾向が数年 続けば明るい兆しが見えてくると思われるが、 産婦人科に関しては全国以上に厳しい状況にあ ることを示している。
研修内容・カリキュラム内容に関しては79% が満足できる内容であったことを示している。 スーパーローテートをし、将来の専門としたい 分野の技術が身につかないという不安を感じて いるのが11%、不安はないと答えていたのは 74%であった。研修到達目標は84%が把握して いると答え、自らの研修目標ははっきりしてい ることが示唆された。一方、指導医あるいは診 療科の研修目標は設定されているのが54%、設 定されてないと答えたのが44%で、ローテート する際、まだ充分な目標が示されてない段階に あると思われる。指導医の指導内容は84%が満 足しているとの回答を得た。研修医の立場か ら、指導医を評価する体制になっているかに対 して、81%があると答え、ないと答えたのは5% で、システムとして双方向性の評価ができる環 境にあることが示された。
「地域保健・医療」の研修を診療所で受けた のは59%で、当初想像したより少ない印象を受 けるが、初年度なので、単独型・管理型研修病 院と診療所との連携がスムーズに行われなかっ た背景も在るのかも知れないし、診療所での研 修医の指導に戸惑って手を上げなかったことも 一因かもしれない。診療所で研修したと回答し た研修医より多くの意見・要望があった。急性 期病院以外のあらゆる医療・介護施設やサービ スを見ることができて、医療・介護の全体像が 見渡せてよかった。熱心な指導医のもと外来診 療の基本や地域医師会活動を学べた。離島の診 療所で定期外来、慢性期ターミナルの入院患者 さん、介護医療、デイケア、救急などの総合診療 を学べた。離島研修をしたが、必要最低限の検 査で診断をつけなければならない状況は大変勉 強になり、あとは、大病院へ紹介するタイミン グなど、大病院ではできない研修ができ充実し ていたとの回答が多かったが、一方地域の病 院・診療所は非常にのんびりしていて、多くの ことを吸収したいこの時期に地域医療を研修す る必要があるか疑問に思う。先生が多忙すぎ て、教育・指導の面で少し物足りない印象を受 けたという意見もあった。診療所研修や離島で の研修は多くの体験と地域医療の理解も含めて 充分に価値ある研修であることを示している が、もう少し、指導医側(多忙な日々の診療の 中であるが)の熟練度の向上やスケジュール作 成の工夫が望まれる。
沖縄の地域医療に対して興味がありますかと の質問に対して、興味があると答えたのは74% で、興味がないと答えたのは19%であった。興 味があると答えた中で、離島が多く沖縄こそ地 域医療の必要性を感じる。離島という環境でも う一度働いてみたいと思う。離島(診療所)研 修をし、怖さももちろん経験したが、地域に根 付いた医療の楽しさを知り、また、必要性も痛 感したと記していた。多くの研修医が離島での 研修を経験し実りあるものであったと感じ、臨 床医として一人前になった時、再度離島での医 療に従事したいという気持ちが現れており、 「地域保健・医療」の研修は将来においても良 い結果を導くであろうとの印象を受けた。
後期研修・専門研修へ望むことはありますか の問いにあると答えたのは59%で、ないと答え たのは29%であった。示唆に富んだ意見がいっ ぱい網羅されておりご一読いただき、特に後期 研修・専門研修を実施されている病院の指導医 は参考にして欲しい。
最後に、2年間の研修の仕上げ(到達目標達 成のチェック等)や進路決定の時期、また後期研修・専門研修のための勤務病院を探さなけれ ばならない時期にアンケートに答えてくれた研 修医の皆さん、そして何度も連絡をしたにもか かわらず快く協力を頂いた各管理型研修病院の 院長・臨床研修担当責任者へ、紙面を借りて心 より感謝申し上げる。新医師臨床研修制度一期 生の若き医師達が後期研修・専門研修において も、あらゆる場面に対応できるように更に多く の症例を経験し、専門的技術と知識の向上を得 て、そして人格を涵養し素晴らしい医師として 成長することを念願する。
お知らせ
日医生涯教育協力講座
セミナー 脳・心血管疾患講座
日本医師会生涯教育講座5単位
日本内科学会認定内科専門医認定更新2単位
心不全薬物治療のこつ
〜急性期から慢性期まで、予後改善をめざして〜
日 時:平成18年7月21日(金)18:30〜21:30
場 所:沖縄コンベンションセンター 会議棟B 2階大会議室講演
<セミナー>
座長 中頭病院 ちばなクリニック循環器センター長 安里 浩亮
1.症例提示「ピモペンタンの併用でカテコラミンからの離脱に成功し、β遮断薬を増量しえた重症拡張型心筋症の一例」
琉球大学医学部循環系総合内科学 垣花 綾乃
2.症例提示「β−blockerが著効した慢性心不全の数例」
南部徳洲会病院 副院長 川満 克紀
3.症例提示「当科における慢性心不全の治療(心臓再同期療法)について」
浦添総合病院 循環器センター長 大城 康一
<基調講演>
座長 琉球大学医学部循環系総合内科学 教授 瀧下 修一
「急性及び慢性心不全の治療 update-Four“C”」
日本医科大学第一内科 教授 清野 精彦
共催:沖縄県医師会 日本医師会 第一製薬株式会社