受動喫煙の影響

常任理事 大山 朝賢(健康おきなわ2010推進委員会委員)
1.はじめに
受動喫煙防止条例が施行されて、禁煙が徐々 に浸透し、受動喫煙の影響にも関心が持たれ始 めた。本論は那覇第2合同庁舎で今年5月に行 われた、総務省沖縄行政評価事務所主催の「沖 縄地域さわやか行政サービス推進協議会」での 講演を中心に記述しました。演題は「受動喫煙 について」で、筆者のあとに「受動喫煙対策に 対するJTの取り組み状況等について」タバコ販 売会社の方が手短に話された。受動喫煙は能動 喫煙と同じような作用で人体に影響を及ぼすと 力説すれば、後者はそれを打ち消す文章で持論 を展開した。
2.ニコチンの濃度は副流煙の方が多い
能動喫煙による主流煙より副流煙に、ニコチ ン、タールや一酸化炭素といった有害物質がよ り多く含まれている。タバコの煙には4,000種 以上の科学物質が含まれ、そのうち発がん性が 確認されているものだけでも200種を超えると いう。気体と粒子相のそれぞれに含まれる代表 的物質の分布を見ると表1のごとくである。発 癌物質、心臓血管・呼吸器毒性物質はいずれを とっても副流煙により多く含まれ、発がん物質 であるジメチルニトロサミンは最大100倍、呼 吸器毒性物質であるアンモニアやホルムアルデ ヒドは最大50〜170倍が副流煙に含まれる1)、2)。
ニコチンの致死量は青酸カリと同等またはそ れ以上の毒性がある(表2)。しかし一本のたば こ(シガレット)の煙に含まれるニコチン量が 少ないため、短時間にうける影響はほとんどな い。葉タバコの誤食事故では酸性の胃液中での 吸収が不良なこと、ニコチン自体に催吐作用が あるため重篤な中毒の発症はまれである。しか しニコチンの浸出液(飲み残しのジュースの缶 に吸殻を入れた場合など)を摂取すると吸収が 早く重症中毒となる危険性がある3)。
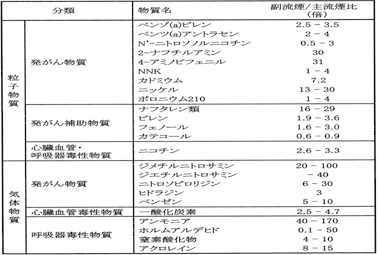
表1.タバコ煙の粒子物質と気体物質
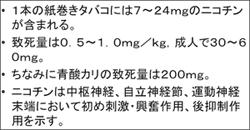
表2.タバコ(ニコチン)
3.受動喫煙による死亡
同室内で喫煙が行われると、部屋の広さや換 気にもよるが、一般的に喫煙者当人が吸収する 10分の1の煙を吸い込むことになると言われて います。WHO(世界保健機関)は平成13(`01) 年5月31日の禁煙デーに、「受動喫煙によって人 口100万人あたり年間147〜251人の死亡者が発 生する」との警告を発表した。これは分煙の徹 底した米国のデータを基にしたものであるが、 我が国の、国立がんセンターも「年に1万9000 人が受動喫煙死、うち肺がんによる死亡が1,000 〜2,000人」と発表している。これはなにも米国 のデータの追従ではなく、国立がんセンターの 平山が1981年と1984年に発表した、26万人の 17年にわたる追跡調査(平山コホート)を参考 にしている2)、4)。ちなみに喫煙と職場の受動喫煙 による呼吸機能低下と各国で発表されている受 動喫煙による肺がんのリスクを図1、2で示した。 ―― 職場で受動喫煙にさらされると軽喫煙と 同等の呼吸機能の低下がおこる(図1,FVC=努 力性肺活量、FEV1=努力性呼出での最初の1秒 量、FEF=最大呼気中間流量)。夫の喫煙量が増 えるほど非喫煙妻の肺がんのリスクが増える (図2−A,B)。受動喫煙による肺がんのリスク の上昇は腺がんで顕著(図2−C)。職場の喫煙 者が多いほど非喫煙者の肺がんリスクと腺がん リスクが上昇(図2−D)。幼少時の受動喫煙量 が多いほど成人後の肺がんリスク上昇(図2 E、 *は有意差あり)等――。
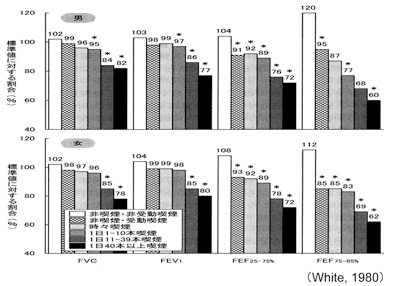
図1.喫煙と職場の受動喫煙による呼吸機能低下
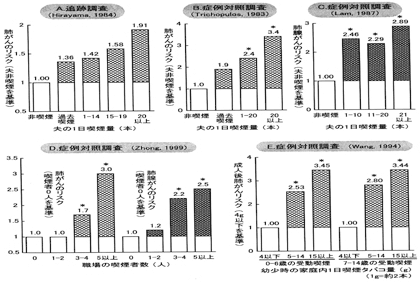
図2.受動喫煙による肺がんの発症を示す多数の証拠
4.考察
受動喫煙の内容は「純粋に医学的見地から」 との依頼者、総務省の「沖縄地域さわやか行政 サービス推進協議会」の希望であった。そこで 医師会作成のパンフレット「健康宣言〜たばこ 編〜」を配布し、胎児、新生児、幼児と話を展 開していった。各省庁の出先機関の方々には、 受動喫煙の防止を謳った健康増進法第25条の 施行(平成15年5月)以来、施設内禁煙や分煙 に尽力された経緯もあり熱心に聞いて頂いた。
わが国の、3大死因のトップを占めるがんの うち、男性は1位が肺がん、ついで胃、肝がん の順、女性は1位が胃がんついで大腸、肺がん の順位であるが肺癌の伸び率が著しい。ちなみ に沖縄県では男性は1位が肺、2位:胃、3位: 大腸、女性では1位が肺、2位:大腸、3位:胃 がんである。死因として本県では肺癌が男女と も飛びぬけているために、本土のマスコミから その理由について何回か質問をうけた。ひとま ず、日本復帰前は軍作業に従事されている男性 はほとんどが喫煙者だったことを挙げただけ で、それ以外はと聞かれると「不明」と答え た。本土の疫学的調査ではたばこ消費量の増加 と共に肺がんによる死亡も増加しているし、復 帰前の本県での一人当たりのたばこ消費量は本 土よりはるかに多い5)。そういえば昭和30〜40 年代、パスポートをもって本土で勉強していた 学生のお土産は値段が手頃で持ちやすいたばこ が多かった。
たばこの毒性や受動喫煙の被害等の研究報告 は「先進国」に多くみられる。しかし、我が国 には世界に誇れる「平山コホート」なる研究報 告が1981年に報告されている。これに対し日 本たばこ産業(JT)の報告では、平山コホート も含め、受動喫煙の肺がんのリスクに関して は、科学的に明らかな証拠が得られているとは 言えず、「受動喫煙が重大な疾病のリスクを伴 う」かどうかを結論付けるには、今後更なる研 究が必要と論じたてた。
受動喫煙の被害は能動喫煙に比較し発症頻度 は低いものの、能動喫煙と変わらない疾病を惹 起すると力説する筆者に、JTは以下のようなス ライドの文章で反論した。外国の有名な新聞、 The Washington Times, The New York Times, The Timesやその他のメディアから抜 粋したコメントを読み上げてインパクトを上手 に阻害していた。その文章の1例を示すと「世 界保健機関(WHO)は、受動喫煙と肺癌に関 連性がないことのみならず、保護的な効果さえ 持つことを示す研究の公評を保留した。この驚 くべき結果は、受動喫煙の健康リスクに関する 議論を巻き起こすこととなった。欧州7カ国12 センターに研究を委託したWHOは、研究結果 を公表せず、内部の報告書にその結果の要約の みを掲載した・・・」(表3)。JTの発表はすべ てこのスタイルで、医師の質問を軽くいなす準 備をされた周到な文章構成であった。
生まれながらに煙の好きなヒトは見たことが ない。焚き火で好んで煙のなかに居るヒトも見 たことがない。公害が盛んに論じられる今日、受 動喫煙の被害についてはこれまで以上の医学の 研究を待たねば確証は獲られないのであろうか。
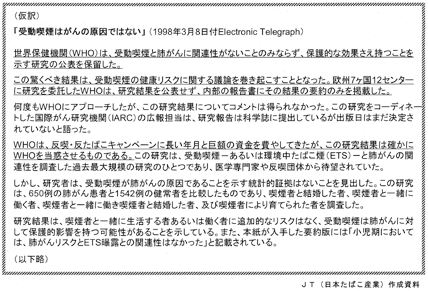
表3.受動喫煙研究に関する記事(3)(Electronic Telegraph)
参考文献
1) 沖縄県医師会 編:パンフレット「健康宣言〜たばこ編〜」
2) 加濃正人 編:タバコ病辞典、実践社出版
3) 和田 攻 :中毒診療実践ガイド 文光堂出版
4)Hirayama T : Br Med J (Clin Res Ed)282(6259):183−185
5) 沖縄県医師会報 平成16年8月号