私の柔道回想録

嘉陽外科 嘉陽 宗吉
齢80 過ぎとなり、自分が歩んで来た今まで の人生を静かに振り返ってみると、職業として の医師の外に何をして生きて来たであろうか、 趣味の面で人生に些かの潤いがあったであろう か、静かに胸に手を当てて考えても、何もない。 全く無趣味極まる人生であったと悔やまれてな らない。然し、ただ一つだけはある。それは柔 道だ。それで柔道と私との関係について子供や 孫達に話しておく積りで思い出すままに書いて みたいとおもう。
(小学校時代)
周囲にラジオ、テレビも無い時代で、柔道に 関する情報は皆無で、例えあったとしても子供 の時は柔道についての知識はゼロで何の興味も 無かった。子供同志で相撲をとって遊ぶのが関 の山であった。
(旧制中学校時代)大阪府立市岡(いちおか)中学校
旧制中学校では正課の武道として剣道、柔道 があり、何れかを選ばねばならなかった。剣道 用具を揃えるには費用がかかるので、私は柔道 を選らんだ。
或る日、授業時間に先生が「嘉陽、あとで教 官室に来るように。」と言われた。私は(授業 態度が悪かったのかな、真面目に受けた積りだ が。)と心配して後刻、恐る恐る教官室を訪ね ると、「嘉陽は外の運動部に入っているのか?」、 「いいえ」、「それなら柔道部にはいらんか、そ して先輩たちのように体を鍛えて強くなれ。」 「はい、入れてください。」で一件落着。即日、 柔道部に入った。当時、上級生には4 年生、5年生で二段、三段がいて憧れていた。「ようし、 何時かは俺も!」と言う気があった。しかし、(な ぜ先生は俺を柔道部に誘ったんだろう?、ひょ っとしたら俺、才能があるんと違うかな?)と 自惚れたが悪い気はしなかった。
翌日から練習に身を入れた。しかし、この時 期に先生が背負投げを教えてくれたのが最期の 教えとなった。それは先生が間もなく出征され、 すぐに戦死されたからである。
この頃から日本は敗戦の気配が次第に濃くな り中学の低学年にも学徒動員令が出て、我々も 軍需工場に引き出され、勉強やスポーツ所では なくなった。これが中学3 年の夏まで続いて敗 戦となった。敗戦後は生活難で柔道どころでは なかった。中学5 年を卒業するまで柔道とは無 縁の生活であった。
(旧制高校時代)第七高等学校(通称七高、鹿児島にあった)
この時代は米軍の命令で柔道、剣道は禁止さ れていた。しかし、七高では同好の士が集まっ て鹿児島市内のお寺で密かに練習(畳を立てて、 外部からは見えないように、声を出さないよう に)していた。住職が柔道好きで協力してくれ た。しかし試合も無く、大した成果も無かった。
(大學時代)名古屋大學医学部
その頃、米軍による学校柔道禁止令は解かれた。
私は大學の寮にいたが、某日、医学部の上級 生3 名が訪ねてきて、「名大に柔道部を復活し ようと運動している、君も参加しないか。」と 言う。私は即座にOK した。某日、集まった顔 触れは名大の全学部からなり、即ち法学、文学、 経済、教育、農学、理学、工学、医学、等々多 彩で、何れも過去に多少とも柔道の経験があり、 「柔道大好き」の連中ばかりであった。
柔道部の行事として各種の試合があった。私 の戦歴について述べると、多くの勝ち負けがあ ったが概して勝ちの方が多かったと思う。
(1)七帝戦
これは旧帝国大學即ち北海道、東北、東京、 名古屋、京都、大阪、九州の7 大學間の試合で 毎年、夏休みに各大學持ち回りで行われた。こ れは7 大學の学生の柔道のレベルが似通ってい たので行われていた。
この七帝戦で私は大いに活躍した。他大學と の試合で私はよく背負投げで4 〜 5 人抜きをや った。この事は大会終了後の大会長総評で褒め られた。
(2)東海地区学生柔道大会
始めの団体戦で名大は私が頑張って5 人抜き をしたが敗退した。次いで個人戦で私は名大代 表で出た。対戦相手の籤引きで最初に巨漢の優 勝候補NO.1 のI 選手(身長190 センチ余、体 重110 キロ余)と当ってしまった。「えらい事 になった、まるで電柱と試合をするようなもの だ。勝負はもう始めから判っているから、俺は 棄権する。」と言うと名大の先輩達が「恥ずか しい棄権は絶対にするな!担架は用意するから 絶対に出ろ!」。との厳命。そこで私は腹を決 めて試合に出た。審判の「始め!」の合図で私 は相手の襟をとると同時に背負を掛けました、 私は心中に(どうせ負けるんなら一回くらい技 を掛けるゼスチャーをやらんと格好が悪い。) くらいの気持ちであった。所が意外や相手の足 先が畳から浮きかけた感じがしたので、驚いた のは私である。まさかと思ったが私はこの機を 逃さず担いだ相手を畳に投げつけた。ズシンと 大きな音をたてて相手は畳に落ちた。相手もま さかの、よもやの展開に仰天したことであろう。 会場は騒然となった。そして試合場から退場し た時に相手選手が監督からこっぴどく叱られて いるのが垣間見えた。これらの事は一瞬の事で あったが私の脳裏には鮮明に焼きついている。 この一件があってから私は俄然、気が大きくな り、実力以上の勝負をして二段、三段の相手を 次々に倒して決勝戦まで破竹の勢いで勝ち進ん だ。しかし決勝戦では五段の相手に寝技(押さ え込み)で敗れた。後で聞く所によればこの五段は某大學の正規の学生ではなく聴講生で、家 では一家で柔道場を経営しているとの事であっ た。言わばプロであった。道理で学生にしては 強すぎると納得した。
(3)その他の試合
大學在学中、アメリカ軍との試合では物凄い 巨漢(恐らく130 キロ以上はあった)と対戦し たことがあるが、(こんなのに押さえ込まれた ら息もできんわい)と思い、試合始めの合図と 同時に一気に背負投をかけたら見事に決まり、 アメリカ軍チームは唖然としていた。
柔道余話
(1)大學卒業後の某日、新幹線に乗っていると、 通路を何回も往復し、私の近くに来ると、ゆっ くり歩く男がいる。始めは気にしなかったが、 やがて注意して見るとはっと気が付いた(H 大 のI 君だ!)と同時に相手も(名大の嘉陽さん でしょう!)と来た。それからはビールと茶菓 子を買い、往時を偲びながら寸時歓談した。I 君とはかつて七帝戦で戦ったことがある。
(2)私は卒業後の或る時期に船医をしていた。 乗っていた船が定期検査のため、岡山県の造船 所にドック入りした事がある。或る時、私は暇 なので船の周りをぶらぶらしていたら、技術者 らしい人がじーっと私を見つめるので私は「此 処に居てはいかんのかな」と立ち去ろうすると、 「失礼ですが名大の嘉陽さんと違いますか?」 と声をかけてきた。よくよく見るとはっと思い 出した。ヘルメットをかぶっていたので始めは よく解らなかったがH 大のN 君だ。彼とも大戦 した覚えがある。彼の仕事が終ってから近くの 料亭でご馳走になり、往時を思い出して暫し歓 談した。愉快であった。
なんで柔道か??わからない??
私は中学校入学以来、柔道には随分、時間を 費やしてきた。柔道着は汗臭いし(年中、殊に 夏は)、冬には裸では冷たいし、ことに氷の張 る名古屋の冬はひどかった、震えあがった、愉快であった思い出は無い。練習はきついし、疲 れるし、少しも面白くない。殊に、七帝戦前の 合宿練習はきつかった、夜は階段を四つん這い でないと昇れなかった。お箸も重くて食事しに くかった。それでも(練習の量のみが勝敗を決 する)との信念で飽きもせずに続けてきたのだ ろう。今、思えば我ながら不思議である。よく よく、畳に投げられても反射的に起き上がり、 痛くないこと、そして肉体を酷使することに快 感を覚えたのかもしれない。
何で背負い投げか?
中学に入学した時に始めて習ったのが背負い 投げで、それで戦前の柔道はおわり。柔道の投 げ技は沢山あるが、また練習もしたが、試合の 時、ここ一番となると、どうしても背負投げが 反射的に出てしまう。
学生柔道仲間では(名大の嘉陽の背負投げは要注意)とマークされた。
昔の柔道仲間が未だに柔道とは縁が切れず、 歳をとっても時折、道場に顔出ししているのは、 まさに「雀、百まで踊り忘れず。」の類であろ うが、判るような気がする。
段位について
柔道をしていた人はよく何段かと問われるこ とが多い、私は初段である。しかし学生時代の 最盛期には三段か四段の実力はあったと思って いる。多くの試合では三段には負けなかった、 四段、五段には勝ったり負けたりした。
学生の始めの頃はずっと白帯で試合に出てい た。その理由は(段位は時期、体力によって変 わるものだ。永久不変ではないから取らなくと もよい。)と考えていた。段位を取るには費用 もかかるし、それよりはビフテキでも食べたほ うが強くなると思った。それで試合には何時も 白帯で出ていた。そして大抵、勝つのでしまいには(白帯の帝王)と新聞に書きたてられた。
ところが後日、学生柔道連盟から「実力相応 の黒帯を締めて試合に出るように。」と注意を 受けた。それで昇段試合を受けて一回で初段を 取った。以後は黒帯を締めて試合に出るように なった。
大學卒業後、鳴門病院に勤務している時は近 くの鳴門高校に出かけて練習した。沖縄に帰っ てからは赤十字病院に勤めながら、近くにある 警察本部の道場に行って練習していた。
開業してからは何処の団体にも所属しないの で試合には出られず、次第に柔道から足は遠のいた。
その後は沖縄相撲に転向したがこれは後日に話そう。
今は体力も衰えて血気盛んだった面影は全く ない。歳には勝てず寂しい限りである。
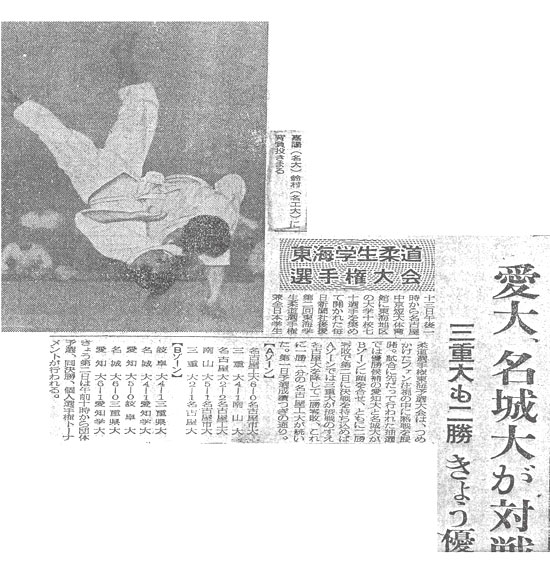
1953 年に私が試合にでた時の毎日新聞スナップ写真