第55回社会保険指導者講習会
〜「画像診断update −検査の組み立てから診断まで」〜

琉球大学大学院医学研究科放射線診断治療学講座助教
與儀 彰
平成23 年10 月13 日(木)〜 14 日(金)の 2 日間、日本医師会大講堂にて「画像診断 update −検査の組み立てから診断まで」をテー マに第55 回社会保険指導者講習会が開催され た。私は沖縄県医師会を代表して参加したが、 各領域において第一線でご活躍されている先生 方を講師として招いており、放射線科診断医で ある私にとっても勉強になる会であった。
以下、それぞれの領域ごとに概要を報告する。
●PET-CT
PET はpositron emission tomography の略 語で、陽電子放出断層造影を意味する。PET-CT を有する施設は増加しており、2009 年の時 点で264 施設に上る。2010 年の診療報酬改訂 にて悪性腫瘍の適用が拡大し、早期胃癌を除く 悪性腫瘍に対してFDG-PET を施行出来るよう になった。FDG-PET が診療に与えるインパク トは大きい。病期診断がより正確になるのみな らず、治療効果判定や予後予測についても研究 が進んでいる。特に乳癌や悪性リンパ腫の治療 効果判定に対するFDG-PET の有用性は高い。
頭頸部癌においては、特に重複癌の検出に有 用である。食道癌は生理的集積が少ないため、 FDG-PET にて発見されやすい。
肺癌は病気診断および再発診断に有用である が、1cm 以下の結節の良悪性の鑑別は困難とさ れる。またN2 診断に有用だが、1cm 未満のリ ンパ節の診断成績にばらつきがある。
乳癌は、局所診断はマンモグラフィやエコー 検査には及ばないが、他臓器転移や術後再発の 診断には有用である。また、上述のように術前 化学療法の効果判定にも有用で、両者は2008 年度版乳がん診療ガイドラインにおいても推奨 グレードはB に設定されている。骨転移にも有 用であるが、造骨型は骨シンチの方が検出率は 高い。
胃癌に対してはFDG-PET の有用性はやや低 く、スキルス・印環細胞癌でのFDG の集積は 低い。
胆嚢癌は内腔型や塊状型は高集積になるのに 対して、壁肥厚型は検出困難である。また、し ばしば問題となる黄色肉芽腫性胆嚢との鑑別 は、FDG-PET でも難しい。
直腸は炎症によってFDG が集積するため、 直腸癌の診断はやや難しいことがある。しかし 再発腫瘍の検出感度は高く、有用である。
膵癌にはFDG はよく取り込まれるが、糖尿病合併例では集積が低下することがある。
子宮癌にはFDG は良好に集積し、播種、遠 隔転移、再発腫瘍の検出にはCT やMRI よりも 有用である。
卵巣癌に関しては、原発巣の診断精度はあま り高くはなく、これは正常卵巣の排卵時期から 黄体形成期に生理的集積がみられることに拠 る。ただし閉経後の卵巣にFDG が集積した場 合は、癌を疑うべきである。また播種の検出に 関してはCT よりも有用性が高い。
●中枢神経・頭頸部
認知症の画像診断の目的は、硬膜下血腫、腫 瘍、水痘症などの器質的疾患を除外すること、 血管性認知症の診断、アルツハイマー型認知症 (AD)と他の変性性認知症の鑑別、AD の早期 診断、である。変性性認知症にはAD 以外にも 前頭側頭型認知症、レビー小体型認知症など様々な病型があり、それぞれ特徴的な画像所見 を呈する。正しい診断には頭部MRI や脳血流 SPECT での精査が必要であり、画像統計解析 は主として核医学検査で行われていたが、近年 ではアルツハイマー病診断支援ソフト (VSRAD)も日常臨床で活用され、実績を挙げ ている。
脳卒中の症例において、まずはCT で脳出血 を除外することが重要である。続いて急性期脳 梗塞の診断だが、2005 年10 月のrt-PA による 血栓溶解療法の認可に代表される治療法の進歩 により、急性期脳梗塞の早期診断が非常に重要 である。急性期脳梗塞の診断は主に拡散強調像 に拠るが、単純CT でのいわゆる“early CT sign”も診断に有用である。ただし、early CT sign を同定するには一定のトレーニングが必要 で、また各施設の正常頭部CT 像にも慣れてお かなければならない。MELT Japan のHP では early CT sign の画像が掲載されているため、 是非ご覧頂きたい。
めまいに対しては、米国放射線科専門医会が 検査の妥当性尺度(ACR appropriateness Criteria)を報告している。良性等位性めまい は画像で異常を認めることは稀であるが、メニ エル病では前庭水管や内リンパ嚢の異常を評価 するため、あるいは炎症や腫瘍の合併を除外す るために画像診断は有用である。細菌性迷路炎 は迷路の閉塞による液体信号の消失を認め、内 耳道内あるいは小脳橋角部病変は画像で容易に 検出できる。これらを踏まえ、めまいの症例で は、内耳道を含めた造影MRI を行うことが最 も妥当性が高いと結論づけている。ただし、中 枢性めまいと末梢性めまいとでは検査内容が異 なるため、可能な限りこれらを区別してもらう ことが重要である。
●呼吸器
HRCT で肺野すりガラス影を呈する疾患とし て、真菌症(侵襲性アスペルギルス症、ムコー ル症など)や敗血症性塞栓症、抗酸菌症(結 核、非結核性抗酸菌症)などの感染性疾患、原 発性肺癌(高分化型腺癌、扁平上皮癌)、転移 性肺癌(血管肉腫、絨毛上皮癌、骨肉腫など)、 リンパ増殖性疾患などの腫瘍性病変、非感染性 非腫瘍性病変としてはWegener 肉芽腫症や好 酸球症、器質化肺炎がある。感染性疾患や非感 染性非腫瘍性疾患は出血や炎症を、腫瘍性病変 は肺胞壁に沿う腫瘍の進展や出血を反映する。 出血を示唆する所見としてCT halo sign が特 徴的で、真菌症や敗血症性塞栓症などでよくみ られるが、腫瘍からの出血でも認められる。こ れらを鑑別していく際は、免疫能が正常か異常 か、単発病変か多発病変かを判断することが有 用である。
高分化型腺癌と器質化肺炎は時として鑑別が 難しいが、高分化型腺癌は癌自体が線維化をし て縮んでいくため、辺縁が不整で、周囲の気管 支や血管を巻き込むようになる。2cm 以下の小 型腺癌の分類と進展に関する仮説として野口分 類が有名で、純粋なすりガラス影を呈する現局 性の細気管支肺胞上皮癌(BAC)からBAC + 肺胞虚脱、BAC +線維化とすすむにつれて内 部にconsolidation が増加していくとされる。高 分化型腺癌において、HRCT におけるGGO の 割合を50 %で2 群に分けた場合、予後に有意 差がみられた、という報告(Fig.1)もある。こ のほか、内部の石灰化や脂肪の有無も高分化型 腺癌と器質化肺炎の鑑別に有用である。ただ し、肺気腫やブラ肺に生じた肺癌の進展や形態 は通常の判断基準が適用できないため、いかな る場合でも肺癌の可能性は念頭に置いておくべ きである。pure GGO を認めた場合は、出来る限り薄いスライスでのHRCT にて病変の性状を 確認し、1 〜 3 ヶ月程度の経過観察をおいて増 大を認めた際、BAL やTBLB または生検を検 討する必要がある。
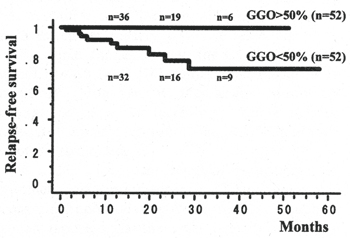
Fig.1 高分化型腺癌におけるHRCT 所見と予後
単純X 線写真にて肺門や縦隔の拡大を認めた 場合は、CT での精査が必要である。単純CT にて縦隔や肺門部に占拠性病変を認めた場合 は、可能な限り造影CT を施行して質的診断を 行う。ヨード造影剤が不可能な場合はMRI も 有用である。縦隔腫瘤は縦隔の位置(上縦隔、 前縦隔、中縦隔、後縦隔)、性状(嚢胞性、充 実性)である程度の鑑別が可能である。心外膜 脂肪や腕頭動脈の蛇行、食道裂孔ヘルニアは縦 隔腫瘤と間違われやすく、注意が必要である。
最初の胸部単純X 線写真では、縦隔腫瘤を指 摘することはしばしば困難なこともある。また 肺門部肺癌もしばしば見落とされるが、無気肺 による肺葉の容量減少で生じた葉間線・横隔 膜、肺内血管の偏位を見逃さないことが重要で ある。
●心臓・血管
胸部単純X 線写真にて、心血管影は従来右2 弓、左4 弓からなるとされてきたが、外側へ凸 という意味で弓を作るのは右第2 弓(右房)、 左第1 弓(大動脈弓)、左第4 弓(左室)だけ である。よってこの名称は国際的には通用しな い。新しい呼び方として、右縁上部(上大静 脈)、右縁下部(右房)、左縁上部(大動脈弓) に左縁中部(肺動脈および左心耳)、左縁下部 (左室)がある。
心・縦隔影の拡大を来す疾患には心拡大、胸 腺、心膜液貯留、縦隔病変、縦隔型肺癌、リン パ節腫大、胸膜腫瘍、縦隔側胸水、大動脈およ び分枝動脈の病変、静脈系の病変がある。これ らの所見はしばしばオーバーラップするが、心 膜液貯留の診断にはepicardial fat pad sign が 有用である。
心・縦隔陰影の偏位をきたすものとして胸 水、気胸、無気肺、縦隔・肺腫瘍、漏斗胸、胸 椎側湾、straight back syndrome、右胸心、 Scimitar 症候群、肺形成不全・無形性、肺動脈 近位部欠損、先天性心膜欠損などがある。 Scimitar 症候群はScimitar sign と呼ばれる上 下方向の線状影、心臓の右方偏位、右肺低形成 が特徴である。また左側心膜欠損では、左側臥 位での心陰影の著しい左方偏位が特徴である。
心大血管の石灰化を来す疾患として、収縮性 心膜炎、心筋梗塞、心室瘤、心筋内腫瘍、リウ マチによる心内膜石灰化、心腔内血栓や心腔内 腫瘍の内部石灰化、動脈硬化や梅毒、川崎病、 動脈管開存などがある。
心右縁上部の膨隆を来す病態には、腕頭動脈 の蛇行、大動脈弁狭窄、総肺静脈還流異常があ る。上縦隔腫瘍でも同様の変化を来すことがあ る。心右縁下部の膨隆を来す疾患として Ebstein 奇形、大動脈弓部の膨隆には大動脈 瘤、。肺動脈弓の膨隆には心房中隔欠損による 肺高血圧症、肺動脈弁狭窄症、左上大静脈遺 残、修正大血管転位がある。これらの部位の膨 隆は、腫瘍性病変でも認められることがあり、 その場合はhilum overlay sign の有無が鑑別に 有用である。胸部下行大動脈の膨隆を来す疾患 には僧帽弁狭窄症や左房粘液腫がある。これら は左房拡大が原因で、肺高血圧に伴うkerley's B line、肺胞性肺水腫も認められる。胸部下行 大動脈の膨隆を来す疾患としては、動脈瘤、急 性期高安動脈炎、後縦隔腫瘍などがある。
近年はCT やMRI の発達が目覚ましいが、そ れでも胸部単純X 線写真には全体が外観でき、 簡便で安価で、何より低被曝であるというメリ ットがある。自然放射線による被曝が2.4mSv/ 年であるに対して、胸部単純X 線写真での被曝 は0.1mSv/枚である。よってスクリーニングや 経過観察には最適で、今後も重要な役割を担う。
●乳房
近年、我が国での乳癌の罹患率は上昇傾向を たどり、女性の罹患率は一位である。これに伴 い乳癌による死亡率も依然上昇しているが、こ れに対しアメリカやイギリスでは乳癌による死 亡率は低下しつつある(Fig.2)。この違いは乳 癌検診率の差にあると考えられる。乳癌を予防することは現時点では不可能なので、早期発見 に努めていくことが重要である。
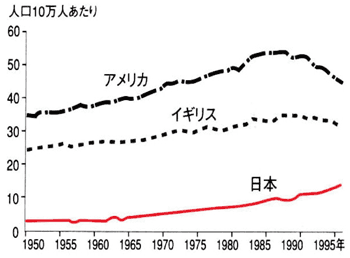
Fig.2 各国の乳癌死亡率
乳癌に伴う症状、所見として、しこり、乳頭 分泌、乳房痛がある。しこりは乳癌の重要な所 見であるが、小さいしこりや深い位置にあるし こり、厚い乳腺や皮下脂肪に覆われたしこりは 触知が難しい。また月経周期にあわせてしこり を生じることもあるので、医師に診察してもら うことが重要である。
乳癌の検査には触診の他にマンモグラフィ、 超音波検査がある。マンモグラフィは1 回の被 曝線量が約1 〜 2mSv で、年間自然放射線量 2.4mSv よりも低く、侵襲は低い。圧迫を加え ることで乳腺などの重なりが減り、診断しやす い画像が得られる。さらに、石灰化を検索する ことでしこりを作らない乳癌の発見が可能では あるが、乳腺量の多い人では発見感度が低下す る欠点がある。これに対し、超音波検査は被曝 がなく乳腺量が多いほうが発見が容易な点が特 徴である。しかし、術者の技量に大きく依存 し、脂肪性乳房での腫瘤の検索、腫瘤を形成し ない乳癌の検索は不得手である。この二つの検 査に触診を併せ、相補的に検査を組み立ててい くことが重要である。また、検査を継続して受 けさせることも重要である。
細胞診や針生検で乳癌と診断された場合は、 全身CT による転移巣の検索、MRI による乳癌 の広がり診断や対側乳房の病変検索を行うこと が重要である。両者はまた、両側乳房を同時に 検査することが可能であるメリットもある。 MRI は術前化学療法の効果判定にも有用である。
●骨・関節・軟部・脊椎
軟部腫瘤の鑑別は、石灰化の有無や隣接骨へ の影響、MRI での信号パターンが重要な鍵とな る。石灰化を伴う良性軟部腫瘍には海綿状血管 腫、陳旧性神経鞘腫、深在性軟部組織平滑筋 腫、骨外骨腫、傍骨性(骨化性)脂肪腫などが あり、石灰化のパターンでもある程度の良悪性 の鑑別がつく。またMRI において多くの腫瘍 はT1 強調像(T1WI)で低信号、T2 強調像 (T2WI)で高信号を呈する傾向にあるが、脂肪 や亜急性期の血腫、メラニン、蛋白濃度の高い 液体はT1WI で高信号を呈し、またT2WI で緻 密な膠原線維やヘモジデリンは低信号を呈す る。これらを同定することで、腫瘍の鑑別がつ くようになる。骨破壊のパターンとしては地図 状骨破壊、虫食い状骨破壊、浸透状骨破壊があ り、地図状骨破壊には硬化縁を伴うもの、辺縁 明瞭で膨張性発育を呈するものや、辺縁不明瞭 なものがある。これらの所見は少々のオーバー ラップがあるものの良悪性の判断に不可欠で、 各疾患の特徴的所見であることもある
骨粗鬆症の早期診断には骨密度測定が必要で ある。原因として閉経後のエストロゲンやテス トステロン不足、加齢性変化、ステロイドなど の医薬品や内分泌疾患に伴う続発性骨粗鬆症が ある。骨粗鬆症性骨折は高齢女性に好発し、仙 骨に多い。典型的には、骨シンチやMRI にて 両側仙腸関節と仙骨の異常による“ホンダサイ ン”を呈する。
腰痛に対するアプローチで重要なことは初診 時に臨床所見から診断トリアージを行うこと で、脊椎腫瘍や外傷・骨折、馬尾症候群、感染 性・炎症性脊椎炎などのレッドフラグ疾患を鑑 別することである。レッドフラグのない急性腰 痛に対しては、基本的にはMRI をせずに経過観 察をする。ただしレッドフラグ病変による腰痛 症は2 %以下に過ぎず、神経根症状を伴う腰痛 も10 %以下で、9 割弱が非特異的腰痛とされ る。神経根症状を伴う腰痛に対して、慢性症例 では術式検討を前提としてMRI は推奨される。 しかし進行性でない急性症例では推奨されない。これは、無症候性の人でも退行性変化など 同様の所見を認めることが多いためである。ま た非特異的腰痛に対しては、CT やMRI 検査は 患者の予後改善に貢献市内ばかりか不必要な治 療に繋がるおそれがあるため、MRI は推奨され ない。腰痛を訴える患者は非常に多く、多彩な 病態がこれに関与する。不必要な画像検査を減 らすためにも、最初のトリアージが重要である。
●CT ・MRI 検査・造影剤の適応と副作用
造影剤は基本的に診断薬であって治療薬では ない。そのため重篤な、時に軽度であっても副 作用が出現したときに患者の納得が得られない 場合が多い。また副作用の種類は多彩で時に重 篤に陥ることがあり、ある程度のリスクファク ターが分かってはいても予知することは容易で はない。よって造影剤の使用に関しては慎重な 検討が必要であるが、多くの施設では造影剤の 使用は主治医の判断に委ねられているのが現状 で、そして各診療科の医師に造影剤の危険性が 認知されているとは言い難い。
造影検査のリスクマネージメントに重要な要 素として、1)CT やMRI における造影検査の適 応の検討、2)造影検査依頼時の問診、説明と同 意、3)副作用の種類の把握、4)副作用の注意と 対処法、5)日常の準備、定期的な準備、が挙げられる。
1)において、造影検査の目的は病変の描出能 の向上、病変の質的診断や広がり診断がある。 これらは、例えば肝細胞癌においては造影剤が 必須であるが、肺癌においては必要ではない。 また肺門リンパ節転移の検索には造影剤が必要 なこともあるが、縦隔リンパ節の確認は単純 CT で十分である。疾患によって造影剤の適応 は細かく分かれており、そういう点で画像診断 ガイドラインの整備が必要である。少なくとも 造影検査を行う時には、造影することによって 得られる情報(利益)が、造影のリスクより高 い場合に施行されなければならない。
2)において、造影剤を使用する際に問診を行 い、使用上の危険性と利益の説明を行い、同意 を得ることは重要である。その際、薬剤使用の 適応や投与量、投与に際しての注意は添付文書 から把握しておく必要がある。
3)の副作用の種類は、急性の副作用(Fig.3) と遅発性の副作用(Fig.4)に大別される。前 者は造影剤投与中ないし投与直後に生じ、重篤 な症状を来しうる。後者は投与後一週間程度で 生じ、ほとんど生命の危険性はない。2005 年 の鳴海らの報告によると、非イオン性ヨード造 影剤の重度副作用の発現率は0.04 %(2920 例)、ガドリニウム造影剤では0.0065 %(480 例)であった。また死亡例は、前者は0.0003 % (185例)、後者は0.0001 %(11 例)であり、重 度副作用の発現率は決して高くない。
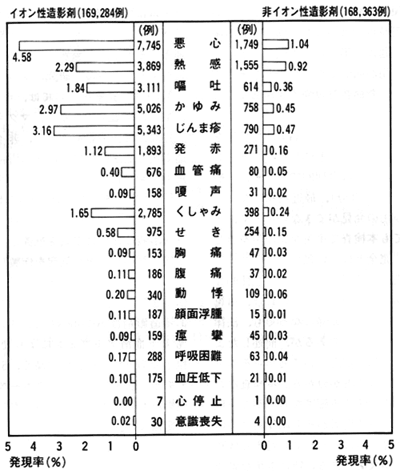
Fig.3 ヨード造影剤の急性副作用の種類と頻度
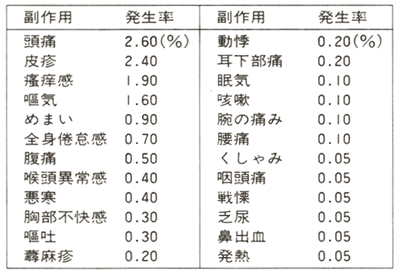
Fig.4 ヨード造影剤の遅発性副作用の種類と頻度
4)において重要なのは造影検査オーダー時に 造影検査が診療に必要であること、副作用の危 険性と種類、頻度について話し、副作用発生時 は即座に対処を行うことをしっかり説明するこ とである。また気管支喘息や腎機能低下などリ スクファクターの有無についても確認する必要 がある。造影剤投与中は造影剤漏出の有無を確 認し、撮影が始まる前まで状態の変化がないか 確認し、投与後も皮疹や嘔気、咳、くしゃみな どの前駆症状が出現していないか観察する。全 身状態が良好であれば静脈ルートを抜去し、そ の日は多めの飲水を勧める。副作用が出現した 際は即座にバイタルを確認して対症療法を開始 し、呼吸障害や循環障害が出現した場合には躊 躇せずに緊急チームを招集してチーム到着まで 緊急大量輸液、アドレナリン投与を基本に適切 に処置を施していく。
5)については、常日頃から救急カートの整備 や院内緊急時コールシステムの構築を行い、ま た各検査毎に同意書、危険因子を再確認してい くことが必要である。また、造影検査に関する インシデントレポートを分析して定期的なミー ティングで問題点を検討し、またアナフィラキ シーショックに対する対応のシミュレーション を行うことで、緊急時の初動の遅れを防ぐこと が可能となる。
●泌尿器・生殖器
血尿の原因は多彩であるが、画像診断の適応 となる疾患は主に結石や腫瘍である。主な検査 法として腹部超音波、腹部単純X 線写真 (KUB)、排泄性尿路造影(IVU)、CT、MRI がある。各検査には一長一短あるので適切な検 査法の選択が重要であるが、特に被曝に関して は慎重にならなくてはならない。尿路結石の場 合、低線量CT でも十分に診断可能な画像が得 られることが報告されており、低線量ヘリカル CT が第一選択である。しかし、尿路上皮系腫 瘍に対しては造影剤の使用が必要である。特に 腎癌に対しては単純、動脈相、実質相、排泄相 など複数の撮影がなければ、正しい診断は出来 ない。
血尿精査において従来はIVU がinitial study として用いられてきたが、尿路結石の検出、尿 路上皮腫瘍の検出、水腎症の原因検索、尿路の 解剖の把握には限界がある。CT urography (CTU)は経静脈的に造影剤を投与後、MDCT を用いて排泄相を含めて撮影したもので、これ らの欠点を補完するとして注目されている。過 去の報告で、尿路上皮腫瘍の検出にてCTU は IVU に対し感度、特異度ともに優れるが、RP と比較した場合は感度は同程度で、特異度はや やRP に劣るとされている。いずれにせよ、尿 路上皮系腫瘍が疑われた場合は、CT が第一選 択となっていく可能性がある。既に泌尿器科側 のガイドラインにこのような動きがみられ、 EAU 2004 guideline for upper urinary tract transitional cell cancer ではIVU が血尿検索の 第一選択検査でCT は小さな腎盂、尿管腫瘍の 検出に劣る、とされていたが、2011 年に改訂 された際はMDCT を用いたCTU がgold standard と表記されるに至っている。本邦において も、2006 年3 月の血尿診断ガイドラインでは、 肉眼的血尿に対してヨード造影剤が使用できる 場合にCTU を推奨している。顕微鏡的血尿患 者に対してCTU を行い、33 〜 42.6 %で血尿の 原因を同定でき、感度は92.4 〜 100 %、特異 度は89 〜 97.4 %とされている。“顕微鏡的”を 含む血尿患者の尿路上皮腫瘍を有する可能性は 0.9 〜 7.3 %といわれているが、肉眼的血尿を呈 する40 歳以上の患者で、化学物質(アニリン 色素、ナフチラミンやベンチジンなど)の職業 的暴露や喫煙の既往がある場合は、尿路上皮腫 瘍のリスクが高いため膀胱鏡やCTU にて積極 的に精査をすべきである。
●放射線被曝
放射線被曝の人体への影響は、受けた線量が 高線量か低線量かによって異なる。低線量域の 境界は吸収線量( G y : 物理的線量) で 200mGy、実効線量(Sv :臓器感受性から発癌 を考慮した線量)としては100mSv と考えられている。低線量被曝であれば、ほとんどの影響 (DNA 損傷)は数日で修復される。次に、同じ 線量でも急性被曝(一過性の被曝)より慢性被 曝(分割して受ける被曝)のほうが後に残る DNA 損傷は少ない。これは、線量率効果によ って被曝の間隔毎にDNA 損傷の修復が行われ るためである。高線量の急性被曝にIVR 後の皮 膚障害、低線量の急性被曝にCT、注腸造影、 PET などがある。両者の慢性被曝にはIVR 術 者やRI 従事者がある。これらの中でCT は比較 的被曝量が高く、問題となることが多い。CT での被曝は、従来の単純X 線撮影とは異なる回 転照射による加算が特徴的で、胸部CT では10 〜 20mSv、dynamic study や頸部〜骨盤CT で は40 〜 50mSv となる。他の検査と比べると多 い線量だが、しかしそれでも100mSv を超える ことはなく、2 日程度でDNA の修復は完了す る。また、CT の開発によって被曝線量の軽減 技術が進歩し、近年では逐次近似法によって体 幹部CT 被曝線量を30 〜 60 %減少させること が可能となった。
水に放射線を照射すると、水のO-H 結合が 切断されて活性酸素が発生する。放射線の主た る作用は活性酸素の発生によるDNA 損傷で、 これによる遺伝子、細胞膜、血管壁の傷害が 癌、動脈硬化、循環障害、老化の原因となる。 突然変異がひとつでもあれば癌が発生する可能 性がある。しかし、活性酸素を過剰に発生する 因子は放射線以外にもタバコ、運動、紫外線、 環境汚染、炎症、発癌物質など多くの物質があ り(Fig.5)、さらに、これら因子が複合するこ とで発癌リスクは相加的に高くなる。
かつてICRP(国際放射線防護委員会)は長 年にわたり放射線はどんなに微量でも有害とし てきたが、現在は5mSv 以下の被曝を問題視す る意見はない。100mSv 以下の低線量での発癌 リスクの増加は、原爆被害者の長期の追跡調査 を持ってしても、確認出来ない程度である。今 後100 万人規模の前向き研究を実施したとして も、疫学上影響を検出することは難しいと考え られる。
CT で発癌したという証拠はなく、証明も困 難である。CT の被曝は急性の被曝だが、多く は局所の被曝なので原爆と同様に発癌するとは 限らない。しかし、喫煙者が肺のCT を受けた 場合、僅かにリスクが上乗せされる可能性はあ る。よって、やはり無意味な被曝は不必要で、 CT の適応については慎重になるべきではある。 ただし、これを気にするあまりCT の適応のハ ードルを挙げすぎたり、線量を落としすぎて診 断精度を下げるようなことがあってはならない。
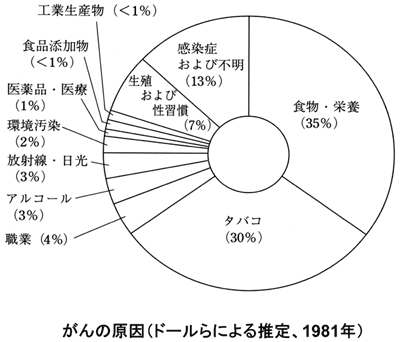
Fig.5 活性酸素を過剰に発生する因子
例年、社会保険指導者講習会には本会よ り2 名を派遣し、その後、県内にて伝達講習 会を行っております。しかし、今回は、東日 本大震災による同講習会の開催が遅れたこ と並びに関係学会等がその時期に集中した ことにより、1 名の先生しか派遣できません でした。同講習会は2 日間開催されており、 伝達講習会を1 名の先生で行うことは負担と なるため、会報への報告と代えさせていただ きます。