第111回九州医師会総会・医学会及び関連行事
Ⅱ.九州医師会連合会委員・九州各県医師会役員合同協議会
- 日 時:平成23年11月19日(土) 午前10時~
- 場 所:ホテルニューオータニ佐賀

司会者より開会が宣言された後、池田秀夫九 州医師会連合会会長(佐賀県医師会長)より、 概ね次のとおり挨拶があった。
九州医師会連合会会長挨拶
本日は、原中会長より中央情勢についてご講 演いただくことになっている。例年、日医に対 する意見・要望を九州各県へ照会し、それらに 対する日医の見解を含めて原中会長より講演い ただいており、今年度も九州各県から、国民皆 保険維持に密接に関連する医療保険制度の一本 化とTPP、診療報酬の不合理是正、医師不足や偏在、医師養成システム、医療の消費税、終末 期医療や特定健診受診率と後期高齢者支援金減 加算問題等、多岐にわたる要望、質問を頂いた。
先般開催された、日医代議員会において、 種々の問題について質疑が行われたばかりであ るが、原中会長からは、日医代議員会以降の諸 情勢の日医の考え方についてお話しいただける と期待している。
また、12 月の政府予算編成も深まってきて おり、例年、予算編成の時期になるにつれ、財 源不足の穴埋めをするため、主事の社会保障費 抑制政策が打ち出される。
今年も、社会保障審議会の医療保険部会、介 護保険部会等で厚労省から受診時定額負担を始 め、70 歳~ 74 歳までの医療費一部負担2 割化 の実施、介護保険の自己負担の引上げや、一部 給付項目の除外項目等が提案されている。
また、一部報道では、次回の診療報酬改定に ついて、政府与党は引下げを視野に検討してい るとの情報も流れており、これらの問題につい て、日医としてどう対処していくのか、政治主 導を掲げる与党民主党にどうアプローチしてい くのか等について、日医の戦略、戦術について お聞かせいただきたい。
原中会長の講演の後に、質問の時間を設けているので、ご発言を宜しくお願いしたい。
座長選出
慣例により、九州医師会連合会池田秀夫会長が選出された。
講 演
「中央情勢報告」
日本医師会長 原中勝征先生
民主党政権になり、日医として意見を申し上 げる機会が増えたと思う。例えば、各執行部の 先生方が直接官僚の所へ出向き、話しができる 環境になり、医療が関係している委員会にもほ ぼ参加できるようになった。その中で、医師会 に好意的な議員は8 割以上で、日医の要望を受 け入れてもらえる環境であるのは事実である。
ただ、議員とは別に官僚組織があり、官僚は 自民党時代から引き継いだ事を実行しようとし ている。厚労省に関しては特定看護師を含む看 護問題、小泉政権から引き継いでいる混合診療 の問題等、アメリカからの要求が官僚の中で続 いていると感じられる状況である。
官庁の力関係の中で、厚労省は弱く財務省が 中心となり日本の政治は動いていると感じる。 大きな変化といえば、財務省の主計局の次長と 審議官が医療費改定について日医の考えを聞か せてほしいと日医を訪問された。その際、日医 として1)自然増に関してはそのまま続けてほし い、2)ネットでマイナスではなく必ずプラスに してほしい、3)入院、外来の配分(55 対5)ま で示したのは財務省の越権行為で、予算に関す る事が財務省の役割であり、医療の内容にまで 入るのはいけないと申し上げた。
状況は変わってきているが、国民皆保険を堅 持するために問題が生じてきている。特に、国 連総会の際、日米の首脳が会うと必ず、いろい ろな事が変わってくる。野田総理に関しては、 突然TPP が表れた。郵政民営化の際、どうし てマスコミが日本の世論をつくるのに集中して 賛成したのか。「郵政改革は日本の政治改革の 入口だ、これに反対する人は切り捨てる」とい う小泉前首相の言葉を崇め、日本中の世論を作 った。マスコミの在り方は日本に大変な間違い を起こしてきたエネルギーであったと考える。 今回もTPP の推進派の意見だけを報道する事 になると考えられる。
TPP に関して勉強しても理解が出来ず、国 民も理解できない。TPP を行うと経済はスム ーズになり、日本の企業が外国にいく際、関税 の弊害もなくなりスムーズにいく事ばかりが報 道されているのが現状である。実際、その影に 隠れているものは何であるのか、我々に知らさ れていない事は何なのか、個人的に聞いている 所である。ところが、官僚には問題点等は知ら されており、政治家には知らされていないとい う事が嘘か本当か耳に入った。
1 年ごとに代わる政治家というのは、その場しのぎの約束をしており、正義の弱さを感じ る。政治家の質の問題と同時に機関の問題も絡 みあって、本当の内閣政治がされているのか危 惧している。その中でも、権力を持っているの は内閣なので、政治家といろいろな話し合いを しながら、日医の真意を理解していただかなけ ればならない。
医療関係について理解がある方々と日医の担 当副会長、常任理事が定期的にモーニングカン ファレンスを行い、その時の状況を判断する際 に役立っている。外部との会議を盛んに行い、 医師の偏在の問題等に対して、医師会の意見を 申し上げていこうと動いており、かなり浸透し てきている状態である。
先生方の意見が国を通して実現する方向に少 しずつではあるが、向かっていると感じている が、まだまだ十分ではないので、今後もきちん としていきたい。
Ⅰ.東日本大震災への対応
今回の震災で、15,833 名の死者、3,671 名の 行方不明者、5,943 名の負傷者の報告があった。 JMAT として、現在までに1,700 チーム近い派 遣をしており、医師、スタッフの総数は6,800 人となっている。先生方にはボランティアとし て参加して頂き、自身の診療を休んで現地へ行 って頂いた事に御礼申し上げる。また、政府の 方から感謝されていると同時に、費用に関して は県からの要求額が支払われる事に決定した。
今回、内閣府から要望があり、被災者健康支 援連絡協議会を立ち上げた。これは、被災時、 政府と各県のパイプができておらず、被災者が放 置されている状況であったからである。幸いな事 に、被災された県の医師会から日医へ毎日情報 提供があり、その情報を政府へ提供していた。
震災発生から3 週間たっているにも関わらず 瓦礫の下に遺体が放置されていた事に対して憤 慨し、政府に対して強く意見を述べ、総理大臣 へ政府の動き方の悪さを指摘した。日医からの 提案として、医療費の実態調査を行い、医療費 の値上げの検討よりも先に厚労省の方々が被災 地へ出向き被災者を救うことが先ではないかと 申し上げたが、政府は関係ない顔をしていたの が実情であったので、政府として、官僚として の責任はどこへいったのかと申し入れを行った。
今になって厚労省から各県に部長、課長が出 向き、各市町村には若い人たちが出向いて現場 からの意見を取り入れる制度ができたが、その 前に、我々の情報が効果的であったという事が 分かり、日医を中心として被災者健康支援連絡 協議会を設置してほしいと要望があり、立ち上 げた。現在40 団体以上加入している。今後は、 被災された地域の医療機関をどうやって再生す るかが最大の問題であり、被災者の方々は8 ヵ 月経過した今、将来に対しての不安を感じてい る。被災者は不満を言う事もなく、じっと我慢 して耐えていた状況であるにも関わらず、政府 は原発の問題ばかりを取り上げ、被災地で苦労 している国民の姿は取り上げなかった。しか し、日医が中心となり政府への伝達事項により 政府が動けたことが参考になり、被災時の情報 共有が大事であることを実感した。今後、想定 される地震に対して連絡の中心となる会に育っ ていくだろうと思う。防災の大切さ、大変さを 感じたところである。
また、被災地とテレビ会談を行い、会議を全 国の医師会へ公開し、情報を共有した。それに よって出てきた問題に対して、いち早く対処で きたと思う。最初に出てきた薬の問題に対して は、日本製薬工業協会と愛知県医師会に協力し ていただき、8.5 トンの薬を用意して頂いた。 また、8.5 トンの薬剤は、ハーバード大学で防 災関係の勉強をしている日本人の先生がアメリ カ大使館へ掛け合い、横田基地から岩手県、宮 城県へ空輸し、なんとか1 か月間もつだけの薬 を運ぶことができた。
本来なら、政府がやらなくてはいけない事を 日医がやった事に対して感謝されたが、本来や らなくてはいけない政府が何もできなかった事 を反省し、次に繋げてほしいと申し上げた。そ ういう事があり、被災者健康支援連絡協議会を 中央防災会議に代わるきちんとした活動ができる実行部隊に成長して欲しいと考える。
Ⅱ.国民皆保険を維持するための雇用環境の是正
現在、世界中で日本とスウェーデンの保険は すばらしいと言われている。しかし、スウェー デンは今後100 年もつと言われているが、日本 は、後10 年で保険制度が崩れるだろうと言わ れている。その原因として、人口問題、労働環 境問題、少子化問題があげられている。日本の 65 歳以上の人口は、2042 年にピーク(約3,900 万人)を迎え、2055 年には、65 歳以上が41 % になるのに対し、就業人口(15 ~ 64 歳)は 51 %である。その中にも失業者が増え、若い人 でも生活保護を受けているのが現実である。現 在、若者1.8 人で1 人の65 歳以上を支えてお り、2055 年には1 対1 になるであろうと推測さ れる。高齢になっても安心して老後を過ごせる 社会であるかが大きな問題になると考えられる。
現在、アメリカからの派遣法が拡大し、非正 規職員が増えてきている。日本の株式の配当を 外国にもっていかれており、配当を高めるため に労働分配率が54.2 %であったが、現在42 % と10 %減となっている。そのために、いつで も首をきれる派遣法が拡大されてしまった。
それと同時に未婚者が増えてきているのも事 実である。未婚者が増えると少子化になる事は 目に見えている。200 万円以下の所得者が増え ており、その人達が結婚しておらず、収入と結 婚率が比例しているのが分かる。
Ⅲ.超高齢社会を見据えた社会保障全体の長期ビジョン
日本の最新年次合計特殊出生率は1.37 であ る。韓国は以前子供を増やす政策があったが、 現在は、先進国中最低の1.15 である。日本は 韓国に次いで低い。この数字から見てもわかる ように、わが国では今後少子化の問題が深刻化 することを考え、民主党のマニフェストを作成 する際に、当時の国民生活研究会でこども手当 を提案した。子供が増加しているフランスやドイツ、イギリスにしても、こども手当が出来て から子供の数が増えていることがわかっていた ためである。
こども手当は、収入がある人は支給を受けな い、或いは小額で良いという議論があったが、私 は収入に関係なくこども手当を支給するべきだと 主張した。医療については収入に関係なく同一 のサービスを受けているが、税金や医療保険は収 入に応じた負担をしている。負担とサービスを受 けるのは別だと考えたことによるものである。
諸外国における非摘出子の割合をみると、結 婚はしないが子供は欲しいという女性が増加し ており、スウェーデンにおいてはOECD 加盟 国の間で2 番目に高い。一方日本は、非摘出子 に対する社会的偏見が根強く残っているため か、韓国に続き2.1 パーセントと低くなってい る。また、子供を育てて負担に思うことの調査 では、出費がかさむとの回答が1 位にある。働 くことが出来ない環境や、時間的な制約等も主 な要因として挙がっている。
しかし、30 数パーセントの人、数にすると 約10 万人が、収入があり、子育てできる環境 が整備されれば、子どもを産みたいと希望して いることがわかっている。
子供を産める環境作りを早急に整備し、少子 化対策を行わなければ、生産・労働力人口の減 少、日本経済成長の低迷や、日本の社会保障は 持続しないと考える。本会は政府と一体になっ て解決を図るべきと考えている。
現在、高齢者(65 歳以上)1 人を若者2.8 人 で支えているが、2025 年には若者が2.0 人、 2050 年には若者1.3 人で支えなければならない 時代となる。超高齢社会はかねてから予想され ており高齢者医療制度の見直しはもちろん重要 ではあるが、目先の課題に翻弄されず、将来を 見据えた長期ビジョンを早急に示すべきである。
Ⅳ.医療費の引き上げと患者一部負担割合の引き下げ
-国民の安心を約束する医療保険制度-
国家予算に占める医療費の割合を見てみると、一般会計歳出のうち、社会保障関係費は、 2010 年度当初予算で27.3 兆円(29.5 %)から 2011 年度予算では28.7 兆円(31.1 %)になっ た。そのうち医療分については、8 . 0 兆円 (8.7 %)から8.3 兆円(9.1 %)となった。平 成20 年までは、社会保障費自然増の2,200 億 円が削られていた時代だったが、民主党政権 下、社会保障費削減を撤廃したことにより、医 療費が増額になった。しかし、入院が中心とな っており、大学病院に於いては11 ~ 12 %の収 入増となっている。
医療費の国庫負担割合では、1983 年度と比 較して、2009 年度は株主配当にすべてを回そう という動きから事業主負担が減少し、地方公共 団体や個人負担が大きくなっている。我々は、 ここの改善を主張すべきである。
我が国の患者一部負担割合については、先進 諸国に比べ高いにも関わらず、財務省は財源確 保のため、70 ~ 74 歳の負担(現在1 割負担に 据え置き)を3 割に引き上げようとしているの である。
現在、わが国には推定無保険者が100 万人い ると言われている。雇用形態の変化により、派 遣社員が増加し、彼らが失業した歳に加入する のが国民健康保険だが、保険料が高い上、加入 手続きが自動的ではないことから、無保険にな っている失業者は少なくない。また、生活苦に より家庭を持てる見通しがない中、保険料を滞 納する世帯が20 パーセントを超えている。短 期被保険者証交付世帯と資格証明書交付世帯 が増えていることも問題である。
被用者保険の保険料率の格差や市町村国保間 の保険料負担の格差も生じており、日医では、 日本の医療保険制度を維持するために、すべて の国民が同じ医療を受けられ、支払い能力に応 じて公平な負担をし、将来にわたって持続可能 な制度となるように、最終的には公的医療保険 の全国一本化を目指し、財務省、厚労省に対し て提案しているところである。
我が国の医療費抑制は診療報酬の引き下げが 続いていたが、昨年度はやっと0.19 %上がっ た。しかし、ネットでプラス改定となってお り、診療報酬は若干上がってはいるが、これは 社会保障費の自然増2,200 億円が加わったこと によるものだろうと見ている。入院や大学病 院、600 床以上の病院は少なくとも6 パーセン ト以上、大学に至っては10 パーセント以上の 収入増があるが、慢性疾患病棟を抱えた病院は 上がっておらず、平均すると6.6 パーセント増 になる。その一方、薬局については、3 パーセ ントも増加しており儲かっている。そこは、き ちんと改定する必要がある。
Ⅴ.2012 年度診療報酬・介護報酬同時改定について
2012 年度の診療報酬・介護報酬同時改定に 関しては、去る5 月19 日、厚生労働大臣に対 し次の通り要請した。
3 月11 日に起こった東日本大震災の復興に 巨費を要することから、2012 年度の診療報酬、 介護報酬同時改定を見送ること、今年度の医療 経済実態調査、薬価調査・保健医療材料価格 調査については正確な調査結果がでないので見 送るよう要望している。また、介護報酬の改定 は見送るが、介護保険料の決定のために必要な ことは行うこと、不合理な診療報酬、介護報酬 については、留意事項通知や施設基準要件の見 直しを行う事、必要な医療制度改革は別途行う ことを申し入れた。
Ⅵ.政府「社会保障・税一体改革成案」について
-受診時定額負担に反対する-
日本医師会は、高額療養費を見直し、患者負 担を軽減することには賛成だが、その為に病気 などで通院している患者さんに更なる負担を求 めることには反対している。公的医療保険であ る以上、高額療養費のあり方を見直すための財 源は幅広く保険料や税財源に求める事を要求し ている。
受診時定額負担については、現在1,000 万人 の署名運動を実施しており、政府与党を中心と して日本医師会は受診時定額負担を認めないという事を申し入れている。
Ⅶ.医療分野における規制改革の問題点とTPP 参加に対する日本医師会の考え方
TPP に参加し、もし合意すると「混合診療 の全面解禁や医療への株式会社参入」という合 意項目を実行しなければならない状況になり国 民皆保険制度の崩壊につながる。
混合診療の解禁を進めているタイでは、お金 のある人と無い人との差がはっきりついてお り、国立病院の9 割の患者は国内外のお金のあ る人で、お金の無い人は1 割しか国立病院に入 れない。また、イギリスではお金の無い人の胃 癌の診察に3 年も待たされた。混合診療を進め る国ではこうした現象が起こっている。
TPP 問題がいかに我々医療界全体の中に大 きな影響を与えるかという事を考えていかなけ ればいけない。また、日本人医師と外国人医師 のクロスライセンス(お互いの国の医師免許を 認めること)についてだが、受け入れの際には 日本の医師免許を取得していただくという事を 申し上げている。
TPP に対するマスコミの対応についても、 社会的使命を行使していただく事を申し上げて いこうと思っている。
現在、韓国と米国間で結ばれたFTA(自由 貿易協定)では、米国政府が韓国政府に異議を 唱え、自国の意見を入れ始めた為に韓国議会は これを廃止するという動きが出てきている。 TPP の問題に関しても最終的には国会議員の 衆議院の否決という事を目指して行動していく 事が『最後の砦』だと考えている。
質問・要望事項等
フロアーからの質問に原中会長が次のとおり回答された。
不合理の是正はなるか(福岡県医師会)
〔要 旨〕
日医では10 月12 日の定例記者会見におい て、不合理な診療報酬項目の見直しにむけての 基本方針で、「前回の診療報酬改定の結果、医 療費が大規模病院に偏在し、地域医療がまさに 危機的状態に瀕していることから、診療所、中 小病院に係る診療報酬上の不合理を重点的に是 正する。」との内容で、特に緊急性、重要性が 高い項目14 項目を整理し公表されたが、これ ら項目の中での日医が考える優先順位をお示し いただき、今後の対応・展望についてご意見を いただきたい。はたして、日医にはこれらの不 合理を是正するだけのエビデンスをお持ちか。
九医連では日医にたいし度々、項目③にあげ られている「入院中患者の他医療機関受診の取 扱いの見直し」を強く求めてきましたが、改定 直後に一部緩和された後は中医協での議論は進 行していない。患者のフリーアクセスそして医 療機関連携を阻むこの様な取り決めは即刻改定 前の状態に戻していただきたい。この件に関し ては前回改定時の外来管理加算5 分要件緩和の ように全国の医師会から強い要望がなされてい るはずである。会長の不合理の是正に向けての 決意をお伺いしたい。
●回答:基本的には官僚が主張したものは全て 入れていくが、その中でも日医が絶対に入れて はいけないものに関して申し入れをするところ である。仮に14 項目全てダメであれば全て反 対していく。医療関係の決定をする委員会等に どうして反対するのか理由も説明し、定期的に 訴えていく。
臨床研修制度における「基幹型臨床研修病院の指定基準激変緩和措置」の延長の要望について(宮崎県医師会)
〔要 旨〕
宮崎県においては医師の絶対数の不足と偏在 により、地域医療を支える勤務医が激減し(こ の10 年間に県内の20 歳代医師数- 49 %、30 歳代医師数- 19 %の減少)、救急医療やへき地 医療が崩壊し憂慮すべき状態にある。
そのような中、本県の基幹型臨床研修病院は 6 病院と全国で2 番目に少なく、平成22 年度のマッチングで研修医募集定員75 名に対し、マ ッチ者数は30 名(40 %)と全国最低の臨床研 修医総数であった。大病院の少ない当県におい ては、県・医師会・大学・民間病院が一致協力 して、限られた数の基幹型臨床研修病院におい てプログラムの改善と広報により、研修医確保 に現在も努力しているところである。
基幹型臨床研修病院の指定基準の強化におい て、現行の激変緩和措置が廃止されると、本県 の基幹型臨床研修病院6 病院のなかの1 病院 が、指定基準の「入院患者数年間3,000 人以 上」に該当せず指定取り消しとなる(入院患者 数年間約2,000 人が実績)。この病院は、病床 数124 床ではあるが、毎年継続的に研修医を受 け入れており、地域の開業医や離島診療所、在 宅医療などの幅広い分野と連携した研修内容と なっており、経験すべき病態・疾患・手技等に ついても1 年目でほぼ経験できる体制を確保し ている。また小児科研修も充実しているなど当 県に欠くことの出来ない研修病院である。
さらに、「2 年間連続して研修医の受入れ実 績がない場合の指定取り消し」の項目に該当す る恐れのある他の3 病院も指定が取り消される 可能性があることを憂慮している。受入れ実績 のなかった当該病院についても、指導医の確 保・研修プログラムの充実など、ハード・ソフ ト両面の充実を図っており、今後の県内での研 修施設として医師会としても期待をしていると ころである。
我々は、「大学病院に研修医を集め医師の派遣 機能を復活させる」方針に賛成をしているが、 地域の中小規模病院において、質の高い臨床研 修を実施している病院には、引き続き基幹型臨 床研修病院としての役割を果たしていただき、 県内に定着する医師の増加を図りたいと考えて いる。大都市と地方では多くの面で環境が異な ることから、地域の特性を考慮しながら研修施 設を選択することが必要だと考える。
激変緩和措置の延長を行っていただけるよう、日本医師会のお力添えをよろしくお願いしたい。
●回答:日本医師会では、医学教育の提案とし て大学4 年終了時に前期試験を実施し、残りの 2 年間は全ての診療科の実習を積極的に行い、 実のある診療の実技を勉強させ、卒業時の試験 は実務だけの試験にするという事を提案してい る。これは大学の先生方の考えと一致してい る。研修に関しては、県全体として研修医を取 扱う中間的な機関や各大学の中に研修医を派遣 あるいは教育をする責任のある機関を作ってい ただき、研修医の定員については、県の大学卒 業者と同じ数にするという事を提案している。
地方の医師不足と偏在について(研修医の問題等を含む)(鹿児島県医師会)
〔要 旨〕
2004 年、新医師臨床研修制度が創設されて 以来、全国各地で医師不足・偏在の問題が顕著 になっている事は今さら申すまでもない。
鹿児島県医師会では、昨年から地域の住民、 行政、医師が語り合える場として、現地懇談会 を始め、これまでに曽於、薩摩、奄美、枕崎、 南薩、指宿、いちき串木野市・日置、の7 ヶ所で 実施してきた。その中で、どの地区も医師不足 による地域医療の崩壊の危機を抱えている現状 が改めて浮き彫りになった。特に、小児科医、産 科医の減少、夜間二次救急医療体制構築の問題、 病院勤務医の不足等は喫緊の課題になっている。
先日、2011 年度の「医師臨床研修マッチン グ」の最終結果が公表され、都市部以外の内定 者割合が過去最大といううれしいニュースが飛 び込んできた。本県も、前年より24 人増の97 人と、充足率が6 年ぶりに6 割を超えた。県行 政、大学、医師会、臨床研修指定病院が一丸と なって取り組んできた成果がようやく出てきた ものと考えるが、地域や診療科の偏在解消への 真の取り組みはこれからが正念場である。
日医においては、本年4 月に「医師養成につい ての日本医師会の提案-医学部教育と臨床研修 制度の見直し-」と題して、臨床研修制度の基 本的方向性等、様々な改革案を示しておられる。
臨床研修制度および医師の偏在問題等について、中央情勢ならびに日医の方向性について御教示いただきたい。
●回答:最近の傾向で、大学で産科に進む学生 は増えたが、過酷な労働条件という理由でお産 は行わないという先生方が増えている。難しい 問題ではあるが一生懸命検討をしていく。
小児科に関しては女性医師が多く、出産育児 で病院を離れる事があるが、現在、日本医師会 では女性医師が現場復帰する為の委員会の設置 や政府からの援助を受けながら再就職を手当し ている。また、日本医師会で女性医師に関して 人材の派遣を行っていて、少しずつではあるが 成果を出している。
現在、医学部の定員数を増やしており15 年 先には国際レベルに達するが、その時に偏在と いう問題が出てくる。日本医師会では、各県の 大学において偏在を無くすような講義をしてい ただきたいという要望を出す予定である。
特定健診における目標受診率未達成時の支援金加算について(長崎県医師会)
〔要 旨〕
平成20 年にスタートした特定健診は、5 年後 の平成24 年までに各保険者に以下のとおりの受 診率(実施率)の達成を求めている。また、この 受診率を達成できなかった保険者へは、後期高 齢者支援金を最大10 %加算すると噂されている。
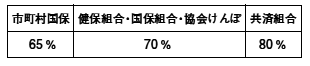
この加算は、「高齢者の医療の確保に関する 法律」の中にあるが、平成23 年7 月に厚生労 働省が開催した「第3 回保険者による健診・保 健指導等に関する検討会」で、「高齢者医療確 保法において、各保険者の定める特定健診等の 実施目標の達成状況に応じて、保険者に係る加 入者の見込数等を勘案して、政令で定める方法 により、10 %の範囲内で各保険者が支払う後 期高齢者支援金の金額を加算減算することとな っているが、現在まで政令は定められていない。」となっている。
また、後期高齢者医療制度を廃止し、新制度 へ移行する可能性もあり、後期高齢者支援金の 加算減算が実施されるのか?されないのか?わ からないのが現状である。
国民の健康と予防を考えた場合に特定健診を 受診することの必要性は認めるが、このような 後期高齢者支援金が加算減算されるような制度 に日医としてはどのように対応してきたのか? 黙認するのか?
ましてや、厚生労働省が公表している平成20 年及び21 年の保険者別の受診率は以下のとおり で、平成24 年の目標達成は厳しいと思われる。
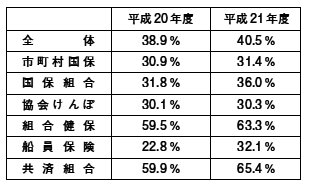
受診率を達成できなかった保険者へ平成25 年から後期高齢者支援金の10 %加算が行われ た場合には、財政力の乏しい保険者(特に市町 村国保)はより一層運営が厳しくなり、結果 として保険料アップにつながる恐れがある。
これまでの日医の対応からは、このような保 険料が増減する可能性のある制度について容認 しているようにしか思えない。
財源ありきではなく、公平・平等に医療が受 けられる社会保障制度を守るのが日医の方針だ と思うが、今後どのように対応していくのか?
ご意見をお伺いしたい。
●回答:もう一度考えさせていただいて、今後効果のある方向へ検討していく。
消費税増税に対し、負担増に対し、対策は充分なのか。(熊本県医師会)
〔要 旨〕
消費税が導入された際に医療界の増税については充分議論されているとは思えない。
この様なことに疎い、当時の日医の少数の理 事が重大な決定をしてしまったのが現在大問題 になっているといわれる。
充分の準備と論点整理、又、日医一般会員の了承のもと交渉をすすめてもらいたい。
●回答:消費税増税の分だけ負担増になるとい う事は決してない。医師の負担が無いように消 費税に対する担保を話し合っているところであ る。しかし政治手法によって法律を変えなけれ ばならないとなると相当な時間がかかるので、法 律を改正せずに消費税の負担増を無くしていく。