非アルコール性脂肪肝炎(NASH)の診断と治療
ハートライフ病院消化器内科
佐久川 廣、城間丈二
【要旨】
近年肥満の増加とともにNAFLD(nonalcoholic fatty liver disease)が増加 している。NAFLD は進行性のNASH(nonalcoholic steatohepatitis)と肝硬変に 進行しない単純脂肪肝に分けられる。NASH の診断は組織学的になされ、肝実質の 10 %以上の脂肪変性と門脈域および肝小葉内のリンパ球の浸潤、風船様膨化の所 見が必要である。NASH と単純脂肪肝の鑑別は血液や画像診断では困難だが、血小 板と肝線維化マーカーがNASH の存在予測に役立つ。NASH の治療はその病態よ りインスリン抵抗性の改善と酸化ストレスの抑制が主体となる。食事や運動療法に よる生活習慣の改善が基本になり、薬物の投与により肝酵素の改善が得られること も多い。しかしながら、肝硬変に進行すると予後は不良である。
はじめに
1990 年代前半頃まで脂肪肝は肝硬変に進行 しない疾患と考えられていて、肝臓専門医には 興味のない疾患であった。しかしながら、飲酒 歴のない中年女性にアルコール性肝障害に類似 した病変が報告されるようになり、nonalcoholic steatohepatitis(NASH)が注目され、 学会でも盛んに取り上げられている。
本稿ではNASH の診断と治療について最近 の知見を含めて解説する。
(1)NASH とNAFLD
NASH に関連する報告の中にNAFLD とい う疾患名が出てくる。Nonalcoholic fatty liver disease という疾患名で、日本語に直訳すると 非アルコール性脂肪肝疾患ということになる。 NAFLD は広い疾患概念で、その中に肝硬変に 進行するNASH と肝硬変に進行することのな い単純脂肪肝が含まれている。NASH も単純 脂肪肝もエコー上脂肪肝があり、肝酵素が上昇 を示すことが多い。NASH は肝臓の病気として 肝臓専門医が関わる必要があり、単純脂肪肝は メタボリック症候群の表現型として認識され、 多くの医師が関わる病態である。
(2)NASH の診断
NASH は非アルコール性脂肪肝炎と訳され るが、この診断名は3 つの部分からなる。すな わち、1)非アルコール性、2)脂肪肝、3)肝炎で ある。その各々のパーツに対して専門家間の意 見は統一していないが、現在スタンダードにな りつつある基準について記述する。
非アルコール性の定義は必ずしも明確でない が、肝臓に障害を与えない飲酒量ということに なる。もちろん、飲酒量が肝臓に与える影響は 個人差があり、正確に定義することに無理があ るが、大部分の人にとって問題とならない飲酒 量ということになる。非アルコール性の定義と して、男性がエタノール換算で30g/日以下 (日本酒1 合、ビール700ml、泡盛0.5 合に相当)、女性が20g/日以下である。一方、アルコ ール性の定義は、平均の飲酒量が80g/日以上 (5 年間以上)とされている。したがって、飲酒 量が30g/日~ 80g/日の人はアルコール性でも なければ、非アルコール性とも言い難いという グレイゾーンである。エタノールの肝での代謝 は50 ~ 60g/日とされているので、現実的には 1 日平均50g の飲酒量で肥満があって、肥満に よると思われる脂肪肝炎を来たしているという 症例によく遭遇する。この場合、学問に従うと NASH と診断できないが、治療方針はNASH と同様である。下手に禁酒を勧めると甘党にな り、脂肪肝炎を悪化させる可能性もある。
脂肪肝は病理学的な定義で、通常生検で採取 された肝実質の10 %以上に脂肪沈着あれば脂 肪肝と診断してよい。病理学者の脂肪肝の定義 は一般に30 %以上であるが、NASH は病気が 進行する程脂肪肝の程度が弱くなるので、進行 したNASH が診断から除外されるという不都 合が生じる。
NASH における肝炎の定義が一番重要で、 非進行性の単純脂肪肝と鑑別することは臨床的 意義が大きい。肝実質内にリンパ球が浸潤する 像は単純脂肪肝でも程度の差はあれよく見られ る。Matteoni ら1)は肝細胞の風船様膨化を重 要視したが、これは定義が比較的に明確で理解 しやすい。その後、Bruntら2)を中心に NAFLD Activity Score(NAS)が提唱され た。これは病理所見を要素毎に分類し、点数化 し、より客観的評価を意図したが、やや複雑で 一般の臨床医には理解しづらいものになってい る。多くの専門医はMatteoni の分類を基準にしている(表1)。すなわち、NASH の病理学 的診断は、10 %以上の脂肪変性とリンパ球の 浸潤を主体とした壊死炎症反応に風船様膨化が 加わった組織像(風船様膨化が目立たなくとも 肝細胞周囲線維化や隔壁線維化がある場合は NASH と診断してよい)である(表1 のType 3 とType 4 がNASH)。
表1 Types of Nonalcoholic Fatty liver Disease
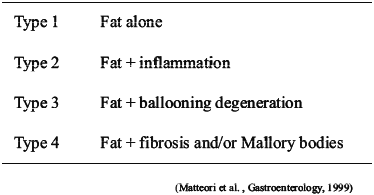
NASH は中年女性に多い疾患で、閉経後に 増加する。女性の場合、20 歳代、30 歳代は痩 せが問題になることが多いが、40 歳代以降肥 満が増加する。一方、男性は20 歳代、30 歳代 の比較的若い人にNASH が多い。どうして NASH が女性に多いのか、閉経後に増えるの かは分かっていない。女性は閉経後に肥満が目 立ち始め、脂質代謝異常も高率に合併する。そ のようなことが、関係しているであろうと推測 されている。肥満、特に内臓肥満は男性に多 く、肥満に関連した疾患、すなわち糖尿病や高 血圧、高脂血症はやや男性に多い。にも拘わら ず、NASH は女性に多い。
NASH は疾患概念が比較的に新しいため、 鑑別診断を厳格に行うようにという専門医の 意見を聞く。NASH の本質は肥満やインスリ ン抵抗性に関連した進行性の病気ということ である。鑑別診断を厳格にしすぎると治療の 遅れを招きかねない。非アルコール性の定義の 項でも触れたが、エタノール換算で30g/日以 上の飲酒歴を有するNASH(すなわち、肥満 やインスリン抵抗性に関連した進行性の病気) は多数存在する。沖縄県民で例えば泡盛1 合 を晩酌で飲む習慣がある人は健康な生活を送 っていることが多い。美食家で肥満があれば、 飲酒より摂取カロリーの方が問題であり、肥 満に関連したNASH を発症することは納得が 行く話である。
NASH の診断の条件として肝炎ウイルスの 感染を否定するようにと説明されている。C 型 肝炎ウイルスが陽性なら、恐らく肝障害の原因 はC 型であろう。しかしながら、B 型の場合、 多くが無症候性のキャリアであり、肥満のHBs 抗原キャリアに肝障害が見られたら、NASH やNAFLD の可能性を考えた方が、正しい診断に 行きつくであろう。特にウイルス量が少ない (HBV-DNA < 5LC/ml)場合は、B 型肝炎ウ イルスが原因というより、肥満があれば脂肪肝 を念頭に置いた方が良い。
非アルコール性の定義を超える飲酒歴を有す るNASH、HBs 抗原陽性のNASH、抗核抗体 陽性のNASH は普通に存在すると考えてよい。 NASH は既にありふれた疾患になっており、い つまでも鑑別診断を厳格に行うと本質を見失う ことになりかねない。
NASH はMatteoni らが提唱したように脂肪 肝+リンパ球浸潤+風船様膨化を呈する疾患で あり、病理学的にしか確定診断がつけられな い。しかしながら、NAFLD は成人の20 ~ 30 %いると言われ、NAFLD の10 %がNASH (成人全体の2 ~ 3 %)と推定されており、 NAFLD の全ての症例に肝生検を行うことは現 実的ではない。また、NASH は肥満や糖尿病 の患者の中に多く見られ、これらの疾患によく 合併する脳梗塞や冠動脈疾患に対して抗凝固剤 を使用している患者をしばしば経験する。した がって、肝生検の対象を絞り込むとともに生検 によらない診断(主に単純脂肪肝との鑑別)が 重要なテーマとなっている。
NASH は脂肪肝に炎症が加わった病態であ
り、多くの場合肝酵素(GOT、GPT)の上昇
が認められる。しかしながら、肝酵素の値と
NASH の進行度との間には相関がなく、肝酵
素の値でNASH と単純脂肪肝を鑑別するのは
困難である。したがって、GPT が高いから
NASH ということにはならないが、一方で、
GPT が正常であれば、多くの場合NASH を否
定してよい。最初のスクリーニングとして
GPT![]() 40 IU/L であれば良性の単純脂肪肝と
して扱う。ただし、進行したNASH の場合、
肝酵素が正常化することもあので、注意が必要
である。この場合は血小板が判断材料になる。
図1 に示すようにGPT>40 IU/L あるいは血
小板< 15 万の症例はNASH の可能性を念頭に
置き鑑別診断を進める。
40 IU/L であれば良性の単純脂肪肝と
して扱う。ただし、進行したNASH の場合、
肝酵素が正常化することもあので、注意が必要
である。この場合は血小板が判断材料になる。
図1 に示すようにGPT>40 IU/L あるいは血
小板< 15 万の症例はNASH の可能性を念頭に
置き鑑別診断を進める。
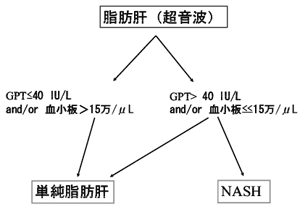
図1 NASH のスクリーニングと鑑別診断の進め方
我々の施設では肝線維化マーカーを鑑別診断
に用いている3)。Ⅳ型コラーゲン7S![]() 5 ng/ml
あるいはヒアルロン酸
5 ng/ml
あるいはヒアルロン酸![]() 43 ng/ml の何れか一
方を満たせば、NASH を強く疑い肝生検の対
象にしている。Ⅳ型コラーゲン7S
43 ng/ml の何れか一
方を満たせば、NASH を強く疑い肝生検の対
象にしている。Ⅳ型コラーゲン7S![]() 5 ng/ml
とヒアルロン酸
5 ng/ml
とヒアルロン酸![]() 43 ng/ml は通常の検査の正
常上限値と異なるが、ROC 曲線という統計学
的手法を用いて、各々の検査における最も正診
率の高い値をカットオフ値と定めた。我々の検
討ではⅣ型コラーゲン7S とヒアルロン酸のど
ちらか一方がカットオフ値を超えた場合の
NASH の正診率は80 %で、前向き調査で検証
(validation)した場合の正診率も82 %であっ
た(表2)
43 ng/ml は通常の検査の正
常上限値と異なるが、ROC 曲線という統計学
的手法を用いて、各々の検査における最も正診
率の高い値をカットオフ値と定めた。我々の検
討ではⅣ型コラーゲン7S とヒアルロン酸のど
ちらか一方がカットオフ値を超えた場合の
NASH の正診率は80 %で、前向き調査で検証
(validation)した場合の正診率も82 %であっ
た(表2)
表2 肝線維化マ-カ-によるNASH の存在予測
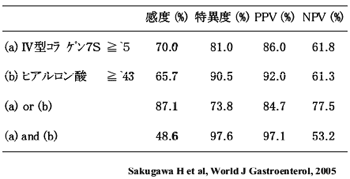
これまで、様々な臨床的パラメーターを用い てNASH と単純脂肪肝の鑑別が試みられてい るが、正診率80 %くらいが限界であり、どの ように指標を組み合わせても80 %を大きく上 回ることはないであろう。日本の中でNASH を臨床的に研究しているグループがフェリチン (男性300ng/ml 以上、女性200ng/ml 以上)と 空腹時のインスリン(10 μ U/ml 以上)およびⅣ型コラーゲン7S(5 ng/ml 以上)の3 つの 臨床的パラメーターを用いてNAFIC スコアを 提唱している4)。各々の指標が括弧内に示した カットオフ値をこえた場合、フェリチンが1 点、 インスリンが1 点、Ⅳ型コラーゲン7S が2 点 とし、合計点が2 点以上の場合のNASH の診 断における感受性は60 %、特異性は87 %とこ れまでの報告を上回る良好な成績であるが、正 診率は残念ながら80 %に届いていない。
臨床的パラメーターによるNASH の存在予 測には限界があるが、脂肪肝の全例を肝生検す るわけにはいかないため、やはり予測のパラメ ーターにはそれなりの臨床的有用性がある。ど の検査値を予測に用いるかは専門医間でも意見 が分かれるのは当然であり、各々の施設で使用 しやすい指標を用いればよいと思う。コストや 簡便さを考慮すれば血小板とⅣ型コラーゲン 7S は利用しやすく、鑑別に有用な検査と思わ れる。
(3)NASH の治療
NASH の治療として確立されたものはない が、どのような病気でもそうであるように原因 療法が基本である。NASH は肥満やインスリン 抵抗性に関連した進行性の疾患であり、肥満対 策は治療の基本になることが多い。吉松5)は、 肥満者には独特の生活習慣の癖があり、行動変 容を起こさせることが大切と指摘し、体重日記 による管理を行い、成果を上げている。我々の 施設では栄養士の協力で個別栄養指導を行い、 肥満の改善を目指しているが、必ずしも成果を 上げていない。いざとなったら、入院による短 期間のダイエットの方法もある。これは中牟田 ら6)の報告であるが、肝移植ドナーに対して短 期間の栄養および運動療法を行い、多くの症例 でダイエットに成功している。具体的には、入 院後、1,400K カロリー/日から開始して2 日毎 に1,200K カロリーさらに1,000K カロリーま で落として、その間に毎日600K カロリー消費 に相当するエアロバイクなどを使用した運動療 法をしてもらう。約2 週間入院して、退院後は 1,400K カロリー/日の食事療法を維持するとい う内容である。我々の施設でNASH の2 症例 に対してこの治療を試したが、2 例とも体重が 減少し、脂肪肝や肝酵素値が改善した。
NASH の薬物療法は確立されたものはない が、病態を考慮した治療薬の選択がなされてい る。NASH はよくDay ら7)が提唱したように Two hits theory がその病態を説明する上で便 利である。すなわち、インスリン抵抗性によっ て脂肪肝が起こり、そこに何らかの酸化ストレ スが加わって炎症をもたらすというものであ る。インスリン抵抗性改善薬として、ピオグリ タゾン、メトフォルミンらが有効との報告があ る。また、酸化ストレスを緩和するビタミンE も有効性が報告されている。我々の施設ではウ ルソデオキシコール酸とビタミンE、ベザフィ ブラートを主に用いている。これらの3 剤いず れかの1 つ以上の処方で約60 %の症例に明ら かな肝酵素の改善を認めた。さらに治療効果を 高めるためには、当然のことながら、徹底した 食事療法が有効である。
(4)NASH の予後と今後の課題
NASH は進行性の病気であるが、肝硬変にな るまではほとんどの場合無症状である。しかし ながら、肝硬変がChild B に進行したあたりか ら、肝不全症状が急速に進行し、欧米では肝移 植を受ける症例も多い。肝不全症状(黄疸、腹 水、肝性脳症)が出始めると治療抵抗性で、ダ イエットもほとんど効果がなく、かえって栄養 状態を低下させ、腹水の増強を招いたりする。
NAFLD の研究には2 つの大きなテーマがあ る。1 つはどのような症例が進行性の疾患であ るNASH になりやすいかということと、2 つ目 が、NASH の中でどのような症例が末期肝不 全に進行するかということである。NASH 発症 に関する1 つのヒントとして、NASH が女性に 多いということが上げられる。NAFLD の多く は単純脂肪肝であり、NAFLD の有病率は男性 が圧倒的に高いが、NASH は女性に多く、特 に中年以降の女性に多い。NASH のリスクファクターとしてよく取り上げられるインスリン 抵抗性や内臓肥満だけでは説明できない現象で ある。一方、末期肝不全に進行するリスクファ クターやメカニズムも解明できていない。肝不 全に進行する症例は痩せていく傾向があり、特 に四肢の筋肉量が低下する。これはウイルス性 やアルコール性肝硬変にもみられる現象であ り、NASH 由来の肝硬変に特徴的という訳で はない。ウイルス性の肝硬変、特にB 型肝硬変 の場合は、抗ウイルス剤の使用で肝不全の進行 を抑えることが可能で、C 型やアルコール性も ある程度原因療法により進行を抑えることがで きる。しかしながら、肝硬変に進行したNASH の場合、肝不全症状が出始めると今のところ打 つ手がないという状況である。したがって、肝 硬変になる前に治療介入し、食事療法や生活習 慣の改善を図るとともに内服薬をしっかり服用 させて、定期的に通院してもらうことが大切で ある。
最後にNASH と発癌との関連であるが、大 まかにいうとB 型やC 型のウイルス性肝硬変に 比較すると肝癌発症率は低く、アルコール性と 同等である。最近、肥満と癌、特に消化器領域 の癌との関連が注目されている。アメリカから の報告8)によると肥満男性はBMI 正常の男性 と比較して、2 倍以上肝癌になりやすいとされ ている。また、糖尿病患者はコントロールと比 較して肝癌を発症しやすいという報告もある9)。 インスリン抵抗性や鉄代謝と関連して出現する 酸化ストレスは発癌の原因となることが知られ ているため、NASH と肝癌との関連が注目され たが、他の原因による肝硬変と比較して肝発癌 が起こりやすいことはない。しかしながら、中 年以降の人口の増加によりNASH は今後ます ます増加するであろうし、それに関連する肝癌 も当然増加する。将来的にはウイルス性肝硬変 から発症する肝癌よりNASH 由来肝硬変から 発症する肝癌の比率が高くなるものと予測さ れ、今からその対策をとる必要がある。
文献
1)Matteoni CA et al: Nonalcoholic fatty liver disease: A
spectrum of clinical and pathological severity.
Gastroenterology 116: 1413-1419, 1999.
2)Brunt EM et al: Nonalcoholic steatohepatitis: a
proposal for grading and staging the histological
lesions. Am J Gastroenterol 94: 2467-2474, 1999.
3)Sakugawa H et al: Clinical usefulness of biochemical
markers of liver fibrosis in patients with nonalcoholic
fatty liver disease. World J Gastroenterol 11: 255-
259, 2005.
4)Sumida Y et al: A simple clinical scoring system using
ferritin, fasting insulin and type Ⅳ collagen 7S for
predicting steatohepatitis in nonalcoholic fatty liver
disease. J Gastroenterol 46: 257-268, 2011.
5)吉松博信:体重コントロール:減量の意義・目標・方
法. 日本医師会雑誌136 : S195-S199, 2007.
6)Nakamuta M et al: Short-term intensive treatment for
donors with hepatic steatosis in living-donor liver
transplantation. Transplantation 80: 608-612, 2005.
7)Day CP et al: steatohepatitis: a tale of two‘hits’?
Gastroenterology 114: 842-845, 1998.
8)Calle EE et al: Overweight, obesity and mortality
from cancer in prospectively studied cohort of US
adults. N Engl J Med 348: 1625-1638, 2003.
9)El-Serag HB et al: Diabetes increases the risk of
chronic liver disease and hepatocellular carcinoma.
Gastroenterol 126: 460-468, 2004.
Q U E S T I O N !
次の問題に対し、ハガキ(本巻末綴じ)でご回答いただいた方で6割(5問中3問)以上正解した方に、 日医生涯教育講座0.5単位、1カリキュラムコード(23.体重増加・肥満)を付与いたします。
問題
次の設問に対し、○か×印でお答え下さい。
- 1)NASH は男性に多い疾患である。
- 2 )脂肪肝症例で肝酵素の上昇する症例はNASH と診断してよい。
- 3)NASH は一般に肝線維化マーカーが上昇する。
- 4)HBs 抗原陽性であれば、脂肪肝があってもNASH は否定的である。
- 5)NASH 由来の肝硬変はウイルス性肝硬変と比較して予後良好である。
CORRECT ANSWER! 2月号(Vol.47)の正解
膵癌診療における最近の進歩
問題
膵癌に関して、次の設問1 ~ 5 に対し、○か×印でお答え下さい。
- 1.肥満は膵癌の危険因子の一つである。
- 2.膵臓の小嚢胞や膵管拡張は膵癌を疑う間接所見として重要であり、精査を行う必要がある。
- 3.膵癌は難治性の癌であり、切除術においては拡大リンパ節・神経叢郭清が必須である。
- 4.Gemcitabine は生存期間延長と症状緩和効果が証明され、遠隔転移を伴う膵癌の一次治療として推奨されている。
- 5.術中放射線療法は有効性が証明され、施行することを推奨されている。
正解 1.○ 2.○ 3.× 4.○ 5.×