更年期障害の診断と治療

ALBA OKINAWA CLINIC 着床研究センター所長
佐久本 哲郎
(Ⅰ)はじめに
更年期障害とは日本産科婦人科学会は、「閉 経の前後5 年間を更年期といい、この期間に現 れる多種多様な症状の中で、器質的変化に起因 しない症状を更年期症状と呼び、これらの症状 の中で日常生活に支障をきたす病態と更年期障 害とする」と定義している。さらに「更年期症 状、更年期障害の主たる原因は卵巣機能の低下 であり、これに加齢に伴う身体的変化、精神・ 心理的要因、社会文化的な環境因子などが複合 的に影響することにより症状が発現すると考え られている」としている。
一方医療現場においては更年期障害の各種の 症状が要因別に示されているが、患者の訴えは さまざまであるところから、その症状と要因を 的確に関連づけることが困難な場合が多い。こ れは更年期障害は各種の要因が複雑に関係して 起こる症候群であるからである。また患者は自 分の言葉で症状を訴えるため、医療者はその訴 えを適切に医学的に判断する必要がある。
本稿においては更年期障害の症状、成因、診 断、治療について更年期医療ガイドブック1)に基づいて解説する。
(Ⅱ)更年期の診断
前述したように更年期は閉経前後5 年間のこ とと定義している。閉経とは卵巣の活動が次第 に低下し、ついには月経が永久に停止すること (Menopause)をいう2)。臨床的には月経が12 ヶ月以上停止した時点で閉経と診断する。子宮 摘出による無月経の場合は性腺刺激ホルモンで あるfollicle stimulating hormone(FSH,卵 胞刺激ホルモン)の値が40mIU/ml 以上でかつestradiol(E2,エストラジオール)値が20pg/ml 以下をもって閉経とする3)。それにた いし更年期は、それまで順調であった月経が不 規則になっていることや3 ヶ月以上の無月経が あり、かつFSH,E2 値が閉経レベルに達しな い状態で判断することができる。すなわち月経 が不規則で、FSH が高値、E2 が低値を示せば 卵巣機能が低下したと考えられる。
(Ⅲ)更年期障害の症状
更年期障害の症状は大別すると自律神経失調 症状、精神的症状、その他の3 種類に分けられ る(表1)4)。症状の原因としては、女性ホル モンの低下に伴う内分泌学的変化、患者をとり まく環境の変化に起因する心理社会的変化など が複雑に関与して表現されると考えられてい る。主な症状について下記に述べる。
表1 更年期障害の諸症状
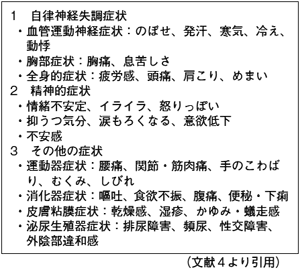
(1)肩こり:首筋から肩胛骨にかける重い感 じ、張った感じ、不快感をいう。約50 %にみられる。
(2)ほてり(ホットフラッシュ): 2 ~ 4 分 間持続する熱感および発汗があり、血圧変 動がないまま頻脈になる。顔面からはじま り頭部、胸部、全身へと広がる。臨床的に は顔面のほてり、発汗のみを訴えることが ある。約60 %に認める。
(3)頭痛:器質的疾患(脳血管障害、頭蓋内 血腫)などをはじめに除外することが重要 である。痛みの起こり方と経過を理解する ことが大切であるので、発症の頻度、強度、 前兆、心理的ストレスの有無など把握する。
(4)易疲労感:更年期症状と考えられている が、非特異的症状であり、あらゆる疾患に 認められる。貧血や低血圧など身体所見に 異常が無く訴えのみが強い場合にはうつな どの神経疾患の除外は必須である。
社会的要因からおきていることが多いので 問診が重要である。
(5)腰痛: 原因として運動器疾患があげら れる。この場合体動により増強し安静によ って軽快する。症状の持続時間で分類さ れ、急性腰痛は6 週間以内で消失、3 ヶ月 以上持続する場合は慢性腰痛とよばれる。 更年期女性の腰痛には変形性脊椎疾患、解 離性大動脈瘤、十二指腸潰瘍や膵炎などの 疾患の鑑別が重要である。
(6)不眠:頻度の高い訴えである。入眠障害 (寝付きが悪い)、熟眠障害(眠りが浅い)、 早朝覚醒(早朝に目覚める)がある。
(Ⅳ)更年期障害の診断
本症の診断には、月経が不規則になってきて いること、種種の症状からE2 低下と関連が深 い血管運動障害(ホットフラッシュや発汗など) を認めること、各種の器質的疾患の除外および 精神疾患の除外に加え、症状が日常生活に大き な影響を与えていることに留意することが重要 である。表2 に更年期障害と鑑別を要する他科 の疾患を示した5)。それぞれに対応する検査を 加えて鑑別することが肝要である。具体的には肩こりの場合は血圧測定、頸椎のレントゲン、 必要ならCT,MRI を行う。ホットフラッシュ や発汗などの場合甲状腺機能検査、ECG が有 用である。倦怠感の場合は肝、腎機能検査、血 糖、CBC、CRP、血清脂質の検査を行う。腰 痛の場合は整形外科的検索が必要である。
表2 更年期障害と鑑別を要する他科疾患
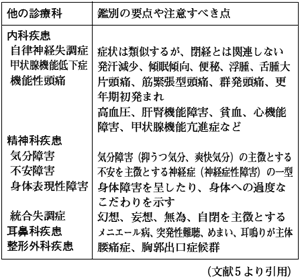
更年期症状の評価には以前より質問用紙によ るKupperman index6)や簡略更年期指数(SMI) がある。これらは症状の点数化により状態を把 握し、治療効果をみるのに用いられている。 2001 年日本産科婦人科学会生殖・内分泌委員 会による日本人女性の更年期症状評価表も有用 である7)。
(Ⅴ)更年期障害の治療
更年期障害の治療にはホルモン補充療法 (HRT)、漢方療法、向精神薬療法がある。更年 期障害における各種の症状のうち、ほてり、の ぼせ、発汗、動悸などの血管運動症状が閉経前 後にまず認められる。遅れて頭重感、不眠、不 安、憂うつなどの精神神経症状が出現する。そ の後易疲労性、肩こり、腰痛などの運動神経症 状が加わる。泌尿生殖器の萎縮症状、骨粗鬆症 などは閉経後数年以上経過してから増加する。 それ故治療にあたっては症状を引き起こしてい る要因を考慮して決めることが大切である。
(1)ホルモン補充療法(HRT)
ホットフラシュなど重症な血管運動障害 や尿道・膣粘膜の炎症性症状などエストロ ゲン低下、欠落に伴う症状にたいしてはま ずHRT を行う。HRT をおこなうにあたっ ては禁忌に注意をはらう必要がある。それ を表3 に示した8)。禁忌の症例は勿論であ るが、沖縄県においてはメタボリックシン ドロームの増加が指摘されているところか ら、BMI25 以上の肥満例や、37 才以上で 一日15 本以上の喫煙者へのHRT 施行は血 栓症発症のリスクが高いので注意を要す る。2002 年のWHI(Women’s Health Initiative)の中間報告でHRT の有用性よ り有害事象が強調された。しかしながらそ の後の詳細な検討から日本産科婦人科学会 と日本更年期学会は安全なHRT の施行に あたっては、5 年以内の施行、60 才未満あ るいは閉経後10 年以内、エストロゲンの 投与経路・種類、メドロキシプロゲステロ ンアセテート(MPA)の種類に注意すれ ば安全に行えることを発表した9)。また HRT 施行にあたっては乳ガンのスクリー ニングが重要である。
表3 ホルモン補充療法禁忌
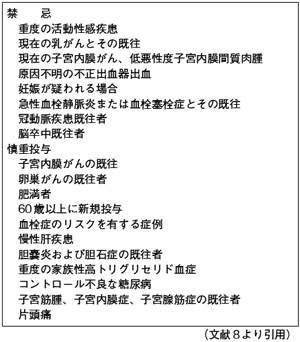
使用薬剤
経口エストロゲン製剤:最も汎用されて いるのは結合型エストロゲン(CEE,プ レマリン)である。悪心,嘔吐などの消化 器症状がおこりにくく、長期投与を行う HRT に適している。0.625mg /日投与す るが、半量投与や隔日投与もある。最近新 たに経口エストラジオール剤(ジュリナ) も使用可能である。
経皮吸収型エストロゲン製剤:エストロ ゲン添付剤(エストラーナ、フェミニス ト)は近年普及している。貼付剤は末梢血 管から直接吸収されるため血中濃度が安定 し、肝臓での初回通過効果を回避し、胃 腸、肝障害が起こりにくく、血中トリグリ セライドの上昇を抑える利点がある。一日 1 枚(0.025mg)の貼付を一日おきに行う。
HRT の投与方法
子宮を有するかどうかで投与方法が決め られている。すなわち子宮を有する女性に エストロゲン単独で投与すると子宮内膜癌 の発症を増加させ、黄体ホルモン剤の併用 で減少するということが1960 年代に報告 された。このことより子宮摘出後の女性に はエストロゲン単独投与、子宮を有する女 性にはエストゲン・黄体ホルモン剤投与を 原則とする。
(A)cyclic sequential method
結合型エストロゲン0.625mg /日を25 日間投与する。
後半の12 日間に黄体ホルモン剤MPA を 5mg/日併用する。
休薬中(5 日間)に消退出血がおこる。
5 日間の休薬後同様に投薬する。
(B)continuous combined method
結合型エストロゲン0.625mg と黄体ホル モン剤MPA2.5mg を持続的に投与する 方法である。この投与で子宮内膜が萎縮 するために行われた方法であるが、不正 出血がしばしばおこるのが欠点である。
このような場合再度(A)の方法を行なって不正出血を改善してから本法に戻る と良い。
その他に(A)と(B)の変法があるが 詳細は更年期医療ガイドブックを参照して ください。
(2)漢方薬療法
漢方薬はよく知られており、副作用も少 なく、更年期の不定愁訴に汎用されてい る。またHRT や向精神薬との併用も可能 である。近年、漢方薬の更年期障害への効 果のエビデンスが日本東洋医学会から報告 されてきた10)。それによると漢方療法(当 帰芍薬散、加味逍遥散、桂枝茯苓丸)と HRT は同等の効果があることが報告して いる。症状別にみると咽頭症状、心悸亢 進、めまいなどに漢方が有効であるとして いる。2005 年から2008 年に弘前大学を中 心にした多施設共同無作為化二重盲検群間 比較試験で行った更年期不定愁訴に対する 加味逍遥散ならびにHRT の効果の検討で は、抑うつ、不安、睡眠にたいする効果は HRT、加味逍遥散とも差はなかった。加 味逍遥散がより有効であると考えられた症 状は入眠障害、興奮、イライラ、めまい、 手足のしびれであったのに対し、HRT は 夜間覚醒、ささいなことが気になる、抑う つ、肩こりに有効であったとしている。
いずれにしても漢方薬を適切に選択する にはいわゆる証を見極めて治療を行う随証 療法に精通することが必要である。
(3)向精神薬療法
主に不安症状、不眠、抑うつ症状などの 精神神経症状に使用する。
抗不安薬としてはエチゾラム(デパス)、 クロチアゼパム(リーゼ)、ジアゼパム (セルシン、ホリゾン)、オキノゾラム(セ レナール)、などがある。
抗抑うつ症状、抗うつ病薬には各種ある が、近年うつ病の標準的治療ガイドライン では軽度、中等度の状態に対する第一選択 は選択的セロトニン再取り込み阻害剤 (SSRI)またはセロトニン・ノルアドレナ リン再取り込み阻害剤(SNRI)である。 SSRI にはパロキセチン(パキシル)やフ ルポキミン(テフロメール、ルボックス) が、SNRI にはミルナシピラン(トレドミ ン)がある。
更年期障害の治療に用いる抗うつ剤、抗 不安剤は精神疾患患者より少量ではある が、患者個々により用量は大きく異なり、 副作用も違う。それゆえ向精神薬の使用に あたっては専門医の意見を参考にするのが 望ましい。
(Ⅵ)おわりに
社会の高齢化に伴い健康長寿をいかに維持す るかが問題となってきている。
女性のライフステージを考えれば更年期は通 過点にしかすぎない。この時期の女性のホルモ ン変動や社会、生活環境を理解することによ り、更年期障害により的確に対処することがの ちの健康長寿につながることと考える。
文献
1)日本更年期医学会編:更年期医療ガイドブック.東京、2008
2)日本産科婦人科学会編:産科婦人科用語集・用語解説集.改訂第2 版、東京、2008
3)Speroff L,Fritz MA,: Menopause and perimenopausal
transition. In Clinical gynecologic endocrinology and
Infertility. 7th edition. Lippincot Williams & Wilkins,
Phyladelphia 2005, 621-688
4)相良洋子:女性ホルモン補充療法の再評価-いわゆる
更年期障害に対するHRT の効果.産と婦8(41):
1043-1049, 2003
5)岩本一朗、堂地勉:更年期の不定愁訴とその対応.産
婦人科治療100(4):370-376, 2010
6)Kupperman HS, Blatt MH, Wiesbader H et al. :
Comparative clinical evaluation of estrogenic
preparations by the menopausal and amenorreheal
indicies. J clin Endocrinol Metab 13: 688-703, 1953
7)日本産科婦人科学会生殖・内分泌委員会:日本人女性
の更年期症状評価表.日産婦誌53: 13-14, 2001
8)麻生武志編:ホルモン補充療法. 研修ノートNo54.日
本母性保護産婦人科医会1-43, 1995,
9)日本産科婦人科学会・日本更年期学会編(監):ホル
モン補充療法ガイドライン.東京、2009
10)高松 潔、小川真理子:更年期障害に対する漢方療法-そのエビデンスとHRT との比較-.産婦人科治療100(4):394-400, 2010