第110 回九州医師会総会・医学会及び関連行事
常任理事 安里 哲好
去る11 月12 日(金)から14 日(日)の3 日間にわたり、鹿児島市におい て九州医師会連合会総会・医学会並びに関連諸行事が開催されたので、その 概要を報告する。
Ⅰ.第100 回九州医師会連合会臨時委員総会
日 時:平成22 年11 月12 日(金) 午後5 時〜
場 所:城山観光ホテル(鹿児島市)

定刻になり、江畑委員(鹿児島県)の司会の もと、会が進められた。
九州医師会連合会長挨拶
池田![]() 哉九州医師会連合会長(鹿児島県医師
会長)より概ね次のとおり挨拶が述べられた。
哉九州医師会連合会長(鹿児島県医師
会長)より概ね次のとおり挨拶が述べられた。
この度、九州医師会連合会の委員総会が第 100 回という大きな節目を迎えたことは、誠に 感慨深いものがある。九州各県の先輩、偉人の 方々が幾多の困難を乗り越え、努力を重ねなが らこの会を営々と築いてこられたことに対し深 く敬意を表したい。
さて、昨今の医療環境を考えると、高齢者窓 口負担増、国民皆保険制度の根幹を揺るがし、 市場原理につながる医療ツーリズムや医療にお ける総合特区構想等様々な問題が浮上してきて いる。
私ども九州医師会連合会は、これまで以上に 日本医師会を強力に支えながら、医療崩壊を阻 止すると共に、国民が安心できる医療提供体制の再構築と国民皆保険制度の堅持を強く訴えて いきたいと考えているので、皆様の特段のご理 解とご支援を賜りたい。
来賓祝辞
原中 勝征日本医師会長 (代読 横倉義武副会長)
横倉副会長より、まず、今年の4 月から日医 役員に九州医師会連合会より小職と今村定臣常 任理事、藤川謙二常任理事を推薦、当選させて いただいたことに対するお礼が述べられた後、 以下のとおり祝辞の代読があった。
第100 回の九州医師会連合会委員総会の開催 を衷心よりお祝い申し上げる。
医学・医術の恩恵は、社会生活と遊離しては 存在し得ないものである。そして、医師会の存 立の使命は、社会生活と医師との仲介である。 医師は進んで医師会に加入することで、社会に 対して医師の責任を認識すると共に、医療の正 当なる名誉と適正な対価を医師会活動を通して 保持していかなくてはならない。そのために も、医師会員の融和・団結を図る必要がある。 本日から開催される九州医師会連合会の諸行事 はまさに強固な医師の団結に繋がるものと確信 している。
日本医師会は、わが国を日本一の健康長寿国 に導いた国民皆保険制度の堅持を主軸に、真に 国民が求める医療提供体制の構築に向けて、国 民と共に努力していくので、九州医師会連合会 の先生方のより一層のご支援をお願い申し上げ 挨拶とする。
座長選出
慣例により、座長に九州医師会連合会長の池 田会長が選出された。
報 告
1)第314 回常任委員会について
本委員総会に先立って開催された第314 回常 任委員会の報告・協議内容が、本委員総会の報 告協議と重複するとして、報告は割愛された。
2)九州医師会連合会事業現況について
池田委員(鹿児島県)より資料に基づき、平 成22 年4 月1 日から9 月30 日現在までに行わ れた九州医師会連合会事業(常任委員会、委員 総会、各種協議会等)及び関連行事について報 告が行われた。
3)九州医師会連合会歳入歳出現計について
野村委員(鹿児島県)より資料に基づき、平 成22 年9 月30 日現在の九州医師会連合会歳入 歳出現計について報告があった。
なお、歳入・歳出合計並びに差引残高につい ては下記のとおり。
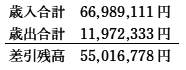
4)第110 回九州医師会医学会および関連行 事について
池田委員(鹿児島県)より資料に基づき、11 月12 日(金)の前日諸会議、13 日(土)の合 同協議会、総会・医学会、14 日(日)の分科 会、記念行事について報告があった。
議 事
第1 号議案 第110 回九州医師会連合会総会 における宣言・決議(案)に関する件
座長の池田会長より、現下の医療情勢を踏ま え宣言・決議の原案を作成した旨の提案理由の 説明が行われた後、三宅委員(鹿児島県)より 朗読があり、審議した結果原案のとおり承認さ れ、翌13 日(土)の総会に上程することが決 定された。
その他
「支払い基金の審査の強化・画一化」について
当委員総会に先立て開催された常任委員会に おいて、宮崎県医師会の稲倉会長から問題提起 のあった支払い基金の審査強化・画一化につい て、日本医師会横倉副会長から、その現状につ いて概ね以下のとおり報告があった。
今年の4 月に「審査支払機関のあり方に関す る検討会」が発足し、私は第2 回目の検討会から 参加し、昨日は第9 回目の検討会が開催された。
何故、検討会が立ち上がったかと言うと、規 制改革会議の議論の中で、審査会が独占業務を 行っており、競争のないものであると指摘され たこと。また、電子レセプト、電子請求がレセ プト枚数の8 割近くなっているとして、審査を 全て電子化できないものかと保険者側が強く求 めているためである。
このことについて、私どもは、医療の特殊性 ということから、機械審査だけでできることで はないと常に主張し続けている。また、全国の 審査実態がどうか確認するよう求め、全国から 十数人の支払基金の審査委員会委員長若しく は、国保審査委員会の会長に意見陳述をしてい ただいた。その意見陳述の中でも支部間の格差 が多く認められた。
実際に、福岡県と山口県のレセプトを相互に 交換して審査を行い、さらに、両方のレセプトを 千葉県に送って審査してもらったところ、やっぱ り格差があったということである。
また、各支部の審査委員長に対するヒヤリン グの中で、審査委員長は「審査委員の負担が大 きい、それぞれの地域の診療行動に幾分かの差 異が出ることはいたしかたないと言うことを支 払い側は認識してほしい」と口を揃えて話しを していた。
ただ、審査の実態について種々話し合いをす る中で徐々に理解が得られるようになってい る。検討委員会では、審査判断基準として明文 化されたスタンダードは必要である。しかし、 それぞれの地域特性に応じたある程度の差異が あっても仕方ないと言う意見にほぼ集約できつ つあるが、難しい面もある。
それに対し、支払基金の意見は、現行のルー ルは、個別性を重視する医療との関係で、相当 程度の裁量の余地が認められている。そのため に様々な解釈が成立する。これは、都道府県単 位の審査委員会がそれぞれでローカルルールを 設定せざるを得ない要因になっている。審査の 不合理な差異を解消するには支払い基金におい て、専門分野のワーキンググループを編成し、 審査委員会からの審査照会の実施等、審査委員 会の強化に取り組むばかりでなく、厚生労働省 においても保険診療ルールの解釈に混乱を生じ ないような保険診療ルールの明確化に取り組む 必要があるとしている。
また、当検討会に出席されている内保連の前 の会長である斎藤先生は、国民皆保険の中で審 査基準の地域間格差があることがおかしいと言 う指摘は一般論としてはある程度理解できる。 しかし、これまでの議論で、地域の審査の実態 を聞くと、医療提供体制や疾病構造、患者の年 齢構成、県民一人当たりの医療費に相違があり、 格差もある程度納得できる部分もある。一律の 審査基準を押し付けることが、地域住民の幸せ に繋がるのか、リーズナブルな格差は是認して もいいのではないかとの意見を述べられていた。
これを受けて座長は、審査基準については、 審査のルールが診療側にもわかるようにしてい く必要がある。リーズナブルな格差とはどうい うものなのかについては今後究明する必要があ ると発言をした。
コンピュータ審査に関する議論については、 専門家から説明があり、コンピュータ審査につ いて、ある程度の問題点は集約できるが、最終 的に査定するかどうかは人間の目が必要である と話をしていた。健保組合等からは、当初、保 険者が主張していた審査委員のいらない審査を との声は少なくなってきた。
しかし、昨日の検討会で次の新たな問題があ がってきた。
支払基金の審査と国保の審査が一緒できない ものかという議論がでてきた。レセプトソフト の統一化はできると思うが審査の統一には問題 がある。
再審査の問題として、1 回目再審査は原審を 行った審査委員が行うが、それに納得でいなく て再々審査となった場合、同じ審査委員が行っ ても両方納得しないのではいかないということ で、再々審査の場合はブロック単位で審査会を 設置してはどうかとの意見があがっている。
直接契約の問題、これは3 〜 4 年から調剤薬局と保険者が直接契約を行い、保険者が審査を しているという実態がある。これは医科にもち 込まれる可能性もあり、そうなるとフリーアク セスを阻害することになりかねないので、医科 まで広げるのは反対と主張している。しかし、 保険者側は直接契約したいという意志がある。
また、ある健保組合から、保険者に領収書を 提出させ、保険請求と突合せたら恒常的に4 〜 5 %の不正請求があると、とんでもない発言があ った。もし、それが事実であれば医師会としても 厳しく対応するが、領収証がないからといて不正 請求というのは判断が間違っている。医療機関 も一部負担金の未払いに苦労している。そのよ うな時は領収証はない。しっかり精査をしてエビ デンスに基づいて発言するよう注意を促した。
以上のように、審査の問題、支払基金のあり 方の問題等が種々議論されているが、格差をど の程度認めるかと言うことについては、診療ル ールで明文化できるところは明文化し、双方の 共通認識の下でやっていくべきである。また、 地域においては文章で明確にできないような格 差もあるので、ある程度の差異は認めなければ ならないということが、検討会における現段階 の共通認識となっている。