沖縄糖尿病週間に寄せて〜連携して糖尿病に打ち克とう!〜

すながわ内科クリニック院長
中部地区医師会理事
中部地区医師会糖尿病標準治療推進委員会委員長 砂川 博司
(1)はじめに
本県は全国一の肥満県である。男性の二人に 一人、女性の四人に一人が肥満である。肥満は メタボリック症候群の要因であり、メタボリッ ク症候群は糖尿病を高率で発症する。本県40 歳以上の糖尿病患者数は約65,000 人、糖尿病 予備軍は約130,000 人と推定される。糖尿病患 者の80 %は医療機関での治療を受けているが、 その半数は治療を中断している。また、治療を 受けていても、血糖コントロールなどの治療が 不十分で合併症が進行してしまう患者も少なく ない。糖尿病性腎症の悪化による新規人工透析 導入率は全国ワースト2 位である。
この状況が続けば、患者さんの生活の質低 下、社会的損失の増大を招くことになる。この ような実状を踏まえ、県内各医師会では、糖尿 病専門医を中心に基幹病院と診療所医師の治療 連携を展開している。中部地区では「すべての 糖尿病患者にいつでもどこでも高質な標準治療 を提供する」をめざし、2007 年10 月「沖縄県 地域医療連携体制推進事業」の補助を受け「糖 尿病標準治療推進委員会」(以下標準治療推進 委員会)を組織した。専門医・かかりつけ医・ 看護師・保健師・栄養士・薬剤師が連帯し、 「発症を減らす」「中断者を減らす」「合併症の 進展を阻止する」取り組みをしているのでその 概要を報告する。
(2)委員会発足の経緯と目的
中部地区の成人人口は約20 万人、そのうち 約10 %(2 万人)は、治療中断および未治療 者(1 万人)を含む糖尿病患者、約20 %(4 万 人)は境界型であると推定される。およそ6 万 人の早期介入および治療が必要な糖尿病患者に 対して、糖尿病を専門とする医師は少数であ る。糖尿病患者が地域基幹病院を含む中核的病 院と専門クリニックに集中している現況もあ り、今後増え続ける糖尿病患者に十分対応でき るか、課題は大きい。
そこで、地域の専門医が中心となり、かかり つけ医を巻き込んだ日常診療における糖尿病標 準治療の実践、顔の見える関係づくりに取り組 むことになった。標準治療指針委員会の発足で ある。委員会の構成メンバーは、糖尿病専門の 医師6 名、保健所医師1 名、保健師2 名、栄養 士1 名、薬剤師1 名の総勢11 名、活動の目的 は、「糖尿病地域医療連携システム」の構築 (表1)である。
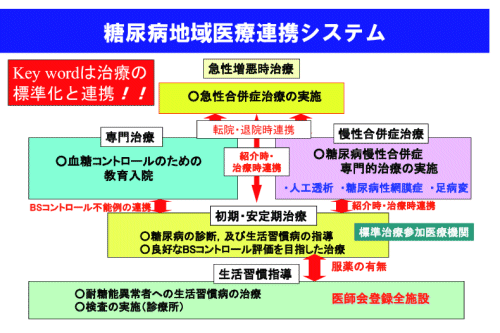
表1
「治療の標準化と顔の見える連携」をキーワ ードに、5 年計画で、「急性増悪時治療施設、 専門治療施設、慢性合併症治療施設等、中核的 病院(専門施設)および専門医の役割の明確 化」「初期・安定期治療を担う施設および医師 への糖尿病治療技術の移転」「糖尿病医療連携 パスを用いた中核的病院(専門施設)と地域診 療所の医療連携」を行うこととした。めざすは 「ひとりの糖尿病患者を、血糖コントロール状 況や病態に応じて、地域の医療機関が連携して サポートする体制」の確立である。
(3)委員会活動状況
糖尿病地域医療連携システムの構築段階を表2に示す。
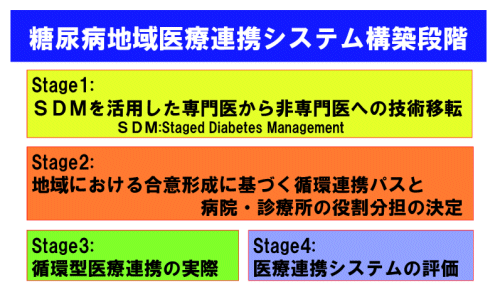
表2
Stage1(2007 〜 2009 年)では、糖尿病診 療技術移転のためのティーチインの場を設定し た。テキストには「SDM(Staged Diabetes Management2008)」「糖尿病標準治療ガイド (日本糖尿病学会編)」「糖尿病治療のエッセン ス(日本糖尿病対策推進会議編)」を採用、糖 尿病専門医による全体講義・講演会(奇数月)、 中核的病院(沖縄県立中部病院・中頭病院・翔 南病院・ハートライフ病院)医師と近隣診療所 医師との症例検討会(Small Group Meeting) (偶数月)をそれぞれ実施した。年間12 回実施 される講義・講演会・スモールミーティングに 1/3 以上出席した医師へは「修了証」が発行さ れ、それぞれの医師が所属する医療機関は「糖 尿病標準治療施設」に登録される。2010 年7 月現在、2 病院36 診療所が「初期・安定期治 療施設」に登録され、「糖尿病の診断および生 活習慣病の指導」「良好なBS コントロール評価 を目指した治療」を展開している。
講義・講演会・スモールミーティングへの医 師およびコメディカル(看護師・栄養士・保健 師・薬剤師)の参加延人数は、2007 年度: 94 名、95 名、2008 年度: 213 名、162 名、2009 年度: 311 名、408 名である。5 年がかりの長 期計画で取り組んだ事業のため、なかだるみや マンネリも危惧されたが、参加者は会を重ねる ごとに増え続けている。地域の先生方の糖尿病 治療に対する熱意と意欲、「地域の糖尿病患者 は地域で支援する」という連帯の輪の広がりを 実感している。
(4)今後の取り組みについて
2010 年の今年はいよいよStage2 へ移行す る。Stage2 では、「インスリン治療の導入・維 持方法」の研修と並行して、地域循環パスの作 成、病院・診療所の役割決定、検査項目および スケジュールの確認、逆紹介・バリアンス基準 の確立を行っていく予定である。 Stage3(循環型医療連携の実施)、Stage4 (医療連携システムの評価)については、本事 業最終年度となる2011 年をめどに完成させて いく予定である。
医療連携の実施に際しては、医療機関相互の IT ネットワークシステムの構築・活用等も視 野に入れている。連携評価については、1) 新規 患者数(境界型から糖尿病移行患者数)は減少 したか?2) 未治療・中断者は減少したか?3) 合 併症進展患者数は減少したか?(例、透析患者 数の減少、下肢切断数の減少等)4) 地域の糖尿 病患者の満足度は高まったか?などの項目を掲 げ、継続的評価と検証を行っていく予定であ る。地域の疫学的データとして蓄積することが できれば、将来的には地域の健康管理データベ ースとして糖尿病の予防・治療管理、早世予防 (沖縄県の長寿復活)に活用できるのではない かと考えている。
(5)おわりに
糖尿病はもはやすべての診療科にまたがる疾 患となり、地域かかりつけ医の果たす役割はま すます重要となった。潜在的糖尿病患者のほり おこしと早期介入、継続治療は、地域医療の中 心的役割を担う、かかりつけ医の存在なしには 実現しない。地域の医師および各医療機関が連 携して糖尿病患者の早期介入、継続治療に取り 組むことによってはじめて、糖尿病治療の最終 目標である「合併症の進展阻止」「健康な人と 変わらない日常生活の質(QOL)の維持」「健 康な人と変わらない寿命の確保」に一歩近づく ことができると確信する。