「沖縄県医師会労災部会」について
沖縄県医師会労災部会の歩み

労災部会長 久場 長毅
県医師会報に労災部会についての記載が少な いので、35 年以上も前の事でもあり、歴史み たいに大げさなタイトルで纏めるのはいささか 気が引けるが、嘗て「労災医会と云う数人の外 科医で発足した集まり」から出発した労災医会 について薄れた記憶をたどりつつ報告する。
日本本土では、労災保険制度は、昭和22 年 から開始されている。
米軍統治下の沖縄では、1953 年(昭28)に 労働基準法が成立し、1964 年(昭39)に労働 者災害補償保険法が施行されたが運用について は、流動的であったとのことである。
労災保険診療に関する件では、支払い方法の 改善と支払い期間の短縮についての要望が記載 されている。(労災医会発足当時の労災保険指定医会役員名を以下表2 に示す)
会長:山田之朗、伊志嶺玄喜、幸地昭二、他 理事6 名の記載がある。
表2
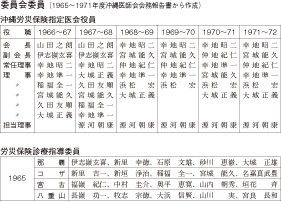
労災医会も次第に参加する医師が増え、組織 も大きくなってきた。
沖縄県に復帰した後にも、何故か私の所に現 在の「県医師会労災部会」の前身である「労災 医会」の商標やドル時代からの復帰前後のもの である領収書等の書類が残っている。県医師会 の県の字がついていないので県医師会とは別の 存在であったらしい。たぶん県医師会も各地区 医師会も現在のように整然としてない時代に外 科系の医師の何人かが主体になって沖縄労働局 との話し合いの場としてできたらしい。
当時、労働災害診療は、自由診療であったか ら慣行料金を労働局との間で設定して請求して いた。問題が生じた時に局と医師側との話し合 いが持たれ、その時出来た「医師側の集まりが 労災医会」であったのだろう。主として外科系 の医師であったが、その他の科の医師もおられ た。新規開業医が労災医を申請した時の相談も 「労災医会」が受けたらしい。労働局側からは、 労災医療に適正な加療がなされているか「労災 医会」に審査相談を嘆願され、それが恒常化し て労働局側では「労災指導委員会」と呼ぶよう になったと思う。委員会が何を指導するのか当 初はよくわからなかったが労災医療の審査委員 会みたいなものであった。
私の記憶では、復帰前年会長は、幸地昭二、 副会長に浜松宏、外に伊志嶺玄喜、故仲地紀 仁、故宮城能久の先生方がいらっしゃ った。審査に際しては地方労災局側医 師として大城徹先生が参加された。
労災診療費は一点単価12 円と全国 統一され、復帰前の沖縄もこれに準じ ていた。しかし各検査、手術、点滴 注射、心電図、X-P 写真など他府県 ではそれぞれ管理料として特別料金を 設定していたらしい。
九州地区でも労災医療については個 室料金、検査料、手術等に管理料が 加算されており、私共労災医会でも 度々九州地区会議と称する会議があ り、福岡県に自腹を切って出張研修を受けたも のである。また、九州労災病院の先生を招聘し て講演してもらった事もあった。労災医も20 名を越えるようになり、皆の為に自腹を切って 福岡県の会議に出席したり、講師の招聘する時 の費用などが必要と云う事になり労災医会の会 費を徴収することになった。以後今日まで毎年 会計報告がなされている。
当時、沖縄の企業が労災保険に加入している 会社は、全国的に見ても低かったが、それでも 労災医療費、休業補償、傷病手当金、その他の 補償を支払っても尚、労災保険金の積み立てに は余裕があったと思われる。
労災事故の多い企業は、労働局からの事故指 導のため公共事業がもらえない等の不利益があ った。その上、労災事故のない企業は、表彰さ れるので治療費を密かに企業が支払ったり、社 長のポケットマネーで支払ったり、いわゆる 「労災かくし」で、敢えて表に出さないことも あったと聞く。現在では、労災かくしは、犯罪 として取締りの対象になっている。
指導委員会のメンバーも局側の一部の方々 も、沖縄の企業が拠出した金はできるだけ沖縄 の労災医療で消費すべきとの考える人もあり、レセプトの審査も現在よりも緩やかであったか と思う。
日本復帰以前の話ではあるが、特筆すべきこ とに沖縄労働局長と労災医会長との間で度重な る交渉の結果、冷房費の請求いわゆる「療養担 当費(療担と呼んだ)」の覚書が交換されたこと である。一日7 点を5 月から11 月まで支払うこ とを認めてもらった。私ども労災医側は、北海 道では暖房費を認めているではないか、沖縄で は夏は猛暑であり入院室が高温多湿になるので、 創傷が化膿し易く、ギプスを巻いても不潔にな り治療に支障をきたすので冷房費を認めて欲し いとの趣旨であった。交渉が困難だったのは、 寒くて死人が出ることはあっても暑くて死人が でる事はないと労働局側の主張である。困難な 交渉の結果、労働局側がそれではと、冷房費の 名目ではなく「療養担当費」の名目で対応して くださった。半年間一日7 点の療養担当費は大 きな成果であった。この療養担当費は日本復帰 後も続き平成3 年頃廃止となった。また一点単 価を15 円位に上げて呉れと交渉したが、全国統 一だ、との一言で日の目は見なかった。
平成3 年、労災診療費が、健康保険診療規定 に準ずる事になり、日本各地区独自の上乗せ管 理料も、私ども労災医会が苦労して勝ち取った 「療養担当費」いわゆる冷房費も請求できなく なった。
労災保険事業は、1972 年(昭47)日本復帰 とともに、琉球政府から沖縄労働局に引き継が れた。ところで、相互扶助の名の下に沖縄の企 業から集めた労災診療費の余剰保険金は、中央 に吸収されてしまうらしい。
健康保険制度と異なり労災医療は自由診療だ とはいっても、労災診療費請求やレセプト等の 書類審査は厳しくなされている。その支払い業 務量は、膨大なものになり医療技術の複雑化に より診療内容も多様化し点検項目も多くなるな ど専門性も要求された。
一時、労災指導委員会は、午後6 時から9 時 まで月一回の軽食付きで定期的に行われてい た。6 名の委員と地方労災医が参加し激論をか わしたり、教えてもらったり、疑問点は診療側 に確認したり労働局に資料の要求をしたり、治 療上の情報を交換したりした。基本的に労災保 険は、自由診療を建前にしていたので、健康保 険算定基準に従っていたとはいえ、社保や国保 とは違う観点から審査されていたとは思う。
労災診療費、各種請求書・レセプトや事務処 理のスピード化が要求され、全国的に財団法人 労災保険情報センターR o u s a i h o k e n Information Center(RIC)が、1989 年(平 成元年)に厚生労働省より委託を受けて設立さ れた。
当初の趣旨は、各医療関係者が労災医療費を 請求しても、労働局側で労災事故についての調 査があり、労災事故と認められて初めてレセプ トの審査になり、その医療が適正である時支払 いが行われるので調査に時間を要し何ヶ月も支 払いが遅れたりしたので、医療側から治療費の 請求があったらRIC が翌月に立替払いしてく れる為に出来た財団法人と聞いていた。何故か 数年後には、レセプト審査業務はRIC が担当 することになる。
沖縄県では、1991 年(平3 年)RIC が開設 され、同時に、全国共通との理由でこれまで認 められていた「療養担当費」いわゆる冷房費は 廃止されてしまった。
同、平成3 年、労災医会は、幸地昭二会長か ら仲本嘉見先生に引き継がれ、沖縄県医師会の 傘下に入いり、「沖縄県医師会労災部会」と称 している。
ところで、平成4 年突然会計検査が入いっ た。幸い、前年で冷房に要した「療養担当費」 を廃止してあったので他府県と違って特別料金 の採用がない事が評価され、レセプト審査も概 ね適正であるとされ会計検査院からの重大な指 導はなかったといわれる。とは言え、北海道の 暖房費はそのまま残されたらしい。
その時の会計検査の結果、夜間の審査会、軽 食の提供も不可、審査労働局員の残業も不可と なった。
医師の審査会は「労災保険診療指導委員会」と称するようになり、労働局で月1 回、昼間午 後4 時半まで、RIC 職員の事務的審査した診療 請求書レセプトを適正・照会・返戻すべきか疑 問点を再審査チェックしている。労災保険診療 指導医師は、自分の診療時間を割いて審査に参 加するので、開始時間も終了時間もまちまちで ある。幸い現在のところ、大問題になる事例が なく、大勢集まって委員間の討論や相談はなく なった。しかし、診療内容に精通していないこ とがあれば、レセプトチェックの時に何らかの 方法でお互いに相談解決している。
沖縄県では、平成19 年から労災保険請求業 務レセプトは、労災保険情報センター(RIC) に全面的に委嘱している。現在のセンター職員 の勉強振りには、唯々驚かされ感心している。 労災保険の請求は、基本的には赤本・青本にあ る健康保険の診療報酬点数に準じて行っている が、独自に設けられた点数及び金額「労災診療 費算定基準」沿った審査が行われている。平成 20 年久しぶりに会計検査がはいった。沖縄県 は指導が少ない方だが、それでも局員はかなり 神経を使っているようだった。
以上、思い出すままに、労災保険診療関連に ついて米軍統治時代、日本復帰前後、現在に至 るまで「県医師会労災部会の歩み」を報告した。
参考文献
「沖縄労働基準局十年の歩み」
沖縄県医師会歴史―終戦から祖国復帰まで―
(1967(昭42)年度の沖縄医師会会務報告)