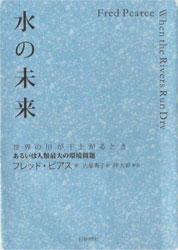世界が生き残るために必要な水の問題

広報委員 石川 清和
水の未来 世界の川が干上がるとき
フレッドピアス 日経BP 社
昔子供の頃に海水浴の後、水浴びをした海岸 のコンコンと湧き出ていた泉の流れが勢いを失 ったのはいつからだろう?農業が主産業の今帰 仁では森林や防風林として木は大切にされてい る。多くの緑が残されているこの土地で地下水 に何が起こっているのか?その答えをこの本が 教えてくれた。
世界の人口はもうすぐ70 億に達する、食料 や衣服を生産するためには膨大な量の水が必要 である。1970 年代の緑の革命により、農作物 の品種改良を行い、荒地・砂漠に灌漑用水路を 開き、河川の水を上流で取水し、農業生産は飛 躍的に増加した。しかし灌漑用水路やダムを作 り、地下水を利用することがさまざまな問題を 引き起こし、水をめぐる問題は地域間だけでな く国家間の問題となりつつある。
上流と下流の国家間で水の利権をめぐり争い が起こり、下流では豊かな自然の恵みが失われ 多くの難民が生じている。インドがインダス川 の上流でダムを作ろうとしパキスタンと深刻な 争いに発展し、核戦争を危惧する声もある。ま た、インダス川上流でインドが乾燥地帯の農業 のため灌漑用に多くの取水を行い、その結果21 世紀初頭にインダス川が河口で干上がってしま い、河口の豊かなマングローブが失われ、漁業 が壊滅的な打撃を受けた。その結果多くの職を 失った人々が都市部に流入しスラム街を作り、 一部はアルカイダの供給源になっているとい う。中国では、黄河上流で砂漠に灌漑水路を作 り、農業が繁栄する一方で、黄河が海に到達す る前に先細り砂の中に消え去るようになった。
砂漠地域では国境付近の二国間にまたがって 存在する地下帯水を一方的にくみ上げて使用す るため、深刻な紛争がおきつつある。地下水 (数千年かけて形成された地下帯水も含め)を くみ上げ乾燥地帯や砂漠で農業を行うことが、 貴重な水資源を枯渇させようとしている。水力 発電を行うためにできるだけ満水にしようとし ている多くのダムは、突然の大雨に対応できず 逆に洪水を引き起こしている。
これらのことは遠い他国のだけの問題ではな い。水の浪費による農業に頼り60 %以上の食 料を輸入に依存し、11 兆円の食料をゴミ箱に 捨てている日本のわれわれにとっても重大な影 響を受ける深刻な問題である。
仮想水を考えると、米1kg = 2,000 〜 5,000l、 小麦1kg = 1,000l、ジャガイモ1kg = 500l、ハ ンバーグ114g = 11,000l、牛乳1kg = 2,000 〜 4,000l、砂糖1kg = 3,000l、コーヒー1kg = 20,000l、1 杯のブランデー= 2,000l、T シャツ1 枚の綿花= 8,000l の水を必要とする。私たちは 膨大な水を 浪費する生 活をしてお り、水の有 難さと、人 類と水の未 来を考えさ せてくれる 1 冊である。