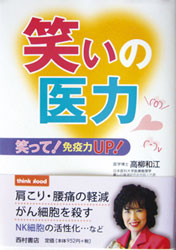将来の兆しがみえる

琉球大学医学部救急医学
久木田 一朗
将来というのは不確定である。私たちには、 将来を考える時、期待と不安が交錯する。しか し、どこかに将来の“兆し”は小さな芽を出し ていて、私たちは気付かないでいるだけかもし れない。気付いている人もきっといると思うが、気付かない人のほうが大部分なので、世間の空 気は今もどんよりとしているのかもしれない。
たとえば、日本の自動車産業は100 年に1 度 といわれる経済危機のドサクサに見舞われ、大 変な事態になっているが、日本の某メーカーは 米国の自動車メーカーを追い越し、世界1 にな ろうとしている。この結果は、もの作りという 分野をみれば、はるか昔、産業革命以前に到達 した日本刀の完成度にその“兆し”があると考 えてみてはどうだろう。「結果をレトロスペク ティブに見るから兆しと言えるんじゃない の?」という反論がさっそく返ってきそうでは ある。しかし、日本刀の完成度を本当に知るも のにとっては、とても納得できることなのだ。
沖縄に来てこの7 月で8 年になろうとしてい る。琉大病院で初年目には麻酔と集中治療、2 年目からは救急医療を主な診療科とするように なった。いずれも命に関わることであり、職業 上気の休まる暇がない。いろんなことを鍛えて こなければならなかったが、この“兆し”をみ ようとすることは救急で患者さんを診る上で重 要な能力とされる。「ICU に急変なし」という 言葉がある。急変とは予想しなかった変化であ るが、ICU の達人に言わせると、「急変と言っ ているのは、その兆しを見逃し、対処を怠った だけなのだ」ということである。
最近、都会でも沖縄でも動物の病院が多く目 につく。中には、診療所がない地域にも動物の 診療所がある。動物診療所は、内視鏡手術や腹 腔鏡手術などもできるようだ。ある元小児外科 の先生の講演で聞いたのだが、最近、日本は小 児の数よりペットの数の方が多くなったのだそ うだ。そういう事情を反映しているのかもしれ ない。ペットより人を大事にしてほしいと思っ ていると誤解しないで頂きたい。私も動物は大 好きである。しかし、日本の医療制度は患者さ んをどこまで大事にしてきただろう。そして患 者さんを大事にする医師をどこまで大事にして きただろう。
元小児外科医の某先生とは東京医療保健大学 の高柳和江先生という。私は遅ればせながら、 最近講演を聞く機会があった。この先生はクウ ェートで10 年間小児外科をしていたそうであ る。その後日本に帰って病院をみてびっくりし たというのだ。クウェートでは小児の患者さん に生きる意欲、勢いがあったというのだ。日本 では子供もしゃちほこ張って寝ているし、回診 だといえば、家族はみんな病室から出されて、 寒そうに子供が取り残され、さあ、胸を開けて と、続く。成人疾患でも、心筋梗塞後にうつに なる患者がみられ、うつを合併すると死亡率が 有意に高まるとの研究もある。そこで彼女が日 本でやりはじめたのが「笑い療法士」、「癒しの 環境研究会」だそうだ。
ともかくその場で、笑う方法を実際にやらさ れたのは学会の特別講演としては異例であっ た。たまたま横にすわった方とペアーになっ て、A さんはB さんを3 つ誉める。B さんは、 ほめられる度に3 回大きな声で「そのとおり」 というのだ。講演のはじめには、座長に向かっ て「ここのみなさん、かたいですね」といわれ ていたのに、これがはじまると会場は笑いの渦 につつまれたのは言うまでもない。日本の医療 事情は暗くなる話ばかり多いが、医療の場の “笑い”は将来の明るい“兆し”ではなかろう か。沖縄県でも那覇市立病院久高学先生の“笑 い”を広める活動は有名だ。救急の場で、笑え ない苦しい時でも、心を通じ合える笑いは患者 さんへの 癒しとな り、治癒 力も高め られると 信じたい。 (写真は西 村書店出 版の「笑 いの医力」 のブック カバー)