平成20 年度九医連医療保険対策協議会
−次期診療報酬改定に対する要望事項−
理事 平安 明

去る1 月24 日(土)、ホテル日航熊本5 階 「阿蘇」において標記協議会が開催されたので、 以下のとおり報告する。
挨 拶
○熊本県医師会 北野会長
本日は各種協議会に先立ち、次期診療報酬改 定について協議を行うということで早めにお集 まりいただき感謝申し上げる。例年は4 月以降 に同協議会を開催しているが、この度日医より 早々と意見を取り纏めるよう依頼があった為、 本日の開催となった。
本会議では来年の4 月1 日の点数改正を見据 え、中医協に対応するため各ブロックから意見 を吸い上げ取り纏めることが目的である。皆様 方のご協力をよろしくお願いしたい。
○日医・中川常任理事
本日はお招きいただき感謝申し上げる。この ように政局が不安定のなかにおいて、診療報酬 改定が年末に控えているが、診療報酬改定率が 何%で決着するのか、私は気がかりでならな い。昨年の12 月24 日に閣議決定された来年度 予算の政府案について、2,200 億円の削減は形 骸化したとの考えがあるが、2,200 億円自体は まだ残っているとの現実がある。日医の執行部 としては「骨太方針2009」からは、社会保障 費2,200 億円の機械的な削減を止めるという文 言を是非入れるよう努力しているところであ る。詳しい内容については会議の中でご説明申 し上げることにして、本日はよろしくお願いし たい。
座長選出
慣例により熊本県医師会前田副会長が座長に選出された。前田座長より診療報酬改定は医師 会の中で最も重要な事項の一つであるので、各 県より忌憚のないご意見を出していただきなが ら、次期診療報酬改定に向けた要望事項を纏め たいと考えている。また中川先生には九州の意 見を中央に持ち帰っていただき、是非御検討い ただきたいと挨拶があった。
協 議
1)次回診療報酬改定に対する要望事項につ いて
最初に、各県より事前に提出された要望事項 について、資料に基づき説明が行われた。
(※資料:次期診療報酬改定に対する要望事項参照)
その他
<中央情勢報告>
○日医・中川常任理事
1)外来管理加算について
先日の中医協において、日医が行った外来管 理加算のアンケート調査の決定を受け、外来管 理加算の期中改定について強く申し入れをした。 これに対して1 号側(支払側)は「減収ばかり を強調し、患者の視点が希薄」であるとして強 く抵抗している。すんなりとはいかないと思う が、我々が強調しているのは外来管理加算の 「5 分要件」という苦渋の決断をしたのは、最終 的には公益側に判断を委ねて決定したもので、 我々は決して納得しているものではないという ことである。デジタル管理加算と外来管理加算 と合わせて240 億円のマイナスなる予想であっ た。それが昨年の4 〜 6 月の日医の緊急レセプ ト調査では800 億円、7 〜 9 月の調査では748 億円となっている。800 億円と740 億円とは有 意差は全くないので、同じと考えてよいと思う。 改定の大前提である見込額をこれほど大幅に 500 億円以上も上回るかつ、TKC の損益分岐点 について4 〜 6 月で見てみると、前年同期の 96.2 %から98.9 %に悪化している。また科別で みると100 %を超えているところもあり、緊急 事態として早急な見直しを求めているところで ある。平成20 年度の社会保障費2,200 億円削減 については、旧政管健保の国庫負担1,000 億円 を健保組合等が負担することを受け入れること から、医療側にもある程度の負担が必要との1 号側からの意見であったが、結果的に廃案にな ってしまった。この大前提がなくなったことか ら医療側の負担についても見直すべきとして、 そこから交渉を始めようと考えている。
2)最近の医療費動向(メディアス)について
厚生労働省の「最近の医療費の動向」(メデ ィアス)が発表されたが、昨年の4 〜 9 月分の 医療費総額として、医科全体で日数補正後、前 年比+ 0.6 %、病院が+ 0.4 %、診療所が0 と なっている。医療費全体としては+ 1.5 %、そ の内訳は調剤が+ 5.4 %、歯科が+ 2.7 %とな っており調剤・歯科が引き上げている状況であ る。いずれにせよ、診療所に関してはかなり苦 しい状況であることが明白となっている。また 大学病院の話が再三出ているが、医療費を経営 主体別にみてみると、大学病院は+ 4.6 %、公 的病院は数が減っているため、− 0.4 %となっ ている。一日当たりの医療費をみると、大学病 院は+ 4.8 %、公的病院は4.4 %で、公的病院 は数は減っているが一日当たり単価としてはプ ラスになっている。TKC 全国会の医業経営指 標では診療所の損益分岐点は、前年同期の 96.2 %から98.9 %と大幅に悪化している。病 院についても92.6 %だったのが、94.9 %とこ れも大幅に悪化している。この原因は先生方も ご存知のとおり、随分患者数が減少している。 これは後期高齢者医療制度が始まったときのマ スメディアのアナウンス等により、高齢者の受 診抑制効果が働いているのだろうと考えられ る。もちろん長期投薬等も考えられるがそのよ うに感じている。何とかこの打開策を探ってい るところである。
中医協において診療所の損益分岐点の話を出 すと、必ず院長報酬等の固定費が多すぎると言 われるが、去年と今年で院長報酬を上げている ところはなく、逆に下げているのではないかと思う。それからすると一定の固定費として考え た場合、損益分岐点が3 ポイント以上は悪化し ていることから、これは説得力のある主張にな るのではないかと思う。
それから診療報酬改定を年末に控えた6 月に 単月調査として医療経済実態調査が実施され、 それを改定の重要な資料にするわけだが、一年 分を12 分の1、経費も12 分の1 にしてという 非常にラフな、改定の専門家から言わせるとそ のようなデータは使い物にならないというよう なデータを用いて改定率の議論を行っている が、現在、中医協では調査実施小委員会を中心 に年間データ、決算データを用いて経営状態を 判断することについて検討されており、実態調 査の方法を変えようと交渉をしているところで ある。最終的には次の改定に間に合うかどうか 分からないが、改定を挟んで前年と次の直近の 一年、この2 年間のデータを各医療機関から頂 き調査することで、ちょうど改定を挟んだ定点 調査となる。これを用いて改定率を検討するよ う強力に申し入れているところである。
3)予算編成の件について
昨年の12 月24 日に閣議決定された来年度予 算の政府案について、社会保障費の2,200 億円 についてはもう問題ないとの話を聞くことがあ るが、私はそれは違うと思う。骨太の方針は小 泉内閣のときから始まっているが、2002 〜 2006 年までの間に、社会保障費の削減が1 兆 500 億円あった。さらに同時に行われた三位一 体改革の社会保障部分について500 億円の削減 があったので、合せて1 兆1 千億円が結果とし て削減された。最初から1 兆1 千億円を目標に していたわけではない。例えば2005 年は500 億円の削減額だし、2006 年は3 千億円の削減額 であった。この1 兆1 千億円を削減できたこと に味をしめた財務省が、今後5 年間も引続きや ろうということで骨太方針2006 に書き込みを したのである。ところが骨太2007 には機械的 に2,200 億円を削減するのではないと基本方針 にあるにも関わらず、7 月末から8 月にかけて の予算概算要求基準には2,200 億円削減と必ず 毎年書くようになった。これが今の大変な状況 を生み出している。2007 年度を例に挙げると、 この時は生活保護の母子加算の段階的廃止に 400 億円の削減と雇用保険国庫負担の1,800 億 円削減とを合せて2,200 億円を手当てしている。
今回の診療報酬改定については、薬価と後発 品及び健保・共済組合等からの国庫負担1,000 億と合せて2,500 億円の財源が手当てできたの で、300 億円余ったものを原資に改定率+ 0.42 の財源になった。今回、介護報酬が3 %上がっ たが、これは2,200 億円の外の部分から財源を 持ってきている。今年の2,200 億円の削減策と して政府案は、年金特別会計に設けられている 特別保健福祉事業資金から1,400 億円、残る 800 億円については道路特定財源を一般財源化 して創設する1 兆円の「地域活力基盤創造交付 金」から600 億円、後発医薬品の利用拡大で 230 億円を充てる考えとなっている。財務省筋 からみると社会保障費の抑制策は230 億円しか 達成されておらず、1,800 億円以上残っている。 財務省の屁理屈だと、今年の年末は2,200 億で はなく4,000 億円削減から始めようと言い出し かねないと危惧している。このようなことか ら、今年の骨太2009 についてはこれを撤廃す ると明確にしなければいけないと考えている。 ただし、仮に民主党政権になった場合にはこの 社会保障費削減が無くなるだろうという考え方 があるが、財務省からみると民主党の方が逆に 組み易いと考えているのでないかと私は思う。
日本医師会では社会保障費の財源として社 保・国保とも保険料の上限額を無くすことを考 えている。上限を無くす事によって4,000 億円 の新たな財源が生まれる。それから特別会計と 独立行政法人、ここに無駄なお金がかなりある と考えている。いわゆる埋蔵金であるが、この 使い道を考えていこうと思う。最後に消費税、 これを考えなければならない。社会保障国民会 議は昨年最終報告を出した。これには2025 年 の医療費を70 兆ぐらいと想定した際に、基礎 年金の安定した財源構成の為、消費税を5 %〜10 %上げよういう話であるが、消費税の国の 取り分は56.4 %しかなく、後は地方に流れる ものである。また、国の取り分である56.4 % の中からは地方交付税として、さらに地方に交 付することが決まっているので、1 %上げても 国は1.5 兆円しか税収がない。現在、消費税は 一般会計の予算総則により、基礎年金、高齢者 医療、介護保険のそれぞれの国庫負担へ充当す ることが決まっているが、基礎年金の国庫負担 分も賄いきれず、5.8 兆円不足している。さら に2 年間先延ばしをして埋蔵金で手当てするこ とになった基礎年金の国庫負担の3 分の1 から 2 分の1 への引き上げ分が2.3 兆円かかり、そ れを加えると既に8.1 兆円の消費税が不足して いる。それで仮に国の消費税を5 %上げたとし ても7.5 兆円の税収しかなく、まだ足りない状 況である。そうなると消費税を5 %上げても医 療費財源には全然足りない。このことを突き詰 めなくてはならない。そうなると財務省は消費 税を10 %、あるいは15 %と上げようとしてく るかもしれないが、冷静に判断しながら年末の 改定率についてロビー活動をやっていこうと考 えている。
4)日医グランドデザイン2009
最後に、2 月の始めに日医のグランドデザイ ン2009 を発表する予定である。そのときに医 師不足対策の日医案を示す予定であるが、結論 としては都道府県医師会の先生方を始め、全国 の病院長、大学病院にもご協力いただいたアン ケート調査を元に、日医では現時点で医師の絶 対数を中、長期的に現在の1.1 倍から1.2 倍にす ることが、適正だという結論になった。これは 医師養成を現在の1.1 倍にすると、10 年後に医 師数が1.1 倍になる。20 年後に医師数は1.2 倍 になる。そのような計算でいこうと考えている。
また医師不足になったもう一つの原因は、医 師の絶対数の不足に加えて「偏在」、これが原 因である。そのきっかけとなった臨床研修制度 の見直したい。臨床研修期間を2 年から1 年に 見直すとともに、医師が医学部を卒業して1 年 間は、各都道府県の地域医療ネットワークに所 属する仕組みを提案する。ネットワークは都道 府県内の大学病院が臨床研修病院としてローテ ーションすることになる。そのときには様々な 問題が発生することが危惧されるが、各地の国 立大学でも卒業すると学生が全部いなくなって しまうということを避ける目的として、卒業し た地元で1 年間臨床研修することによって地域 に根付いた、また、このまま地域に根付きたい という人もかなり増えるであろうという情緒的 なことも考えて進めていこうと考えている。
<質疑応答>
○佐賀県
消費税の問題は、医療機関の損税にも大きく 関わってくる。日医として消費税が増税になる 前に決着をつけるのかどうか。受診抑制につい ても、次回万が一診療報酬が上がらなかった場 合でも引き換えに患者負担を3 割から2 割に引 き下げるといった形で、国民の医療を守るとい う観点から中医協で議論していただきたい。
◆日医・中川常任理事
消費税の問題は、もし引き上げるのが行われ るときには、税制の抜本改革の一環のなかで対 応したいと考えている。受診抑制、窓口負担の 問題についてはグランドデザイン2007 の中に も負担割合を2 割に戻す等、既に提案済みであ るが、これは勿論強調していく。
それから高齢者の為の医療制度であるが、75 歳以上に対する日医案であるが、今回の2009 では今までは保険料プラスの窓口1 割負担とし ていたが、窓口負担分のみとし、保険料は無し にしていきたいと考えている。今の後期高齢者 の方が年金天引きや保険料の値上げの問題を気 にせず、「医療には保険料はいらない」と、そ のようなメッセージを発するべきと考えている。
○佐賀県
医師数の1.1 倍、1.2 倍は労働時間や女性医 師は勘案されているのか。
◆日医・中川常任理事
1.1 倍、1.2 倍の根拠は、全国の病院長に行 ったアンケートとそれに偏在を考慮して計算し ている。厚労省の会では1.5 倍という数字も出 ているようだが、中長期的に医師過剰とならな いよう、また財源を考慮して1.1 倍とさせて頂 いた。
中川常任理事からの中央情勢報告の後、担当 県である熊本県により取り纏められた「次期診 療報酬改定に対する要望書(案)」が示された。 今回、要望する最重点項目並びにその具体的内 容について協議した結果、下記のとおり日医へ 提出することになった。
また、各県医師会より提案された要望事項に ついても参考資料として添付することになった。
<要望書に対する意見・要望等>
○大分県
有床診療所入院基本料について、その役割と 制度的なものを盛り込んだ方がよい。
○福岡県
九州ブロックにおいて提出する要望事項の中 でも、最低限これだけは是非入れたいとする 「最重要項目」を決めた方が良いのではないか。 日医では各ブロックから様々な意見が出される ため、必ずしも我々の要望事項全てが取り上げ られるわけではない。
○日医・中川常任理事
改定の現場では判断できず、実際に現場の先 生方が困っているものを優先的に上げていただ ければよいと思う。
<次期診療報酬改定に対する要望書>
診療報酬改定の要望事項
過去4 回にわたる診療報酬のマイナス改定 と急激な医療制度改革は地域医療の崩壊を引 き起こしており、医療機関はかつてない多く の困難な局面に立たされている。
現今の診療報酬改定は、本来「明確なエビ デンスと検証を踏まえた上で十分議論し対応 する」という基本的な理念ではなく、財政論 が中心となり医療費削減と抑制が目的化され、 このことが今日の医療崩壊を招来した最大の 要因であることは明白である。国民が求める 安心・安全な医療を確保するためには、公的 な医療費財源の確保が不可欠であり、診療報 酬の大幅なプラス改定が是非とも必要である。
平成20 年4 月の診療報酬改定で、大きな国 民的論議を呼んだ、後期高齢者医療制度に連 なる新たな診療報酬項目の後期高齢者診療料 や後期高齢者終末期相談支援料を始めとして、 日常の外来診療に大きな混乱と深刻な影響を 与えている外来管理加算の算定要件の見直し、 特に「5 分間ルール」の設定は最も不合理な ものである。このような医療崩壊の危機の回 避には、国の責務による財源確保と共に正当 で合理的な診療報酬改定が必要である。
以上の観点から九州医師会連合会は次の事 項を最重点要望項目および不合理な診療報酬 項目の問題点を列記し、その実現を強く要求 するものである。
最重点要望項目
1.再診料の外来管理加算算定要件の見直し、
特に「概ね5 分を超える」時間要件の撤廃
2. 初・再診料および時間外、深夜加算の点数
の引き上げ
3.入院基本料(一般病棟、有床診療所、療養
病棟および有床診療所療養病床)の引き上げ
4. 特定疾患療養管理料の対象疾患の拡大と算
定要件の是正
5. 軽微な処置の正当な評価
6. 投薬および処方箋、処方料の是正
7. 疾患別リハビリテーションの均一平等化
8. 手術の技術料と材料費の分離
9. 小児科外来診療料
10.後期高齢者診療料
11.DPC
12.施設基準の簡素化と段階的適用への緩和
13.医療安全・感染防止対策・医療廃棄物処理等費用の正当な評価の新設
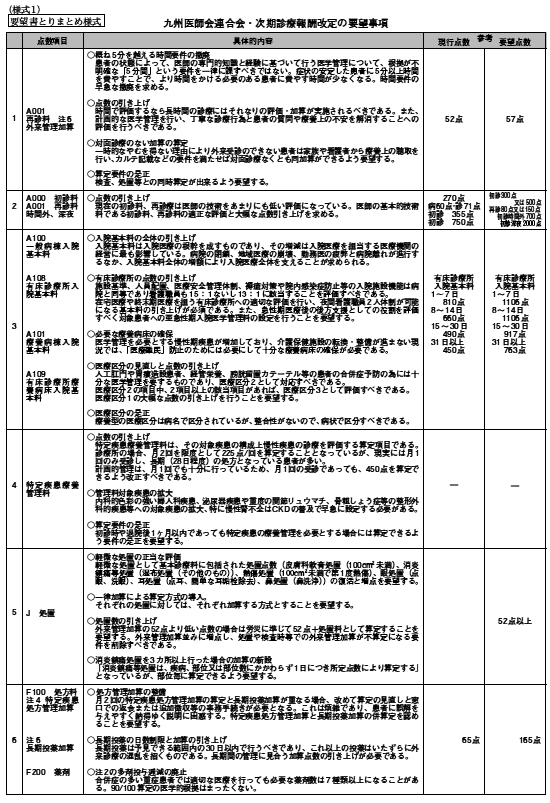
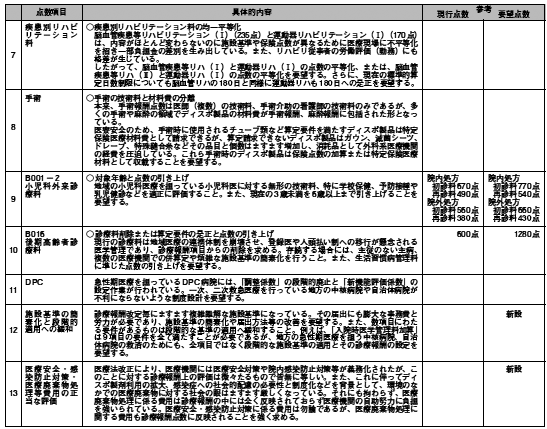
印象記

理事 平安 明
平成21 年1 月24 日、ホテル日航熊本にて九州医師会連合会医療保険対策協議会「次期診療報 酬改定に対する要望事項」についての協議が行われた。この会議は例年4 月以降に開催するよう だが、今回は日医から早々に意見を取りまとめるよう依頼があったとのことである。
小泉内閣の「骨太の方針」として5 年間で1 兆1 千億円の社会保障費を削減することが閣議決 定され、以後医療の現場で様々な問題が表出し医療崩壊が現実味を帯びてきたことは周知の通り である。平成20 年診療報酬改定は特に疲弊が著しい産科や小児科、勤務医に対する手当がなされ た格好であったが、外来管理加算の5 分要件等、想定外の影響が出ており、特に診療所において は経営的に厳しい結果となっている。
各県からの要望は、最重点要望項目として13 項目にまとめられた。外来管理加算算定要件、後 期高齢者診療料など平成20 年改定で経営的にも世論的にも大きな影響があった項目をはじめ、今 後日医で取り纏め年末の診療報酬改定の議論に反映されることとなる。しかし、医療費の総枠が 増えない限り個別の要求が満たされても医療全体としての厳しい状況は改善されない。まずは、 社会保障費の機械的削減を止めることが重要で、日医としても「骨太の方針2009」からは社会保 障費の抑制策の撤廃の文言を入れるよう努力しているとのことであり、今後の成果を見守りたい。