機能性ディスペプシア診療の現状と課題
琉球大学医学部附属病院光学医療診療部
金城 渚
【要 旨】
胃もたれ、胃の痛みは日常の診療でよく遭遇する上腹部愁訴である。このような 症状を有しても、消化性潰瘍や癌などの器質的疾患を伴わない機能性ディスペプシ ア(functional dyspepsia : FD)は頻度の高い症候群といえる。
わが国においては、いまだ“慢性胃炎”とFD の疾患概念の混乱があり、認識は 低い。早急に適切な診断名が必要である。
病態にはさまざまな要因が関与しているとされ、酸分泌異常、消化管運動機能異 常、内臓知覚異常が挙げられる。
それ以上に心理社会的要因の関与も大きいとされ、症状の受容と病態の説明によ る保証が症状改善に結びつくことも多い。
薬物療法としては酸分泌抑制剤、消化管運動賦活剤を中心に用いる。
はじめに
ディスペプシア症状(dyspepsia)とは上腹 部を中心とした疼痛や不快感を意味し、上腹部 愁訴と訳されている。
症状として心窩部痛や心窩部不快感、食後の 早期飽満感や膨満感がある。
ディスペプシア症状を持ち医療機関を受診 し、血液学的検査、消化管内視鏡や腹部超音波 検査を行ってもこれらの上腹部愁訴を説明し得 る器質的疾患が発見されないFD は日常臨床で 多く見受けられる。
かつては、このようなFD 患者を実際には病 気が無いのに症状を訴える心気的性格傾向で、 神経質な患者と考え、診療上軽く扱う傾向があ ったことは否めない。このような訴えには生命 予後への影響は少ないため、あまり重要ではな いといった漠然とした考えがあったからかもし れない。
しかし、実際にはディスペプシア症状が患者 の生活の質(QOL)に与える影響は大きいと 指摘1)されており注目を集めている。
Ⅰ FD の疫学
1999 年に報告された日本と欧米の上腹部症 状の疫学調査では、過去3 ヵ月間で上腹部症状 を有する割合は米国60 %、日本では26 %と報 告2)されている。
厚生労働省統計表データベース(http://wwwdbtk.mhlw.go.jp/toukei/index.html) によると、平成17 年の調査では消化器系疾患 の推計患者総数は、約827 万人であった。その うちディスペプシア症状が多く含まれると考え られる胃炎及び十二指腸炎と診断された患者は 72 万人であり、消化性潰瘍の63 万人より多い。
同省における国民生活基礎調査より、上腹部 愁訴を有する総数の推移は、横ばい状態であ り、減少傾向は見られない(図1)。
平成16 年の同調査においては、“胃のもたれ・むねやけ”の有訴者率は女性で高く、男女 とも加齢に伴って増加の傾向を見る。“胃痛・ 腹痛”の訴えも女性に多く、高齢者より若年者 に多い傾向であったと報告(図2)している3)。
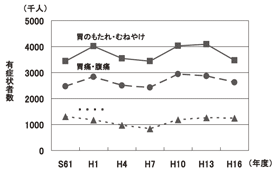
図1.厚生省および厚生労働省大臣官房統計情報部編
国民生活基礎調査に見る上腹部有症状者数の推移
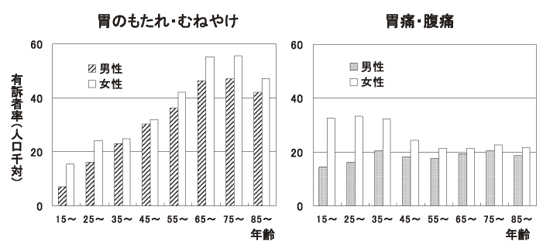
図2.厚生労働省統計表データベースシステム 国民生活基礎調査
(健康表)平成16 年に見る上腹部愁訴の性・年齢別の有訴者率
Ⅱ FD の定義
機能性消化管傷害の分類と診断基準を定めた ローマ国際委員会ではRome Ⅲを2006 年に報 告している4)。診断基準を表1 に示す。
この基準によるとFD は、胃・十二指腸から 発する症状であることが明確になっている。
症状の部位を上腹部に限定しており、前胸部 や腹部中央および下腹部の症状は含めない。
また、Rome ⅢではFD を食後愁訴症候群 (postprandial distress syndrome : PDS)と 心窩部痛症候群(epigastric pain syndrome : EPS)の二つの症候群に分けている。
前者のPDS は食事摂取との関連が強いとい われており、FD の8 割を占めるとされている。 食事摂取早期の飽満感と胃のもたれの2 種類の 症状に限定されている。
後者のEPS は、食事と無関係な心窩部痛と 心窩部灼熱感の2 種類に限定されている。
FD におけるRome ⅡからⅢへの改良点は、 “非特異型”という難解な分類が削除され、症 状に由来する分類となり理解し易くなった。
嘔気・嘔吐、呑気症や気(おくび、げっ ぷ)は別項目に分類され簡略化された。また発 症時期や病悩期間が短縮単純化され臨床上用い 易くなった点である。しかし“6 ヵ月以上前か ら症状があり、3 ヵ月間は上記の診断基準を満 たしている”期間については、臨床医からまだ 長すぎるとの意見もあり、議論の余地が残され ている。
表1.Rome ⅢでのFD の分類と診断基準
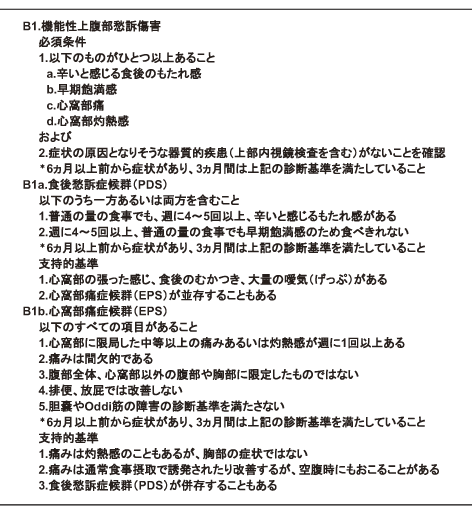
Ⅲ 日常診療におけるFD の診断
FD の診断は、Rome Ⅲに定義される症状を有 し、一般血液生化学的検査、消化管内視鏡、腹 部超音波などのルーチン検査で症状を説明する に足りるような異常所見がない場合になされる。
一般臨床においては、Rome Ⅲで定義される 症状の出現状況をすべて厳格に適応する必要は ないと考える。
ルーチン検査前の問診において消化管出血、 急激な体重減少、高度貧血等の警告症状が除外され、既往歴・検査受診歴、また患者の性格傾 向等から、かなりの確率でFD の診断が可能で ある。
その他、胃排出能検査、消化管内圧測定、内 臓知覚検査などの特殊検査があるが、主に研究 を目的に行われており、一般臨床では必ずしも 必要ではない。
Ⅳ 症状発現の病態生理学的機序
FD の病態にはさまざまな要因が関与してい ると言われており、遺伝的素因、消化管運動不 全(胃排出遅延、胃前庭部・底部の協調運動障 害、胃内食物分布の障害)、内臓知覚過敏、 H.pylori 感染、中枢の問題が挙げられる5)。表 2 に示す。
表2.FD の病態生理学的機序 (文献6 より要約)
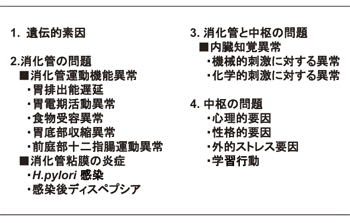
食物が咀嚼され食道を通るときの刺激により 胃底部の弛緩が生じる。これをreceptive relaxation(受容性弛緩)と呼ぶ。食物が胃底 部内に入ると、その圧刺激によりさらに同部位 が弛緩し、より多くの食物を受け入れる反応を adaptive relaxation( 適応弛緩) または accommodation reflex と呼ばれ、最近この反 応の異常が症状と密接に関連すると考えられて いる。
その他、FD の病態には、消化管内腔からの 物理的・化学的刺激、心理社会的ストレスなど の外的要因も加味され、複合的にさまざまな要 因が関与していると推測されている。
Ⅴ わが国におけるFD への姿勢
わが国では、“慢性胃炎”という保険病名の 下でFD に対する治療が行われている。
一般医の中には、“胃もたれ”、“胃の痛み” 等を慢性胃炎の症状であると認識されている方 もいると思われる。
慢性胃炎とは、胃粘膜の病理組織学的炎症や 粘膜構造の変化を指すものである。ディスペプ シア症状とはまったく異質なものであり、同じ 場で議論すべきものではない。病理組織学的に 定義されるべき慢性胃炎とディスペプシア症状 は、全く切り離して考えるべきである。
慢性胃炎は、症状で定義されるものではな い。しかし、消化性潰瘍や癌などの器質的疾患 がない上腹部愁訴に対し、適切な保険病名がな いためやむなく使用されてきた病名でもある。 三輪ら6)は、この学問的な概念の混乱そのもの よりも、この概念の混乱に乗じて安易な治療が 行われてきたことを認識すべきであると指摘し ている。
今後、器質的疾患のないディスペプシア症状 に対する適切な診断名が、速やかに命名される べきである。FD の疾患概念が確立されれば、 この疾患への認識と理解も深まるものと考えら れ、将来より優れた治療法へも結びつくものと 思われる。
Ⅵ FD に対する薬剤の治療効果
FD の薬物治療有効性についてのエビデンス の確認は、必ずしも容易ではない。
対象がすでに内視鏡検査などの検査を受け器 質的疾患を除外された患者(functional dyspepsia 患者)と、ディスペプシア症状を有して いるが未だ検査が行われていない患者(uninvestigated dyspepsia)を区別する必要がある。 この両者によって薬物の有効性が異なるからで ある。検査後のFD 患者に対する薬物治療の効 果はきわめて限られていることが明らかとなっ ている。
質の高い臨床試験におけるメタ解析では、ヒ スタミン受容体拮抗剤(H2RA)およびプロト ンポンプ阻害剤(PPI)は、その効果が限定的 であるものの効果が認められるとされる。
消化管運動賦活剤であるシサプリドは、FD 治療の標準的薬剤と評価された。しかし、循環 器系の副作用による突然死症例が報告されたこ とから2000 年に発売停止となり、市場より撤 退した。さらに、Cochrane Database では、消 化管運動賦活剤によるFD 治療効果は良好な成 績を示すものの、各報告間でのバラツキが大き く、publication bias の可能性が高いとされ、 その効果は疑問視されている7)。一方、日本国 内で行われた大規模臨床試験で、胃炎治療薬を 比較対照としたセロトニン5HT4 受容体刺激剤 であるモサプリドは、ディスペプシア症状改善 に有効であることが確認されている8)。
またFD では、プラセボ効果が強く30 ~ 40 %に認められていることが広く知られてい る9)。これは、単にプラセボ効果ということだ けではなく、インフォームドコンセントの中で 得られた医師-患者信頼関係と、十分な説明作 業と保証がもたらしたものとも考えられる。
FD の臨床試験においては、試験デザイン、対 象者、治療期間の設定、評価方法など治療効果 に影響を与える要素が少なくない。また、前述 のごとくFD の病態は複合的に作用している可 能性が高いことも示唆され、対象集団の偏りに よって治療効果が微妙に左右されることがある。
その他も漢方薬(六君子湯)や抗不安剤・抗 うつ剤などの治療法が試されているが、確実な 効果をもたらす薬剤としての検証には十分とは 言えない。FD に対する治療効果の集積は、今しばらく時間を要するものと考える。
表3 にFD に対し治療効果が期待できる薬剤 を示す。ただしFD 自体が保険病名となってい ないこと、そして一部の薬剤は慢性胃炎、消化 器心身症の保険適応になっていないことに注意 が必要である。
表3.FD に対する薬物療法
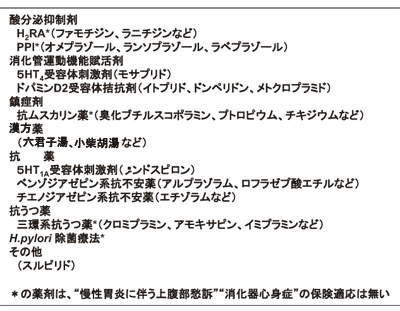
Ⅶ FD の治療方針は?
それでは、FD に対しどのような治療方針が 推奨されるのか?
図3 に興味深いデータを示す。胃酸の上腹部 症状発現への関与を検討する目的で、健常ボラ ンティアを対象に胃内に酸と真水を注入し、被 検者が自覚する症状の種類と程度を検討してい る10)。
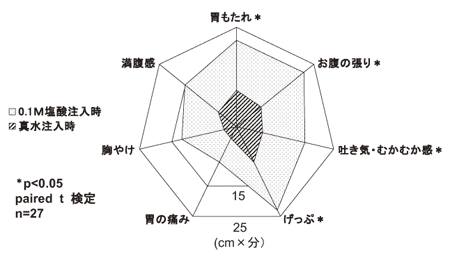
図3.酸および真水による上腹部症状の発現
症状の内容や程度は被検者によって異なって いたものの胃内への胃酸注入は真水に比して有 意に強い症状を誘発し、胃内の酸が症状を誘発 することが明らかとなった。
注目すべき点は、従来消化管運動不全型の症 状と考えられていた“胃もたれ”、“お腹の張 り”、“吐き気・むかむか感”、“げっぷ”の項目 で酸と真水で有意差を認めたことであり、酸が 消化管運動不全型の症状を起こすことが実験的 に明らかにされた。
Lee らは、健常人の十二指腸へ酸を注入し反 応を調べ、酸の注入によりディスペプシア症状 が惹起されることを確認した。さらに酸注入に 伴い胃運動や受容性弛緩が変化し、胃内拡張刺 激に対する感受性が高まることも観察された11)。
胃酸過多はディスペプシア症状発現の一因に 過ぎないが、他の生理学的異常をも誘発するた め、治療初期のターゲットとして胃酸は重要と 思われる。
実際に臨床でわれわれが使用する薬剤でエ ビデンスのあるものは、胃酸分泌抑制剤(特 にPPI)と運動機能賦活剤が主となると考え られる。
胃酸がさまざまなディスペプシア症状を誘発 すること、酸そのものが消化管運動機能異常や 内臓知覚過敏を引き起こすことを考慮すると胃 酸分泌抑制剤が最も有用と思われる。
胃酸分泌抑制剤の単独使用か、運動機能賦活 剤併用による効果が十分に得られるか、否かの エビデンスは今のところ無く、今後の検証を待 ちたい。
薬剤以外では、FD におけるプラセボ効果を 鑑み、症状の受容、その病態の説明と保証、す なわちインフォームドコンセントの中で構築さ れる医師-患者信頼関係も肝要と考える。
文献
1)Enck P, Dubois D, Marguis P?: Quality of life in
patients with upper gastrointestinal symptoms :
results from the Domestic/International
Gastroenterology Surveillance Study(DIGEST).
Scand J Gastroenterol 34(suppl 231); 48-54 : 1999
2)Stanghellini V : Three-month prevalence rates of
gastrointestinal symptoms and influence of demographic
factors : results from the Domestic/International
Gastroenterology Surveillance Study(DIGEST).
Scand J Gastroenterol 30(suppl 231); 20-28 : 1999
3)厚生労働省大臣官房統計情報部編国民生活基礎調査
4)Tack J. Talley NJ. Camilleri M. et al : Functional
gastroduodenal disorders. Gastroenterology 130 ;
1466-1479 : 2006
5)Choung RS, Talley NJ. Novel mechanisms in
functional dyspepsia. World J Gastroenterol 12 ; 673-
677 : 2006
6)三輪洋人、大島忠之、富田寿彦:ディスペプシアに対
する科学的な治療戦略.日消誌. 104 ; 1594-1600 :
2007
7)Moayyedi P, Soo S,Deeks J, et al : Pharmacological
interventions for non-ulcer dyspepsia. Cochrane
Database Syst Rev 1 : 001960 : 2003
8)Hongo M : Initial approach and pharmacotherapy for
functional dyspepsia a large clinical trial in Japan.
Gastroenterology 130(suppl 2) ; 506 : 2006
9)Moayyedi P, Soo S,Deeks J, et al : Pharmacological
interventions for non-ulcer dyspepsia. Cochrane
Database Syst Rev 18(4) : CD001960 : 2006
10)三輪洋人: 胃酸分泌と上腹部症状に関する最近の知
見. 診断と治療94 ; 877-884 : 2006
11)Lee KJ, Vos R, Janssens J, et al : Influence of
duodenal acidification on the sensorimotor function of
the proximal stomach in humans. Am J Physiol
Gastrointest Liver Physiol 286 ; G278-G284 : 2004
著 者 紹 介

琉球大学医学部附属病院
光学医療診療部
金城 渚生年月日:
昭和37年 11月17日出身地:
沖縄県 那覇市出身大学:
福岡大学医学部 昭和63年卒略歴
昭和63年6月 琉球大学医学部附属病院 第1 内科(研修医)
平成元年10月 泉崎病院勤務
平成2年10月 琉球大学医学部附属病院 第1 内科(医員)
平成3年4月 与那原中央病院勤務
平成4年4月 県立八重山病院勤務
平成6年4月 琉球大学医学部附属病院 第1 内科(医員)
平成9年10月 琉球大学医学部附属病院 第1 内科(助手)
平成13年10月 琉球大学医学部附属病院 光学医療診療部(助教)専攻・診療領域
消化器病(上部消化器疾患、H.pylori 関連疾患)消化器内視鏡その他・趣味等
釣り
Q U E S T I O N !
問題:機能性ディスペプシア(FD)について正 しいものを一つ選んでください。
- a.わが国ではディスペプシア症状を訴える 人は、減少傾向にある。
- b.FD の症状は、下腹部の疼痛も含まれる。
- c.ディスペプシア症状と慢性胃炎は同じ症 状である。
- d.FD に対してはプラセボ効果は少ない。
- e.FD 治療には酸分泌抑制剤が第一選択薬 である。
訂正とお詫び
2 月号会報の生涯教育コーナーに掲載いた しました豊見城中央病院の玉城正弘先生の 「無症候性虚血性心疾患をCT で評価する- 冠動脈石灰化指数を中心に-」について、 著者紹介部分(97 頁)の所属医療機関を琉 球大学医学部脳神経外科とあるのは、豊見 城中央病院内科の誤りです。
ここに、訂正し衷心よりお詫び申しあげ ます。
CORRECT ANSWER! 12月号(vol.44)の正解
急性胆管炎診断・治療 ~ガイドラインを中心に~
問題:グリオーマ治療は一筋縄ではいかない難 治性腫瘍であるが、根治が期待できる腫 瘍はどんな場合か?誤りをひとつ選べ。
- 劣位半球に存在する
- 腫瘍の境界は鮮明である
- 非高次機能部に存在する
- 全摘出術が可能である
- 201Tl-SPECT で201Tl の取り込みのある腫 瘍である
正解 5.