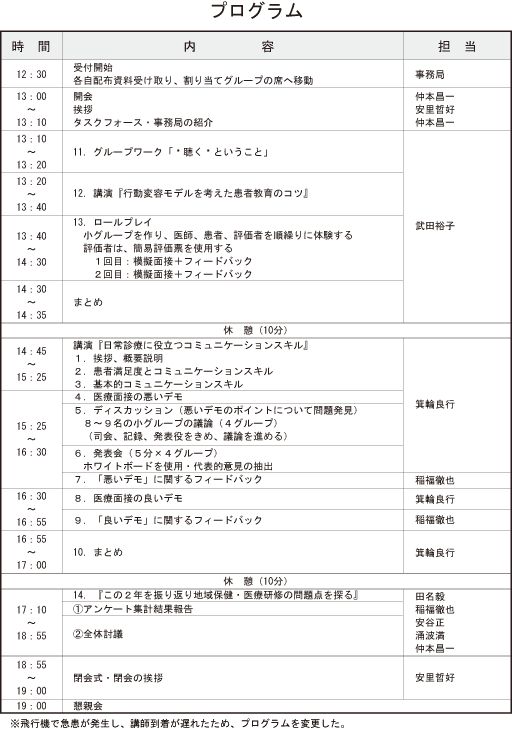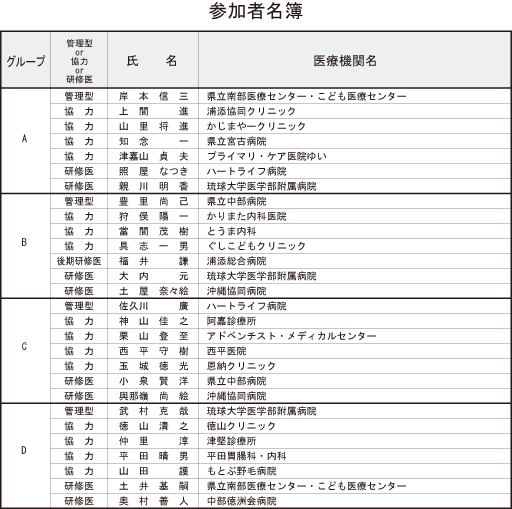戞1夞巜摫堛偺偨傔偺僗僥僢僾傾僢僾島廗夛
乣峴摦曄梕偟丄尋廋堛偲嫟偵恑壔偡傞巜摫堛乣
忢擟棟帠丂埨棦丂揘岲
夁嫀偵丄乽巜摫堛偺偨傔偺嫵堢儚乕僋僔儑僢 僾乿傪3夞峴偄丄偙偺搙乽巜摫堛偺偨傔偺僗僥 僢僾傾僢僾島廗夛乿傪僇儖僠儍乕儕僝乕僩僼僃 僗僩乕僱乮暯惉19擭3寧21擔丄媂栰榩巗乯偵偍 偄偰奐嵜偟偨丅
抧堟曐寬堛椕嫤椡巤愝丒恌椕強堛巘15 柤丄 椪彴尋廋昦堾堛巘4柤丄弶婜尋廋堛8柤丄屻婜 尋廋堛1柤乮寁28柤乯偺嶲壛偺傕偲丄擔掱偼敿 擔僐乕僗側傟偳丄屵屻1帪傛傝巒傑傝崸恊夛傕 娷傔屵屻9帪傑偱懕偄偨丅摉擔憗挬偺懪偪崌傢 偣傪娷傔寁7夞偺儈乕僥傿儞僌傪奐偒丄摿偵崱 夞偺庡梫僥乕儅偱偁傞亀偙偺2擭傪怳傝曉傝抧 堟曐寬丒堛椕尋廋偺栤戣揰傪扵傞亁偵娭偟偰偼 偦偺恑傔曽偵丄擇揮嶰揮傕偁傝丄摉擔傑偱専摙 偟偨寢壥丄慡懱摙榑夛偲徧偡傞戝摙榑夛傪峴偆 偙偲偲偟偨丅
摉擔丄枼椫椙峴愭惗乮惞儅儕傾儞僫堛壢戝妛 媬媫堛妛晹嫵庼乯偑旘峴婡偺拞偱偺姵幰媫曄傊 偺懳墳偺偨傔摓拝偑抶傟偨偺偱僾儘僌儔儉偺弴 彉傪曄峏偟丄10暘娫偺傾僀僗僽儗乕僉儞僌乮僌 儖乕僾儚乕僋乽乬挳偔乭偲偄偆偙偲乿乯偺屻偵丄 晲揷桾巕愭惗乮搶嫗戝妛堛妛嫵堢崙嵺嫤椡尋媶僙儞僞乕彆嫵庼乯偵傛傞亀峴摦曄梕儌僨儖傪 峫偊偨姵幰嫵堢偺僐僣亁偲戣偟偨島墘偑峴傢傟 偨丅偝傜偵丄4偮偺僌儖乕僾偵暘偐傟4柤偺柾媅 姵幰偝傫偺嫤椡傪摼偰丄奺僌儖乕僾偲傕2徢椺 偵偮偄偰丄儘乕儖僾儗僀傪捠偠偰丄堛巘偺栶 妱丄巌夛幰偺栶妱偲僌儖乕僾敪昞幰偺栶妱傪扴 偭偨丅

僌儖乕僾儚乕僋乽乬挳偔乭偲偄偆偙偲乿
亂C僌儖乕僾傛傝偺島墘偺姶憐亃
丒峴摦曄梕儌僨儖偵傛傞姵幰嫵堢偼丄摉堾偺 DM奜棃偱庢傝擖傟偰偍傝丄柤慜偼抦偭偰偄 偨偑丄撪梕偵偮偄偰島媊傪庴偗偨偺偼弶傔偰 偱旕忢偵嶲峫偵側偭偨丅
丒姵幰偺忬懺乮僗僥乕僕乯傪廫暘偵攃埇偡傞偙 偲偑戝愗偱丄偦偺忬懺傪偄偐偵揔愗偵昡壙偡 傞偐偲偄偆嬶懱揑側曽朄傪暦偗偰傛偐偭偨丅
丒奺僗僥乕僕偺姵幰偝傫傪巜摫偡傞忋偱丄帺屓 岠梡姶傪崅傔傞偙偲偑廳梫偱偁傞偙偲傪棟夝 偱偒偨丅
丒旕忢偵偄偄撪梕偺島墘偱偁偭偨偺偱丄傕偆彮 偟帪娫傪偲偭偰嬶懱揑側働乕僗偵偮偄偰傕島 媊偟偰傎偟偄偲巚偆丅

儘乕儖僾儗僀
亂D僌儖乕僾偺姶憐亃
丒妛廗宱尡儌僨儖偐傜丄撉傫偩偙偲偺抦幆曐帩 偼埆偔丄懱尡偟偨偙偲偑岠壥揑偱偁傝仺儘乕 儖僾儗僀傪峴偆偲椙偄丅
丒峴摦曄梕偺僗僥乕僕丗柍娭怱婜仺娭怱婜仺弨 旛婜仺峴摦婜仺堐帩婜仺媡栠傝丅
丒Self亅Efficacy丗帺屓岠梡姶偑戝愗仺庡帯堛 偐傜偁側偨側傜偱偒傞偲尵傢傟傟偽丄帺屓岠 梡姶偑崅傑傞丅
丒栤戣夝寛傾僾儘乕僠丗1乯栤戣傪埖傢偢夝寛傪 扵傞丅2乯僑乕儖傪偮偔傞丅3乯僼傿乕僪僶僢僋 乪偑傫偽傝傑偟偨偹乫4乯儗僼儗乕儈儞僌乽3擔 偟偐懕偐側偐偭偨乿仺乽3擔傕懕偄偨偺偱偡 偐乿偲弎傋偰偄偨丅
枼椫愭惗偼丄偼偠傔偵亀擔忢恌椕偵栶棫偮僐 儈儏僯働乕僔儑儞僗僉儖亁偵偄偰丄乽姵幰枮懌 搙偲僐儈儏僯働乕僔儑儞僗僉儖乿偲乽婎杮揑僐 儈儏僯働乕僔儑儞僗僉儖乿偵偮偄偰島墘傪峴偭 偨丅堷偒懕偒丄乽堛椕柺愙偺埆偄僨儌乿偲乽堛 椕柺愙偺椙偄僨儌乿偵偮偄偰柾媅姵幰偝傫偺嫤 椡傪摼偰儘乕儖僾儗僀傪峴偄丄乽堛椕柺愙偺埆 偄僨儌乿偵偮偄偰偺4僌儖乕僾偛偲偺僨傿僗僇 僔儑儞傪峴偭偨丅
亂乽姵幰枮懌搙偲僐儈儏僯働亅僔儑儞僗僉儖乿偵 偮偄偰丄A僌儖乕僾傛傝偺姶憐亃
姵幰枮懌搙傪堄幆偟偰忢偵恌椕偡傞偙偲偺廳 梫惈傪妛傇偙偲偑偱偒丄枮懌搙偑堛妛偺幙傗堛 椕宱塩偵怺偔偐偐傢偭偰偄傞偙偲傪擣幆偟丄柺 愙偺僐儈儏僯働亅僔儑儞僗僉儖傕戝曄嶲峫偵側 傝丄僗僉儖偺奺崁栚傪堄幆偟丄崱屻偺柺愙偵惗 偐偟偰偄偒偨偄丅

堛椕柺愙僨儌

僌儖乕僾儚乕僋嶌嬈

僌儖乕僾敪昞
亂乽婎杮揑僐儈僯働亅僔儑儞僗僉儖乿偵偮偄偰丄 C僌儖乕僾傛傝偺姶憐亃
忣曬廂廤丄堛巘亅姵幰娭學丄夝庍儌僨儖丄旕 尵岅揑側僐儈儏僯働亅僔儑儞丄堛椕柺愙偱偼 Opended Question傗恌嶡偺嵟屻偵乽傎偐偵 壗偐偁傝傑偣傫偐乿亅Door knob Question丄 懀偟丒妋擣丒嫟姶摍偺僗僉儖偺杹偒曽側偳幚嵺 偵巊偊傞榖偑懡偐偭偨偲弎傋偰偄偨丅
亀偙偺2擭傪怳傝曉傝抧堟曐寬丒堛椕尋廋偺 栤戣揰傪扵傞亁偺僐乕僫乕偼揷柤婤愭惗偺巌夛 偵傛傝恑傔傜傟丄1乯帠慜傾儞働乕僩偺寢壥曬崘 偵偮偄偰愢柧偟丄2乯娗棟宆椪彴尋廋昦堾丄抧堟 曐寬丒堛椕尋廋嫤椡巤愝偲尋廋堛偺3偮僌儖乕 僾偵暘偐傟丄傑偢偼傾僩儔儞僟儉偵栤戣揰傪嫇 偘偰傕傜偄丄1乯偺寢壥偲2乯偺栤戣揰偺拞偐傜拪 弌偟丄3僌儖乕僾傪拞怱偲偟偨戝摙榑夛傪峴偭 偨丅懡偔偺栤戣揰傗堄尒偑弌偝傟偨偑丄帪娫傕 梊掕傛傝30暘埲忋僆乕僶乕偟偰偄偨偺偱丄師偺 5揰偵偮偄偰摙榑傪峴偭偨丅
嘥丏尋廋堛偵懳偟丄偳偙傑偱幚慔偟偰傕傜偆偐丠
丒姵幰偼丄尋廋堛偺恌嶡傪媮傔偰偄側偄偺偑尰 忬偱偁傞丅廬偭偰丄摉堾偱偼尒妛廳帇偱偁 傞丅乮嫤椡巤愝丒恌椕強乯
丒摉堾偺曽恓偼丄姵幰慡偰傪恌偰傕傜偆乮怴 姵丒嵞姵栤傢偢乯丅偦偺拞偱壗偐傪姶偠庢偭 偰傕傜偆丅偦偺屻丄巜摫堛偑恌嶡偟偰偄傞丅 仺帪娫偑偐偐傞丅乮嫤椡巤愝丒棧搰恌椕強乯
丒1廡栚偼丄尒妛丅2廡栚偵怴姵傪恌偰傕傜偭 偰偄傞丅巜摫堛偺徹彂偲尋廋堛偺幨恀傪懸崌 幒偵挘傝弌偟偰丄姵幰偝傫偵尋廋堛偺帠傪愢 柧偟丄嫋戻傪摼偨偆偊偱丄堦弿偵恌嶡傪峴偭 偰偄傞丅庤媄偵偮偄偰偼丄愑擟栤戣偺柺傕偁 傞偺偱丄偝偣偰偄側偄丅乮嫤椡巤愝丒棧搰恌 椕強乯
丒婋尟偱側偄庤媄偵偮偄偰偼丄尋廋堛偺婓朷傪 暦偒側偑傜丄偱偒傞偩偗嶲壛偝偣宱尡偟偰傕 傜偆丅傑偨丄娕岇巘偵僩儕傾乕僕偟偰偄偨偩 偒丄尋廋堛偑偱偒偦偆側庤媄傪傗偭偰傕傜偆 乮懸偪帪娫抁弅岠壥乯丅側偍丄婋尟側庤媄偵偮 偄偰偼偝偣偰偄側偄丅乮嫤椡巤愝丒恌椕強乯
丒搒巗宆偺恌椕強偱偼丄姵幰偺堛椕儗儀儖傊偺 needs偑崅偔丄尋廋堛偵偳偙傑偱偝偣偰傛偄 偐擸傓偲偙傠偱偁傞丅乮嫤椡巤愝乯
丒暷崙幃偺奜棃尋廋傪庢傝擖傟偰偄傞丅恌嶡偵 娭偟偰偼丄嵟弶偺2擔娫丄恌椕僔僗僥儉傪尒 偰偄偨偩偒丄幚嵺偵恌嶡傪峴偆丅偦偺屻丄僨 傿僗僇僢僔儑儞傪峴偄丄擻椡偺偁傞尋廋堛偵 娭偟偰偼丄愢柧傑偱傗偭偰傕傜偆丅偦偆偱側 偄尋廋堛偵娭偟偰偼丄巜摫堛偑愢柧傪峴偭偰 偄傞丅傑偨丄庤媄偵娭偟偰偼丄宱尡偑偁傞傕 偺偵娭偟偰偼丄幚嵺偵峴偭偰傕傜偆偑丄宱尡 偑側偄応崌丄傑偨偼丄尒妛偺傒偺応崌偼偝偣 側偄丅乮嫤椡巤愝丒恌椕強丗僞僗僋乯
丒尋廋堛梡偺恌嶡幒偑偁傞丅巜摫堛偺敾抐偺傕 偲偵姵幰偺historic媦傃physical傪偲偭偨忋 偱丄巜摫堛偑summarize傪峴偆丅偦偺屻丄曽 恓傪妋擣偟丄専嵏偺僆乕僟乕摍傪寛傔傞丅傑 偨丄僫乕僗偑條巕傪尒偰丄巜摫堛偑僞僀儈儞 僌傛偔僒億乕僩偟偰偔傟偨丅乮尋廋堛乯
丒僐儊僨傿僇儖偺巇帠傪偡傞婡夛偑偁傝丄戝曄 婱廳偩偭偨丅乮尋廋堛乯
丒娗棟宆昦堾偱偼丄1擭娫偱廩暘側僗僉儖傪杹 偔帠偑壜擻偱偁傞丅堦曽丄堛椕柺愙偵娭偟 偰丄OSCE偺傒偱偼儅儞僱儕壔乮宍奫壔丠乯 偟丄愙嬾偺嵞僩儗乕僯儞僌乮娗棟宆庒偟偔偼 庴偗擖傟恌椕強偱乯偑昁梫偱偁傞丅峏偵偼丄 曐尟恌椕偵娭偡傞曌嫮傪庴偗擖傟巤愝偱嫵偊 偰偄偨偩偗傟偽偁傝偑偨偄丅乮娗棟宆乯
嘦丏僼傿乕僪僶僢僋乮怳傝曉傝乯偵偮偄偰
丒2擭栚尋廋偺嵺偵Dr.僐僩乕恌椕強偺嶣塭偑 峴傢傟偨恌椕強傊尋廋偵峴偭偨丅偦偺帪偼丄 僼傿乕僪僶僢僋偑側偐偭偨丅姰慡偵巤愝撪偱 庤弍傑偱姰寢偝傟傞偺偱丄傓偟傠丄姵幰偝傫 偐傜捈愙僼傿乕僪僶僢僋傪庴偗偨丅乮尋廋堛乯
丒枅擔丄奜棃偺廔傢傝偵丄婥偵側傞揰摍傪挳偒 弌偟丄Discussion偟偨丅乮尋廋堛乯
丒枅擔僼傿乕僪僶僢僋偑偁偭偨丅屵慜偼恌嶡傪 儊僀儞偵丄屵屻偼宱尡偟偨徢椺傪傑偲傔偨傕 偺傪巜摫堛偲堦弿偵僼傿乕僪僶僢僋偟偰偄 偨丅巜摫堛偑姵幰攚宨側偳傪攃埇偟偰偄偨偙 偲偑報徾揑偱偁偭偨丅傑偨丄棧搰昦堾偺尋廋 偱傕摨條偵枅擔僼傿乕僪僶僢僋偑峴傢傟偨丅 扴摉偺巜摫堛偐傜宱尡偟偨徢椺傪壗偱傕偄偄 偐傜彫僲乕僩偵婰擖偡傞傛偆姪傔傜傟丄尰嵼 偱傕妶梡偟偰偄傞丅乮尋廋堛乯
丒2 恖偺尋廋堛傪岎屳偵枅廡悈梛擔偺7:30 乣 8:30偵徢椺敪昞傪偝偣偨丅偦偺敪昞偵懳偟丄 僣僢僐儈傪擖傟丄傾僪僶僀僗偟偰偄傞丅傑偨丄 尋廋堛偺motivation偵傕傛傞偑丄擖堾姵幰偺 夞恌傪幚慔偟偨偄丅乮嫤椡巤愝丒棧搰昦堾乯
丒motivation傪偁偘傞偨傔偵丄枅擔偺栚昗傪棫 偰丄枅擔払惉偱偒偰偄傞偐傪妋擣偟偰偄傞丅 庴偗擖傟巤愝偵懳偟偰丄儌儔儖傗恎偩偟側 傒丄尵梩尛偄摍傕娷傔偨僼傿乕僪僶僢僋傪傗 偭偰偄偨偩偗傞偲偁傝偑偨偄丅傑偨丄僼傿乕 僪僶僢僋偡傞撪梕丄帪娫偑抦傝偨偄丅乮娗棟 宆乯
丒徢椺傪傑偲傔偰捀偄偨傕偺傪挬or栭偵30暘 掱搙偺僼傿乕僪僶僢僋傪峴偭偰偄傞丅偪側傒偵丄暈憰偵偮偄偰偼丄堦恖慜偲偟偰埖偭偰偄 傞偺偱偲傗偐偔尵偊側偄丅乮嫤椡巤愝丒恌椕 強丗僞僗僋乯
丒1儢寧偱妛傋傞偙偲偼寛傑偭偰偄傞傛偆偵巚 偆丅堦斒揑偵偄偊偽丄姶愼徢偱偺僶僋僥儕傾 彍奜丄惗妶廗姷昦偺杮恖偺motivation傪崅傔 傞僇僂儞僙儕儞僌丄崅楊幰堛椕偱偺幮夛怣擮 偺挷愡丄mild depression偺尒暘偗曽摍偑奣 偹栐梾偱偒傞傛偆偵僼傿乕僪僶僢僋偡傞丅 乮嫤椡巤愝丒恌椕強丗僞僗僋乯
嘨丏尋廋偱岺晇偟偰偄傞偙偲
丒枬惈姵幰偺働傾傪尋廋嫵堢偺拞偵庢傝擖傟偰 偄傞丅乮嫤椡巤愝丒恌椕強乯
丒堛椕僗僞僢僼偺慡偰偺怑柋傪宱尡偟丄棟夝偟 偰偄偨偩偔丅乮嫤椡巤愝丒恌椕強乯
丒抧堟曐寬偺尋廋栚揑偵傕傛傞偑丄奜棃恌椕傗 奺庬帒尮媦傃惂搙偺棟夝丅乮嫤椡巤愝丒昦堾乯
丒嵟弶偺1廡娫偼丄敀堖傪拝偢僫乕僗傗僜乕僔 儍儖儚乕僇乕摍偲摦偄偰偄偨偩偒丄僠乕儉堛 椕傪妛傫偱傕傜偆丅傑偨丄儂僗僺僗丄娕偲傝 偺宱尡丄姵幰丒壠懓偐傜傒偨帯椕丒働傾偺慖 戰摍丄偦偺巤愝側傜偱偼偺尋廋撪梕傪慜柺偵 弌偡丅乮嫤椡巤愝丒昦堾乯
嘩丏尋廋婜娫偼偳偺偔傜偄偑揔摉偐丠
1乯1廡娫偺傒
庴偗擖傟傞尋廋堛偺悢偵墳偠偰乮庴偗擖傟悢 偑懡偄偨傔1廡娫偺傒乯丅幚嵺偼丄1廡娫偱偼丄 棧搰堛椕傪抦傞偙偲偼偱偒側偄丅乮嫤椡巤愝丒 棧搰恌椕強乯
2乯2廡娫掱搙偱傛偄
1廡栚偼丄巜摫堛偲偺晅偒崌偄曽傪巉偭偰偄 傞丅2廡栚偐傜帺暘偺僗僞儞僗偱摦偄偰偄傞丅 婓朷偑偁傟偽丄3廡娫傕壜擻偲偟偰偄傞丅傑偨丄 棧搰偼奀偑嬤偄偨傔丄乽壞乿偵徢椺偑懡偔丄僶 儔僄僥傿乕偵晉傫偱偄傞丅壞偵棃偰偄偨偩偗傞 偲偄傠偄傠側宱尡偑偱偒傞偲巚偆丅乮嫤椡巤 愝丒棧搰恌椕強乯
3乯1廡娫偼抁偄
棧搰恌椕強傪帺桼榞偱嵞搙朷傓尋廋堛傕偄傞丅曐寬強摍偼丄偍媞偝傫埖偄偱廔傢偭偰偟傑 偆丅乮仸庴偗擖傟偰傞巤愝偵傛偭偰婜娫偼堎側 傞乯乮娗棟宆乯
4乯1儢寧偼抁偄
枬惈幘姵偺応崌摍丄姵幰偺恀偺宱堒偑捛偊側 偄偨傔丅乮嫤椡巤愝丒恌椕強乯
5乯3儢寧偱傕懌傝側偄
尋廋堛偺傗傞婥師戞丅僐儊僨傿僇儖嬈柋側偳 尰応傪棟夝偟巒傔偨崰偵廔傢偭偰偟傑偆丅 乮嫤椡巤愝丒棧搰昦堾乯
亙僞僗僋僼僅乕僗亜
庴偗擖傟巤愝偺摿挜偵傛偭偰丄婜娫丒帪婜偼 偦傟偧傟峫椂偝傟傞傋偒偱偁傞丅娗棟宆巤愝偺 搒崌偩偗偱寛傔傜傟傞偺偱偼側偔丄娗棟宆巤愝 偲庴偗擖傟巤愝偲偱榖偟崌偆応傪偮偔傞昁梫偑 偁傞丅
嘪丏尋廋堛偺motivation傪偁偘傞偵偼丠
丒尋廋堛偑偳偺傛偆側needs傪帩偭偰偄傞偐偑 key偵側傞偺偱偼側偄偐偲巚偆丅巜摫堛懁傕 偁傞掱搙尋廋堛傪娤嶡偡傞傋偒丅娗棟宆偐傜 庴偗擖傟巤愝傊偺昡壙昞摍偺忣曬傪帠慜偵憲 傝丄needs偵偁偭偨僾儔儞傪棫偰傞偲椙偄偺 偱偼丅乮尋廋堛乯
丒巤愝枅偺抧堟曐寬丒堛椕尋廋偺偟偭偐傝偟偨 栚昗傪宖偘傞丅乮娗棟宆乯
丒抧堟曐寬丒堛椕巤愝愭傪尋廋堛帺恎偵慖戰偝 偣傞丅乮僞僗僋乯
丒偄偄偲偙傠傪尒偮偗偰丄梍傔偰偁偘傞偙偲丅搘椡偟偨偙偲傪擣傔傞偙偲丅乮嫤椡巤愝丒恌 椕強乯

慡懱摙榑
崱夞幚巤偟偨乽巜摫堛偺偨傔偺僗僥僢僾傾僢 僾島廗夛乿偼丄怴偟偄帋傒偱傕偁傝丄彫埾堳夛 偱壗搙傕帠慜専摙夛傪帩偪丄嶲壛幰偵偲偭偰偄 偐偵廩幚偟偨島廗夛偵側傝摼傞偐傪榖偟崌偭 偨丅偦偺寢壥偵偮偄偰偼丄嶲壛幰偺姶憐傪楍婰 偟偨偄偲巚偆丅1乯擔忢恌嶡偺僐儈儏僯働乕僔儑 儞僗僉儖傾僢僾偼儕僗僋儅僱僕儊儞僩偺忋偐傜 傕戝愗偱丄庒偄尋廋堛偑偙傟傜偺偙偲傪妛傫偱 偄傞偙偲偵丄怱嫮偔巚偆偲摨帪偵帺暘傕娷傔儀 僥儔儞偺愭惗偵僗僉儖偑朢偟偄偺傪幚姶偟丄崱 屻傕懡偔偺曽偵島廗夛嶲壛傪姪傔偰傎偟偄偲巚 偆丅2乯嶲壛幰偑懡條偱傛偐偭偨丅3乯敿擔僗働僕 儏乕儖偱偪傚偆偳椙偐偭偨丅4乯傕偭偲尋廋堛傪 嶲壛偝偣偰傛偄偲巚偆乮儌僠傋乕僔儑儞傪忋偘 傞偨傔偵傕乯丅5乯嫵堢偺応偱偼丄島廗偲偄偆偲 庒偄愭惗曽偑懡偄拞丄儀僥儔儞偺愭惗偑擬怱偵 嶲壛偝傟偰偄偨偺偵姶柫偟丄尋廋堛嫵堢偵掕昡 偺偁傞壂撽側傜偱偼偲巚偭偨丅6乯尋廋堛偑嶲壛 偡傞偲尵偆偺偼丄尵偄偨偄偙偲偑廫暘偵尵偊傞 偵偟傠尵偊側偄偵偟傠丄岎棳偺応偲偟偰旕忢偵 廳梫偩偲巚偆丅傑偨丄尋廋堛嫵堢偼幚嵺偵嫵堢 尰応傪尒偰側偄恖偑丄怓乆側惂搙傪嶌傞偙偲偑 懡偔丄尰幚偲棟憐偺僊儍僢僾偑戝偒偄姶偠傕偟 傑偡丅側偺偱丄偙偆偄偭偨尋廋偺拞偱丄條乆側 棫応偺恖偨偪偑曌嫮傪捠偠偰岎棳偡傞婡夛傪憹 傗偡偙偲偑丄傛傝椙偄堛椕偵偮側偑傞偲峫偊傑 偡丅偲偰傕傛偄婡夛偵嶲壛偝偣偰偄偨偩偒杮摉 偵桳擄偆偛偞偄傑偟偨丅
埲忋丄嶲壛幰偺堦晹偺姶憐傪楍婰偟傑偟偨 偑丄崱屻偲傕嶲壛偟偨偄丄崱屻偲傕懕偗偰梸偟 偄偲尵偆梫朷傕偁傝丄庒偄堛巘払偺堢惉偺偨傔 偵傕丄巜摫堛偺峏側傞僗僉儖傾僢僾偲堄尒岎 姺丒恊杛偺応偲偟偰傕丄壜擻側尷傝丄戞2丒戞 3偲懕偗偰偄偒偨偄偲堄傪嫮偔偟偨丅嵟屻偵丄 枼椫愭惗丄晲揷愭惗丄5柤偺僞僗僋僼僅乕僗偺 愭惗曽丄偦偟偰4柤偺柾媅姵幰偝傫偺曽乆偵怺 偔姶幱抳偟傑偡丅

僞僗僋僼僅乕僗偺愭惗曽
慜楍嵍傛傝丂晲揷桾巕愭惗丄彫惗乮埨棦揘岲乯丄枼椫椙峴丄拠杮徆堦
屻楍嵍傛傝丂堫暉揙栫愭惗丄揷柤婤愭惗丄桹攇枮愭惗丄埨扟惓愭惗

崸恊夛