沖縄県立中部病院 院長 松本 廣嗣 先生
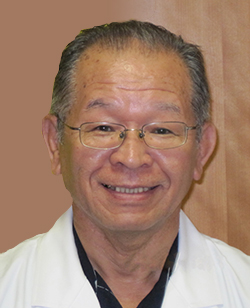
新しいことを始めるときに必要なのは「若者、馬鹿者、よそ者」だそうです。
質問1. この度は、沖縄県立中部病院 院長へ の就任おめでとうございます。
ご就任に当たってのご感想と、今後の抱負をお聞かせ下さい。
有り難うございます。感想と抱負ですか。10 年ぶりに古巣に戻って参りましたが、いわゆる 名物先輩方の姿が消え、後輩たちが幹部や中堅 として頑張っているので、かつてのような甘え はもう許されないのだなあという感じですね。 スタッフが若返っているのは確かですが、むか し院内に満ち れていた野生のパワーは影を潜 め、より洗練されたものに変わっているように 感じます。
「新しいワインは新しい革袋へ」ということ ですかね。新しいことを始めるときに必要なの は「若者、馬鹿者、よそ者」だそうで、中部病 院には全て揃っているようです。
やる気のある職員が多く、常に中腰で今にも 駆け出しそうな姿勢を感じます。しかしそれぞ れが思い思いの方向のベクトルを持っていて、 いわばどこに向かうか分からない沢山の活発な 偽足を持ったアメーバーのようなイメージで す。私の役目はこのエネルギーを一つの方向に 向けてやることだろうと思います。そうすれば すばらしいパワーを発揮することが出来る集団 となるでしょう。
質問2. 県立八重山病院院長として離島医療を経 験された先生への期待は大きいと思いますが、 今後離島支援の中核的役割を担っている県立中 部病院院長として医療確保、救急医療等様々な 問題にどのような支援をお考えでしょうか。
中部病院を離れて10 年間、県庁を皮切りに那覇病院、南部医療センター、八重山病院と渡 り歩いて分かったことは、離島・へき地の医師 確保や救急医療における、研修医の重要性でし た。県内で取り組まれている研修制度がいかに 重要な意味を持つものか改めて考えさせられました。
離島・へき地病院では琉球大学による支援も 大きいのですが、新臨床研修制度が開始されて 以降、医局に所属する医師の減少により、離島 やへき地への医師派遣では随分ご苦労されてい ると伺っております。
南部医療センター・こども医療センターでも 研修制度が導入されていますが、小児科以外の 診療科では後期研修医の数が伸び悩み、未だ屋 根瓦の体制がとれず指導医の負担は大きく、そ の結果として離島・へき地に医師を派遣する能 力が十分発揮できておりません。
しかし近年、中部病院にしても、外科・内科 はなんとか後期研修医の確保が出来ているもの の、小児科・産婦人科はかろうじてギリギリの 線を確保する状況で、耳鼻科・眼科・泌尿器科・ 整形外科・皮膚科に至っては研修希望者がおりません。
このような中で離島・へき地中核病院は、病 院事業局の伊江局長初め篠崎企画官や大新垣主 任の強力な支援により、なんとか他府県からの 医師確保が出来ました。しかし今後もずっと保 証されている訳では決してありません。
全ての県民が医療の恩恵に浴するためには、 離島・へき地医療の維持はもちろん、救急医療 や小児医療、周産期医療などを将来にわたって提 供する体制が求められます。こうした仕組みの 維持には研修医の存在は欠かせませんし、こうした医療を通して研修医も医師として成長でき るのです。県立病院や琉球大学のみにとどまらず、 沖縄の研修病院が全体で離島医療を支援する仕 組みを構築していきたいと考えております。
質問3. 県立中部病院は臨床研修において国内 外からも高い評価を受け、研修希望者が多数お られるようですが、今後の展開や目指すところ 等、先生のご意見をお聞かせ下さい。
我々の研修はあくまでも卒後初期から一般専 門医general subspeciality の研修を行う施設だと 思います。スタッフそれぞれは、専門医として 先端的医療を押し進めても、研修医にとっては あくまでもsuspeciality の入り口までをしっか りした基本を修得し、標準的診療を学ぶ場です。
最近は急いで専門医になりたがる方が多い様 ですが、医師としての最初の5 〜 6 年くらいは みっちり基本を学んだ方が、専門分野に進んだ 後も応用が利くと思います。専門医として果た して何年社会に役立つのかを考えると、公務員 であれば60 〜 65 歳で定年を迎えるのでせい ぜい30 〜 35 年、肉体的制約を考慮すればもっ と短いかもしれないという焦りがあるのかも しれません。しかし今のところは医師は死ぬま で医師なのですから、長い目で自分の専門医と しての人生を眺めてみた方がいいのではないで しょうか。中部病院では外科・内科・小児科・ 産婦人科を中心に幅広くかつ奥行きのある研修 を推進していきたいと考えております。
研修医制度は初期2 年、後期2 年、フェロー シップ2 年の形をとるのがよいのではないで しょうか。研修医は県立病院では嘱託医の身分 ですが、この処遇の制約は主治医の立場で業務 を遂行しようとすると、応召義務や労働基準法 上の問題を生じます。出来る限り早急に適切な 処遇に変更すべきだと考えますし、病院事業局 長の理解を求めながら改善して参りたいと思います。
質問4. 県医師会に対するご要望がございましたらお聞かせください。
沖縄県内の3 つの研修事業をまとめる要の働 きはすばらしいと思います。さらに後期研修医 の確保につながる活動にも強力な支援をいただきたい。
県のクリニカルシミュレーションセンター は沖縄県の研修制度を支援する目的で作られ ているので、地域医療再生基金が修了する平 成26 年度以降のセンター運営には、医務課共々 直接関わって安定した運営に協力していただきたい。
質問5. 最後に日頃の健康法、ご趣味、座右の銘等がございましたらお聞かせ下さい。
たいした健康法をやっている訳でなく、せい ぜい犬(黒のラブラドールレトリバー)との散 歩程度でしょうか。それも最近は土日に限られ ています。天気が悪かったり、犬の運動不足の ときには犬をウォーカーに乗せて運動させなが ら、15cm 高の階段の昇降を一緒にやることも ありますが、だいたい人間の方が先に音を上げ てしまいます。
趣味は、料理と果樹栽培。料理は創造的でし かもすぐ答えが出るところがいいですね。果樹 はいろいろやってみましたが、現在も残存して いるのはマンゴー、アテモヤ、アビュー、リュ ウガン、ジャボチカバ。それぞれにまだ勉強中 ですが実りの楽しみがあります。
最近の座右の銘は「万象肯定、万象感謝」で す。今年の1 月、運転しながらラジオを聞いて いるときにこの言葉を初めて聞きましたが、本 当にいい言葉だなあと感じ入りました。元気の でる言葉だそうです。
この度はお忙しい中、ご回答頂きまして、誠に有難うございました。
インタビューアー:広報担当理事 金城 正高