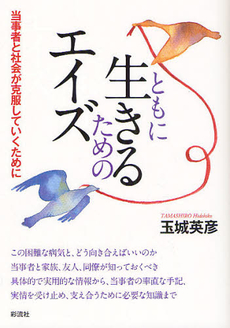ともに生きるためのエイズ
〜当事者と社会が克服していくために〜
(玉城英彦著 彩流社)

国立病院機構沖縄病院 院長 石川 清司
著者は、沖縄本島北部、今帰仁村古宇利島の 出身である。私とは、名護高校時代の同期であ り、級友であり、やんばるの自然をこよなく愛 する仲間でもある。
高校時代はテニス部に属し、練習に明け暮れ た。その勢いが現在も続いているかのように精 力的に著作活動を展開している。恋島への手紙 〜古宇利島の想い出を辿って(新生出版)、世 界へ翔ぶ〜国連機関をめざすあなたへ(彩琉 社)、社会が病気をつくる〜持続可能な未来の ために(角川学芸出版)等の著作がある。
長い間のWHO 本部での勤務の後、現在、北 海道大学の医学部で教鞭をとっている。WHO でのエイズの疫学、感染予防対策で陣頭指揮を とった経験のまとめの書である。
かつて「らい予防法」が悲惨な人権侵害を引 き起こしたように、「エイズ」という疾患もま た同様の社会現象を引き起こしていることに対 する警鐘の書とも言える。
「エイズ」という用語は、一般市民の間で日 常的に用いられている。しかし、その疾患に対 する情報が正確に伝わっているかどうかは疑問 である。本書を一読してみて、「エイズ」とい う疾患の背後に潜む社会現象は、医療従事者に も理解できていないことが分かる。ましてや、 一般市民には、表面的な現象のみが偏見として 映し出されているのが現状であろう。
エイズとは、後天性免疫不全症候群と訳され、 ウィルス感染である。感染してから症状が出る までには数年から10 年以上もかかると言われ ている。感染のルートは①性行為、②輸血、③ 母子感染と3 つがあり、咳や皮膚が触れるなど のことでは感染しない。約80%が性交渉で発 生し、そのほとんどが異性間の性行為による。
著者は、先進諸国の中で、日本はエイズ感染 者、患者が増加の一途をたどっている特殊な国 だと指摘し、注意を喚起している。
エイズが問題となった発端は、ゲイの社会に あり、同性間(男性間)の性行為は感染のリス クがより高くなる。どのような社会、民族にも 同性愛者は存在し、少数派であるがために迫害 を受けていると著者は寛大に受け止めている。 日本人には理解しがたい社会だと考えるが、保 守的の一言でかたづけて良いものであろうか。 性教育のよってたつ基盤はいずこに。
著者は主張する。国民は、エイズに関して理 解を深めてもらいたい。感染者に対しては早期 発見による早期治療に臨んで欲しい。エイズは コントロール可能な疾患である。このことが、 社会においては感染の拡大を防止することにつ ながる…と。
古宇利島という小さな島から、世界規模で物 事を考え、行動していくこの著者のエネルギー は、やはり沖縄の青い海と青い空の構成する限 りない空間が後押ししているような気がする。 益々の活躍を期待したい。