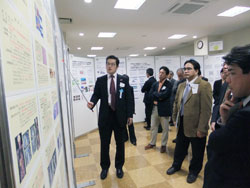第113回沖縄県医師会医学会総会

理事 當銘 正彦
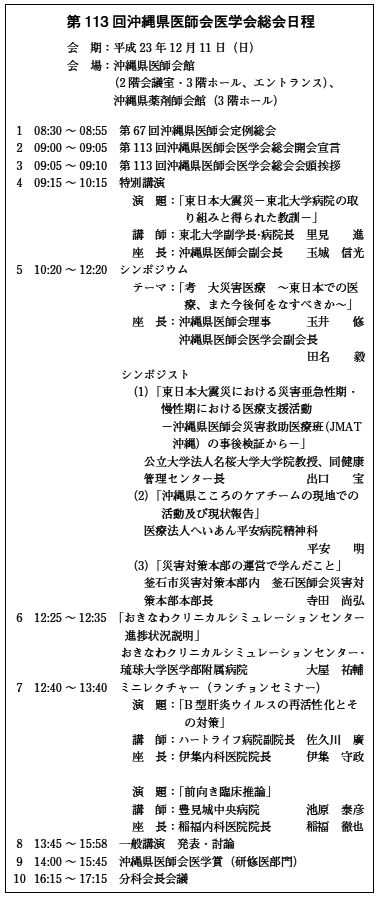
12 月の第2 日曜日を定例とする県医学会総 会が今年も粛々と行われた。以前は土日の2 日 間を掛けて行われていたが、昨年12 月の第 111 回からは現在の様な1 日方式になっている ため、プログラムは可成り過密になっている。 今回は一般演題が223 と多かったこともあり、 13 会場に分かれてのポスターセッションとなっ たが、医師会館だけでは間に合わず、4 会場は 隣の薬剤師会館を借用しての開催という異形と なった。今回から新設された「沖縄県医師会医 学会賞(研修医部門)」もこの様な県医学会の 活況を後押しする大きな一因になったものと考 える。新たな企画に挑戦する県医学会の勇断 に、深甚なる敬意を表したい。
先ずは日程表を参照して頂きたい。医学会の 開催に先立って、定例の県医師会総会が行われ た。総会では、平成22 年度の会務報告と収支 計算書の報告の後、懸案である法人制度改革に 伴う県医師会の今後の組織的態様について、執 行部より「一般社団法人」への移行を決意した 経緯の説明があり、滞りなく満場一致で採択さ れた。
医学会は、名嘉村博県医学会会長並びに瀧下 修一医学会会頭の挨拶で開会宣言され、早速、 東北大学病院長である里見進先生の特別講演 「東日本大震災−東北大学の取り組みと得られ た教訓」が行われた。那覇高20 期生である里 見先生は、来年度から東北大学の総長になると のホットなニュースが先だって流れたばかりで あり、図らずも今回の特別講演は、彼の凱旋帰 郷の舞台となった感である。
引き続き行われたシンポジウムも「考 大災 害医療〜東日本での医療、また今後何をなすべきか」と大震災にフォーカスされたものであ り、県医師会の出口宝先生、平安明先生に釜石 市で災害対策本部長として奮闘された寺田尚弘 先生を交えての3 人のシンポジストによる共演 であったが、今回は特別講演、シンポジウムと 災害対策医療一色の企画となった。突然に襲い 掛かって来る“予期せぬ出来事”“想定外の事 変”に相対する医療は、如何に普段からの心構 えと訓練が大切であるかが、繰り返し語られた 一日であった。そして一たび発災の有事に際し て、医療人は率先して行動することの使命と倫 理、即ち“いざ鎌倉”の精神を普段から強く保 持する覚悟が共通した認識である。
昼食時間を挟んで、琉球大学第3 内科教授・ 大屋祐輔先生から「おきなわクリニカルシミュ レーションセンターの進捗状況」の報告がなさ れた。来年4 月オープンに向けて建築工事は順 調であり、そして何よりも東洋一のシミュレー ションセンターを目指してコンテンツの充実に 一所懸命であることが熱く語られた。
続いて、休む間なくミニレクチャーの2 題で ある。最初はハートライフ病院・佐久川廣先生 の「B 型肝炎ウィルスの再活性化とその対策」 である。良い抗体= HBs 抗体、悪い抗体= HBc 抗体の説明は非常に分かりやすく、専門外 の者にも非常に参考になったものと思われる。 免疫抑制剤や抗がん剤等の強力な化学療法が一 般化する昨今の医療において、HBs 抗体の確認 だけでは不十分であり、HBc 抗体を測定してい ないとDe novo 肝炎を誘発して悲惨な結果を招 きかねない病態生理を丁寧に解説して頂いた。
次いで豊見城中央病院・池原泰彦先生の「前 向き臨床推論」は、非常にスマートな瞠目すべ きレクチャーであった。総合診療科領域におけ るEBM 的手法を用いた診断学の修練法を、可 成りの質のレベルで披露して頂いた。取り分け semantic qualifier SQ という手法は、普段か ら誰もが無意識のうちに行っている方法ではあ るが、これを意識化して追求することにより診 断が画然とレベルアップするものであることが 如実に感じられた。この様な総合臨床的な新し いスタイルの研修教育をリードする、若き指導 医の出現を心から歓びたい。
さて最後のプログラムは一般演題である。個 人的には自分の専門領域である呼吸器内科セッ ションを聴講したかったのであるが、今回は本 医学会の初企画である県医学会賞の掛かった2 年目の初期研修医による15 題の発表を聞かせ て頂いた。県立南部医療センターから2 題、那 覇市立病院から2 題、協同病院から2 題、浦添 総合病院から2 題、豊見城中央病院から2 題、 中頭病院から2 題、そして琉大病院、赤十字病 院、ハートライフ病院から各1 題のラインアッ プである。審査を任された8 人の委員と各病院からの応援団が入り乱れて、最後まで白熱した 討論が繰り広げられたが、全般的な印象とし て、発表される研修医の皆さんが何れも臆する ことなく堂々とプレゼンテーションする姿に、 沖縄県における臨床研修制度の着実な成果の一 端を垣間見る思いであった。栄えある第1 回の 受賞者は、以下の3 人である。

・最優秀賞 永村良二先生(沖縄協同病院)「脾臓摘出後34 年経過して発症したover whelming post-splenectomy infection の1例」
・優秀賞 喜名みちる先生(那覇市立病院)「悪性リンパ腫と鑑別を要した大腸低分化腺癌の一例」
・優秀賞 林裕樹先生(那覇市立病院)「胃転移を来たした乳癌の一例」
受賞された3 人を含め、各病院から選ばれた 15 人の若き戦士達に心からの拍手を送りたい。 そして、この沖縄県医師会医学会賞が今後益々 充実し、沖縄県における卒後臨床研修の更なる 発展の弾みにならんことを祈念して、本稿を閉 じたい。

左から、受賞した林先生、喜名先生、永村先生
会頭挨拶

第113回沖縄県医師会医学会総会会頭 瀧下 修一
このたび、名嘉村沖縄県医師会医学会会長の ご配慮により第113 回沖縄県医師会医学会総会 会頭をお引き受けすることになりました。県医 師会活動として全国に類を見ず、しかも伝統の ある本医学会総会の会頭の任にあたることは誠 に光栄に存じますが、沖縄県医師会、医療、医 学教育などで多大な功績を残された諸先輩に比 べるべくもない私としては恐縮するばかりです。
少し、自己紹介をさせていただきます。私は、 1988 年4 月から2009 年3 月まで、国立循環器 病センターへ転出した5 年間を除いて、琉球大 学医学部第三内科(現、循環器・腎臓・神経内 科)および琉大医師会に在籍しました。現在は 医療法人おもと会沖縄リハビリテーション福祉 学院学院長を務め、琉大医師会顧問、沖縄県医師会治験審査委員会委員長を兼ねています。
医師会医学会との関わりは、2004 年4 月か ら2008 年3 月まで琉大医学部附属病院病院 長・琉大医師会会長であったこともあり県医師 会理事を拝命し、学術担当理事として医学会副 会長を務め比嘉實会長を補佐させていただいた ことです。この間、一般演題のWeb 上の登録 化、データベース化が実現し現在に至っていま す。特別講演の決定、講演者、座長の選出など は分科会会長会議、幹事会での熱心な討議で決 定されましたが、発表演題で沖縄県医師会雑誌 に投稿された論文の査読者の選定、掲載不可と 評定された論文への対応など総会後の仕事が結 構あったことや、総会への医学部学生、コメデ ィカルの方の出席なども前向きに検討されたことが思い出されます。また、記念すべき2004 年12 月の第100 回総会で進行役を務め、ノー ベル賞受賞者小柴昌俊先生の特別講演「やれ ば、できる」、シンポジウム「沖縄県医師会医 学会100 回の歩み−戦前・戦後・未来−」を感 激をもって拝聴しました。
琉大医師会から会頭をご指名いただくのは恐 らく今回が初めてではないかと思います。本土 復帰の1972 年に琉大保健学部附属病院の医師 10 数名で琉大医師会が発足しました。1979 年 に琉大医学部設置認可、1987 年に一期生卒業、 医師会会員数は1992 年に200 人を超え、以後 200 人台の後半で推移しています。琉大医学部 附属病院は県唯一の医育機関の附属病院として 設置され、その後特定機能病院としてだけでは なく、沖縄県の中核病院として運営されてきま した。しかし、沖縄県の医療体制が県立病院を 基幹とするネットワークで既に出来上がってい るところに落下傘で降下したようなものであ り、よそ者扱いされてきた経緯がありました。 この状況を改善するために歴代の琉大医師会長 や役員は県医師会との関係を強めることを意識 してきました。県医師会には1984 年から県医 師会理事として学術、勤務医担当として迎えて いただいています。とくに最近は附属病院長が 琉大医師会長、県医師会理事を務めて緊密度を 高めています。医師会医学会においては、学術 担当理事が副会長を務め、多くの教授(診療科 長)が医学会分科会の会長として活動に加わっ ているほか、総会における座長やミニレクチャ ーの講師、研修医の症例発表など琉大医師会会 員の関与は少なくありません。医学部および附 属病院の使命として教育、高度医療および研 究・開発の推進、専門医養成等を担っており、 県内の他の医療機関とは異なる多くの面があり ますが、本土でみられる大学を頂点とするヒエ ラルキーを目指すものではなく双方向での地域 医療への関与、他医療機関との交流の比重を高 めているところです。今回の琉大医師会からの 会頭指名はこれらをさらに進めよとの医学会会 長のメッセージと理解しています。
昨年3 月11 日に発生した大地震による東日 本大震災、原発事故による被災は急性期を乗り 切りましたが、未だ復興の兆しも見えない状況 が続いています。この間、沖縄県でも県医師会 や医療機関から多くの医療スタッフが現地に行 かれ支援に尽力されました。6 月の本会におい ては大災害時の医療等について総会としての対 応が困難でしたが、今回は被災地最前線の医療 を支え続けておられる東北大学病院の病院長里 見進先生(日本外科学会理事長、那覇高校ご卒 業)による特別講演「東日本大震災―東北大学 病院の取り組みと得られた教訓―」と大災害医 療についてのシンポジウムを組んでいます。こ れらを通じて医療人自らの問題として深く捉え ること、大災害への具体的な対応の基盤ができ ることを願っています。また、臨床研修関係の プログラムでは来春完成予定の沖縄県、県医師 会と琉大が連携した「おきなわクリニカルシミ ュレーションセンター」の進捗状況の説明が予 定されています。
医学会総会は学術・研修面だけではなく情報 交換の場でもあります。多くの先生方のご参加 をお待ちしています。終わりにあたり、本総会 の開催にご尽力いただいた関係者の皆様に感謝 申し上げるとともに、沖縄県医師会医学会のさ らなる発展を祈念いたします。
特別講演
「東日本大震災−東北大学病院の取り組みと得られた教訓−」

東北大学病院病院長 里見 進
3 月11 日に発生した東日本大震災では東北 大学病院も、研究棟や外来棟、手術室、検査室 などに多大な被害を受けた。ただし病棟は制震 構造の新築で患者にはほとんど被害はなく、ま た職員も奇跡的に無傷であった。一時的にはラ イフラインが全てストップし機能不全に陥った が、非常用電源や人海戦術で乗り切った。発災 当初は東北大学病院が震災被害の最前線であろ うと考えていたが、情報収集の結果、県の沿岸 部が津波によって壊滅的な被害を被っているこ とが明らかになったので、段階を踏んで支援を 開始することにした。第一段階としては対策本 部の立ち上げと院内の医療安全の確認、トリア ージ体制の整備である。かねての訓練通り約 20 分後には対策本部、40 分後にはトリアージ 体制を作ることができた。この段階で懸念され たことは食料、医薬品、生活用品の不足、交通 手段の不足であった。使用可能であった衛星電 話を通して全国の大学病院や学会、在京の大学 関係者にお願いして必要な物資を搬送してもら った。また、大学の各部局に依頼して部局の車 両を運転手つきで病院に集めてもらうことにし た。第二段階では病院の機能回復を図りつつト リアージを継続し、仙台市周辺の医療機関への 支援を開始した。今回の地震では震度の割に家 屋の損壊は少なく予想したほどのトリアージ患 者は来院しなかった。第三段階では県の内外の 医療機関への支援を強化した。県北部の沿岸部 では多くの医療施設が壊滅的な被害を受け機能 不全に陥っていた。かろうじて機能している最 前線の病院を疲弊させないように、医療スタッ フを食料、医薬品とともに連日送りこむと同時 に、被災病院からの入院患者を無条件で受け入 れることとした。また患者搬送の中継基地とし ての機能も果たし、透析患者を自衛隊機を使っ て北海道へ搬送した。第四段階は避難所の医療 体制の整備段階である。宮城県だけで1,000 か 所はあったと推定されている避難所の医療を維 持するために、震災直後は急性期の医療チーム の派遣を依頼し、その後は慢性期の医療や感染 症の多発する状況に対処するためにエリア・ラ イン制を提唱し、長期滞在できる医療チームに 責任を持って医療を支えてもらう体制の整備を 行ってきた。この体制は9 月いっぱいで終了し たが、この間多くの医療チームの派遣を受けた ことで、医療の全面崩壊は食い止められたと思 う。全国の温かいご支援に感謝申し上げる。
震災後7 カ月が過ぎ、被災地の医療を今後ど のように再興するかが大きな課題である。短期、 長期の課題があるが、最終的な街づくりのプラ ンが決まるまでは長期的な展望は描けないと考 え、県の復興会議では1 ないし2 年の間医療が 崩壊しないように対策を立てることとした。基 本的には残った公的病院を中心に必要な仮設の 診療所を設置することとし、民間の診療所の開 設も積極的に支援することになった。医療の本 格的な再興には医療資源の有効活用を図る上か らもIT 技術等の積極的な活用が望まれる。
シンポジウム
「考 大災害医療〜東日本での医療、また今後何をなすべきか〜」

(1)「東日本大震災における災害亜急性期・慢性期における医療支援活動
−沖縄県医師会災害救助医療班(JMAT沖縄)の事後検証から−」

公立大学法人名桜大学大学院教授、同健康管理センター長
出口 宝
はじめに
災害急性期医療が「避けられた災害死」を防 ぐことがその目的とされているのに対して、災 害亜急性期・慢性期の医療支援は、「災害から免 れた命」を守る医療となる。そして、DMAT (Disaster Medical Association Team)などの急 性期専門の医療チームが災害発生後48 時間以内 に活動を開始するのに対して、災害亜急性期・ 慢性期の医療支援活動はこれら急性期チームが 撤収する災害発生後およそ4 日目から始まり、 被災地の医療の復興まで継続することとなる。
東日本大震災において、沖縄県医師会は災害 亜急性期・慢性期の医療支援を行うべく、3 月 14 日に独自の判断で沖縄県医師会災害救助医療 班(以下、JMAT 沖縄)の派遣を決定して、翌 15 日には岩手県へ派遣した。そして、壊滅的被 害を受けた岩手県上閉伊郡大槌町の城山体育館 に仮設診療所を開設して、6 月1 日に撤収する までの79 日間で15 チーム79 名を派遣して延べ 5,110 名への診療を行うなどの医療支援活動を 行った。この貴重な経験を今後に活かしていく べく、今回の震災における大槌町の状況と JMAT 沖縄の活動を検証して、災害亜急性期・ 慢性期における医療支援活動について検討した。
方 法
大槌町を医療圏とする釜石医師会災害対策本 部が配布した3 月20 日から5 月31 日までの避 難所ならびに医療チームに関する情報、そして JMAT 沖縄の現地日報を分析して、大槌町にお ける1.避難者と医療支援チーム数の推移、2. 避難者数と受診数の推移、3.拠点診療と巡回診療における受診数と受診率の推移、4.城山 仮設診療所における受診数の推移、5.JMAT 沖縄の初動から撤収までを検討した。さらに、 派遣された医療班員への事後アンケート調査か ら、6.JMAT 沖縄の派遣事業の在り方につい て検討した。
結果と考察
1.避難者数が最も多い亜急性期早期には活 動していた医療支援チーム数は少なく、避難者 数に対する医療支援チーム数の供給に不均衡が みられた。早期に活動を開始していた医療支援 チームは独自に情報を収集して活動を開始して いた。多くの情報が得られない災害発生早期の 初動は自律型分散型が有効であると思われた。 2.経過とともに避難者総数は減少していった が、それに比較して受診数の減少は少なかっ た。早期では医療ニーズ密度が高くなると思わ れた。3.診療形態では巡回診療よりも拠点診 療の方が受診数ならびに受診率ともに高かった が、交通手段のない被災地においては巡回診療 も不可欠である。しかし、医療が壊滅した被災 地の早期には、どこに行けば医療支援を受ける ことができるのかを明確にすることが重要であ り、拠点診療から開始することが優先されると 思われた。4.撤収計画は、現地災害対策本部 と調整しながら地元医療機関による保険診療の 再開とともに開始して、慎重に段階的に縮小し ていくことが重要と思われた。5.被災地にお ける現地災害対策本部が早期に機能することが 望まれ、その指揮下で全ての医療支援チームが 活動するべきであると思われた。6.JMAT 沖 縄の現地活動ならびに後方支援にはある程度の 評価を得られたが、平時から災害医療に対する 研修などが必要であると思われた。
災害亜急性期・慢性期における医療支援活動 は被災地のニーズに合わせた『初動』、『継続』、 『撤収』が重要である。今回の経験を活かして、 平時から災害医療支援活動に対する備えをして おくことが望まれる。一方、本県にも広域大規 模災害が発生する可能性があることを念頭に置 き、本県の特徴も考慮して今回の大震災を経験された被災地の関係者から学ぶことが重要と思われる。
(2)「沖縄県こころのケアチームの現地での活動及び現状報告」

医療法人へいあん平安病院精神科 平安 明
東日本大震災の発災後、県医師会は直後にア クションを起こし岩手県大槌町の支援活動に入 った。様々な課題はあろうが初動としては的確 な判断であったと思う。
今回の被害はその殆どが津波によるものであ り、その特徴として死亡・行方不明者に比べて負 傷者の割合が低いことがある。初期から重症者の 対応のみならず慢性疾患の治療継続や避難所生 活での衛生面の問題、集団感染等が医療上の課 題になった。一方で、被災範囲の広さや被災者の 多さは過去に例を見ず、直後から様々なストレス 反応による抑うつ、不安、不眠等をベースにした 体調不良を訴える方が多かったようである。
初期にはまず生命危機への対応が優先され、 PTSD を含めたメンタルケアは少し遅れてから 本格化するといった認識をもっていたが、今回 の災害は事情が異なっていた。その要因の一つ として、被災者を支える役割を担うはずの行政 スタッフも多くが被災しており、地域によって は保健担当者のほとんどが亡くなっているとい った状況が挙げられる。そういうことを考慮す ると、当初最も重視されたことは、まずは現地 に行くこと、行政の役割を補完すること、極論 すると“とにかく応援に行く”ことであったの かもしれない。
現地の情報が著しく不足している中、沖縄県の「こころのケア」活動は岩手県の要請があっ てから動き出した。民間精神科病院の組織であ る沖縄県精神科病院協会(沖精協)に県から人 材派遣の協力要請があり、協議した結果、県と 沖精協の合同チームを派遣することとなった が、この調整に約3 週間を要した。行政と民間 病院が一体となって派遣体制を構築したことは 評価できるが、少し時間がかかりすぎたと思 う。私自身は今回のことを通して「こころのケ ア」においても医療救護活動同様に初動の判断 は自発的、自律的であるべきだと実感した。
沖縄県の「こころのケアチーム」は主だった ところで3 つあり、県/沖精協合同チーム、国 立病院機構琉球病院チーム、県保健師チームで ある。いずれも岩手県に派遣され、県/沖精協 チームと保健師チームは大船渡市、琉球病院チ ームは宮古市で支援活動を行なった。
私は県/沖精協チームの第2 陣として4 月11 日から18 日まで支援活動に携わった。チーム 構成は医師、看護師、心理士、精神保健福祉 士、事務員の計5 人で、ロジスティックは県保 健福祉部が担った。当時の活動内容は、避難所 の巡回、医療救護班や保健師から紹介のあった ケースの診察や自宅等への訪問診療、地元の医 療機関との連携や相談調整業務の補完、現場か らの様々な情報を行政に届ける等、医療のみな らず御用聞き的なこともやるようにした。
県/沖精協チームは、4 月5 日から9 月30 日 まで計19 チーム、延べ87 名が支援活動に従事 し、一旦区切りをつけた。最終チームからの報 告では、大船渡市は瓦礫の撤去は一見進んでい るが、小学校の校庭等場所を移してまとめられ ただけで、あの日の傷跡はまだ至る所に残って いる。避難所はほとんどが閉鎖され生活の拠点 は仮設住宅に移っているが、衣・食といった生 活基盤の心許無さに加え、不安、寂しさ、孤独 といったメンタルな問題が浮き立ってきてい る。行政スタッフの疲労もピークをとっくに超 えている。このような被災地の現状を鑑みる と、精神的な支えはまさにこれから必要とされ るのではないかと感じずにはいられない。
初動と同様、撤収もまた重要である。県医師 会の医療救護チームは現地の診療態勢回復の状 況を見ながら、非常にうまく撤収出来たように 思える。こころのケアに関しては「ここで終わ っていいのか、むしろこれから必要ではないの か」といった思いがつきまとうが、我々が出来 ることには自ずと限界がある。
医学会当日は県/沖精協チームとしてのこれ までの活動を振返り、皆さんのご意見もいただ きながら今後の支援活動のあり方や平時になす べきこと等考えてみたい。
(3)「災害対策本部の運営で学んだこと」

釜石市災害対策本部内釜石医師会災害対策本部本部長
寺田 尚弘
はじめに
3 月11 日に発生した東日本大震災に際して は、医療支援チームの派遣を中心に医師会の多 くの先生方、医療スタッフの方、事務職の方々 はじめ多くの方に助けていただいた。まずは深 く御礼申し上げる。
本日は今回の大震災に際し、釜石市災害対策 本部としての釜石医師会災害対策本部が経験し た震災対応についてご報告申し上げ、この報告 が今後どの地域にも起こりうる震災対応の一助 となれば幸いである。
釜石医療圏は釜石市、大槌町の2 つの自治体 をカバーする人口5.5 万人の医療圏である。釜 石医師会も同様に両地域をカバーしている。今 回の震災で多くの医療機関が甚大な被害を受け、 特に大槌地域の医療機関はすべて全壊であった。
災害対策本部医療班の成立・初動について検 証してみた。もともと災害時に起動する医療班については市町村の定める地域防災計画にその 定義、立ち上げ方、活動内容など詳細が記され ている。その中で医療班の主な役割は被災地域 への救護活動であった。しかしながら今回の震 災はその規模が大きく、地域防災計画を支える 多くの前提が発災とともに機能しなくなった。 医療班もまたその定義や活動内容を柔軟に変え ることが求められた。最終的に釜石医師会災害 対策本部が行政の一部門の役割を果たしつつ、 地域全体の医療状況を把握し、県外からの医療 支援チームを指揮し、またそれを支える連携系 の構築・維持をその役割とすることとなった。
災害対策本部医療班の活動内容は大きく2 つに分けられた。1 つは『指揮系』の仕事であり、もう一つは『連携系』の仕事である。
『指揮系』の主な仕事は、本部方針を立て、 医療支援チームを把握・統括し、その活動をバ ックアップすることであった。特に活動報告会 を通しての医療支援からの情報の収集と本部か らの情報の配布、医療支援チームが立ち往生し ないための介入などを行った。また避難所から の撤退調整、医療支援チーム自体の引き上げに 際する引き継ぎ管理なども行った。
『連携系』の主な仕事は指揮系のバックアッ プであった。当医療圏にもともとあった医療連 携、介護連携、福祉・行政連携や内陸の医療圏 との連携など平時の連携が機能するかどうか、 無事を確認しバックアップにあたった。
災害医療の状況全般を把握し、コントロールしてゆく上で大切なことは平時からの顔の見える『連携』であると感じた。
地元医師会が果たすべき役割について。今回 当医療圏では災害対策本部医療班を釜石医師会 が担当した。地域によっては急性期病院が指揮 をとったところも多かったかと思う。どの組織が まとめ役を行うにしても重要なことは事前のコン センサスであると感じた。どの組織がまとめ役を 担当し、関連機関はその指揮系や連携系に組ま れる、という基本的なコンセンサスづくりが医療 における災害対策の基本前提なのではないかと考 える。これは県医師会のレベルでも郡市医師会 のレベルでも同じことが当てはまると考える。
個々の判断でバラバラに動くことが本部を最 も混乱させることになるため、チームが編成す ることが非常に有効であると感じた。具体的に は、診療科別にチームを作り、現地入りも含め た長期的なバックアップ体制は特にklein で有 効であった。事象別でいえば、感染コントロー ルチームは感染拡大兆候を報告すると翌日には 現地入りしてくれたし、深部静脈血栓症予防チ ームは避難所をスクリーニングして、避難民の 予防啓発に大きな力を発揮した。いずれにして も避難所横断的な支援チームはメインの医療支 援チームと連携することで大きな役割を果たし たと思う。このようなチームの投入を順序良 く、計画的にできたわけではなかったが、それ は私の見識不測が原因であって、準備可能なこ とであったと反省している。直接被災された先 生方は仮設診療所の再建に奔走する必要がある し、被災地で難を逃れた病院やクリニックは押 し寄せる患者をこなしてゆくことで手いっぱい となると思われる。
最後に再度平時の連携の重要性を強調したい と思う。医療連携のみならず顔の見える地域連 携は単に横をつなぐ接続ツールではなく、連携 それ自体が推進力を持つモーターのような働き をすることを痛切に感じた。当医療圏でも改め て連携の重要性を共通認識としたところである。
ミニレクチャー
(1)「B 型肝炎ウイルスの再活性化とその対策」

ハートライフ病院 佐久川 廣
B 型急性肝炎は、その多くが一過性の感染 で、肝炎発症後ウイルスが排除され、治癒する と言われていました。しかしながら、これまで 既往感染として扱ってきた症例でもHBc 抗体 が陽性であればウイルスが肝臓内に存在し続け ることが肝移植の研究の中で明らかにされまし た。最近、免疫抑制剤や化学療法を受けた既往 感染者にB 型肝炎の再活性化が起こることが問 題になっています。特に分子標的治療薬での再 活性化は劇症化例も多く、治療抵抗性で、予後 が悪いことが報告されています。
沖縄県の成人の約40 %はB 型肝炎ウイルス に暴露されており、再活性化を起こす可能性の ある症例は多いと考えられます。患者さんに免 疫能を抑制する薬剤を使用する場合は、必ず HBc 抗体をチェックして下さい。そして、HBc 抗体が陽性なら、一度肝臓専門医に診てもらっ て今後の方針を話し合うことが重要です。分子 標的薬の中で特にリツキシマブは要注意で、B 型肝炎を発症した場合は、救命率が非常に悪い ことが報告されています。当院でもリツキシマ ブによるB 型肝炎ウイルスの再活性化を2 例経 験しました。2 例とも抗ウイルス剤開始時に黄 疸を認めませんでしたが、治療抵抗性で、何れ も救命出来ませんでした。
免疫抑制剤や抗がん剤は多くの先生方が処方 しており、B 型肝炎ウイルスの再活性化について理解を深めてもらうことは非常に重要と思わ れます。本講演では自験例を中心に文献的考察 を含めて解説したいと思います。
(2)「前向き臨床推論」

豊見城中央病院 池原 泰彦
現在私は豊見城中央病院にて内科初診外来を 週9 コマ担当しております。これは年間通算す ると約2,500 の初診患者数となり、疾患も Common disease からKiller disease、Rare disease まで多岐に渡り、広い範囲で診察をす る機会に恵まれています。
9 コマの内5 コマは後期研修医と併診してお りますが、研修医への指導、多岐に渡る疾患、 時間の制約という現実を踏まえると、現場では 常に『速く正確に診断をつける』という事が重 要となります。
この『速く正確に診断をつける』という目的 を達成させるために、前向き臨床推論という戦 略を用いています。これは診察前情報からある 疾患を想定し効果的な質問を繰り返しながらリ アルタイムに推論を行うHistory に重点を置い た推論法です。
一般外来において診断に寄与する割合は、 History : Physical :検査が8 : 1 : 1 と言 われており、History に重点を置く推論法は合 理的です。
初診外来診療は常に時間との戦いです。History の段階で疾患が想起できずにPhysical、 検査に進んだ場合、検査結果が出た後から足り ない情報を集める事になります。そのため History 再聴収・Physical 取り直し・検査追加 等となり、時間の制約が比較的緩い病棟診療で はそれほど問題にはなりませんが、限られた時 間しかない外来では望ましくありません。
時間と情報に限りのある中、History から疾患を想起し、リアルタイムで推論していく事は有効な戦略です。
前向き臨床推論では以下の4 つが軸となります。
1)VABCDE(問診票から得られる診察前情報)
Vital /Age/ Background/ Chief complaint/Duration/ Sex
診察前情報から得られるキーワードを軽視してはいけません。Vital と問診上の小さな見落としにより大きな落とし穴に落ちることは稀ではありません。
2)SQ(Semantic Qualifier)
患者の発した言葉を抽象度の高い医学用語に 置き換えた情報。簡潔なプレゼンテーション と言えます。例えば『75 歳女性の昨夜から の右膝の発赤を伴う痛み』という主訴は75 歳女性→高齢女性 昨夜から→急性発症 右 膝の発赤を伴う痛み→単大関節炎となり SQ はAcute large monoarthritis in an elderly woman となり、細菌性関節炎と偽痛 風が鑑別に挙がります。
3)illness script
個々の疾患の時間経過を重視した臨床像。あ る疾患が時間によってどう経過するかを観察 すると、physical では区別が難しい疾患も鑑 別が可能となります。例えば右下腹部痛とい う主訴に対して考えられる疾患は虫垂炎、憩 室炎、腸間膜リンパ節炎、ウイルス性腸炎、 細菌性腸炎、PID などがありますが、これら の疾患は全て痛みの時間経過(illness script) が少しずつ異なります。発症から治癒までの 時間経過をより多くの疾患で理解していくこ とが重要となります。
4)引き算診断
『この症例は○○のillness script に当てはまら ないので違う疾患に違いない』という推論法。 例えば『この症例は下痢があり一見急性胃腸炎 に類似するが、illness script に当てはまらな いので急性虫垂炎やその他の疾患に違いない』 と考える事が出来ます。
この4 軸は全てHistory に基づいていますが、それぞれを駆使して推論していくのが前向き臨床推論です。
豊見城中央病院は群星沖縄(研修病院群プロ ジェクト)に参加しています。そして実際に私 も日々研修医の指導にあたっています。群星で は『Common Disease 中心の救急、プライマ リ・ケア研修を実践する』というのが7 つのコ ンセプトのひとつとなっていますが、プライマ リ・ケア研修にはCommon disease のバリエー ションに富んでいる内科初診外来が重要な役割 を果たしています。
検査、時間等の制約の多い初診外来を『診断 はつかなくてあたりまえ』という姿勢で臨むの ではなく、前向き推論を行うことにより速く正 確に診断がつくようになると、初診外来は全く 違ったものとなります。ともすれば『振り分 け』と揶揄される内科初診外来ですが、診断を つけなければ内科初診外来の存在理由はありま せん。診断推論は研修医教育でも非常に重要 で、ジェネラリストを目指さない医師にも問題 解決に必ず活きてくる技能です。今回沖縄県医 師会主催の場で臨床推論に関するお話をさせて 頂く機会を得たことに心から感謝致します。

一般講演演題・演者一覧
循環器外科
1.感染性心内膜炎に対する僧帽弁置換術後に左室仮性瘤を生じた1 治験例
浦添総合病院 心臓血管外科 安藤 美月
2.AVR+CABG 後の上行仮性瘤に対する治療
南部徳洲会病院 心臓血管外科 戸塚 裕一
3.順行性選択的脳灌流を使用した上行大動脈置換術の検討
琉球大学医学部 第二外科 山城 聡
4.AAE および右鎖骨下動脈瘤を合併したMarfan 症例
に対する一期的David 手術、解剖学的右鎖骨下動脈血行再建術の工夫
琉球大学大学院胸部心臓血管外科学講座 神谷 知里
5.心臓外科周術期にトラネキサム酸過量投与にて強直間代性痙攣をきたした長期透析患者症例の検討
県立中部病院外科 井上 学
6.小児のMR に対する僧帽弁形成術の1例
牧港中央病院 心臓血管外科 達 和人
7.閉鎖性気管外傷
県立中部病院 外科 島垣 智成
8.救命し得た超高齢者(90 歳)の腸骨動脈瘤切迫破裂の一例
豊見城中央病院 外科 花城 清俊
9.腹部大動脈ステントグラフト内挿術におけるAortouni-iliac 法の検討
琉大医学部 第二外科 比嘉 章太郎
10.大動脈解離を伴わない上腸間膜動脈解離の一例
那覇市立病院 浅井 恵
11.上腸間膜動脈血栓・塞栓症の4 例
那覇市立病院 外科 名城 れい子
12.救命に成功した院外発症Non-Occlusive Mesenteric Ischemia の1例
県立中部病院 宮地 洋介
13.下腿膿瘍を来した下肢静脈瘤の1 手術例
琉球大学大学院医学研究科胸部心臓血管外科学講座 仲栄真 盛保
乳腺内分泌外科
14.腫瘍切除およびリンパ節生検に際してγ線検知装置が有効であった症例
琉大医学部第二外科 平安 恒男
15.乳腺疾患におけるMDCT 画像所見の研究 -CT 画像所見から乳癌biology を読み解くことができるか-
那覇西クリニック 乳腺外科 玉城 研太朗
16.当院における乳癌センチネルリンパ節生検の手技と、2 年間の成績報告
北部地区医師会病院乳腺科 野村 寛徳
17.薬物治療抵抗性の紡錘細胞癌の一例
那覇西クリニック、那覇西クリニックまかび、県立南部医療センター・こども医療センター 滝上 なお子
18.内視鏡補助下甲状腺手術(VANS 法)62 例の経験
浦添総合病院 外科 長嶺 義哲
19.Automated Breast Volume Scanner(ABVS)の使用経験
豊見城中央病院 乳腺科 比嘉 国基
20.乳房痛とその関連因子についての検討〜浦添総合病院健診センター婦人科検診問診票より〜
浦添総合病院 乳腺センター 時沢 亜佐子
循環器内科
21.末梢血白血球数は、糖尿病冠動脈疾患患者の心血
管イベントを予測する
豊見城中央病院 循環器内科 新崎 修
22.僧帽弁輪石灰化(MAC)に付着し多発性塞栓症を
起こしたGroup G streptococcus(GGS)による感
染性心内膜炎の一例
ハートライフ病院循環器内科 前本 均
23.当院の2010 年度緊急PCI 症例の検討
沖縄協同病院 佐久田 豊
24.当院における外来通院型心臓リハビリについて
大浜第一病院 大城 康一
25.FFR ガイドによるPCI 低侵襲化への取組み:左冠
動脈主幹部直下へのPCI を回避しえた前下行枝tandem
lesion の一例
大浜第一病院心臓血管センター循環器科 前田 武俊
26.トレッドミル負荷中に前上膵十二指腸動脈瘤の破
裂をきたした1 例
那覇市立病院 大城 登喜子
27.バレーボール中にAED にて蘇生した致死性不整脈
を伴う心疾患の1 例
中部徳洲会病院 宇野 研一郎
28.頻拍性心房細動から心不全を発症し、カテーテル
アブレーションにて改善がみられた一例
豊見城中央病院 大庭 景介
29.リード抜去を要したCRT-D リード感染症の1 例
豊見城中央病院 山中 裕介
30.発作性心房細動後の洞停止にて失神、外傷性くも
膜下出血を来たし、カテーテルアブレーションにより
治療を行った一例
豊見城中央病院 循環器内科 二宮 実穂
31.院外心肺停止後、PCPS、IABP 導入するも救命
し得なかった、両側肺動脈の広汎腫瘍塞栓症の一例
中部徳洲会病院 友利 隆一郎
呼吸器外科
32.原発不明縦隔リンパ節転移を切除5 年後に発見された肺癌の一例
国立病院機構沖縄病院 外科 河崎 英範
33.単孔式胸腔鏡下手術を施行した同時性多発胸腺腫の1 例
中頭病院 外科 仲嶺 盛
34.当院における進行・再発非小細胞肺癌に対する
Bevacizumab 併用化学療法施行例の検討
国立病院機構沖縄病院 外科 饒平名 知史
35.縦隔発生気管支性嚢胞の臨床像の多様性
国立病院機構沖縄病院 外科 石川 清司
36.当院で経験した肺カルチノイドの1 例
浦添総合病院 呼吸器センター 松岡 裕
37.腫瘍型4mm のAAH の1 例〜正常肺胞上皮細胞か
らAAH への移行像〜
沖縄赤十字病院 外科 宮城 淳
38.当院で行っている食道癌に対する鏡視下手術
浦添総合病院 呼吸器センター 澤田 徹
39.左上肺静脈と左下肺静脈が共通管であったHOT 施行中の左上葉肺癌の1 例
中頭病院 藤原 善寿
40.CPA 後にflail chest を来たし肋骨固定術で奇異性呼吸が消失した1 例
中頭病院 外科 大田 守雄
41.多発肋骨骨折、横隔膜損傷を伴う外傷性気胸に対し胸腔鏡補助下止血術を施行した1 例
中頭病院 外科 日高 竜太
42.当院で経験した良好な経過を得られたLVRS の1 例
浦添総合病院 呼吸器センター 渡辺 丞
43.胸骨正中切開により摘出した縦隔甲状腺腫の一例
南部徳洲会病院 伊元 孝光
44.腎型にて発症した縦隔内副甲状腺腫による原発性
副甲状腺機能亢進症の1 例
南部徳洲会病院 宮崎 洋介
45.当院における小型肺癌切除例の検討
豊見城中央病院 外科 我喜屋 亮
46.原発性肺癌が疑われた術前未確診肺病変の検討
琉球大学大学院胸部心臓血管外科学 古堅 智則
一般外科
47.Streptcoccus pyogenes による壊死性軟部組織感染症により右上肢切断術を施行した一例
県立中部病院 外科 國崎 正造
48.PEG 困難例に対する腹腔鏡併用下経皮内視鏡的胃瘻造設術(LAPEG)
沖縄赤十字病院 外科 豊見山 健
49.18 歳の1 型糖尿病患者に発症した特発性腸重積症の一例
中部徳洲会病院 川満 菜津貴
血液
50.CMV 感染症を契機に発症した血球貪食症候群の一例
ハートライフ病院 上原 盛幸
51.サイトメガロウイルス初感染を契機に発症したクー
ムス陰性自己免疫性溶血性貧血の一例
ハートライフ病院 血液内科 大濱 昌代
52.診断に苦慮したEBV-associated NK/T cell lymphomaの一例
県立南部医療センター・こども医療センター 新垣 若子
53.化学療法中に可逆性後頭葉白質脳症(PRES)を来した思春期白血病の1 例
琉球大学医学部 第二内科 仲地 佐和子
54.免疫抑制療法により凝固が正常化し手術を行った軽症後天性第VIII 因子インヒビターの1 例
中頭病院 内科 林 正樹
55.初回化学療法としてAzacitidine を使用した高リスク骨髄異形成症候群(MDS)3 例の検討
沖縄赤十字病院 血液内科 朝倉 義崇
56.輸血離脱にてDeferasirox 内服休止後再度輸血依存となり同薬内服再開後も輸血依存にて経過中の骨髄繊維症の一例
那覇市立病院 内科 内原 潤之介
呼吸器内科
57.胸部単純CT からHTLV-1 関連細気管支炎が疑われた1 例
県立中部病院 呼吸器内科 馬場 洋行
58.胸腔鏡下胸膜生検で診断し得たマイコプラズマ胸膜炎の一例
県立中部病院 内科 高倉 俊一
59.胸水精査にて結核性胸膜炎が疑われた一例
北部地区医師会病院 金城 康治
60.当院における非結核性抗酸菌症手術症例の検討
国立病院機構沖縄病院呼吸器内科 原 真紀子
61.特発性上葉限局型肺線維症の1 例
国立沖縄病院 呼吸器内科 那覇 唯
62.当院におけるサルコイドーシスの検討
県立中部病院 呼吸器内科 玉城 仁
63.ECMO 下に両側同時全肺洗浄を行った続発性肺胞蛋白症の一例
豊見城中央病院 小幡 景太
64.喀血で来院し3D-CT で診断した巨大気管支動脈瘤の1例
豊見城中央病院 呼吸器内科 比嘉 剛二
65.Saccharopolyspora rectivurgula が原因と考えられた慢性農夫肺の一例
豊見城中央病院 金武 有為子
66.産褥期に増悪した慢性好酸球性肺炎の一例
県立中部病院 内科 中山 泉
67.慢性好酸球性肺炎の一例
中頭病院 呼吸器内科 喜屋武 夏海
68.seawalker 後に発症したimmersion pulmonary edema の一例
県立中部病院 呼吸器内科 山城 信
腎・泌尿器
69.Neisseria mucosa によるCAPD 腹膜炎の一例
豊見城中央病院 リウマチ膠原病・腎臓内科 張 同輝
70.手術侵襲後の急性腎不全に対するPMMA ダイアラ
イザーによる持続血液浄化療法
沖縄協同病院 徳岡 優生
71.意識障害を伴ったリチウム中毒に対し集学的治療を行い救命できた一例
県立中部病院 腎臓内科 瀬尾 卓司
72.透析治療を経ずに先行的腎移植(preemptive 腎移植:PET)を施行した慢性腎不全患者の一例
豊見城中央病院 外科 沖 哲
73.豊見城中央病院における生体腎移植20 例の成績
豊見城中央病院 外科 大田 守仁
74.慢性維持透析者に発症したCUA;calcific uremic arteriolopathy(calciphylaxis)の一例
沖縄医療生活協同組合 沖縄協同病院 木村 百合
75.維持透析29 年間で様々な骨代謝病変を呈した一症
例=現在からみる病態の解釈と治療法の変遷=
沖縄協同病院 玉城 元之
76.2 度の意識障害をきたした慢性腎不全患者の一例
豊見城中央病院 幸地 祐
77.長期SLE 患者に急性発症したネフローゼ症候群に対して血漿交換療法が著効した一例
おおうらクリニック 大浦 孝
78.長期の寛解を経て発症したseronegative rheumatoid vasculitis の一例
県立中部病院 呼吸器内科 安里 哲矢
肝胆膵外科
79.術前に鑑別し迅速に対応しえた胆嚢捻転症の1 例
中部徳洲会病院 外科 中島 温
80.クリップレス、臍部切開創のみによる当科における
単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術の実際
豊見城中央病院 外科 島袋 誠守
81.胆道狭窄としてチューブステントを長期留置されていた膵・胆管合流異常の1 手術例
浦添総合病院消化器病センター外科 加藤 拓也
82.肝門部胆管癌との鑑別が困難であった良性胆道狭窄の1 例
浦添総合病院消化器病センター外科 斎藤 由希子
83.腹腔鏡下膵頭十二指腸切除の報告
中頭病院 外科 砂川 宏樹
84.Vater 乳頭部腫瘍に対し腹腔鏡補助下経十二指腸的乳頭部切除を施行した1例
中頭病院 卸川 智文
85.受傷機転不明の外傷性膵損傷に対し膵頭十二指腸切除術を施行した一例
中頭病院 外科 嘉数 修
86.膵頭十二指腸切除術後の胃空腸吻合部に狭窄をきたした1 例
ハートライフ病院 外科 西原 実
87.若年女性に発生し4 つの組織型を併せもったIPMN分枝型の1 例
中頭病院 病理科 矢田 圭吾
脳神経外科
88.腰痛で発症した右中大脳動脈破裂によるくも膜下出血の一例
浦添総合病院救命救急センター救急総合診療部 岩永 航
89.筋間アプローチにて治療した脊髄硬膜外神経鞘腫の2 例
浦添総合病院 脳神経外科 原国 毅
90.当科で行われた頸動脈ステント術の検討
浦添総合病院 脳神経外科 銘苅 晋
91.血管内治療を行った後大脳P2-P3 分岐部動脈瘤
県立南部医療センター・こども医療センター 前田 肇
92.裸眼3D 液晶モニターを用いた術前3D 画像の検討
琉球大学医学部 脳神経外科 宮城 智央
93.原因不明の中枢神経限局性血管炎の一例
琉球大学医学部 脳神経外科 長嶺 英樹
総合医療
94.浦添総合病院での在宅緩和ケアのまとめ
浦添総合病院 新里 誠一郎
95.緩和医療の現場で−在宅での看取り症例の検討
国立沖縄病院 緩和医療科 大湾 勤子
96.当院緩和病棟への紹介入院患者についての検討
国立病院機構沖縄病院 上原 忠大
97.当院における癌終末期の入院治療・緩和ケアについて
那覇西クリニック 上原 協
98.浦添市在宅医療ネットワークの現状と問題点
名嘉村クリニック 大浜 篤
99.繊維筋痛症を含む慢性疼痛患者に対する集団認知行動療法
南部病院緩和ケア/ペインクリニック 笹良 剛史
100.禁煙治療における心理療法の役割 動機づけ面接法を中心に
ちばなクリニック 清水 隆裕
101.「こむらがえり」に芍薬甘草湯を用いた112 例の臨床的考察
首里城下町クリニック第一・第二 田名 毅
102.総合感冒薬により急性薬剤性肝炎を発症した一例
県立中部病院 内科 朴 大昊
103.視力障害から発症した多発性硬化症疑いの一例
県立中部病院 宇土 有巣
104.妄想気分、被害妄想への宗教的概念を用いた支持的精神療法とspiritual well-being についての検討
博愛病院 仲里 淳
105.豊見城中央病院の再生医療への取り組み
豊見城中央病院 外科 城間 寛
106.進行大腸癌治療における樹状細胞ワクチン療法の取り組みについて
豊見城中央病院 外科 照屋 剛
消化器内科
107.胃静脈瘤の4 例
那覇市立病院 宮里 賢
108.後上膵十二指腸動脈瘤破裂に対してコイル塞栓術が有用であった1 例
浦添総合病院 消化器病センター内科 明石 麻里
109.全身転移を来したBarret 腺癌の一例
沖縄赤十字病院 内科 石橋 興介
110.肺胞出血を伴った播種性糞線虫症の1 例
中頭病院 伊良波 朝敬
111.当院における大腸腫瘍に対する治療戦略 〜主に大腸ESD のすみ分け・意義について〜
豊見城中央病院 消化器内科 峯松 秀樹
112.好酸球性腸炎の1 例
浦添総合病院 潮平 淳
113.止血目的の放射線療法が有効であった横行結腸癌術後腹膜転移巣の空腸浸潤の1 例
浦添総合病院 消化器病センター内科 金澤 孝祐
114.高齢で発症したHenoch-Schoenlein 紫斑病の一例
県立中部病院 消化器内科 太田 龍一
115.胆管腫瘍に対する超音波内視鏡下穿刺吸引法(EUS-FNA)の有用性
県立中部病院 吉田 幸生
116.ダブルバルーン内視鏡による治療が有用であった術後再建腸管を有する胆道結石の2 例
中頭病院 消化器内科 陣内 駿一
117.膵腫瘍に対する超音波内視鏡下穿刺吸引組織診(以下EUS-FNA)の有用性の検討
県立中部病院 消化器内科 知念 健司
118.IDUS が術前診断に有用であった下部胆管癌の1 例
中頭病院 消化器内科 崎原 正基
119.門脈ガス血症をきたした過酸化水素大量服用の一例
県立南部医療センター・こども医療センター内科 窪田 圭志
120.ショック状態で救急搬送となった門脈ガス血症の一例
豊見城中央病院 消化器科 糸洲 美代香
121.当院における免疫抑制・化学療法に伴うHBV Reactivation の検討
県立中部病院 消化器科 山田 航希
122.活動性慢性肝炎を伴ったNASH の1 例
ハートライフ病院 富里 孔太
123.早期診断により劇症化に至らず治療しえたHBV再活性化による急性肝炎の1 例
県立中部病院 内科 木全 俊介
124.当院で経験したアメーバ性肝膿瘍の2 例
那覇市立病院 玉城 祐一郎
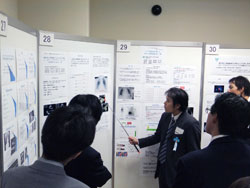
形成外科
125.当院における入院加療を要する小児熱傷患者の治療
プロトコル〜小児外傷チーム結成後の成果:第1 報〜
県立南部医療センター・こども医療センター形成外科 西関 修
126.腹部感染性大動脈瘤に対する人工血管置換術に際し、腹直筋弁にて人工血管の被覆を施行した1 例
県立南部医療センター・こども医療センター形成外科 円谷 悠子
127.真皮脂肪移植の美容外科への応用
当山美容形成外科 當山 護
整形外科
128.化膿性手関節炎の3 例
南部徳洲会病院 整形外科 五日市 綾美
129.広範囲腱板断裂に対する術後成績
はえばる北クリニック 安里 英樹
130.骨粗鬆症性椎体圧潰に伴う遅発性脊髄麻痺に対する後方手術の2 例
南部徳洲会病院 整形外科 金城 幸雄
131.THA 術後帯状疱疹と思われた下肢末梢神経炎2例の経験
豊見城中央病院 永山 盛隆
132.脛骨骨近位部に高度骨欠損を伴ったRA 膝関節に対するTKA の経験
豊見城中央病院 整形外科 富山 聡
小児科
133.当院における新生児不整脈の検討
県立南部医療センター・こども医療センター 小児循環器 島袋 篤哉
134.沖縄県立中部病院ICU に入院した小児の検討
県立中部病院 小児科 赤峰 敬治
135.2010 年度の小児救急受診制限を検証する
県立中部病院 小児科 小濱 守安
136.MRSA 肺膿瘍を発症した一例
中部徳洲会病院 小児科 上原 卓実
137.マイコプラズマ感染症入院症例のPA 抗体価の検討
県立中部病院 小児科 松茂良 力
138.親から感染したと考えられ、無呼吸発作、チアノーゼで受診した乳児百日咳の一例
県立南部医療センター・こども医療センター小児科 山本 賢一
139.巨大脾腫と汎血球減少より門脈血行異常症の診断に至った小児の一例
県立南部医療センター・こども医療センター小児血液 腫瘍科 屋宜 孟
140.拡散強調画像にて白質に一過性高信号を呈したSturge-Weber 症候群の一例
県立南部医療センター・こども医療センター 松岡 剛司
141.歩行困難を主訴とし診断が異なる2 乳幼児例
ハートライフ病院 小児科 青山 貴博
142.長期間の拒食によりビタミンB1 欠乏症を発症した11 歳男児の一例
中部徳洲会病院 小児科 大越 猛
沖縄県医師会医学賞(研修医部門)内科
143.腹痛をきっかけに判明した結核性大動脈瘤の一例
県立南部医療センター・こども医療センター 呼吸器内科 西口 潤
144.細菌性髄膜炎を合併した播種性糞線虫症の一例
沖縄協同病院 伊波 悠吾
145.認知症症状を契機に診断し得た神経梅毒の一例
浦添総合病院 総合内科 三浦 航
146.脾臓摘出後34 年経過して発症したoverwhelming postsplenectomy infection の1 例
沖縄協同病院 総合内科 永村 良二
147.ATL に随伴した傍腫瘍症候群が疑われた一例
ハートライフ病院 血液内科 後藤 敬子
148.Hirschsprung 病の新生児例2 例〜母親も同疾患であった1 例と消化管穿孔・敗血症をきたした1 例〜
県立南部医療センター・こども医療センター新生児科 中奥 大地
149.悪性リンパ腫と鑑別を要した大腸低分化腺癌の一例
那覇市立病院 喜納 みちる
150.著明な腹水を伴なった甲状腺機能低下の3 例
浦添総合病院 消化器内科 前住 忠秀
151.原発性アルドステロン症の疑いで評価した498 例
豊見城中央病院糖尿病・生活習慣病センター 小波津 香織
152.MPO-ANCA 関連血管炎が疑われた高齢女性の一例
豊見城中央病院 神経内科 城間 美咲
沖縄県医師会医学賞(研修医部門)外科
153.当科で経験した二次性気胸の検討
琉球大学医学部附属病院卒後臨床研修センター 川上 智子
154.飛行機搭乗後に症状が悪化した左巨大肺嚢胞の1 例
中頭病院 平井 雄喜
155.87 歳の高齢者に見つかった乳頭部腺腫の1 例
沖縄赤十字病院 外科 儀間 清悟
156.胃転移を来たした乳癌の一例
那覇市立病院 林 裕樹
157.膀胱内BCG 注入療法後に発症した感染性腹部大動脈瘤の一治験例
中頭病院 心臓血管外科 仲村 尚司
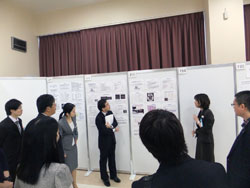
消化器外科
158.Ommaya reservoir にて治療した胃癌髄膜癌腫症の1 例
ハートライフ病院 外科 宮平 工
159.宿便性大腸穿孔様の症状を呈した大腸癌閉塞による穿孔
県立中部病院 外科 別城 悠樹
160.妊娠に合併した肝転移を伴う若年性大腸癌の一症例
県立南部医療センター・こども医療センター 宮城 大雅
161.著明な多発肝転移を伴う若年者大腸癌に対して集学的治療を施行した一例
ハートライフ病院 外科 新里 輔鷹
162.上行結腸の狭窄を来たした結腸リンパ腫の一例
豊見城中央病院 外科 安里 昌哉
163.大腸内視鏡および経肛門的用手的操作にて摘出し得た義歯誤嚥の一例
浦添総合病院 消化器病センター外科 福嶋 真弥
164.放射線性腸炎による腸管癒着を合併した義歯誤飲の一例
県立中部病院 外科 菊川 元博
165.貧血増悪で見つかった小腸悪性リンパ腫の一例
大浜第一病院 外科 高江洲 享
166.imatinib による間質性肺炎のため、局所治療をくりかえしている再発小腸GIST の一例
浦添総合病院 消化器病センター外科 白井 智子
167.イマチニブ術前化学療法が有用だったGIST の1 例
県立中部病院 外科 田邊 太郎
168.小腸合併切除を要したparasitic leiomyoma の1 例
中頭病院 外科 石野 信一郎
169.腹部鈍的外傷による遅発性盲腸穿孔の1 例
豊見城中央病院 濱田 祐斗
170.腹部杙創による盲腸・小腸損傷をきたした1 例
南部徳洲会病院 外科 金城 泰幸
171.腹部鈍的外傷に伴う虫垂断裂の1 例
浦添総合病院消化器病センター外科 本成 永
172.盲腸・虫垂憩室穿孔の1 例
ハートライフ病院 外科 国吉 史雄
173.虫垂杯細胞カルチノイドの一例
豊見城中央病院 須田 晃充
174.門脈気腫を合併した穿孔性虫垂炎の1 例
中頭病院 玉野井 徹彦
175.炎症性腸疾患を疑われたメッケル憩室出血の一例
県立中部病院 外科 藤居 勇貴
176.急性腹症で発症し、虫垂切除術後に川崎病の診断基準を満たした1 例
県立南部医療センター・こども医療センター小児外科 水野 智子
救急・麻酔・ICU
177.小児集中治療科入院統計から見える、沖縄県小児集中治療の変化と今後の課題〜沖縄県小児死亡の減少を目指して〜
県立南部医療センター・こども医療センター 水野 裕美子
178.妊娠中に非産科手術の全身麻酔を行った2 症例
中頭病院 麻酔科 本成 登貴和
179.Duchenne 型筋ジストロフィー患者の全身麻酔の経験
琉球大学医学部 麻酔科 新垣 かおる
180.減圧症治療に対する遠隔医療の試み
南部徳洲会病院 高気圧酸素治療部 樋口 さやか
181.多発外傷により発症した重症呼吸不全に対し、気道圧解放換気(APRV)と二相性体外人工呼吸器(BCV)が奏功した1 例
県立南部医療センター・こども医療センター 多田 欣司
救急
182.原因不明のショックに対し一日で20L 以上の補液を行うも血圧を維持できなかった一例
豊見城中央病院腎臓・膠原病リウマチ内科 西平 守邦
183.右足しびれで受診したStanford A 型の胸部大動脈解離の一症例
大浜第一病院 内科 花城 徹
184.当院に搬送された心肺停止症例の検討及び考察
中頭病院 島袋 耕平
185.躁鬱薬内服による慢性リチウム中毒の一症例
中部徳洲会病院 泉 惠一朗
感染症
186.肺炎球菌による細菌性髄膜炎にて死亡した1 歳児の一例
沖縄協同病院 日比野 世光
187.突然の呼吸苦にて発症した感染性大動脈瘤の一例
―これからの治療戦略―
県立中部病院 長嶺 由衣子
188.腹壁結核の一例
中頭病院 内科 岩田 はるか
189.粟粒結核により播種性血管内凝固症候群(DIC)をきたした2 例
県立中部病院 内科 西岡 典宏
190.旅行後発熱持続を主訴に受診した腸チフスの一例
県立南部医療センター・こども医療センター総合内科 垣花 一慶
191.帰国後に発症したレプトスピラ症の一例
ハートライフ病院 島袋 全志
192.本県3 例目のツツガムシ病の1 例
県立宮古病院 内科 名嘉村 敬
193.経過観察できた急性HIV 感染の症例
県立南部医療センター・こども医療センター 城田 ふみ
内分泌・代謝
194.高LDL 血症患者におけるLp(a)の臨床的解析
島尻キンザー前クリニック 島尻 佳典
195.摂食不安定高齢者に対する糖尿病薬選択の提案
ハートライフ病院 内科 安谷屋 徳章
196.持効型インスリン1 回法による治療効果の検討
豊見城中央病院糖尿病・生活習慣病センター 佐久田 静
197.当院に通院されている2 型糖尿病患者の特徴〜内臓脂肪面積からみた2 型糖尿病の治療計画〜
大浜第一病院 糖尿病センター 高橋 隆
198.当院におけるシタグリプチン投与の効果についての検討:著効する患者の予測因子は?
大浜第一病院 糖尿病センター 谷川 幸洋
199.痙攣発作で受診した、著明な低血糖を伴う甲上腺クリーゼの1 例
県立南部医療センター 神納 幸治
200.医原性甲状腺機能低下症の2 例
県立南部医療センター・こども医療センター 和田 伊織
201.当院で経験した原発性副甲状腺機能亢進症
豊見城中央病院 新垣 桂
202.当初原発性アルドステロン症を疑われた、サブクリニカルクッシング病の一例
豊見城中央病院 眞境名 豊文
203.当院での副腎静脈サンプリングの工夫〜 3DCT による副腎静脈描出の有用性〜
豊見城中央病院 循環器内科 嘉数 真教
204.カテコラミン高値を契機に睡眠時無呼吸症候群と診断した一例
琉球大学大学院医学研究科内分泌代謝・血液・膠原病
内科学講座(第二内科) 仲村 英昭
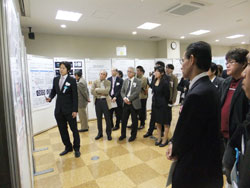
神経内科
205.おきなわImmediate Stroke Life Support(ISLS)コースの開催経験,今後のあり方
琉球大学医学研究科循環器・腎臓・神経内科学 伊佐 勝憲
206.両側声帯麻痺を発症した多系統萎縮症の一例
県立中部病院神経内科 古閑 和生
207.心原性脳塞栓症の急性期治療の経過で原発性脳室内出血を併発した一例
県立南部医療センター・こども医療センター 笠 芳紀
208.起立性低血圧が著明なpure autonomic failure の1 例起立性低血圧が著明なpure autonomic failureの1 例
那覇市立病院 内科 小渡 貴司
209.シプロヘプタジンが奏功したShapiro's syndromevariant の一症例
豊見城中央病院 神経内科 長谷川 樹里
210.間歇的低酸素血症を呈した奇異性脳塞栓症の1 例
琉球大学大学院医学研究科循環器・腎臓・神経内科学 崎間 洋邦
211.本態性血小板増多症による血栓形成から脳主幹動脈閉塞を来たし,脳梗塞を発症した一例
琉大医学部第三内科 呉屋 よしの
産婦人科
212.妊婦のサイトメガロウイルス感染症の1 例
県立中部病院総合周産期母子医療センター産科 直海 玲
213.HTLV-I 母子感染に関するデータ分析
豊見城中央病院 産婦人科 前濱 俊之
214.帝王切開術直前抗生剤投与後アナフィラキシ―を起こした一例
琉球大学大学院医学研究科環境長寿医科学女性・生殖医学講座 北條 真子
215 . 妊娠中に高血圧を認めず帝王切開術後にreversible posterior leukoencephalopathy syndrome(PRLS)、Preeclampsia、HELLP 症候群を発症した1 例
県立北部病院 産婦人科 知念 行子
216.当院で経験した致死性骨異形成症の3 例
県立南部医療センター・こども医療センター 産婦人科 栗原 みずき
217.卵子提供にて双胎妊娠したターナー症候群の1例
県立南部医療センター・こども医療センター 産婦人科 菅 更紗
218.異常細胞診指摘9 年後に子宮頚部腺癌Ib1 期となった一例
豊見城中央病院 産婦人科 濱川 伯楽
219.当院で施行した治療的円錐切除術に関する臨床的検討
豊見城中央病院 産婦人科 當眞 真希子
220.Gn-RH アナログ投与後に肺塞栓症を発症した一例
那覇市立病院 産婦人科 池宮城 梢
221.メトトレキサ―ト(MTX)2 段階投与により子宮
温存可能であった帝王切開創部妊娠の一例
豊見城中央病院 白石 康子
222.BMI44.8 の高度肥満を合併した子宮体部類内膜腺癌の一例
豊見城中央病院 産婦人科 苅部 誠子
223.外来化学療法におけるシスプラチン導入の認容性の検討
豊見城中央病院 産婦人科 上地 秀昭