����23�N�x������t�̋Ζ���������
�ւ���a�@�����Ƃ̍��k��

���ꌧ��t�����t����ψ�
�O�g�@�~�q

����9 ��22 ���i�j���ꌧ��t��قɉ��� �āA���E���e�a�@�̑�\�҂⎖���������Q�� ���A���ꌧ�����ی�������̈�t�m�ۑ�֘A ���Ƃ̉�����܂߁A�����̏�����t�̏A�J�x�� �̐��ɂ��āA�ӌ��������s�Ȃ����̂ŁA���� �T�v�ɂ��ĕ���B
�Q���҂͕a�@��\�҂�15 ���A������11 ���A �����E��2 ���A������t�������7 ���̌v35 ���ł������B
�c�@��
�i1�j��5 �ꌧ������t�t�H�[�����ɂ��ā@�`����擾�ւ̍���̑Ή��`
���ꌧ��t�����t������
�����@�j�q

����7 ��23 ���i�y�j�A �{��قɉ����ď����� �t�t�H�[�������J�Â� ���̂ŁA�ȒP�ɂ��̕� ��������B
�ߔN�A�{�ݑ��̏��� ��t�A�J���ɂ��Ă̗����Ǝ��g�݂��i�� �ɂ�A������t���̈ӎ����v�����߂���� ���ɂȂ��Ă����B�����ŏ�����t����ł́A�� ��22 �N�x�̏�����t�t�H�[�����ł́u��t�� �����Ă����ׂɕK�v�Ȏ��Ƃ́H�v�Ƒ肵�āA�� �_��������t���g�Ɍ����A�A�J���p�����邽�� �ɁA�܂��A�ӔC���ʂ������߂ɉ����K�v���c�_ ���s�Ȃ����B���̌��ʁA�u����̎擾�v���� ����t����t�Ƃ��ĐӔC���ʂ������Ƃ̈�� �q����Ƃ̕��������B�Ƃ��낪�A��ǂɑ� ���Ȃ�����t�����������݂ł́A�j������ ������̎����ɂ��Ă̏�s���͂��� ���Ȃ����_�Ԍ������̂ŁA���N�x�̑�5 �� �t�H�[�����́u������߂������v���e�[�}�� ���ĊJ�Â����B
�����œ����e��啪��̐搶���Ɏw����Ƃ� �ďW�܂��Ă��������A�e�f�Éȃu�[�X��݂��A ���������ڎw����t�⌤�C��A��w������ ���āA����擾�ɕK�v�ȗՏ��o����K�v�N ���ȂǗl�X�ȏ���������A������t�Ȃ� �ł͂̋^��⑊�k�ɉ�����ȂǁA�ǂ��R�~���j�P�[�V�����̎��ԂɂȂ����B
�i2�j��t�m�ۑ�֘A���Ƃ̊T�v
���ꌧ�����ی����㖱��
����@�R�j�A���c�@�Y��Y

1�D������t���A�J�x�� ����[�⏕����]
��t�̍ďA�Ƃ̑��i �ƋΖ����̐����ɂ� �闣�E�h�~��}�邱�� ��ړI�Ƃ��āA����22 �N�x���珗����t���A �J�x�����Ƃ��J�n�����B
�{���Ƃ́A1�j��t�̍ďA�Ƃ̑��i�F���E���C �����{���A���E������t�̐E�ꕜ�A���x������ ����2�j�Ζ����̐����F��Ë@�ւɂ����Ďd�� �Ɖƒ�̗������ł��铭���₷���������̉� �P���s�����ł���A�e��Ë@�ւ��A������� �I�Ƃ��ĉ��P�{������{����ۂ̕a�@�̌o� �S�ɑ��⏕������̂ł���B��N�̑��z�� 11,938 ��~�ŁA�⏕���͍�10/��10�iH23 �N �x���݁j�ƂȂ��Ă���B
�⏕���̊��p��͎��̂Ƃ���ł���B
�����Ƃ͈玙�A���A���̑���ނ����Ȃ��� ��ɂ��A�d���Ɖƒ�̗���������j����t ���x���̑ΏۂƂȂ��Ă���B
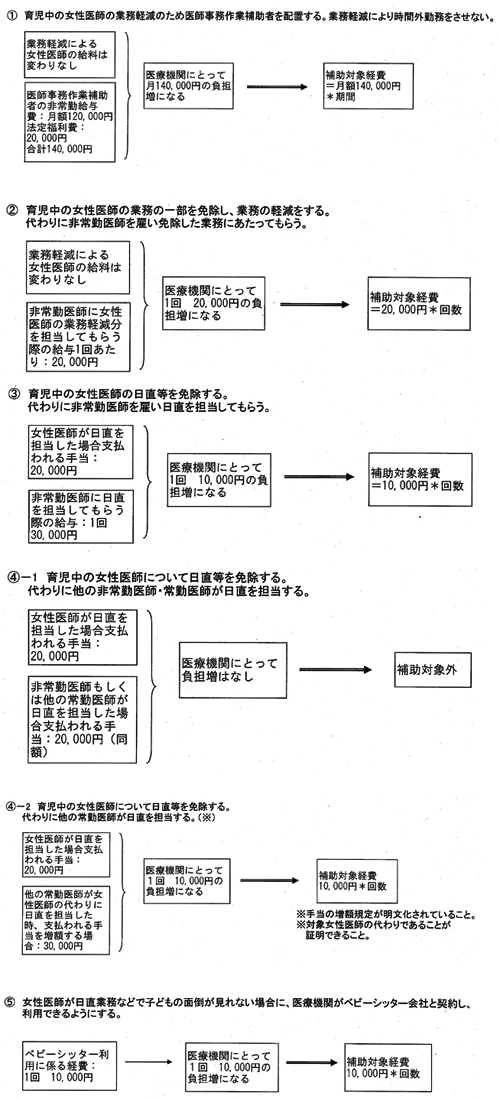
���N�x���\�Z�v�����Ă��邪�A�\�Z���̂��� ���ꗥ10 ���k�������Ƃ��������邽�߁A ����܂œ��l�̉^�p�͓���Ȃ���̂Ɨ\�z�� ���B�i���N�x�́A5 ��Ë@��92 ���̓����z�B�j �������A�����Ƃ����炩�̌`�ŁA������t�x�� �̂��������ɂȂ�ƍl���Ă���̂ŁA�e��� �@�ւ́A���Њ��p���Ă������������B
2�D���㓙�l�ވ琬�E�m�ێ���[����]
1�D���Ƃ̖ړI�E�T�v
�����̐��㓙���琬����ƂƂ��ɁA������ �������啪��̌�i�w���𐄐i���邽�߁A�� �匤�C��֏o�Ȃ���ۂ̗�����x������B�� �������֍u�t�Ƃ��Ĉ�t�����ق���ۂ̗���� �x������B
2�D�Ώ�
�i1�j����{���ȊO�̓��ɏ��݂���a�@�y�ѐf�Ï��ɏ��������t
�i2�j�ւ��n�f�Ï��ɏ��������t
�i3�j���ꌧ���ɏ��݂���a�@�̂����A���Ɍf����a�@�ɏ��������t
- �A�@�ւ��n��Ë��_�a�@
- �C�@�~�}�����a�@
- �E�@�n���Îx���a�@
- �G�@����@�\�a�@
�i4�j���̑����ꌧ�ɂ������Â̏d�v�ۑ�� �W��Ɩ��Ɍg����Ă����t�ŁA�m�����F�� ���
�i5�j�O4 ���Ɍf����҂̂ق��A�u�t���Ƃ��ď� �ق���K�v�������Ï]����
�i6�j�O5 ���Ɍf�����Ï]���҂Ƌ��Ɍ��C�ɎQ ������K�v�������Ï]���҂ŁA�m�����F�� ���
���Y����Ë@�ււ͕���22 �N10 ��13 ���t�� �����ɂĒʒm�ς݁B
�v�j���͌����㖱�ۃz�[���y�[�W�f�� �iH22.10.28 �t���j
����4 ���Ƃ́A�Ζ������������f�ÉȂ̈� �t�ɑ��āA�e��Ë@�ւ���蓖���x�����邱 �ƂŁA�����̉��P��}���t�m�ۂ��x�����邱 �Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B���ƊT�v�͎��̂Ƃ���B
3�D�~�}�Ζ���x�����Ɓi�~�}�Ζ���蓖�j[�⏕����]

1�D�ړI
���̕⏕���́A�� �~�}��Ë@�֓��ɂ��� ���t�̊m�ۂ����� ����ȏł��邽�߁A �x���E��Ԃɂ�����~ �}�Ζ���蓖��n�� �i���z�j�����Ë@�ւɑ��ď��������邱�� �ŁA�ߍ��ȋΖ��ɂ���~�}��ÂɌg���� �t�̏������P�𑣂��A��t�̊m�ۂ��x������� �̂ł���B
2�D�Ώۈ�Ë@��
�~�}��Ë@�ցA�������Y����q��ÃZ ���^�[���͒n����Y����q��ÃZ���^�[�̂� ���A����21 �N�x�ȍ~����V���Ɂu�~�}�Ζ��� �蓖�v��n�݁A�܂��͊����̎蓖�Ăz���� ��Ë@�ցB
�������A�~�}�Ζ���蓖�̑n�݂ɓ������� �́A�����̎蓖�̌��z���A�ƋK���̉����� ���s���Ă͂Ȃ�Ȃ����̂Ƃ���B
3�D�⏕�z
�E�⏕���F�Ώیo���1/3
�E�⏕��z�F 1 �l1 ����x���̒��ԁi13,570 �~�j
�E1 �l1 �����ԁi18,659 �~�j
�E�⏕�z�̎Z��F
- �蓖�z���⏕��z�����̏ꍇ ���@�⏕�z= �蓖�z�~ 1/3
- �蓖�z���⏕��z�ȏ�̏ꍇ ���@�⏕�z= �⏕��z�~ 1/3
4�D�V������ÒS����m�ێx�����Ɓi�V�����S ����蓖�j [�⏕����]
1�D�ړI
���̕⏕���́A��Ë@�ւɂ�����NICU�i�f �Õ�V�̑ΏۂƂȂ���̂Ɍ���j�ɂ����āA�V ������Âɏ]�������t�ɑ��āA�V������� �S����蓖�����x�����邱�Ƃɂ��A�ߍ��ȋ� ���ɂ���V������ÒS����̏������P�� ���A��t�̊m�ۂ��x��������̂ł���B
2�D�Ώۈ�Ë@��
NICU ��ݒu���Ă����Ë@��
3�D�⏕�Ώیo��
�ȉ�1�j��2�j���r���āA�����ꂩ�Ⴂ���z�� �⏕�Ώیo��ƂȂ�B
1�j�o�Y��NICU �ɓ��@����V������S�������t�ɑ��A�V�����̌����ɉ����Ďx�������蓖
2�j4 ��1 ���` 3 ��31 ���܂ł̊ԂɒS������NICU ���@�V�������~ 1 ���~
�E�V������ÒS����蓖���⏕�ΏۂƂȂ�� �́A�A�ƋK����ٗp�_���͂���ɗނ��� ���ނɎ蓖�ɂ��Ė��L����Ă��邱�Ƃ��� ���ƂȂ�B
4�D�⏕�z
�E�⏕�Ώیo���1/3�i�V����1 �l������1 �� �~�~ 1/3 ������j�� NICU ���@�����̂�
5�D�Y�Ȉ㓙�m�ێx�����Ɓi���؎蓖�j[�⏕����]
1�D�ړI
���̕⏕���́A�Y�Ȉ�E���Y�t�Ɍ�t����� ���؎蓖�̈ꕔ��⏕���A�Y�Ȉ�E���Y�t�̏� �����P��ʂ��A���؎{�݂̐l�ފm�ۂ��x������ ���̂ł���B
2�D�Ώۈ�Ë@��
�E������舵���a�@�E�f�Ï��E���Y���i�@ �l�E�l����Ȃ��j
�E�������Ԃɏ��Y�̔D�Y�w��������ꍇ�ɁA ���@����މ@�܂łɂ����镪�ؔ�p�Ƃ��āA �D�Y�w�����ʓI�ɒ�������z�i���i�� ���E��j���j�A���@��p�A�ٔՏ�����A�� �u�E���ˁE���������j��55 ���~�����ł��� ���ƁB
���D�Y�w���C�ӂɑI���ł���T�[�r�X�i�L�O�i�E���ʗ������j�̔�p�������B
3�D�⏕�Ώیo��
�E�ȉ��A1�j��2�j���r���āA�����ꂩ�Ⴂ���z ���⏕�Ώیo��ƂȂ�B
1�j�Y�ȁE�Y�w�l�Ȉ�t�y�я��Y�t�ɑ��A��� ���������̉ɉ����x����ꂽ�蓖�i�� �؎蓖���j
2�j4 ��1 ���` 3 ��31 ���܂ł̊Ԃ̕��،����~ 1 ���~
�E���؎蓖�����⏕�ΏۂƂȂ�ɂ́A�A�ƋK�� ��ٗp�_���͂���ɗނ��鏑�ނɎ蓖�� ���Ė��L����Ă��邱�Ƃ������ƂȂ�B
�E�Y�ȁE�Y�w�l�Ȉ�t�ȊO�̈�t�i�����Ȉ�A �����Ȉ�Ȃǁj��Ō�t�͑ΏۊO�� ����B
�E�l�̊J�ݎ҂̏ꍇ�́A��v������A�䎩�� �ւ̋��^�i�蓖�j���p�Ƃ��Čv��ł��Ȃ� ���߁A�ȉ���1�j�A2�j�����ꂩ�̏ꍇ�ɂ́A�J�ݎҖ{�l�ɂ��Ă��A���̈�Ï]���҂ւ̎� ���̎x���P���ŕ⏕�Ώیo��Ƃ��Đ\������ ���Ƃ��ł���B
1�j�ٗp����Ă��鑼�̎Y�ȁE�Y�w�l�Ȉ�E���Y �t�ɑ��ĕ��؎蓖���x������Ă���ꍇ�B
2�j���݂͑��̎Y�Ȉ���ٗp���Ă��Ȃ����A�A�� �K�����Ɍٗp�����ꍇ�̕��؎蓖���x������ ���Ƃ̒�߂�����ꍇ�B
4�D�⏕�z
�E�⏕�Ώیo���1/3�i�ꕪ������1 ���~�~1/3 ������ƂȂ�B�j
6�D�Y�Ȉ㓙�琬�x�����Ɓi���C��蓖�j[�⏕����]
1�D�ړI
���̕⏕���́A�Տ����C�C����̐��I�Ȍ� �C�ɂ����āA�Y�Ȃ�I�������t�ɑ��A���C �蓖�����x�����邱�Ƃɂ��A�����̎Y�Ȉ�� ��S����t�̈琬��}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B
2�D�Ώۈ�Ë@��
��t�@��16 ����2 ��1 ���ɋK�肷��Տ��� �C�C����A�Y�w�l�Ȑ���̎擾��ړI�Ƃ� �āA�w����̉��A���C�J���L�������Ɋ�Â��� �C���Ă���҂�����Ă����Ë@�� �i�Вc�@�l���{�Y�w�l�Ȋw��w�肷�鑲��� �����C�w���{�ݓ��j�B
3�D�⏕�Ώیo��
�E�ȉ��A1�j��2�j���r���āA�����ꂩ�Ⴂ���z���⏕�Ώیo��ƂȂ�B
1�j�Y�Ȍ��C��蓖1 �l1 ��������̎���
2�j�Y�Ȍ��C��蓖1 �l1 ��������50,000 �~
�Y�Ȍ��C��蓖�����⏕�ΏۂƂȂ�ɂ́A�A �ƋK����ٗp�_���͂���ɗނ��鏑�ނɎ� ���ɂ��Ė��L����Ă��邱�Ƃ������ƂȂ�B
4�D�⏕�z
�E�⏕�Ώیo���1/3�i�Y�Ȍ��C��1 �l1 �� ������5 ���~�~ 1/3 ������ƂȂ�B�j
�i3�j������t�x���Ɋւ���A���P�[�g�������ʕ��т�
���@�i�k����ᏼ�a�@�j�ɂ����鏗����t���A�J�x���̋�̗�
���ꌧ��t�����t����ψ�
�O�g�@�~�q
�A���P�[�g���ʂ̕�
�{�N8 �����{�A�����e�a�@�i���I�a�@�܂ށj ���тɗ�����w��w�������a�@�e�f�ÉȂ�Ώ� �ɏ�����t�x���Ɋւ���A���P�[�g���������{ �����B�i����68.8 ���j
�y������t���z���15 ���A����25 ���A ���C���30 ����������t�ł���B���̌��ʂ� ��A����܂��܂�������t�̊����������Ă��� �Ƒz�肳��A�����̌��C�����������T�|�[ �g���Ă����Ȃ���A�����̕a�@�̈�t�s���� �X�Ɍ������𑝂��Ǝv����B
�y���S�x�E�ҁz��N�x���{�̃A���P�[�g���ʂ� ���Ƃ炵���킹��ƁA�����悻���N20 ���O�� �̈�t�����S�x�E�ɓ����Ă���B�������A���E �̖ڏ��������Ă����t�������A���Ƃ����E�� ���Ă��錻������B
�y�@���ۈ�{�ݐݒu�̗L���z����21 �N�x�̃A�� �P�[�g���ʂƔ�r���āA�ۈ珊�ݒu�{�݂͑��� ���Ă���B�iH21 �N�x�F 43 �{�ݒ�12 �{�݁A 28 ���AH23 �N�x�F 77 �{�ݒ�25 �{�݁A32 ���j �܂��A�a���ۈ���{�̗L���Ɋւ��Ă��A���� 21 �N�x�ɔ�ׁA���{���͑������Ă���B�iH21 �N�x�F 43 �{�ݒ�1 �{�݁A2.3 ���AH23 �N�x�F 77 �{�ݒ�4 �{�݁A5 ���j�����̌��ʂ���� �����́A�����������Ă��Ă���Ɗ�����B
�k����ᏼ�a�@�ɂ�����u������t���A�J�x���v�̕�
�@���ɏA�C����10 �N�ɂȂ�B����܂Ŏ��{ ���Ă���������t�x���ɂ��ďЉ��B���� ��͕⏕���̂��閳���ɊW�Ȃ��s�Ȃ��Ă��� ���̂ł��邪�A��N�K���ɂ��Č������{����� �����Ƃ��邱�Ƃ��ł��A�ꕔ�[�����邱�� ���ł����̂ŁA������܂߂ďЉ��B
�i1�j�j����킸�_��ȋΖ����Ԑ��F���@�́A�� �@�@�\�����S�ŁA�O���ꑮ�̃p�[�g�̗p�͓ �����A�T20 ���Ԓ��x�̋Ζ��ł����Ă��A���� �鎞�Ԃ��ő���Ɋ��p���A��q����J�o�[�̐� �ŁA���ꂼ�ꂪ�A������ƈ�Â�ł���� ���ɔz���B
�i2�j�}�ȋx�݂ɂ��Ή��ł���J�o�[�̐��F���� ��t���������߁A�ʏ�̑�f�̐��ł͊Ԃɍ��� ���A��3 ��f�܂œ��ꍞ��f�\���쐬�B�a �����̋}�ς̊m����J�o�[�����t�̎��� ���Ґ�����ѕs�ݗ����l�����A���S����Ȃ� �悤�ɔz��������A���Έ�t�ł����Ă��A�x ���������_�������Ă��炤���߂ɁA��Έ�t�� �x�ꍇ�̑���f�Ƃ��đg�ݍ��킹�邱�� �ŁA�x�ވ�t���̐��_�I���S�����y������悤 �ɐS�����Ă���B
�i3�j�����E�����̃T�|�[�g�̐��F�����O����� ������E������̊m�ۂ�������A���@��t���� �����邢�͓�����6 ��ȏ�s�����ꍇ�́A���� �����ɒlj��������x���B�܂��A�q��Ē��̈�t �����������鎞�ɂ́A�Վ��ŕەꂳ����̗p�B ��N�x�́A���O����̓�����E������̍q�� ��ⓖ�����̏�悹�����A�ەꂳ���p�ɕ⏕ �������p�����Ă����������B
�i4�j���^�̃����n���F�ǂ̒��x�����邩��{�l �Ƒ��k���āA���^�Ƀ����n����t���A���^� ���I�[�v���ɂ��邱�ƂŁA�Z���ԋΖ��҂̐\�� ��Ȃ��⑽���J�o�[�ɓ����t�̐��_�I���̓I �ȃX�g���X�̉����ɂȂ���悤�ɔz���B
�i5�j����ʐڂ̎��{�F�N��2 ��@���ƒ���ʐ� ���s���A���ꂼ��̈�t�̏�����̔c���ɓw�� �Ă���B�܂��A���̒��ŏ����Ȍl�ڕW������ �Ă��炢�A���`�x�[�V�����̈ێ��E���i�ɓw�� �Ă���B
�i6�j�N�x���{�[�i�X�F�e�W�����̊Ǘ��҂��� �̕]���ɉ����A���ȕ]����@���]���A���ۂ̐� ���I�]���i���Ґ��A����J�ÂȂǁj�f�� ���āA���Ƀ`�[���v���x��]���B
�@���͑��k���ł����蒲�����ł�����B��� �Ȗʂ����X���邪�A���̂悤�Ȃ��Ƃ�ʂ��āA 2001 �N8 ���@���A�C�����A���Ȉオ7 �l�i�� ��3 �l�j�ł������̂ɑ��A2011 �N7 ���ɂ� 12 �l�i����6 �l�j�ƈ�t���m�ۂ��邱�Ƃ��ł��A��Â̎����オ���Ă����Ɗ�����B����� �̂��Ƃ́A�e�{�݂̈�Ò̐�����ӊ��� �قȂ���̂����A�}�����a�@�ɂ͋}�����a�@�� ��́A�������a�@�ɂ͖������Ȃ�̋��݂Ǝ�� ������A����A�܂��܂�������t�̊��������� �鎖���l����Ƃ��ꂼ��̎{�݂ɍ������H�v ���d�ːݒ肵�Ă����������Ȃ��Ǝv����B
���lj��c����
�����a�@�@�\�����a�@�ɂ�����u������t�A�J�x�����Ɓv�̕�
�����a�@�@�\�����a�@�@���@��
�����N�G�搶

��N�x������t���A �J�x�����Ƃ����p���� ���тɂ��Ď��̂Ƃ� ����������B
1�D��g���e
�E�玙�x�ƁA�玙�Z���� �Ζ����x�̊��p
2�D��̓I�ȓ��e
�E�玙�Z���ԋΖ����x���̊��p�ɔ�����ֈ�t 1 �������A���тɈ�ǎ����⏕��1 �� �i���j�y�ѕa���S�������⏕��1 ���i�� ��j��z�u���Ĉ�t�̕��S�y����}�����B
3�D��g�ɂ����镉�S��
- ��p�F�l����Ƃ��Ĉ�t1 ���ɌW�鋋�^��@11,860,479 �~
- ��ǎ����⏕1 ���i��j�ɌW�鋋�^��@1,455,397 �~
- �a�������⏕1 ���i��j�ɌW�鋋�^��@1,243,507 �~
- �@�蕟����i���Ǝ啉�S���j�Ƃ��ā@2,466,570 �~
- ���v17,025,953 �~�̕��S��v�����B
4�D���{����
�E������t�̃��C�t�X�e�[�W�ɉ������Ζ��̐� �̊m���y�ш�t�̈�Ǖ��тɕa���ɂ����鎖���I�ȕ��S�y���Ɍq�������B
5�D�]���E���{����
�E���@�́A��t����15 ����7 ���̏�����t�� �̗p���Ă���A4 ���������ł���2 �����玙 �x�ɒ���1 �����玙�x�ɂ�蕜�w���Ă���B 4 ���̊�����t�͓��@�A�E��Ɍ������Ă���B
�E�o�Y��̈�t�̋Ɩ����͌����������� ���A���@�ł́A������t�̎q��ďA�J�x���� �������邱�ƂŁA������t�����������₷�� �������邱�Ƃ��o�����B
�ӌ�����
�t���[�g�[�L���O�`���ɂāA�ӌ��������s�����B
��t�m�ۑ�֘A���Ɨ\�Z�ɂ���
�ˌ����ݎ}����i�������d�R�a�@���@���j

������t���A�J�x�� ���Ƃɂ�����u��t�v �̒�`�ɂ��āA��� ���C�������܂� �ł��邩�B
����R�j�i�㖱�ہj�@���C��ɂ��Ă͍� �̂Ƃ���z�肵�Ă��Ȃ��B�{���Ƃ̖ړI�́A�� �����Ԃɒ�߂��Ȃ��ٗp�_���ٗp�`�Ԃ����� ���鎖�ł���A���̂Ƃ��됳�K�ٗp�҂�Ώۂ� ���čl���Ă���B�������Ȃ���A�a�@�ɂ���� �͗l�X�Ȍٗp�`�Ԃ�����Ǝf���Ă���̂ŁA�� �̓I�Ɏ���������Ē�����A���֊m�F���Ă� �������B������C��ɂ��ẮA�m�F������� �߂ĕ���B
�m��c�肿������i��l�N���j�b�N�@���j
�����Ƃɂ����闈�N�x�̎��{�\��́B
����R�j�i�㖱�ہj�@���N�x�����̕⏕���� �����͉\�ł���ƍl���Ă���B�A���A���݂� �⏕����10/10 �ƂȂ��Ă��邪�A���̓��̔����� �Đ���������p���Ă��邽�߁A26�N�x�ȍ~�́A���̗\�Z�Ƃ��Ă�1/2 �ɂȂ�\���������B
�ɔg�v�����@���i�������a�a�@�j

���㓙�l�ވ琬�E �m�ێ��Ƃɂ��āA�� �_�ȗ̈�ɂ͎w��㐧 �x�����邪�A���̌��C �ł����Y���Ƃ����p�� ���邩�B
����R�j�i�㖱�ہj�@�ǂ̂悤�Ȍ��C��Ȃ� �������鎑�������O����������A�\�ߐR ���̏�A�ԓ��������B���݂ɁA�ǂ̐\���Ɋւ� �Ă����O�ɏ���������������A�R������ �葱��������Ă���B
�e��Ë@�ւ̏A�J�x���̐��ɂ���
���������@���i������w��w�������a�@�j

�{�@�ł́A�O�@���̎� �ォ�珗����t�x���ɂ� ���Ă͑傫�ȓw�͖ڕW�� ��Ƃ��Čf���A���̕� �j�Ői�߂Ă���B���ۂ� �͐�匤�C�Z���^�[���� ������̊��x������� �݂��A�����𑋌��Ɏx���Ɩ����s�Ȃ��Ă���B�� ��͑�w�a�@�̓��������A�D�P��o�Y�A�玙�Ȃ� �ŁA�x�����K�v�ȏ���̑����͈���i���j�� ����A�Љ�I�Ɏア����̐l�����ł���B�s���� ���̕ӂ���l�����āA����̎ア���̃T�|�[ �g������l���ė~�����B
�剮�S��Z���^�[��
�i������w��w�������a�@����Տ����C�Z���^�[�j

�{���C�Z���^�[�ł́A ����擾��ڎw���� �t���T�|�[�g���邽�߂� �̐����\�z���Ă���B ������t�Ƀt�B�b�g�� ���_��̂���v���O ����������Ă���B�����I�ɂ́A�V�~�����[�V�����Z���^�[�̊��p�� ���l�������B����܂�10 �����̗��p���т��� ��B�܂��A���A���k���ɂ������A���ꌧ�S�̂� ������t�x���̕����Ƃ��Ă���`���Ă��������B
�ΐ쐴�i�@���i�����a�@�@�\����a�@�j

���@�ł́A���ɔF�� ����Տ����������� �肽���Ƃ������j�ɂ� ��A�Տ������݂̂ŗ� ���Ƃ��������Ŗ��N�� �����̈�t���̗p���� ����B�w��\��_�� ���A�D���ȕ������ŗǂ��Ƃ��Ă���B������ �t�ɂƂ��ẮA�����₷���A����擾�̍ŒZ �R�[�X�ɂ��Ȃ�B�w��\���S���������Ă��� ���B������S�Ďx�����Ă���B
���R���s�@���i�암�a�@�j

������t�x���̎�� �g�݂ɂ��ĕ��ɎQ �����B���@�ł̏A�J�� ��Ƃ��ėB����g�� �Ă���̂́A���N7 �� ����n�߂��@���a���� ��ł���B�j����킸 �S�E����ΏۂƂ��Ă���B����̖ڕW�́A�@�� �ۈ珊�̐V�݂ł���B
���{�����@���i�L���钆���a�@�j

���@�̑S�̈�t���� 128 ������A��Έ�84 ���̓��A������t�� 15 �����߂Ă���B�� ���A���C���44 ������ ���A�������C���45���A ������C���32 ������ ����t�ł���B
���@�́A������t�ɑ��ē����₷���Ζ��� ����S�����Ă���B�Ⴆ�A�Ζ����Ԃ̒����A �����Ə��A�x�e�������A�w��͉��肪����Ή̐����͂Ȃ��B����擾�Ɋւ��Ă��A���C �w��a�@�ւ̏o�������������Ă���B�Y�x�� �ǂ����₷�����ɂ���Ǝv���B�܂��A�@���� �珊���ݒu���Ă���A������t�����p���Ă���B
�܂��A�玙�E���x�Ɩ@�̉����ȑO����v�w ��������t�̏ꍇ�A�j����t�̈玙�x�Ƃ��F�� �Ă������т�����B
��R�����@���i���ꃁ�f�B�J���a�@�j

�O�g�搶�̕ɂ� �������^�ւ̔��f�ɂ� ���ẮA�j����킸�� �{���Ă���̂��B�i�� ���F���{���Ă���j
�����쏃���@���i���ꋦ���a�@�j

���@�́A8 5 ���� 2 2 �� ��������t�ł� ��B�����Ƃ��ẮA�� ���Ȃɏ��オ����9 �l ��5 �l����B�܂��A�� �C��ɂ͐�����擾 ����悤�����Ă���B �q��Ē��̈�t�̂��߂ɁA���ԒZ�k�̋Ζ��`�� �i2 ���j���̗p���Ă���B�a���ۈ�͊��Ɏn�� �Ă��邪�A����A�@���ۈ�̐ݒu��ڎw���Ă� ��B�������Ȃ���^�c��̖�������A�s���I �ɉ�����������肪�����B
���ljp��@���i����ԏ\���a�@�j

���@�ł��ƒ�̎��� �œ������ł��Ȃ��� �t��A�������ł��Ȃ� ��t������B��N���� �̉�œ�������`���� ���A�����S�̂Ƃ��ċ� ���セ�̂��̂������ �����Ǝv���Ă���B������t�͂ǂ̕a�@�� �������������g�̊�]����Ζ��`�Ԃ��Ă��� �~�����B�����ẮA���ꂪ�Ζ���̊����P�ɂ��q����B
�������@���i�����a�@�j

�ŋ߂͏������]�� �銳�҂������Ă���_�A �܂��A40 �Έȉ��̎Y�w �l�Ȉ��7 ���������� ����_�܂���ƁA ���㏗����t���ٗp�� ��@���ϋɓI�ɍl�� �Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���@�̗�������5 �N �O����@���ۈ珊�̐ݒu���l���A�ꏊ�͊��Ɋm �ۂ��Ă��邪�^�p���@�ɂ��Č������ł���B
�㗢�������@���i�V�v��a�@�j

30 �N�O�ɕۈ珊���^ �c���Ă������A�o�c�� ���܂��s�����p�Ƃ��� �o�܂�����B���݁A�� �@�ł́A�j���W�Ȃ��A �Ȃ�ׂ��w��ɎQ���� ���Ă���B�܂��A��� ��擾�̍ۂ̏o����p���a�@�����S���Ă���B ���̂Ƃ��돗�ォ����s���̐��͂Ȃ��Ǝv�� ���A������t�̋Ζ����ɂ��ẮA���ア�� ����Ȗ�肪�o�Ă���Ǝv���̂ŁA�ǂ��E��� ����ڎw�������Ă��������B
�F�����q���@�����Ō암���i�C�M�a�@�j

�玙���Ԓ��́A���� �a�@�̕����搶���̃j �[�Y�ɏ_��ɑΉ��ł� ��ƍl���Ă���̂ŁA �q��Ċ��Ԓ��́A���� �a�@�ɖڂ������ĖႦ ����ǂ��Ǝv���B���@ �ł͏�����p�̈�ǂ����邪�A�c�O�Ȃ��疢�� ���p����Ă��Ȃ��B�܂��A�����f�C�T�r�[�X�� ������S���ē�����E���������B
��c�T�ꗝ�����i���ƂԖ�ѕa�@�j

���̐��N�A�i�[�X�� �A�J�����肵�A�o�Y�� �����E���Ȃ��P�[�X�� �����Ă���B���N�O�� �i�[�X��Ώۂɉ@���� �珊�Ɋւ���A���P�[ �g�����{�������A�@�� �ۈ珊��������Ƃ��Ă������p�Ɍ��т��Ȃ� �Ǝv���錋�ʂɂȂ����B�܂��A������t��p �̓��������l���Ă͂��邪�A���̎{�݂̏� �Q�l�ɂ��Ȃ�����g�݂����B
����c�щ@���i�k���n���t��a�@�j

���@�ł́A��̏� ����t��5 ���A���� ��1 ������A3 �����q�� �Ē��ł���B�܂��A3 �� ���O��1 �N�Ԃ̈玙�x �ɂ��I�������オ���A �������A���A�̍ہA�� ���̐��ɂ��Ċ�]���A�_��ɑΉ������B
����Ɋւ��ẮA���ݖ����Ȉオ1 ������ ���T���̊����ň�N�ԑ�w�a�@�֔h������ ����B
�@���ۈ珊���^�c���Ă��邪�A�w���ۈ� �̃j�[�Y���o�Ă��Ă���A����̉ۑ�Ƃ��Ă� ���x���ł��邩�����������B
�{���P���@���i�����a�@�j

�@�l�S�̂�25 ���A34 ���̏�����t������B ������t�ɂ�3 �̗� �ꂪ����B1�j��t�̗� ��A2�j�����̗���A3�j��e�̗���ł���B
1�j��t�̗���́A�j ����ʂ��邱�ƂȂ����l�Ȍٗp�`�Ԃ�S������ ����B�j����t�ɂ����l�̓������������Ȃ��� �A�����������ɂ����A�������ē����h���� ���Ă��܂��_�𒍈ӂ��Ă���B2�j�����̗���� �́A���ゾ���̋x�e����݂��Ă���B3�j��e�� ����ł́A�ۈ珊���^�c���Ă���B30 �l��6 �� ������̎q���ł��邪�A�����A�N��1 �疜���x �̐Ԏ��ł���B��Ë@�ւň�ÈȊO�̎����s�� �Ɩw�ǂ��Ԏ��ɂȂ�B�����Ԏ��ɂȂ�Ȃ��悤 �Ȏx���̂�������������ė~�����B
������t�o���N���[�����O���X�g�̊��p�ɂ���
�m��c�肿�����

�{�o���N�ł́A���[ �����O���X�g�i�o�^�� ��220 ���j�����p���� ���l���z�M���� ����B�z�M���e�͏�� ������A�X�|�b�g �Ή��̋��l�܂ŕ��L�� �����Ă���B���[�����O���X�g�o�^�҂ւ́A�� ��z�M��A�F�l�E�m�l�ւ����[���]������悤 �˗����Ă���A�z�M��A�����ɓ��肷��P�[�X ������B�e��Ë@�ւ������p�������������B
�@��
���ꌧ������t����ψ��@��p�Ύq

�{���͌��̒S���҂� ���t�m�ۑ�̋�� �I�ȗ��p���@�ɂ��� �̐���������A�e��� �@�ւɂƂ��Ă��L�Ӌ` �ȏ��ɂȂ����� �v���B�����g���A���� ��t����̊�����ʂ��Ċ����Ă���̂́A�� ���A�j���Ƃ������ł͂Ȃ��A��l�̈�t�Ƃ� �āA�ǂꂾ�����`�x�[�V�������ێ����A�d���� �p�����Ă���������ł���A����́A������ ���ꂩ������ɂ������A���ۂ͒j����킸 �F�Ŏx�������Ă������Ƃ��厖�ł���Ƃ����� �ł���B
��X����t�ɂȂ������Ɣ�ׁA���͌b�܂�� ����B���̓����́A�����̖Ə��\�����s���ƒf ��ꂽ�B���͂��̂悤�Ȃ��Ƃ͖����Ǝv�����A�����͒j���������ƌ����A���ꂮ�炢�̋C�T �ł���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂ł���B ������t�ɑ�������P�����Ȃ���A���̂� ���ȓ����ӎ����p�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ɗ��� �Ă���B����s�Ȃ�ꂽ������t�t�H�[������ �����ĉ������̗���̊w���̎Q�����������B�� ��́A����̏����v���s����ŁA��X�̘b�� �^���ɕ����A�l�X�Ȏ���⑊�k��ϋɓI�ɍs�� �Ă����B��t�ɂȂ��Ă���ł͂Ȃ��A�w���̍� ���炠�̗l�ȋ@��𑝂₵�A�Ⴂ��t���T�|�[ �g���鎖����ł���B����Ɍq���Ă��������Ǝv���B
�{���͑����̊Ǘ��҂̕��X�ɎQ�����Ă��������A���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B
��ۋL
���ꌧ��t�����t����ψ��@�O�g�@�~�q
�a�@�����Ƃ̍��e����A��5 ��ڂƂȂ�܂����B�A���P�[�g�̌��ʂ�e�{�݂̉@���搶������ ���b�̒�����́A�ۈ珊�̖���Z���ԋΖ����A�����E�����Ə��ȂǁA������t�̗����x���Ƃ� �Ă̊����P�͒����ɐi��ł��Ă���Ɗ����܂����B�����āA����̍��k��ł́A�����̎x�� ����o�ϓI�Ƀo�b�N�A�b�v���邽�߂̏�����t���A�J�x�����Ƃ���㓙�l�ވ琬�E�m�ێ��� ���̑��̈�t�x���⏕���Ɋւ���������������ی����㖱�ۂ��璼�ڎf�����Ƃ��ł��܂������A ��ѓ���ō����a�@�@�\�����a�@���@���̕����N�G�搶����N�x�̓��@�ɂ�����⏕�����p�� ��̓I�Ȃ��b������A�e�a�@�ɂƂ��ẮA�ǂ����ɂȂ����Ǝv���܂��B�����̕⏕���� ���Ɋ��p���鎖�Ɓu����ɂƂ��Ė{���ɂ��䂢���Ɏ肪�͂��v�悤�Ȋ��p���₷���⏕�����x �Ɉ�Ă邱�Ƃ���ł���Ɗ����܂����B
�����ł��m���ɏ�����t���������Ă��܂��B���̏�����t��������������ƈ炿�A�d���𑱂��A ����̈�Â��x������悤�ɁA�e��Ë@�ւ�������t����������������t����F�œw�͂��d�� �Ă������Ƃ��K�v���Ǝv���܂��B