平成22 年度第4 回沖縄県・沖縄県医師会連絡会議
常任理事 安里 哲好

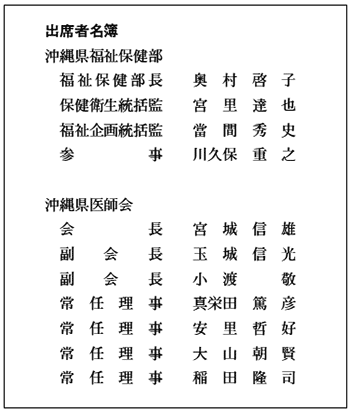
去る1 月27 日(木)、県庁3 階第3 会議室に おいて標記連絡会議が行われたので以下のとお り報告する。
議 題
1.予防接種の一斉開始(4 月)について (県医師会)
<提案要旨>
平成22 年度より、「子宮頸がん等ワクチン接 種緊急促進臨時特例交付金」により子宮頸がん 予防(HPV)ワクチン、ヒブ(インフルエン ザ菌b 型)ワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン の接種事業が実施されることになっている。
しかし、市町村ごとに開始時期が異なり(平 成22 年度開始4 市町村、平成23 年4 月開始21 市町村、平成23 年5 月開始8 市町村、未定8 市町村)、県民が混乱すると考えられる。
ついては、平成23 年4 月より、全市町村が 当該ワクチンの接種ができるようご指導いただ きたい。
<医務課より回答>
ワクチン接種緊急促進事業については、実施 主体が市町村となっている。今回の補助事業は昨年末に国において補正予算が成立したため、 市町村においても十分な準備期間がなかった。
そのため、今年度から事業開始する市町村は 4 市町村と少ない。
その他の全市町村においても23 年度のでき るだけ早い時期に本事業を実施する予定である が、事業開始には、住民への周知等準備に要す る期間が必要であるため、現時点で4 月開始26 市町村、5 月以降11 市町村となっている。
県としては、できるだけ4 月からは全市町村 が実施するよう市町村に対して再度依頼したい と考える。
<主な意見等>
■ 4 月から全市町村が実施するよう、市町村に 対して本日付の文書にて再度依頼する(福祉 保健部)。
2.子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業 の実施について(医務課)
<提案要旨>
平成22 年度国の補正予算においてみだしの 事業の予算措置がなされたことにより、市町村 において対象年齢層に対する子宮頸がん予防ワ クチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチ ンの接種が開始される。それに伴い、市町村と 接種協力医療機関との契約等が必要となる。ご 理解、ご協力をお願いしたい。
なお、主な事業内容は下記のとおりである。
記
1.実施主体:市町村
2.対象ワクチン:子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン
3.事業期間:平成23 年1 月〜平成24 年3 月31 日
4.負担割合:公費負担率90 %、国1/2、市町村1/2
5.基準単価:子宮頸がん予防ワクチン 15,939 円
ヒブワクチン 8,852 円
小児用肺炎球菌ワクチン 11,267 円
※基準額=基準単価× 0.9 × 1/2 が市町村への最高補助額
※上記単価は、平成23 年4 月30 日までに事 業を開始する市町村に適用。ワクチンの実 勢単価を調査した上で、4 ヶ月ごとを目安 に改定する。
6.要望事項:市町村と地区医師会との契約に ついて、基準単価以下で契約していただきた いとの要望が市町村から寄せられている。ま た、このことについては厚生労働省からも日 本医師会へ要望が出されており、ご配慮願い たい。
<県医師会主な意見等>
□各地区医師会に照会したところ、北部地区医 師会は国が示した額で契約予定、中部地区医 師会は国が示した額で契約、他の5 地区医師 会の基準単価は未定となっている。
予防接種事業は、各地区医師会と県内市町 村との契約であるので、基準単価がワクチンの 実勢単価により4 ヶ月ごとを目安に改定される こと及び基準単価以下での契約のお願いにつ いて、各地区医師会に周知する(県医師会)
3.へき地医療を守るための国の補助金等の 制度について(県医師会)
<提案要旨>
離島・へき地の医療体制を維持していくため には、自治体や医療関係者の努力だけでは難し く、補助金等による制度拡充が必要であると考 えている。
特定健診への補助金も含め、へき地の医療を 守るための国の補助金等の制度についてお伺い したい。また、23 年度以降に予定される補助 金等があれば併せてお伺いしたい。
<提案要旨補足>
□現在、県立北部病院において産婦人科医師が いないという問題がある。この課題について は過去何度も出されており、どこかで誰かが 決着をつけないといけない。
産婦人科の医師確保については、県立病 院、琉大、医師会等、全体で協議会を持ち検 討を行うことにしている。5 年後、10 年後の 産婦人科医師をどう育てるか、またどう支援 していくか、そういったことを具体的に検討 していく必要がある(県医師会)
<医務課より回答>
設備整備事業及び施設整備事業については、 当該事業がある場合に国庫補助事業を活用して いる。
県においては、離島・へき地医療の充実を図 るために、新たな沖縄振興に向けた制度要求の 中で、ヘリコプター等添乗医師等確保事業及び ドクターヘリ事業に対する補助制度の新設・拡 充、離島の医療機関への医師派遣及び離島の産 科医師確保のための手当支給に対する補助制度 の拡充を国に提案しているところである。
<主な意見等>
■産科医師の手当の一部を国庫補助事業として 助成を行っており、現在、いくつかの医療機 関から申請が出されている。また、琉大の産 科を希望する学生の修学資金の貸し付けや、 後期研修医(産科等)の研修資金の貸し付け を行っているところである(福祉保健部)。
□産科医師確保の課題は、県立病院だけでは難 しいと考える。琉大や基幹病院等、トータル で議論できる仕組みを考えて行く必要があ る。また、あらゆる補助金を集約し、全体を どうするかということではなく、先ずは産婦 人科医師をどうするか検討してはどうかと考 える(県医師会)。
■現在、県立病院を始め病院にお産が集中する 状況となっている。課題認識は県も一緒であ る。お互い検討していきたい(福祉保健部)。
■修学資金を貸し付けている琉大の学生や、研 修資金を貸し付けている後期研修医の総合的 な配置について検討する場を設けたいと考え ている。また、配置後のフォローについても今 後検討してきたいと考えている(福祉保健部)。
4.重症難病患者入院施設確保事業に係る協 力について(国保・健康増進課)
<提案要旨>
○重症難病患者入院施設確保事業(以下、「本 事業」という。)は、入院治療が必要となっ た在宅の重症難病患者に対して、地域の医療 機関の連携による難病医療体制の整備を図 り、適時・適切な入院施設の確保等を行う事 業である。
○重症化した在宅難病患者に対する入院施設確 保については、これまで患者会や医療機関等 から要望があるが、在宅支援機関や医療機関 等の関係機関が全体的に議論し検討する場が なかったことから、次年度より難病医療連絡 協議会を設置し、事業内容等を検討していき たいと考えている。
○本事業を推進するにあたり、医療関係者に難 病医療連携協議会へご参加いただき、また拠 点病院及び協力病院の確保に関してご協力を 賜りたい。
<主な意見等>
□重症難病患者は長期の受け入れとなる場合が ある。その場合、療養病床での対応となる が、療養病床は診療報酬が包括での算定とな るため、難病患者に処方する治療薬は高く、 薬代だけで医療費の大部分を占め、適切な医 療提供体制を取ることが難しくなる場合もあ る。この辺りの課題についても検討していく 必要がある(県医師会)。
□このようなケースはレアケースということで はなく意外と沢山ある(県医師会)。
■ご指摘いただいた点については、しっかりと 確認整理させていただき、必要があれば国に 対して要望していきたい(福祉保健部)。
その他
福祉保健部医務課より、「診療報酬制度の見 直し又は助成制度の新設等による対策」とし て、県で検討している内容について、概ね以下 のとおり説明がった。
本県の離島・へき地医療について以下の課題 が挙げられている。
(1)自衛隊が急患搬送するヘリに添乗する医師
に関して、派遣する病院に対する資金供与が
無く、病院のボランティアで行われている。
(課題)協力病院の医師派遣の取りやめのおそれ。
(2)ドクターヘリ事業について、燃料費等の高
騰に伴い、実施病院の運営資金が厳しくなっ
ている。
(課題)ドクターヘリ事業の取りやめのおそれ。
(3)離島等の中核病院の医師について昨今の大
学病院の研修医不足から医師確保が厳しくな
っている。
(課題)大学病院等からの医師派遣では医師確
保は厳しい。
(4)離島等における産科医の確保が厳しい。
(課題)産科医が離島に行くようなインセンテ
ィブが必要である。
(5)離島においては、島内での治療が困難な場
合、沖縄本島等で受診するケースがある。
(課題)治療等のための交通費・宿泊費の負担
により、経済的に厳しい。
以上5 点の課題の解決策として、県として以 下の2 案を検討している。
A 案.診療報酬制度による場合
1)ヘリコプター添乗医師の派遣病院、ドクターヘ リ実施病院及び離島等中核病院に医師派遣をす る病院に対して、包括的診療報酬制度(DPC 制度)の見直しにより診療報酬加算を行う。 2)離島等の医療機関において、産科医に対して 手当を支給する場合に、診療報酬加算を行う。
B 案.財政支援による場合
1)ヘリコプター添乗医師の派遣病院に対する財 政支援の新設。
2)ドクターヘリ実施病院に対する財政支援の 拡充。
3)離島等中核病院に医師派遣する病院に対する 財政支援の拡充。
4)産科医に対して手当を支給する離島等の医療 機関に対する財政支援の拡充。
5)離島での治療等が困難な患者に、沖縄本島等 の医療機関で受診する場合、その交通費・宿 泊費を補助。
○離島医療確保に要する経緯であるため、A ま たはB いずれの場合において国の財源で対応 する仕組みを構築する。
<主な意見等>
■沖縄県だけ特別に診療報酬の上乗せが出来な いかと考えている。その財源については国の 公費を充てていただく形。診療報酬というこ とでハードルは高いと考えてはいる(福祉保 健部)。
□診療報酬という考え方は、どちらか一方の項 目を上げれば、一方の項目が下がってしまう 恐れがある。診療報酬という形での議論はし ない方が良いと考える(県医師会)。
5.沖縄県国民健康保険広域化等支援方針の 策定について(報告)(県報告事項) (国保・健康増進課)
この度、市町村国保が運営している国民健康 保健事業を、将来的に統一化して行こうと方針 が示されている。
これは、平成22 年5 月に公布された改正国保 法の中でその前段階として、国民健康保険統一 化していく際の県の支援方針ということで国民健 康保険広域化等支援を策定した。
平成22 年10 月には、市町村で構成される各 地区国保協議会等の代表者を構成員とする沖縄 県国民健康保険広域化等連絡会議を設置し、数 回に亘って議論を行い、平成22 年12 月に沖縄 県国民健康保険広域化等支援方針を策定した。
今後については、市町村国保間でそれぞれの 事情で標準保険税、これらについてどういうふ うに扱っていくか、収納対策にかかる共同実 施、そして医師会と密接な関係をとっていき、 保険事業の推進、これによる医療費の適正化等 について、さらに議論を深めていきたいと考え ている。こういった状況について報告をさせて いただきたい。
今回の沖縄県国民健康保険広域化等支援方 針策定の背景について。
市町村国保においては、従来から保険財政が 不安定となりやすいという構造的な課題があ る。保険財政の安定化を図る観点から、国、県 及び市町村は公費の投入を行っている。
国においては、市町村国保の財政を安定さ せ、現状を改善する狙いから、将来の地域保険 として一元的運用を図るとの観点から先ずは、 市町村国保の運営に関し、都道府県単位による 広域化の方向性を示している。先ず最初のステ ップとして、都道府県は広域化支援方針を定め ることができるとされた。
その方針は、事業の広域化、財政の広域化、 標準設定の3 つの柱で構成されている。
この中で、国保保険料収納率向上への対応と して、各都道府県が進めるインセンティブとし て、従来は収納率の悪い市町村については、本 来入る調整金(補助金)がその収納率に応じて 減額されるペナルティー(減額措置)がある。減 額されないように収納率を上げていくというふう な仕組みがとられているが、今回の改正で県の方 で支援方針を策定すると、市町村に対する減額 措置の適用除外を受けることになっている。
実際に、沖縄県では平成17 年度から平成21 年度までの過去5 年間に29 億円が減額されて きた。本来の収納率をクリアしていればこの分 の補助金が入っていた。
今後の高齢者医療制度の見直しということ で、当初は平成25 年の3 月ごろと報道されて いたが、最近の情報では1 年遅れて平成26 年3 月に、現在の後期に入っている被保険者が国民 健康保険に戻ってくるであろうと言われてい る。最終的には全年齢を対象にして国保の広域 化を図って行こうとしている。
それ以外にも、3,700 億円にも上る法定外繰 入などで運営されている国保について、市町村 国保が抱える構造的な問題の抜本的な解決策を 示して欲しいと要望している。
今後のスケジュールであるが、平成22 年の 末に最終とりまとめが行われ、23 年2 月に法案 提出をする予定であったが、最近の情報では少 し遅れるであろうと、資料の中では25 年3 月 に新しい高齢者医療制度の施行とあるが、平成 26 年3 月になる予定であると言われている。
<主な意見等>
□県から支援策を策定するとペナルティがなく なると言う事だが、そうなるとさらに市町村 においては保険料を徴収するインセンティブ がなくなるのではいか(県医師会)。
■国の方は、マイナスにならないようにという ことで、資料にも示したように那覇市におい ては91 %以上というふうに、保険者規模に 応じた目標価値が設定されている。
従来の目標値よりも那覇市においては厳し くなっている。従前では89 %を越えなけれ ばペナルティがなかった。今回ペナルティの概念を無くしたので、今度は目標ということ で設定をした。これに対するインセンティブ はどうしているかというと県の調整交付金を 活用して、目標を超えた市町村には1.5 倍掛 けへ、あるいは2 倍掛けの調整交付金を交付 する仕組みにした(福祉保健部)。
□高齢者医療制度見直し案であるが、この案が果たして成立するのか疑問である。恒久的な ものではないと思われる。実現の可能性は難 しいのではないか(県医師会)。
■全国知事会でも法案化は難しいとの見解が示 されている。ただ、一つの目標としては設定さ れているのでご理解を願いたい(福祉保健部)。
印象記

常任理事 安里 哲好
議題は5 題もあり、出席者も多く、活発な意見交換がなされた。
議題1「予防接種の一斉開始(4 月)について」、議題2「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事 業の実施について」の提案があった。1)接種の開始時期の問題は各市町村の住民への周知期間等も あり、4 月或いは5 月頃になろうとのこと。2)接種料金は市町村と地区医師会との契約になるが、お およそ基準単価での契約になろう(市町村は基準以下を希望、日医は技術料については基準額を下 回らないよう市町村と交渉することを要望している)。3)ワクチン単価は4 か月ごとに改定する予定 との事。今後、広域化(市町村間の相互乗り入れ)や接種スケジュール(三種混合ワクチンなどの 定期予防接種も含め)の対応が課題となろう。
議題3「へき地医療を守るための国の補助金の制度について」は、産婦人科医の確保・派遣や後 期・専門研修医を育成するために、具体的に実施して行く際に、国庫補助支援とその継続が課題で あろう。産婦人科医の確保・育成は産婦人科領域の医療を担っている多くの医療機関の協力を得て、 オール沖縄で対応して行く必要があり、そこに補助金の集約が望まれる。関係各位の協力を得て、 次年度はぜひ実行して行きたいものだ。
議題4「重症難病患者入院施設確保事業に係る協力について」は、難病医療連絡協議会設置や拠 点病院設置を行っていないのは全国で、当県を含め2 県とのこと。次年度、協議会を設置する予定 であり、それへの参加と、拠点病院及び協力病院の確保への協力依頼があった。
議題5「沖縄県国民健康保険広域化等支援方針の策定について」は、国民健康保険事業の運営の 広域化と財政の安定化を趣旨としている。今後、2 つの大きな課題があろうと思われる。その一つ は保険料の収納率の問題であろう。市町村を中心とすると、課題が如実に現れ、その対策が市町村 単位で具体的に行われるが、県単位になると市町村の責任が不明瞭になり、ペナルティー(29 億円 /5 年間)も課されなくなるであろうし、県はこれまで以上に収納率を向上しうるか。もう1 点は、 県民の疾病予防と健康保持の推進である。特定健診・保健指導受診率の向上も含め、誰が推進して 行くのか、知事か市町村長か。
沖縄県にとって、1 番の課題は肥満・メタボ・糖尿病対策であろう。そして、それらの疾患によ って生じる脳卒中・急性心筋梗塞・慢性腎疾患(人工透析)であろう。肥満・メタボ・糖尿病対策 は市町村を中心に、現状に即した地域住民レベルで進めて行ってもらいたいと強く思うし、その方 が効果的であると考える。2 番目の課題は離島へき地医療であろう。今回はその一環として、産婦 人科医確保・支援及び育成について、財政補助を得て具体的に実践して行くにはどのようにしたら 良いかを提案し、具現化に向けて進んで行くことを確認しあった。