九州医師会連合会平成22年度 第2回各種協議会
3.地域医療対策協議会
副会長 玉城 信光
常任理事 安里 哲好

協 議
(1)子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨 時特例交付金について(佐賀・宮崎・大 分・熊本県)
<提案要旨>
平成22 年度より、「子宮頸がん等ワクチン接 種緊急促進臨時特例交付金」(以下、「特例交付 金」という)により子宮頸がん予防(HPV) ワクチン、ヒブ(インフルエンザ菌b 型)ワク チン、小児用肺炎球菌ワクチンの接種事業が実 施されるが、下記事項について、各県の現状や 問題点についてご教示いただきたい。
1)接種料金の設定について
2)広域化(市町村問の相互乗り入れ)について
3)接種開始期日
4)接種スケジュールへの対応
(Hib、小児用肺炎球菌ワクチンについては、 3 種混合ワクチンなど定期予防接種との関連 もあり接種スケジュールはどのように対応さ れるか)
5)その他(ご意見・問題点等があればご教示ください)
上記提案に対し、はじめに日本医師会の藤 川常任理事より以下のとおりコメントが述べら れた。
【日本医師会藤川常任理事よりコメント】
本件については、平成22 年12 月13 日付の 文書でもって、都道府県医師会、郡市区医師会 に情報提供を行った。内容は概ね以下のとおり である。
・接種費用については、基準額を下回らないよ う実施市町村と交渉することを希望する。
・ワクチンの納入価格については、来年4 月1 日迄に実施する市町村については、業者と充 分な調整を行うよう希望する。
・公費カバー率が9 割となっているが、残り1 割については、市町村財源或いは、一部負担 金徴収、又は所得制限を設ける等、当該市町 村に委ねられている。
・健康被害に対する補償については、今回の実 施主体は市町村であるので、例えば、市町村 が所得制限を設定し、全額自費で接種を受け た場合においても、健康被害の対象となる。
・副反応については、所定の書式を用いて直接 厚生労働省に申請していただく予定になって いる。
上記、コメントを受け、以下のとおり意見交 換が行われた。
<主な意見・質疑等>
○大分県:ワクチンの納入価格が12,000 円とな っており、接種料金の設定が安すぎる。本県で は卸を通してメーカーと交渉したが聞き入れて 貰えなかった。次回は改善していただきたい。
■藤川日医常任理事:4 月以降の価格につい て、厚労省は4 ヶ月毎に実勢納入価格を調査 して設定するということである。
○福岡県:当該ワクチン接種に際しては、医療 機関も充分な説明を受け留意事項を理解する 必要があるとしていることから、本県では、 メーカー側から実施医療機関に対し説明をし てもらうようにしている。
■藤川日医常任理事:日本医師会において、来 る2 月27 日に予防接種講習会を開催し、そ の中で説明するので多くの会員にご参加いた だきたい。
○宮崎県:接種対象者は中1 から高1 となってお り、高1 生はあと2 ヶ月しか期間が無い。宮崎 で既に当ワクチン接種が開始されているのは4 市町で、高1 生は対象から外れる人達が出てく る可能性があるが、他県の状況を伺いたい。
■藤川日医常任理事:全国の市町村で3 月まで に実施するのが2/3、4 月以降の実施が1/3 となっている。
○大分県:本県の某市町村では3 月中に接種す るとい意思表示をすれば、4 月以降であって も補助すると言っている。
○長崎県:長崎市の場合は、本会が交渉し4 回 目の接種が4 月以降であれば、4 回目の接種 料金は全額市が負担することになった。
(2)「地域におけるうつ病に関する支援体制 の強化」事業について(鹿児島県)
<提案要旨>
厚生労働省の平成22 年度補正予算により、 「地域におけるうつ病に関する支援体制の強化」 事業(平成22 〜 23 年度事業)として、九州各 県へ1,000 万円前後の交付金が配分されること になっている。
事業の柱は、1)精神科医と一般かかりつけ医 の連携強化、2)精神医療関係者への研修の2 つ。鹿児島県は、医師会や精神科病院協会への 委託を考えているとのことであった。
1)については、国は、静岡県富士市で取組ま れている、一般かかりつけ医(産業医)と精神 科医の連携強化・専門医への紹介促進などの 「富士モデル事業」を全国に広げたいとの考え のようである。
2)については、精神科医療関係者の資質向上 を目的に研修会を実施して欲しいとのこと。
本県では、事業の実施方法等を検討していると ころであるが、各県の検討状況をお伺いしたい。
当議題については、時間の都合で協議は出来 なかったが、紙面回答における各県の状況は以 下のとおり。
平成23 年度より、医師会が関与して当該事 業の実施を予定しているのは、佐賀、宮崎、長 崎の3 県、熊本は交付金の配分は確認されてい るので医師会に対し相談があれば検討する。沖 縄、大分については、今後行政側からの説明を 受けて進めて行く。
(3)慢性腎臓病(CKD)予防対策事業につ いて(福岡県)
<提案要旨>
福岡県においては、年々増え続ける慢性腎臓 病の予防対策として、腎疾患の発症・重症化予 防、人工透析への移行の減少・遅延を目的とし て、普及啓発及び地域かかりつけ医等との連携 体制の構築を図るため、平成21 年度より腎疾 患予防対策検討委員会を設置し、専門研修会(平成21 年度2 回)や腎疾患予防対策モデル事 業(モデル地区 中間市)等を実施した。
本年も県内2 ブロックで専門研修会を開催 し、さらに北九州市では地域連携クリティカル パスの作成、専門医療機関の登録等の準備を進 めているが、県全体での実施に向けて県内統一 基準を作るべく腎疾患予防対策検討委員会で協 議予定である。
そこで、九州各県の慢性腎臓病(CKD)予 防対策の現状と今後の予定をお尋ねしたい。
上記提案に対し、はじめに日本医師会の藤 川常任理事より以下のとおりコメントが述べら れた。
【日本医師会藤川常任理事よりコメント】
日本医師会の取組としては、関係団体との連 携という事で日本腎臓学会、日本透析学会、日 本小児腎臓病学会の3 学会が中心となって2006 年に設立された日本慢性腎臓病対策協議会に参 画しCKD 対策に取り組んでいる。また、日本 腎臓学会が日本糖尿病対策推進会議の構成団体 として加入しており相互に連携をしている。
日本糖尿病対策推進会議では糖尿病による腎 障害が増大している事から、糖尿病腎症をテー マとした啓発ポスターの作成や尿中アルブミン 実態調査等を行っている。市民向け啓発事業に おいては、平成21 年2 月8 日に日本医師会の 市民公開フォーラム「知って防ごうCKD(慢 性腎臓病)」が開催され、NHK の教育テレビ等 で放送された。その後DVD を作成し都道府県 医師会、郡市区医師会に送付した。
医師向け啓発事業としては、CKD 患者診療 のエッセンス作成、かかりつけ医と専門医との 連携推進等を目的に日本腎臓財団から発行さ れ、日本医師会および日本腎臓学会が監修して いる。日医の全会員に対し昨年の日医雑誌4 月 号に同封している。生涯教育としては日医雑誌 特別号として136 号に腎・泌尿器疾患診療マニ ュアル(小児から成人病まで)を発行してい る。さらに、日医雑誌第138 号第8 号にCKD の概念と対策を作成した。
厚労省では、2008 年4 月から2012 年3 月ま で腎疾患重症化予防のための戦略研究を実施し ており、全国15 の幹事施設、56 の郡市区医師 会により実施されている。
今後、地域におけるかかりつけ医と腎臓病専 門医の連携体制を図るため、日本医師会も積極 的に協力していくこととしている。
その他、日本慢性腎臓病対策協議会主催によ る世界腎臓病講演会等、CKD 啓発イベントが 毎年3 月に実施されている。
上記、コメントを受け、以下のとおり意見交 換が行われた。
<主な意見・質疑等>
○福岡県:この事業は主に平成20 年から始ま った特定健診と非常に密接な関連があると思 う。その中で残念ながら国の基準としてクレ アチニン、尿潜血が必須になっていないの で、日医から必須項目となるようプッシュし て頂きたい。
(4)地域産業保健センターについて(大分県)
<提案要旨>
地域産業保健センター(以下地産保センタ ー)については実施主体が郡市医師会から県単 位に変わり、現場は混乱に見舞われている。当 県においては準備期間の短さ等から県医師会と して受託を見送った経緯がある。平成21 年度 末に事業実施医師会のヒアリングを行ったが事 業の効果自体を疑問視する声が多かった。
当県では本年度は県の産業保健推進センター が事業を行っているが、来年度以降県医師会と して事業受託するかどうかは未定である。現在 県医師会として地産保センターを受託している 県に事業の現状について是非情報を頂きたい。
昨今の厳しい経済状況下においては地産保セ ンターが対象とする雇用50 人未満の事業所に おける産業保健活動の重要性はさらに増すもの と思われる。地産保センターの現状について以 下のような問題点につき日医のお考え、見通し など併せて伺いたい。
1)事業自体が予算執行上の縛りが多く現場に即 した柔軟な活動が行いづらいのではないか
2)現在の業務内容は定期健康診断関連が多いと 聞いているが、今後国が重点を置くメンタル ヘルスや過重労働対策について対応できる 人、予算が担保されるか
3)労働基準監督署、地域行政などとの連携の現 状について
4)全国の地産保センターの実績、活動内容など
5)現在受託している県で産業保健推進センタ ー、メンタルヘルス対策支援センターとの連 携などは効率的に行われているか
上記提案に対し、はじめに日本医師会の藤川 常任理事より以下のとりコメントが述べられた。
【日本医師会藤川常任理事よりコメント】
1)現在は厳しい縛りがあるが、次年度からは、 都道府県医師会が受託した場合に、医師の傷 害保険料の管理的経費や派遣社員等の臨時雇 用にも支出ができるようになっており、相当 程度柔軟な運用が出来るものと理解している。
2)平成23 年度は、事業仕分けの指摘に基づい て暫定的な対応となっているが、24 年度以降 は、医師がメンタルヘルス不調者への介入等 新たな枠組みが行われることになっており、 地域産業保健センターのニーズはますます増 加することが見込まれており、日医としても 必要な予算を獲得すべく厚労省に要請する。
また、従来のメンタルヘルス不調者への対 応は、産業医の有資格者となっていたが、23 年度からは、メンタルヘルスに対応可能な医 師を活用することになっている。
3)円滑に事業を実施するためには、労働基準監 督署や地域行政との連携は重要な事であると 理解しているが、都道府県によって状況は異 なっているものと思われる。
4)当該センターの22 年度の活動実績状況につ いては、現在、厚労省の労働衛生課で中間報 告を集計中であると聞いており、日医として は把握していない。
5)産業保健支援センターとメンタルヘルス対策 支援センターの支援により、地域産業保健セ ンターの円滑なる事業運営と充実が図られて いるものと理解しているが、都道府県医師会 によって状況が異なるものと認識している。
以上の日医藤川常任理事のコメントを踏ま え、以下のとおり意見があった。
○大分県:現在の産業保健のあり方自体を問い 質す必要がある。国はメンタルヘルス対策、過 重労働者対策を打ち出しているが、安全衛生 法の産業医の職務規程で月1 回の職場巡視が 謳われているが、現実の問題として、年3 回で いいから対象事業所を4 倍に増やしたほうが良 い。全ての労働者に産業保健を提供するとい う理念に考え直す必要があるのではないか。
○佐賀県:本県では、郡市区医師会が委託をう けている4 つの地域産業保健センターがある が、1 カ所のセンターに運営に関する指摘が あり、他のセンターもやる気が削がれている のが現状である。
○熊本県:地域産業保健センター事業で全ての 小規模事業所の産業保健をカバーできるわけ ではなく、あくまでも当該事業はサンプル的 事業だと思う。要は当該事業を国民に理解し て頂くことが大事であり、50 人以下の小規 模事業所の産業保健は我々医師会が担うべき だと認識に立って、地域産業保健センターは 医師会が受託すべきである。
(5)医療ツーリズムについて(沖縄県)
<提案要旨>
平成22 年8 月11 日、沖縄県福祉保健部との 連絡会議の中で、県は新たな沖縄振興に向けた 制度提言として「医療特区制度の導入につい て」の提案を考えており、県医師会の意見を要 望された。医療特区申請には、現行医療制度と の関係、そして多くの医療関係者の協力・同意 等、莫大なるエネルギーを要する。また、混合 診療、先進医療、新薬・医療機器の早期導入の 問題、外国人医師の公的保険診療、医療ツーリ ズム、現在の地域医療の保持・継続等、多くの問題がある。一方、誰が旗を高く掲げ進んで行 くのか、どこが実働部隊になるのか、どこが支 援部隊になるのか等もあり、時期尚早であると の意見を述べた。
一方、琉球大学や複数の医療機関等が参加し 「沖縄ウェルネス産業研究会」を立ち上げ、県 行政に答申している。更に、県は沖縄を「世界 に開かれた交流と共生の島」と位置づけ、加え て平成23 年度に外国人観光客30 万人を目標と している。その一環として、観光商工部が「医 療ツーリズム」を促進事業と考えており、「医 療ツーリズム戦略検討委員会」への委員として の要請が県医師会にあり、派遣することになっ た。その際の県医師会の立場として、1)外国人 観光客増に対しては発病・急変時の対応(通 訳、医療費、患者受け入れ態勢)を整え支援す る。2)外国人の医療従事者の研修・教育を支援 する。3)外国人の人間ドック(自由診療とし て)は容認する事を確認し、委員会に参加する ことになった。
「医療ツーリズム」に対して、日本医師会は反 対の姿勢を明確にしているが、各県医師会の現状 とそれに対する考え方をご教示いただきたい。
上記提案に対し、はじめに日本医師会の藤川 常任理事より以下のとりコメントが述べられた。
【日本医師会藤川常任理事よりコメント】
日本医師会では2010年4月14 日の記者会見で 医療ツーリズムについて、深刻な医師不足、看護 職員不足からくる医療崩壊を食い止め、地域医 療を確保することが最優先の課題であるとし、諸 外国の医療ツーリズムの現状を踏まえて慎重に検 討すべきであり、現時点で検討に着手することは 認められないとの早々の見解を示している。
その後、6 月9 日の会見では、「混合診療の全 面解禁と医療ツーリズム」と題して、医療ツー リズムが混合診療の全面解禁への後押しとなり、 国民皆保険の崩壊に繋がるとして、医療ツーリ ズムに対する反対の姿勢を明確に示している。
一方で、6 月18 日に閣議決定された新成長 戦略では国際医療交流の一環として2012 年か ら外国人患者を本格的に受け入れることが示さ れ、これを受けて厚労省は来年度予算の概算要 求に外国人患者の受け入れに資する医療機関の 認証制度の整備をあげ、各都道府県では独自の 取り組みを検討するなど、医療ツーリズムに向 けての動きがある。
日医は、各地域における医療ツーリズムへの 間違った認識からくる期待、地域医療の崩壊が 現実となっている状況において医療ツーリズム についての具体的検討が始まっていることに対 し危惧しているところである。
今般、各地域における医療ツーリズムに関す る動きを都道府県医師会を通じて改めて把握し た。その内容は平成23 年1 月26 日の定例記者 会見において公表した。調査は47 都道府県医 師会を対象に各都道府県における医療ツーリズ ムに対する動向、検討、実施主体、進捗状況、 各都道府県医師会との関係、目標および実現可 能性を尋ねた。第二に医療ツーリズムに対する 各都道府県医師会のコメントを記載いただい た。調査期間は11 月〜 12 月である。
調査回答として、医療ツーリズムに関する動 向は、具体的な動きがあるのは22 件、漠然と した動きがあるのは8 件、不明またはなしが17 件であった。医療ツーリズムに対して明確に反 対を示しているのは28 件、どちらかというと 反対が6 件、中立が7 件、コメントなしが6 件 となっている。
今回の結果では日本医師会の見解に賛同して 医療ツーリズムに対して反対の県が多くみら れ、日医が率先して国に進言して欲しいという 強い意見もあった。
医療ツーリズムに対する主な反対の理由は、 1)混合診療の全面解禁に繋がる、2)国民皆保険 制度の崩壊を招く、3)地域医療の崩壊を招く、 4)医療機関格差の助長、5)地域間格差の助長、 6)所得格差の助長、7)医療の営利産業化・市場 原理の導入に繋がるというものである。具体的 な例をあげると、先端医療の特区構想がある兵 庫県では、医療ツーリズムの事業展開は地域医 療体制整備の障壁となるばかりか、医療本体への営利企業の参入を契機として混合診療の拡大 に繋がり、国民医療の平等性、非営利性を著し く損なう「亡国のシナリオ」であるとの回答が 寄せられた。
日医としては今回の調査結果を受け、医療ツ ーリズムの動向が全国的な広がりを見せている 事は改めて認識し、その流れを食い止める当該 資料を政府へ提言するなどロビー活動に活用す るほか、都道府県医師会においても地元選出の 国会議員との議論に資する資料として提供し、 国民医療を守る姿勢を強めていく所存である。
<主な意見・質疑等>
■藤川日医常任理事:地域医療計画を蔑ろにし て特区が動いた場合、医療スタッフは地域か ら募集をかけることになるので、医師や看護 師らが自由意志による引き抜きが行われるこ とを阻止できるのか。特区を一度許すと自由 市場に放り出される危険性がある。
■葉梨日医常任理事:10年以上前から医療ツ ーリズムは行われており、100 万人の規模で あろうと言われている。特にハンガリーで多 かったが、アジアではインドやタイ、シンガ ポール等の2,000 床ぐらいの病院で旅行のツ アーを組んだり、周辺ホテルをもったり、観 光客を誘致して行われている。1 兆円市場と 言われているが、近々6 兆円ぐらいまでにあ がるだろうと言われている。日本でどういう ものが外国から繰り入れられるのか考える と、高度医療機器が世界一で内視鏡検査が優 れていることはあるが、それほど日本に多く 呼び寄せられるとは思わない。高度の医療を 受けるところか、安く受けられるということ でインドが該当するが、イスラム教などの宗 教と結びついており、移動しながら医療を受 けている形態もある。それほど思惑通りに儲 かる産業として出来るかは疑問である。シン ガポールでは医師の引き抜きに5 倍の給与を 提示している等、医師の偏在が生まれること が考えられるので、地域医療がなるべく崩壊 しない様にしなければならない。
(6)地域医療再生基金(拡充)について (福岡県)
<提案要旨>
平成22 年度補正予算により、地域医療再生 基金(拡充)に2,100 億円が計上された。これ については、全県下で取り組むようになってい るが、九州各県の実情についてお伺いしたい。
上記提案に対し、はじめに日本医師会の葉梨 常任理事より以下のとりコメントが述べられた。
【日本医師会葉梨常任理事よりコメント】
地域医療再生基金は一昨年の自民党政権に引 き続き、民主党政権が2,100 億円の補正予算を 計上した。前回と違うのは三次医療圏までの広 域を対象としている。基金が医療崩壊に対して 出ているが医師会ではなく都道府県単位に下り ており、希望するものが通らない現状にある。 また、受付の期日が非常に短期間である。期日 については先日2 ヶ月程度の延長が発表された が、日医としては政府や厚労省に働きかけて、 医師会等関係団体の意見を聴くと言う文言を入 れることが出来た。
今回の対象事業は公立病院の建て直しによる 施設整備等のハード面だけではなく、ソフト面 (地域医療や医療連携等)に使えるよう各医師会 にも働きかけていただきたい。ある雑誌の座談 会の中で厚労省保険局の幹部職員が医師や医療 機関を指導して、ある方向に持っていくことは 診療報酬が有効である。しかし、地域医療計画 について方向性を持っていくには地域医療再生 基金が一つの大きな武器になると発言している。 官僚が地域の医療計画を思うとおりに引っかき 回すことがないようにするには、現場の医療機 関から声をあげて使っていくことが重要である。
<主な意見・質疑等>
○鹿児島県:1)15億円は各県に配布され事業 者負担はないのか。2)加算額105億円につい ては事業負担があることが望ましいとされて いるのか。
■葉梨日医常任理事:日医からは負担が発生するのでなくフリーに使えるよう発言して きた。
○長崎県:ハード面は事業者負担があり、ソフ ト面の場合は負担なしと聞いているが今回の 通知で変更があったのか。
■葉梨日医常任理事:望ましいという事で、必 ずしも地元で半分出さなくても良いという書 き方がされているが実際どこまで適用される か分からない。
■藤川日医常任理事: 15 億円の部分は負担が なく自由に使ってよいと思う。加算額につい ては緩やかな表現となっており、来週以降、 県から通知があると思われるのでご確認いた だきたい。
○福岡県:病床数10 %削減については文言が 消されたのか。
○鹿児島県:残っている。全額ではないが26 年度以降も継続できる事業で無いとだめ。
○沖縄県:前回の会議でも話したが、一番大切 な事は追加で補助金が出るよりも、現在始ま っている事業があるので、それを後押しする 26 年度以降の予算を付けて欲しい。沖縄で は全島統一のクリニカルシミュレーションセ ンター建設に向け、設計、機械導入と進めて いくと、結局、運用は1 年しかなくなる。
その後、2 年程度継続できると事業として かなりの効果が出ると考えている。
■葉梨日医常任理事:日本医師会でも努力する。
<各県の事業案の検討状況>
○佐賀県:中部医療圏を中心に1)がん医療の充 実、2)医師会を含めた医療関連の総合施設、3)看護学校の支援金。
○宮崎県:1)腎バンクのハード整備、2)医師会 看護学校指導教官の育成資金、3)大学のドク ターヘリ運用のためのコーディネーターの育成、4)加算額に申請し、都城市医師会病院の 新築移転にしたい。
○沖縄県:1)現行のIT地域医療連携の拡充、2)産婦人科医師の養成、3)がん医療の充実。
○大分県:遠隔画像診断システムの構築(前回外れた部分)。
○長崎県:1)あじさいネットの充実、2)県内全域であじさいネットのハード機器整備、3)が ん検診、4)医師偏在→総合医の派遣、5)救急医療(IT を活用した離島に対して)。
○熊本県:1)IT 医療連携と教育、2)大学を中 心としたIT 化した連携を推進→テレパソロ ジーを各中核病院にて整備、3)大学にメディ カルクラーク養成等の医療人育成センター。
○福岡県:1)感染症・結核病床の整備、2)女性医師問題を含めた医療人材の育成。
○鹿児島県:1)医師会病院と公立病院の合併、 2)各医師会病院の統合化等が議題にあがっている。
(7)各県の医師確保対策について(長崎県)
※(7)(8)一括協議
<提案要旨>
長崎県では、平成20 年より小児科、産科の 医師確保対策として、長崎県小児科・産科医師 確保緊急対策資金を創設している。これは、県 内に勤務を希望する初期、後期臨床研修医師に 研修資金を貸与する制度で、今年までの2 年間 に小児科14 名、産科12 名がこの対象となって いる。
長崎県としては、予定の20 名を超え、充足 したものとの判断で今年度で打ち切る計画のよ うである。しかし、NICU のベッド不足・医師 不足により県外への母体搬送例が現在も多くあ り、周産期医療の充実にはほど遠いものがあ る。その理由として小児科医は増えたが、 NICU の専門医が不足している現状がある。
私たちとしては、県内の医療事情を考える と、現在、最も危機的状況にある救急医療と NICU に絞ったこの研修資金の制度の存続を希 望しているが、他県ではこのような制度の現況 は如何か。
(8)「専門医としての総合医」の確立について(宮崎県)
<提案要旨>
今、まさに、日本の医療は崩壊の危機にあ る。国の社会保障政策、診療報酬のあり方、病 院勤務医師の不足、診療科の偏在、地域の偏 在、救急医療の苛酷な現状、医療訴訟の増加 等々、種々の原因が考えられる。
特に病院勤務医師不足の解消、診療科ならび に地域の偏在の解消、救急医療の現場の苛酷な 現状の解消は喫緊の課題と考える。
国・県も可能な対策を講じ始めたが、どれも 中・長期的な対策であり、速効性には厳しい。
そこで、速効性が期待できる対策の一つとし て、「専門医としての総合医」の確立も上がっ てくるものと思われる。
平成22 年4 月に、日本プライマリ・ケア学 会、日本総合診療医学会、日本家庭医療学会が 合併して、日本プライマリ・ケア連合学会が誕 生した。そして、「専門医としての総合医」の認 定にむけて大きく動き出した。これからの医療 の流れを変えうる大きな変革だと考える。医師 会としてこの流れにどう携わっていくべきか、 各県医師会のご意見と、日医の考えを伺いたい。
上記提案に対し、はじめに日本医師会の葉梨常 任理事より以下のとおりコメントが述べられた。
【日本医師会葉梨常任理事よりコメント】
日本医師会では医師数の不足や偏在をどうす るか考えた際、国で言っている程医師数は不足 していないということで、医科大学を創ること に対しては反対している。
日医では医師の養成について一つの案を発表 した。それは、医学部教育と初期臨床研修制度 の見直しで、地域の大学を中心に8 年かけて医 師を養成するという理念の下で作成したもので ある。1 〜 4 年生まで一般教養を見直し必要な教 育を学ぶ。また、1 年生から臨床医学の実習を積 極的に取り入れる。4 年生の時に医学的知識を 問うCVT 試験や客観的臨床能力試験(OSCE)、 臨床実習資格試験を実施し臨床実習の免許を交 付(法的整備を踏まえ)することを想定してい る。5 〜 6 年生では、見学ではなく医行為に参加 できるような臨床実習を行う事も考えている。
医師免許獲得後の2 年間は、プライマリケア 能力を獲得することを目標に一般臨床医として 育成する。1 年目は、内科、救急、地域医療、 精神科を中心に、2 年目には将来専門とする診 療科のプライマリケアを中心に行う。
そのような中で、なるべく都道府県毎に出身 大学の地域で臨床研修を行うという方式を検討 している。そうする事である程度地域に医師が 定着するのではないかと考えている。
どうしても都市部に医師が集中すると大学の 医局制度が機能しなくなったので、派遣機能も 上手くいっていない状況である。一定の医師の 修練するプログラムを全国的に作成していけれ ばと考えている。
小児科・産科の医師確保策については具体的な回答は直ぐに出せない。
<主な意見・質疑等> ※(7)
○長崎県:1)沖縄で脳神経外科の対策があげら れているが成果としてあがってきたのか。2)鹿児島で医師不足対策基金として7,600 万円 を集めているが毎年集めているのか。
○沖縄県:脳外に関しては対策不十分で増えて いないのが現状である。ただ、公募した時点で 離島に配置された背景がある。
○鹿児島県:平成21 年度に医師自身が寄附を 集めたのが7,600 万円で3 年間を予定してい た。その後は県が事業を担うという事で調整 を進めている。今年度は1,000 万円程度だと 思われる。
<主な意見・質疑等> ※(8)
○診療科格差を解決するには何らかの適正配置 が必要。そういう意味での8 年間のうちの2 年間は適正に動くのではないかと考える。そ のような中でプライマリ医(総合医)に繋が るのではないか。若い医師の間で、家庭医療 学会の入会が急速に増えている状況で、家庭医や総合医に魅力を感じている。
このような医師が超専門医と同じレベルで 総合としての位置付けをもっと明確にする事 が結果として、キャリアパスの中にへき地や離 島、救急といったところに組み込まれることに なる。よってゆるやかな強制配置ではなく適正 配置が自動的に起こる可能性はある。佐賀県 の回答にもあるようにフリーアクセスの制限、 人頭割、定額払い、総枠規制に結び付くこと がないよう、総合医の趣旨を認識し日医主導 で創っていくことが望ましい(宮崎県)。
(9)医師会看護学校の今後の方向性について(長崎県)
<提案要旨>
長崎県内には医師会看護学校が6 校あったが 4 年前に北松浦医師会看護学校(准看護科)が 廃校となり現在5 校となっている。廃校となっ た地域では現在看護師不足が深刻となっている。
他の現存する看護学校に於いては教員不足、 実習施設不足、学生数の確保に苦慮しており経 営の危機に瀕している。そんな中、島原市医師 会看護校は平成22 年度で看護高等課程(准看) および専門課程(正看・定時制)を廃止し、平 成23 年4 月に全日制3 年課程看護科(レギュ ラーコース)を開校することになった。長崎市 医師会看護学校に於いても高等課程、専門課程 の定員を減らし、レギュラーコースの定員を増 やす計画のようである。
一方、佐世保市医師会看護学校では専門課程 (正看・定時制)を廃止し高等課程のみを存続 させることを計画している。同じような理由で 経営難にありながらも、進む方向が逆であると いう郡市医師会なりの苦労・苦慮が伺える。
厚生労働省、看護協会は看護大学の6 年制を 含め高学歴化を望み、その通りに進んでいる。 看護師志望の高校生にも高学歴志向があり、こ れからの少子化の中で医師会看護学校は学生の 確保、教員の確保、実習施設の確保などその運 営に際し苦境に立たされるのは必至である。日 本医師会は准看制度堅持を打ち出しているが、厚労省の考えとの間に乖離がみられる。
医師・看護師の養成は本来国・県がなすべき ことであり、診療所が急増した昭和30 年代以降 医師会看護学校が続々と設立されたが、無床診 療所の急増、医療環境の変化などによりその使 命も変化し終わろうとさえしているようだ。経 営のために地域定着率が悪い看護師を養成する のか、会員のために赤字であっても准看、専門 課程の養成を続けるのか、考えどころである。 日医の見解および各県のお考えをお聞きしたい。
上記提案に対し、はじめに日本医師会の藤川 常任理事より以下のとりコメントが述べられた。
【日本医師会藤川常任理事よりコメント】
長崎県医師会から准看護学校運営が厳しいと の指摘があるが、厚生労働省も全日制の正看学 校移行を誘導している。
日医で毎年行っている実態調査では、准看護 学校の志願倍率は2.8 倍に増え、そのうちの2 割は大卒である。日医は厚生労働省との間で准 看制度を継続していくことを確認している。し かし、厚生労働省は補助金を減らしていけば医 師会が准看護師養成から手を引くのではと目論 んでいるようであるが、我々はその手に乗るつ もりはない。
現在、日医と4 病院協会が話し合っているとこ ろであるが、准看護師が政治的に発言できる場 所を設置し、准看護師雇用確保、雇用条件の改 善を図るよう我々がサポートしていこうというこ とである。ただ、その方々には時間的にも経済的 にもゆとりがないということで、日本精神病院協 会にリーダーシップを取って貰い、又、准看護学 校を持っている郡市区医師会の協力を得て組織 作りをして、准看護師を地域医療のマンパワー として確保していきたいと思っている。さらに将 来的には、日医が様々な政策提言をするとき、 選挙の時にも協力が得られるようにしたい。
以上の日医藤川常任理事のコメントを踏ま え、以下のとおり意見があった。
○長崎県:准看の卒業生の多くは進学課程に進んで正看になっている。医師会立の看護学校 の定員の中で准看の定員は約3 割である。開 業医は准看を安い賃金で雇用しているような イメージがあるが、医師会は多くの正看を養 成し、地域に送り出していると言うことをも っとアピールすべきではないか。
■藤川日医常任理事:高校の衛生看護科の殆ど が短大とリンクさせ5 年課程となっている。 このことにより、医師会立看護学校の定時制 に志願する学生が減り、看護学校の存続にも 支障が出てきている。准看の志願者は増えて いるが、定時制に定員割れが生じている。
○長崎県:レギュラーコースの設置申請をし たら、厚労省は准看コースの定員減を求め てくる。
■藤川日医常任理事:これは厚労省の確信犯で ある。現在、特定看護師の問題で喧々諤々や っているが、それに負けると准看護師廃止に 一気に動き出すことになる。また、看護協会 は5 対1 看護を創り、特定看護師制度を法制 化しようとしている。このことについては、 4 病院協会と共に阻止しようとしている。
○沖縄県:那覇市医師会は、進学コースを廃止 してレギュラーコースを設置し、准看とレギ ュラーコースで上手くいっている。准看の受 験者も多く3 倍強となっている。准看の学生 は社会人入学が多く、又、医療機関への定着 率も良いので、その道も残した方が良い思う。
○福岡県:准看は定着率がいいので、地域での 存在感が大きい。医師会は准看の教育にもっ と力を入れるべきではないか。又、特定看護 師の問題についてどう対応するのか。
■藤川日医常任理事:日医は基本的に、特定看 護師制度に反対である。リスク・危険を伴う ことを医師自らがしないで看護師にさせるの は反対である。
現在、心臓血管外科の先生方とも話し合い をしているが、看護協会とは同床異夢の様相 である。看護協会はNP を欲しがっているが、 心臓外科の先生方はNP はどうでもよく、ア シスタント(PA)が欲しいだけである。
○福岡県:そのことを日医はメッセージとして 発するべきではないか。
■藤川日医常任理事:機会を見つけて記者会見 でもしたい。
(10)ドクターヘリの整備について(佐賀県)
<提案要旨>
ドクターヘリについては、九州では、福岡 県、長崎県、沖縄県で配備されている。
佐賀県では久留米大学病院のドクターヘリを 福岡県と、NHO 長崎医療センターのドクター ヘリを長崎県と共同運航しているが、ドクター ヘリを単独配備するよう知事に要望していると ころである。
未配備の県については、ドクターヘリ導入の 見通しについて、どのようにお考えかお伺いし たい。
上記提案に対し、はじめに日本医師会の藤川 常任理事より以下のとりコメントが述べられた。
【日本医師会藤川常任理事よりコメント】
日本医師会では以前から国に対する予算要望 活動の一環としてドクターヘリの全国展開や複 数整備の導入支援を求めてきた。直近の要望書 (H22.7)ではドクターヘリの補助金の増強と実 施地域の拡大、ヘリポートの整備、高速道路の 夜間照明等含む夜間搬送モデル事業の推進や委 託先航空会社の負担軽減を要望している。救命 救急センターへのアクセスの時間は地域によっ て大きな差があり、ドクターヘリの整備促進に より地域格差の是正を図りたいと考えている。 もちろん、ドクターヘリを支える救命救急セン ターと連携する地域医療を再生する事も重要で ある。日医では初期・二次救急医療体制、 #8000 等の電話相談事業、救急医療を終えた患 者を受け入れる後方医療体制の充実も併せて主 張している。平成23 年1 月24 日現在で19 道府 県23 機が運用している。その他、沖縄県の北 部地区医師会病院で実施されている。平成22 年度の基準額は2.1 億円(前年度1.7 億円)で、 国1/2 県1/2 の負担となっている。今年度予算総額は27.3 億円(前年度約20 億円)。予算箇 所は28 か所(前年度24 か所)。更に、県の負 担分に関しては県の財政力に応じ最大50 %ま で特別交付金として出せるという事で、佐賀県 で計算すると9 割(厚労省5 割、総務省4 割) の補助金を得られるということの承諾を得てい る(田舎の地域)ので、可能な限り手をあげて いただき、救命救急率を高めていただきたい。
<主な意見・質疑等>
○佐賀県:様々な検証作業部会等で潜在的なド クターヘリの需要があると考えられている。
○福岡県:高速道路が着陸可能になったので、 今後、学校のグランド等、着陸地点を増やし ていただきたい。
○長崎県:現状、大きな問題点はない。
○沖縄県:県の補助を受けている病院でも持ち 出しがあるという厳しい現状を伺っている。 また、民間(北部地区医師会病院)では補助 金が全く付いていない。また、離島からの搬 送が多いので自衛隊のヘリと遠距離・近距離 をすみ分けて行っている。
(11)地域医療支援病院について(福岡県)
※書面回答のみ
<提案要旨>
平成10 年の第3 次医療法改正により、かかり つけ医支援のための地域医療支援病院制度が発 足したが、12 年経過した現在、福岡県では22 医療機関が地域医療支援病院に指定されてお り、されに申請してくる医療機関が予想される。 これについて九州各県の状況をお伺いしたい。
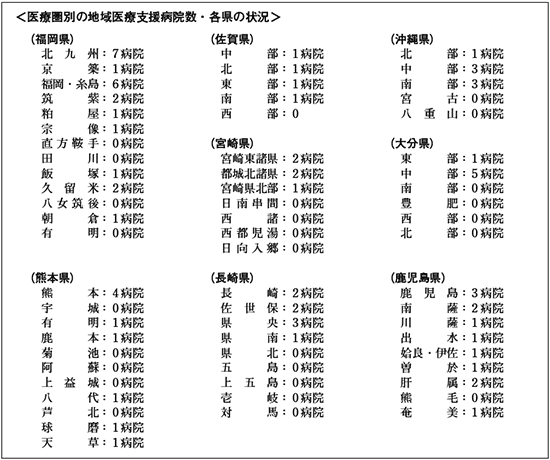
印象記

副会長 玉城 信光
地域医療対策協議会に出席した。地域医療は11 議題を2 時間で協議することになっているので 時間の制約があり個々の発言は少なく日医のまとめの話しを聞く時間が多くなった。
1、子宮頸がん等ワクチンに関して全国的には3 月までの開始が2/3 と多いので4 月になると接 種年令が対象にならない高校生の救済措置が必要だとの指摘があった。沖縄県は4 月以降になる のでその点は問題ないであろうが県医師会と沖縄県との協議の中でも5 月以降になりそうな市町 村があるので少なくとも4 月実施を呼びかけたところである。接種料金を4 月以降見直すことが あるとのことでワクチンの仕入れ価格が重要になる旨の話もあった。
4、地域産業保健センターに関して大分県医師会は委託を受けてないが、どのようにしたものか 質問があった。沖縄県は県医師会を中心に活発に事業を行なっている。小企業の健康管理に大切 な事業であり継続しながら発展させる事が重要であると考える。現在は運用に厳しい縛りがある と言われているが、次年度からは、都道府県医師会が受託した場合に、医師の傷害保険料の管理 的経費や派遣社員等の臨時雇用にも支出ができるようになっており、柔軟な運用が出来るものと 日医の回答がある。また平成23 年度以降はメンタルヘルスケアへの介入等新しい事業を推進する ために日医も予算獲得に努力すると報告があった。
7、医師確保対策として鹿児島で医師不足対策基金として7,600 万円を集めているとの話しがあ った。医師会の力強さを感じた。しかしながら年々基金の集まりが減少しているとの報告もある。 産婦人科医師確保対策の経費など考えさせられる内容であった。
9、医師会看護学校の運営の難しさが話し合われた。厚労省は全日制の正看学校移行を誘導し ている。しかし日医の実態調査では、准看護学校の志願倍率は2.8 倍に増え、そのうちの2 割が 大卒であると報告された。那覇市医師会の志願者も同様の傾向にある。准看護学科卒業者は医療 機関の定着率が高く、医師会としても廃止に反対の立場である。しかしながら那覇市医師会の准 看護学科も実習病院の確保がむずかしく運営を圧迫していると言われている。医師会の先生方の ご協力が必要になる。
また興味を引いたのは日医として准看護師が政治的に発言できる場所を設置し、准看護師雇用 確保、雇用条件の改善を図るようサポートする方法を考えているようである。
10、日本医師会では以前から国に対する予算要望活動の一環としてドクターヘリの全国展開や 複数整備の導入支援を求めてきた。九州各県でも積極的にドクターヘリの導入を進めてほしい旨 の発言があった。
いつもながら地域医療の抱える問題が多く、各県でもそれらの解決に努力している姿勢が見え た。翻って沖縄県ではどうであろうか。予算の少なさと実行力が問われるところであろう。県立 病院への繰り入れが減る時代になればあと2 億ほど地域医療と福祉に回せるのであろう。楽しい 夢を見たいものである。
鹿児島の夜は寒かったが楽しい懇親会とマジックをみせるスナックで来年の忘年会用のマジッ クを多く仕入れて来た。事務局職員のマジックショーが見られることであろう。
印象記

常任理事 安里 哲好
議題が11 あり、各県の提案に対して、日医の葉梨之紀常任理事、藤川謙二常任理事による日医 のコメントを得たのち、提案県からの追加質問があり、必要に応じて各県の意見を求められた。 議題2、11 は紙面上での回答となった。
興味ある3 点について記す。1 点目は当会から提案した「医療ツーリズム」についてである。沖 縄県医師会は1)外国人観光客増に対しては発病・急変時の対応を整え支援する。2)外国人の医療 従事者の研修・教育を支援する。3)外国人の人間ドック(自由診療として)は認めることを確認 し、「医療ツーリズム戦略検討委員会」へ参加することになった現状を説明し、理解を頂きたいと 思った。一方、日医の立場は強固な反対で(その内容は報告書を参照)、九州医師会連合会でも反 対声明を提案しようとの意見があり、沖縄県の現状を鑑みると困惑した。「医療ツーリズム」は医 療ビジネスとしてではなく、国際医療交流や国際医療貢献の域に止まる可能性が高い現況を示唆 している感がした。
2 点目は「地域医療再生基金(拡充)について」で、前回に加え、2,100 億円が計上され、各県 15 億円+α(90 億円)である。各県の検討事項では病院新築、統廃合を含め多種にわたる提案 があった(報告書を参照)。個人的には、現在の事業が平成26 年度以降も継続できるような財政 支援をと言う気持ちがあるが、各地区医師会の意見も取り入れ、県医師会の提案事項としたい。 無論、大学、公立病院や行政よりの提案もされるでしょう。事業計画書は3 月11 日までに県福祉 保健部への提出が定められているので、各関係各位においては早急の検討が望まれる。
3 点目は、「各県の医師確保対策について」が印象に残った。提案県(長崎県)の報告では、小 児科・産科医の医師確保対策として、長崎県小児科・産科医師確保緊急対策資金を創設している とのこと。それにより、県内で勤務を希望する初期・後期臨床研修医師に研修資金を貸与する制 度で、平成20 年度より2 年間で小児科14 名、産科12 名がこの対象になったと述べていた。今後 は救急医療とNICU に絞った研修資金の制度の存続を要望していると報告していた。北九州市で は、小児科・産婦人科医を地域医療ネットワーク(研修病院のネットワーク)の中で育成してい て、産婦人科は3 医療機関にて3 年間、小児科は4 医療機関にて4 年間研修するシステムを進めて いる。当県も参考にしたいものだが、各県行政間における、九州地区での意見交換をする場所は あるのだろうかと案じている。
鹿児島空港から高速バスで会場(城山観光ホテル)に行くと、進行方向右側に新燃岳の噴火が 見えるとのことだが、海側の国道を通るバスを利用したので、その機会はなかった。その代わり、 桜島と錦江湾はくっきりと見え、久しぶりにその雄姿をまじかに感じた。