CKD―MBDについて

豆の木クリニック 吉原 邦男
1.はじめに
腎臓は副甲状腺、骨、腸管とともに生体の Ca, P のバランスを保持する役割をしているの で、腎機能が低下してくると、さまざまな骨・ ミネラル代謝異常が出現する。CKD-MBD (Chronic kidney disease-mineral and bone disorder)とはCKD(慢性腎臓病)に起因す る骨ミネラル代謝異常を呈する全身性疾患で、 次の3 つの異常のうち1 つ以上を含むものと定 義される。(図1)
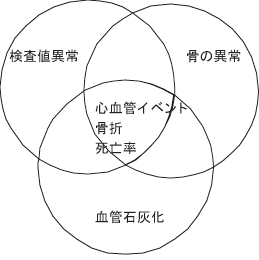
図1 CKD-MBD の概念
- (1)Ca, P, PTH(副甲状腺ホルモン)、ビタミンD などの異常・・・(検査値の異常)
- (2)骨強度など骨の異常・・・(骨病変)
- (3)血管または他の軟部組織の石灰化・・・(異所性石灰化)
CKD におけるミネラル代謝異常は骨病変だ けでなく、血管石灰化、心臓弁膜症などをきた し生命予後を悪くする。CKD では末期腎不全 になって透析に導入されるよりも、心筋梗塞な どの心血管疾患で死亡する方が何倍も多いこと がわかっているが、そのことにミネラル代謝異 常も関与していると考えられる。これまで透析 患者で腎性骨異栄養症(ROD)とよばれてき た骨病変はCKD-MBD の一部とみなされるよ うになった。
CKD-MBD はGFR 60ml/min 以下になると PTH が上昇するとされているので、この頃か ら始まると考えられる。
2.CKD-MBD を構成する3 つの要素について
1)Ca, P, PTH(副甲状腺ホルモン)、ビタミ ンD
血清Ca 値と血清P 値は相互に関連しコント ロールされている。血清Ca 濃度は副甲状腺ホ ルモン(PTH)と活性型ビタミンD により約 8.4 〜 10.0mg/dl の狭い範囲にコントロールさ れている。一方、腎機能が低下すると、尿中へ のP 排泄も低下し高P 血症をきたす。これが活 性型ビタミンD 産生を低下させる。ビタミンD が欠乏すると腸管でのCa、P 吸収が減少し、 血清Ca 値が低下する。低Ca 血症はPTH 産生 を亢進させ骨から血中へのCa の遊出を引き起 こす。その結果高PTH 血症となっていく。 (Trade off 仮説)
もう一方で、高P 血症は骨からFGF-23 (fibroblast growth factor-23)の分泌亢進を もたらし、これがP 利尿促進とビタミンD 活性 化抑制を引き起こす。これもPTH の産生亢進 (二次性副甲状腺機能亢進症)をもたらす。
2)骨病変
CKD ではPTH の過剰分泌により、破骨細胞 が活性化され、骨吸収が亢進し、それに引き続 いて骨形成も亢進するため繊維性骨炎になりや すい。
骨の強度は骨量と骨質で決まるが、繊維性骨 炎では骨量(特に皮質骨)の低下が起こるため 骨折を起こしやすくなる。一方、糖尿病性腎症 の透析患者では骨密度の低下は認められず、低 回転骨型の骨質の低下により骨折を起こしやす くなると考えられる。
3)異所性石灰化
異所性石灰化は血管、関節周囲、心臓などの 軟部組織にみられ、CKD の重要な合併症の一 つである。特に血管石灰化は心血管疾患が CKD 患者の最大の死因であることからもわか る通り、CKD 患者の予後を左右する重要な因 子である。血管石灰化には内膜プラークに起こ るアテローム硬化型石灰化と中膜平滑筋層にみ られるメンケベルグ型石灰化がある。メンケベ ルグ型石灰化は透析患者や糖尿病に特徴的で、 大動脈から細動脈までほとんどすべての血管に 認められる。その機序としては、P が血管平滑 筋細胞に作用すると骨芽細胞へ分化し石灰化が 起こるためとされている。
3.CKD-MBD の診断
CKD-MBD は3 つの異常のうち、いくつあ るかで分類するLBC 分類で評価する。L は臨 床検査値の異常(Laboratory abnormalities)、 B は骨代謝異常(Bone)、C は石灰化(Calcification)のことで、これらの有無でL、 LB、LC、LBC と分類される。(表1)
臨床検査値の異常はPTH, Ca, P, ALP, HCO3-などで診断する。血清Ca 値は補正Ca 値を用いる。(Payne の式)
補正Ca 値(mg/dl)= 血清Ca 値+(4-血清 Alb 値)
骨代謝異常は主に骨代謝マーカーと画像診断 で診断する。骨形成マーカーにはALP, 骨型ア ルカリホスファターゼ(BAP)などがあり、骨 吸収マーカーには骨型酒石酸抵抗性酸ホスファ ターゼ(TRAP5b)などがある。BAP は肝疾 患や血液疾患がない場合は血清ALP 値で代用 する。骨の評価には骨生検が正確だが、侵襲度 が高いので日常的には行われない。そこで、骨 生検の代わりに骨代謝マーカー( A L P や intact-PTH など)で骨の状態を推測すること が一般的となっている。
骨の画像診断としては、単純X-P では手指 骨の骨膜下骨吸収像、頭蓋骨側面のsalt and pepper 像などが繊維性骨炎の所見として有名 である。高齢者やPTH 低値の透析患者では、 腰椎や大腿骨骨頭の骨折をきたしやすいため、 それらの部位の骨塩量を測定し骨折リスクを評 価することは有用である。
血管石灰化の評価には胸部X 線による大動脈 弓部石灰化の評価や腹部単純X 線の腰椎側面 像での大動脈石灰化がスクリーニングに適して いる。より詳細に調べるには、腹部CT により 腹部大動脈の大動脈石灰化指数(ACI)を計算 したり、電子線CT により冠動脈石灰化指数 (CACS)を算出し虚血性心疾患の発症の危険 性を予測したりしている。
表1 CKD-MBD のLBC 分類
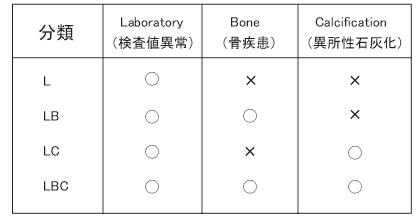
4.CKD-MBD の治療
CKD-MBD の治療の目的は、心血管イベン トのリスクを減少させ、CKD 患者の生命、機 能的予後を改善させることにある。つまり、高 P 血症、低Ca 血症の是正、PTH 過剰分泌の抑 制、そして適切なビタミンD 投与により骨回 転、石灰化を正常に維持し、血管、軟部組織への石灰化を回避することが目標 となる。そのためにはまず、血清 Ca 値と血清P 値のコントロール を計ることが重要である。その後 にPTH のコントロールを計る。
実際の治療においては、保存 期(CKD stage 3 〜 5)と透析 期(stage 5D)では使用する管 理目標や使用する薬剤が異なる。 保存期ではK/DOQI のガイドラ インを、透析期は日本透析医学 会(JSDT)による二次性副甲状 腺機能亢進症治療ガイドライン を参照する。(表2)
保存期ではP 吸着剤としての 炭酸Ca と経口活性型ビタミンD を使用する。透析期にはP 吸着 剤としてさらに塩酸セベラマーと 炭酸ランタンが加わる。ビタミン D はさらに静注剤が加わる。そし て、新たにシナカルセト塩酸塩が 加わる。これらによってJSDT ガイドラインの中央部の目標値 をめざす。(図2)今のガイドラインは炭酸ラン タンとシナカルセト塩酸塩が発売される前に策 定されたものなので改訂される予定である。
シナカルセト塩酸塩の登場によって副甲状腺 摘出術(PTX)の件数が激減している。
保存期で骨粗鬆症の治療のため活性型ビタミ ンD やCa 製剤を投与することがあるが、腎機 能の低下した高齢者に投与すると、時には高 Ca 血症をきたし、それによりさらに腎機能低下 をもたらすことがあるので注意が必要である。
表2 CKD-MBD の管理目標
(CKD 診療ガイド、日本腎臓学会編より引用、改変)
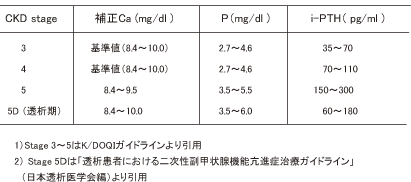
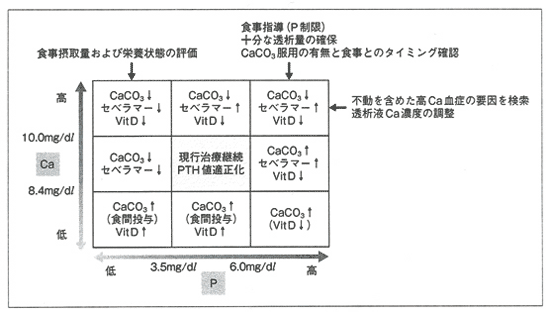
図2 P,Ca の治療、管理(日本透析医学会のガイドラインより)
参考文献
1.日本腎臓学会編: CKD 診療ガイド. 2009. 東京医学
社. 東京
2.深川雅史編: CKD-MBD ハンドブック. 2009. 日本メ
ディカルセンター. 東京
3.『腎と透析』編集委員会編: CKD のすべて. 2009. 東
京医学社. 東京
4.日本透析医学会: 透析患者における二次性副甲状腺機
能亢進症治療ガイドライン.透析会誌2006 ; 39 :
1435-1455