沖縄県立八重山病院院長 松本 廣嗣 先生
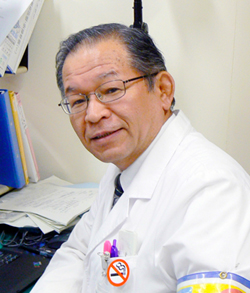
地域住民から「わったー病院」として愛され信頼される病院にしたい。
Q1.この度は、沖縄県立八重山病院 院長へ の就任おめでとうございます。就任に当たっての感想と、今後の抱負をお聞かせ下さい。
研修医時代も含めると今回で4 回目の赴任と なります。最初の赴任が32 年前で、前回副院 長をつとめてからでもすでに16 年経っており ますから結構長いおつきあいです。これも何か の縁でしょうからしっかり勤めを果たして参り たいと思っております。11 年間の長きに亘っ て伊江前院長が築きあげられた体制を引き継ぐ のですから、ちゃんと出来るのか多少の不安が ないわけではありません。地域に開かれた病院 として、離島医療、救急医療、がん診療をはじ め住民が安心して生活でき、観光客も安心して 過ごせる医療を提供できる病院として継続、向 上できますよう、皆様のご支援ご協力をお願い します。
抱負と言えば、定年まで残りわずかしかあり ませんが、地域住民と病院の一体化、研修制度 の導入、新病院建設準備を挙げたいと思います。
Q2.県立八重山病院の現状の評価と、今後の方向性についてお聞かせ下さい。
人モノ金の視点から見てみます。 人について言うと、職員定数は増えました が、相変わらず医師、看護師、コメディカルの 確保に苦労しています。職員はよく頑張ってい ますが、職員の構成を見ると、以前よりも石垣 出身の職員がずいぶん減って、本島や本土出身 者が増えてきている様に感じます。離島の永遠 の課題かも知れませんが、短期間で職員が異動 していく事に伴う諸種の問題があります。八重 山に住み着いて居残る職員に各種業務や責任が 結果的に押しつけられ、疲弊し諦め脱落してい く構図があります。離島の県立病院としては、 職員が交代しても一定の医療レベルを維持し提 供していくことが、最も大切な使命ですから、 何とか特定の個人に依存しない仕組みを生み出 していきたい。
モノに関しては、やはりすでに30 年経過し た病院の古さと狭さが問題ですね。雨漏り、ラ イフラインの老朽化、手術室や分娩室の数と配 置の問題、収納庫の不足、数え挙げればきりが ありませんが、すでに住民の文化生活環境の進 化にそぐわない療養空間になってきておりま す。すぐにも新病院の構想に手をつけるつもり です。
金の面では、昨年までの厳しい県立病院課の 経営改善計画と、診療報酬の改定やDPC 導入 などの影響で、かろうじて黒字を維持していま すが、今年度も職員一丸となって経営努力を行ってまいります。
私の印象が間違っているかも知れませんが、 以前と比べて、八重山病院に対する地域住民の 信頼が多少希薄になっているような感じを受け ます。いろんな状況や経験から生じているので しょうが、八重山病院はもっと地域の方々から 「わったー病院」として愛されて欲しいと思い ます。地域住民は、棚からぼた餅式に、ふんだ んに人材の配置された組織をただ待つのではな く、もっと自分達の病院をよくするための活動 をして欲しいと思います。そのような意味で、 積極的に地域の方と対話する場に出かけていく つもりでいます。
Q3.全国的にも医師不足・看護師不足が深刻ですが、離島医療における医療スタッフの確保という課題について、先生の考えをお聞かせいただけますか。
医師については琉大や中部・南部の県立病院 からの派遣中心にスタッフを確保しています が、今年度は病院事業局としての医師確保事業 が功を奏して耳鼻科及び外科の医師を確保する ことが出来ました。今後も県立病院課の担当に よる積極的な活躍による医師確保が期待できそ うです。
離島はどこでもそうでしょうが、1 年程度の 短い期間で交代していく担当医に対する患者の 不安感や不信感があります。これは次第に病院 に対する不信感へと繋がっていきます。そうな ると従事する職員達の間にも、病院や地域や患 者に対する熱意やロイヤリティーもしぼんで行 き、病院―患者間に不信の悪循環を生じてしま います。
医療従事者は、その知識や技術も真心を添え て提供して初めて患者の信頼を得られるもので す。地域の住民には、繰り返しアピールするこ とで医療の現状、病院の現状を認識してもら い、もっと医療以外の分野での交流を進めて 「自分達の病院」という意識を持ってもらうこ とでお互いの信頼関係を構築できるのではない でしょうか
研修制度の導入は今後大きな意味を持ってく ると思います。他府県の研修病院では沖縄の石 垣島での研修を目玉に、研修医の獲得をやって いるくらいです。それほど魅力があるのであれば 自前で確保することも可能でしょう。離島医療 に興味を持つ学生は想像されているより多いの です。病院が地域と共に育てる研修医は地域や 病院に対する愛着やロイヤリティーを持ちます。 そういう医師が次第に増えていけば地域の住民 や患者の病院に対する信頼も高まります。これ は看護師やコメディカルに関しても同じ事が言 えると思います。一生懸命愛情を注いで育てる ことの重要性はそこにあり、だからこそ住民や 患者の協力も必要なのです。病院が消えてしま った地域の人たちが必死の思いで人材確保に血 眼になっている状況は日本全国で見られます。 沖縄県では、県立病院や大学からの補充でなん とか医師を確保してきましたが、今後も同じよ うに供給出来るのか、はなはだ疑問です。医師 に関してはすべてを自前でまかなうことはとうて い出来ない相談ですから、これまで通り中部病 院や、南部医療センター、琉球大学との連携は もとより、県立病院課の担当部署と協力して全 国の医療機関へ呼びかけていくつもりです。
Q4.八重山諸島には幾つもの離島診療所がありますが、病院との連携はいかがでしょうか。
今回赴任してきてその変化に驚くところは、 地域全体の医師の数が随分増え90 名を超した こと、開業診療所が22 カ所に増え、本土や本 島出身の医師で開業する人が出てきているこ と、町並みがどこにも昔を探し出せないほど新 しくなったことです。
離島診療所には4 つの県立診療所と2 つの竹 富町立診療所があります。県立診療所は自治医 大出身と中部病院のプライマリーケアコースで 研修した医師が配置されていますが、病院全体 で附属診療所をサポートしています。医務課の 医師プールの一人が当院に配置されており、そ の医師の働きで病院医師の負担も相当軽減され ています。しかし、この体制も有り余る医師が いるわけでもなく、新たな体制を再構築する必 要があります。20 〜 30 年前に比べると、患者 の権利意識だけではなく、医師の人権やQOL 重視の姿勢も際だってきており、医師プールや 登録医師制度だけで、これに応えることが困難 になってきていることは確かです。急患に対す る24 時間対応を今後も診療所に維持させるの であれば、医師プールを拡大して診療所は医師 2 人体制に近いものを作る必要があります。離 島・へき地病院では当直や救急をカバーするた めに各科とも医師の数を必要としていますが、 プライマリケア医師、自治医大出身医師を救急 室所属とし、3 交代勤務とすれば各科の医師数 を多少削減できるのではないでしょうか。同時 に、離島診療所の代診やヘリ搬送を担当する体 制にして、いわゆる分業を進めれば、その他の 診療科の医師の疲弊も軽減できると思います。
Q5.本会または日本医師会へのご意見・ご要望がありましたらお聞かせ下さい。
医師会は現在アクティブに沖縄の研修医のサ ポートをすすめているが、非常に大切な事業だ と思います。今では県内にある3 つの大きな研 修病院群をまとめる要としての動きをしてお り、医師を育成する研修制度こそが、今後の県 内の医療を支える医師を確保する上での重要な 役割をなすものだという認識に立っているもの とその慧眼に敬服します。医療界全体で沖縄県 の医療を支えるためにさらなるご努力をお願い したい。
Q6.最後に日頃の健康法、ご趣味、座右の銘等がございましたらお聞かせ下さい。
検診結果は見事なメタボで、いよいよCKD の仲間入りとなりました。これからの目標は体 重を10kg ほど落とすことです。多趣味ですが 今は、果樹栽培と料理が一番燃えます。その 時々で変わるので座右の銘とは言えませんが、 今回は「今日は昨日の続きの今日じゃない。明 日は今日の続きの明日じゃない」を挙げておき ましょう。
この度は、インタビューへご回答いただき、誠にありがとうございました。
インタビューアー:広報担当理事 當銘正彦