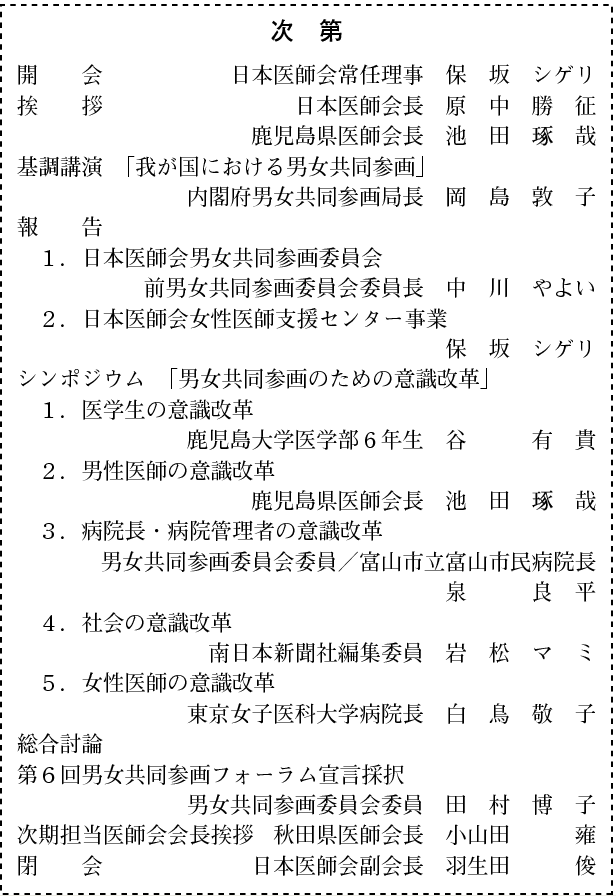日本医師会第6 回男女共同参画フォーラム
「男女共同参画のための意識改革」に参加して

沖縄県医師会女性医師部会委員 (国立病院機構沖縄病院) 大湾 勤子
今年で6 回目となる日本医師会主催の男女共 同参画フォーラムは、鹿児島市で7 月24 日に 開催されました。出席者名簿の参加者はこれま でで最多の483 名と盛会でした。あいにく搭乗 予定の飛行機が、計器不具合のため遅延後、乗 り換えとなり、遅れること2 時間。会場に到着 したのは、式次第の後半部分のシンポジウムの 最中でした。残念ながら前半は、ご紹介できま せんが、参加した感想を述べたいと思います。
シンポジウム「男女共同参画のための意識改革」
1.医学生の意識改革
鹿児島大学医学部6 年生 谷 有貴さん
結婚後医学部に入学。2 年生、4 年生の時に 長男、次男を出産。その間にうつ状態になった り、休学、留年などの経験をしたが、現在は復 学し6 年生に在籍(長男4 歳、次男2 歳)。彼 女の経験から、医学生の意識改革として1) 自分 たちは社会に育ててもらっていると意識するこ と、2) 社会に貢献する義務があると考える、3) 働き続けるために、自分らしく頑張るには何が ベストか考える、4) 欲張りに、自分の「ベス ト」をアピールして協力を得る、5) 周りへの感 謝を忘れないことを挙げていました。子供の存 在で勉強時間を確保することは厳しいが、一方 で勉強に身が入り真剣に取り組むようになった こと、病児保育の必要性を感じていることを述 べていた。会場から、同級生の反応はどうであ ったかという問いに、「男女を問わず『身近な ロールモデルとして参考にしている』と温かい 支援を受けている」と答えていた。
2.男性医師の意識改革
鹿児島県医師会会長 池田 ![]() 哉氏
哉氏
鹿児島は薩摩の時代から「男が家族を養い、 女は家庭を守る」という性別役割分業が当然と されてきた。今、男女の共同・男女の対等を実 現しようとすれば既存の権利や現状の猶予を譲 歩したり、放棄したりしなければならないのは 主として男性である。男女共同参画というの は、熟年世代の多くの男性にとって頭ではわか っていても、なんとなく抵抗を感じるものであ る。医師会長ご自身が今回のテーマに取り組む にあたり、これまでの自分を、男女共同参画時 代を生きる自分に変えるための改造・実践に努 力を始めたことをユーモア混じりでお話にな り、会場は大いに盛り上がっていた。男性医師 の意識改革の締めくくりとして「寛容」と「涵 養」(両方の「かんよう」)が必要だと感じたと 述べておられた。
3.病院長・病院管理者の意識変革 新しい労働環境を模索して−ワークバランスの視点から−
富山市民病院 泉 良平氏
医療ニーズの変化によって、急性期医療にお ける病院医師の負担は格段に増えている。病院 長・病院管理者には、「勤務医が疲弊すること なく、働くことに喜びを感ずる労働環境を提供 することが、病院医療を守るうえで必要であ る」と意識改革することが要求される。女性医 師の能力を活用できるように労働環境を改善す ることが、病院医療の質を向上させるために必 要な医師の確保につながる。自らの生活やいの ちを犠牲にしてまで働いてきた医師像は過去の ものである。病院長は、良好なワークライフバ ランスの下で、男女を問わず医師が能力を発揮 できる病院環境を提案し、また短時間勤務正規 雇用制度などを採用して、勤務医の労働環境を 改善することを模索すべきである。その結果、 そのことが医師確保につながり、病院経営の安 定と医療の質の向上がもたらされることに気付 くべきときが来ているという内容であった。会 場から、正規雇用を増やすと人件費の割合が高 くなり経営上負担はないのかという声があった が、短時間正規雇用は条例化されていること、 身分を保障することで若手に働く喜びを与える ことができ、結果として仕事の能率が上がり患 者増、収益増にもつながると説明された。大学 病院勤務の場合、非常勤の期間が少なからずあ り、大学退職時の退職金や年金に差がついてし まうとご自身の経験から、非常勤ではなく短時 間正規雇用をぜひ進めてほしいと強調された。
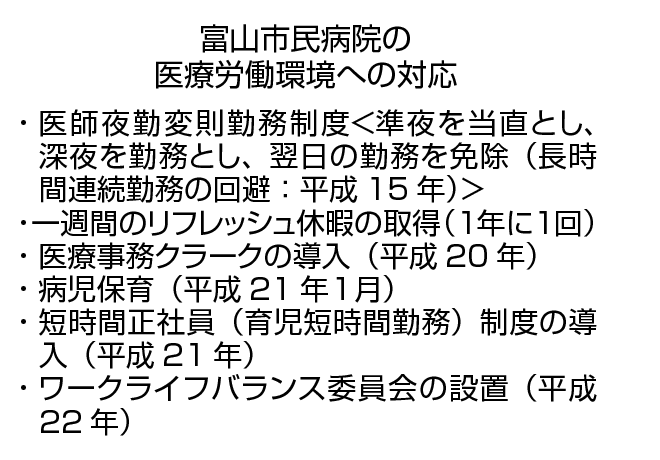
(スライドより引用)
4.社会の意識改革
南日本新聞社編集兼論説委員会委員 岩松 マミ氏
ご自身も女性記者として第一線で活躍なさっ ているが、医師の世界のみならず記者の世界も 女性は結婚、出産を契機に退職することが多 い。鹿児島県は全国に比べ男女共同参画は立ち 遅れている感がある。女性進出はさまざまな分 野で進んでいるが、内閣府男女共同参画局の岡 島敦子氏が基調講演で述べられていたように、 固定的役割分担意識がいまだに根強いことも一 因である。最近は育児休業をとる男性も少しず つ増えており、多様な体験が社員を成長させる と積極的な取り組みを進める企業もある。柔軟 な若い世代の出現で、ゆっくりだが意識は少し ずつ変わってきている。ワークシェアリングに よって男女を問わず皆が働きやすい環境に変わ っていくことに期待したいと述べられた。
5.女性医師の意識改革
東京女子医科大学病院長・消化器内科教授 白鳥 敬子氏
女性医師数の増加はめざましいが、真の男女 共同参画が実現するには女性医師側の意識改革 も重要である。医師は国民の健康と生命を守る という社会的使命を持つ職業である。女性医師 には、出産・子育てなどペースダウンを余儀な くされる期間もあるが、完全離職を避け、自ら のライフプランに応じた貢献の仕方を選択する ことが大切である。どのような状況においても 新しい情報や知識の習得など、常時自ら研鑽す る姿勢を貫き、専門医を取得しキャリアを高 め、ワークライフバランスから勤務形態を提案 するなど自ら道を開拓する気概も持つことが重 要である。このような姿勢と気概こそが昇格や 復職の際、力強いアドバンテージとなる。医師 として社会に貢献できることは素晴らしいこと であり、プロフェッショナルとしての自信と誇 りをもって医療に臨み続けて欲しい。そしてこ のような高い志をもった女性医師が一人でも多 くリーダーとして育成されることが期待され る。強調されていたことは、医師を志した原点 にもどり、all or nothing ではなく、仕事と生 活をたして100 点として継続していくことが大 切だということであった。
5 名のシンポジストの講演のあと、引き続き 質疑応答があった。たくさんの質問があった が、女性医師に限らず男性医師も働きやすい環 境を整えていくための意識改革の啓蒙が必要で あることが再確認されていた。
固定的役割分担への意識改革をとおして、男 女を問わずワークライフバランスを考えながら 勤務形態を選択することは、医療崩壊を防ぐこ とに重要であると再認識しました。高齢化社会 が進む中、出産、育児のみならず介護と仕事の 両立を可能とする労働環境整備と実効が必要だ と思いました。
沖縄県医師会女性医師部会でも、これまでシ ンポジウムを開催し女性医師の現在抱えている 問題や、復職・就業支援へのアドバイスなどに 取り組み始めています。復職支援プログラムの 充実や短時間正規雇用制度の普及などにより、 仕事を継続できる環境づくりに微力ながらこれ からもサポートしていきたいと思います。修学 旅行以来、?十年ぶりの桜島を見ることができ たことも収穫でした。
次回は、平成23 年7 月23 日に秋田県で本フ ォーラムが開催されます。会を重ねるごとに盛 会となっていく本フォーラムが、すべての人び との意識改革と社会的基盤の整備、施策の実現 につながることを期待します。