Pregnancy Related Death とPregnancy Associated Death
=妊産婦死亡統計のパラダイムシフト=
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター産婦人科
村尾 寛
【要旨】
日本では産科的死亡の大幅削減に見事に成功した結果、産科的原因以外の理由に よる妊産婦の死亡の割合が相対的に大幅に増加してしまった。産科的死亡に対する 外因死および病死の比率が、この60 年間で36 倍および6 倍にそれぞれ増加したの である。20 世紀の本邦の産科医の目標は直接的産科的死亡の削減であったが、こ の目標は21 世紀初頭にほぼ達成されたと考える。今は我々医師自身に、妊産婦死 亡に関する「パラダイムシフト」が必要なのである。外因死を含む全ての原因によ る妊産婦の死亡の統計としては、米国CDC・ACOGは既に1986年に “Pregnancy-Associated Death”(妊娠中〜妊娠終了後365日未満の、外因死を 含む全ての原因による死亡)の概念を提唱し、WHO は1990年に、“Pregnancy Related Death”(妊娠中〜妊娠終了後42 日未満の、外因死を含む全ての原因によ る死亡)の概念を提唱している。本稿ではこれらの新しい統計のコンセプトを紹介 すると共に、これらを現実化するために必要な条件について概説した。
<はじめに>
米国政府は、2010 年までに妊産婦死亡率を 出生10 万対4.0 以下にすることを政策目標に 掲げている。しかし2006 年現在の米国の妊産 婦死亡率は出生10 万対13.3 であり、目標の実 現には程遠いのが現状である。一方、日本の 2007 年の妊産婦死亡率は出生10 万対3.2、僅 か35 名であり、米国の国家目標の水準を3 年 前倒しで既に達成している。大変喜ばしい。で は日本の全妊産婦死亡は本当に35 名なのだろ うか?
<統計の定義から>
厚労省の「人口動態統計」に用いられる妊産 婦死亡統計は、以下のように定義されている。 「妊娠中または妊娠終了後満42 日未満の女性の 死亡で、妊娠の期間および部位には関係しない が、妊娠もしくはその管理に関連した、又はそ れらによって悪化した全ての原因によるものを いう。ただし、不慮または偶発の原因によるも のを除く。」
・・・ということは、妊婦の交通事故死亡や 自殺は全く含まれない事になるし、妊娠中にた またま進行癌が見つかって死亡した例も除外さ れる。さらに、患者が医師に、最近の人工妊娠 中絶や自分の妊娠を告げないまま妊娠初期に死 亡した場合も、統計から漏れてしまう。
このようにして妊産婦死亡統計から漏れる症 例数が、ごく僅かなのであれば、大勢に影響は 無いだろう。では実際はどうなのだろうか?
<人口動態統計からの推計>
日本には妊産婦の外因死(事故死亡、自殺、 他殺の合計)や病死に関する統計は存在しない。今回はやむなく、代わりにデータが存在す る「生殖可能年齢女性(16 〜 45 歳)の外因死 率・病死率」を、妊産婦のデータの代わりに試 算したところ、以下のようになった。
まず戦後まもない1950 年から2007 年まで の、妊産婦死亡率と、生殖可能年齢女性(16 〜 45 歳)の外因死率の経緯を人口動態統計1) から試算したものを表1 および図1 に示す。
表1.人口動態統計からの試算
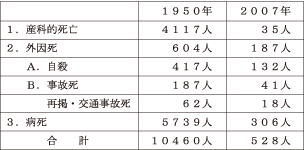
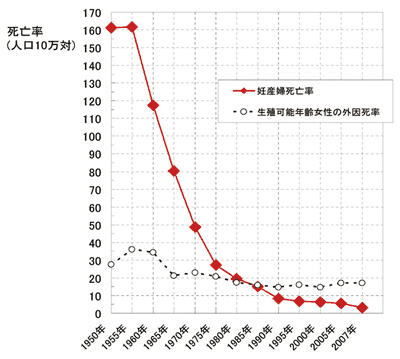
図1.生殖可能年齢女性の外因死率と妊産婦死亡率
1950 年では産科的死亡4,117 人に対し、妊 産婦の死亡率が生殖可能年齢女性のそれと同じ と仮定して試算すると、外因死は推定604 人で あり、産科的死亡の約1/7 にすぎない。しかし 平成19 年には産科的死亡35 人に対し妊婦の外 因死は推定187 人であり、約5 倍を占めてい る。すなわち、この60 年間で産科的死亡に対 する外因死の比率が相対的に36 倍に増えてい るのである。
同様にして病死に関しても同じ試算を試みる と、1950 年には産科的死亡4,117 名に対し病 死が5,739 名と約1.4 倍だったものが、2007 年 には産科的死亡35 名に対し病死306 名と約9 倍を占めており、病死の割合がこの60 年間で 相対的に約6 倍増加しているのである。
見方を変えれば、この60 年間で産科的死亡 の大幅削減に見事に成功した結果、60 年前に は思いもよらなかった事に、産科的原因以外の 理由による妊産婦の死亡の割合が相対的に大幅 に増加してしまったのである。
ここに30 歳の妊娠していない女性がいたと しよう。この女性が人口動態統計上、一年以内 に死亡する確率は人口10 万対39.4、すなわち 約1/2,500 だ。この女性が妊娠したとする。こ の妊娠自体の影響によって一年以内に死亡する 確率は人口10 万対3.2、すなわち約1/30,000 だ。妊娠による死亡率の上昇は、人口10 万対 39.4 に3.2 が上乗せされるが、割合にすれば約 8 %に過ぎない。今後さらに現実の妊産婦の死 亡を減らすには、8 %の方ではなく、92 %を占 めている、妊娠の有無にかかわらず発生してい る女性の死亡の削減に取り組む必要があるので ある。
<パラダイムシフトの必要性>
直接的産科的死亡の削減こそ20 世紀の本邦 の産科医の、それこそ100 年の悲願であった。 この目標は全国規模での総合周産期母子医療セ ンターの整備と共に、21 世紀初頭にほぼ達成 されたと筆者は考えている。換言すれば厚労省 母子保健課が、単独事業で対応できた時代はも う終わった、ということでもある。
我々産婦人科医自身も行政サイドも、共に 「とにかく産科的原因による妊婦の死亡を削減 しないといけない」という過去一世紀間の、呪 縛にも似た思考停止状態から抜け出す必要があ る。21 世紀の日本の妊婦死亡の大多数が、産科 的原因以外の原因で死亡している事実こそ「新 しい現実」であり、たとえ我々産婦人科医師自 身の直接の守備範囲ではなくても、この現実に 対応した対策が必要なのである。すなわち我々には「パラダイムシフト」が必要な のである。
< Pregnancy-Related Death と Pregnancy-Associated Death >
実は他の先進国では、既に約20 年前からこのような「新しい現実」 に対応した妊産婦死亡統計を取り 始めている。しかし、日本では何故 かこのことが殆ど知られていない。
外因死を含む全ての原因による 妊産婦の死亡の統計としては、米 国では既に1986年にCDCとACOG が“Pregnancy-Associated Death”の概念を提唱している2)。 一方WHO は1990年に、これとは 別個に“ Pregnancy Related Death”の概念を提唱した3)。
「Pregnancy-Associated Death」(CDC,ACOG 1986 年);
妊娠中〜妊娠終了後365 日未満の、外因死を 含む全ての原因による死亡
「Pregnancy-Related Death」 (WHO 1990 年);
妊娠中〜妊娠終了後42 日未満の、外因死を 含む全ての原因による死亡
現在は両者が歩み寄る事なく2 つの統計が並 存したまま、行政レベルで統計のデータを既に 取り始めている状況である。米国の多くの州で はPregnancy-Associated Death の統計を開 始している一方で、北欧の国々を中心に国全体 のPregnancy-Related Death の統計が既に始 まっている。
これまでに筆者がPubMed で渉猟しえた、過去 のPregnancy-Associated Death(CDC,ACOG) の文献報告のまとめを表2 に示す。産科的死亡 は直接的産科的死亡237 名、間接的産科的死亡 176 名で、合計413 名であるのに対し、それ以 外の死亡は外因死669 名、外因死以外の原因に よる死亡539 名で、合計1,208 名にものぼって いる。
表2.Pregnancy-Associated Death(CDC,ACOG)の報告一覧
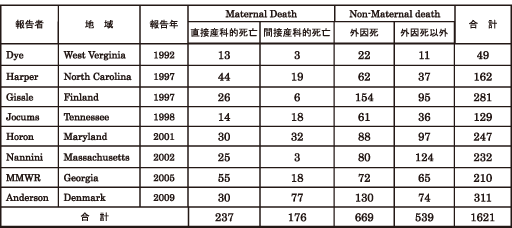
表3.Pregnancy-Related Death (WHO)の報告一覧
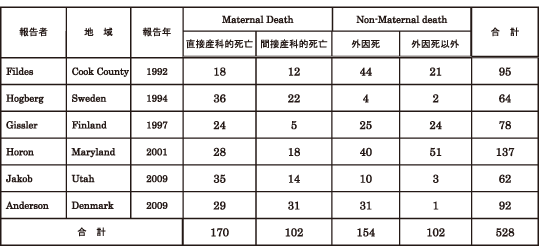
同様に、今回渉猟しえた、過去のPregnancy Related Death(WHO)の文献報告のまとめ を表3 に示す。産科的死亡は直接的産科的死亡 170 名、間接的産科的死亡102 名で、合計272 名であるのに対し、それ以外の死亡は外因死 154 名、外因死以外の原因による死亡102 名 で、合計256 名にものぼっている。
<今後取り組むべき事柄>
まずは統計のとり方に関して、Pregnancy- Related Death あるいはPregnancy-Associated Death の導入を、行政が決定する必要がある。
次に、死亡診断書の書式の変更が必要であろ う。現行の死亡診断書は、現在の妊娠の有無・ あるいは過去1 年以内の妊娠の既往の有無を必 須記入する書式ではないので、これらの記入漏 れを防ぐ仕組みが無い。過去6 週間〜 1 年以内 の妊娠の有無をチェックリスト方式で必ず記入 する形式に変更する必要があると思われる。
また、自殺や事故死した女性が妊娠していた かどうかに関し、現行の制度では全員厳密に調 査する体制には無いため、初期の妊娠を見逃している可能性が大きい。生殖可能年齢女性の死 亡例に関しては、全例導尿して妊娠反応を検査 するよう、臨床医のみならず法医学関係者や検 死官などにも周知する必要があるだろう。
<未来の妊婦検診のあり方を想像してみる>
生殖可能年齢女性の三大死因が自殺・不慮の 事故・悪性腫瘍であるということは、産科的原 因以外の妊婦の死因もまたこれらであろうとい うことを意味する。であるならば、未来の産婦 人科医師の妊婦検診は、従来とは様変わりする だろう。
未来の妊婦検診はどのような形になるだろう か?妊婦検診が生殖可能年齢女性の三大死因へ の予防対策を兼ねた、いわゆる「心身の健康チ ェック」の場に変わると筆者は予想している。
メンタルヘルス面では、例えば自殺予防のた めに、日常的に精神科医・臨床心理士・保健 師・福祉担当者との密接なカウンセリングが必 要となるだろう。不慮の事故予防のためには、 まずは妊婦の交通事故死予防のためのシートベ ルト着用キャンペーンが必要になるだろう。近 年、小児の外因死予防に関して、盛んにキャン ペーンが行われるようになったが、同様の取り 組みが妊婦に対しても必要になるだろう。ま た、悪性腫瘍の早期発見のためには、妊婦検診 がいわゆる「人間ドッグ」を兼ねる形で施行さ れる必要があるだろう。
<参考文献>
1)人口動態統計(平成19 年版) 厚生労働省大臣官房
統計情報部編 財団法人 厚生統計協会
2)Ellerbrock TV, Atrash HK, Hogue CJR, Smith JC.
Pregnancy mortality surveillance: a new initiative.
Contemporary Obstet-Gynecol Vol 33; June, p23-
31,1988
3)Fortney JA. Implications of the ICD-10 definitions
related to death in pregnancy, childbirth or the
puerperium. World Health Statist Quart Vol.43; No
4, p246-248, 1990
Q U E S T I O N !
問題:次の中から正しいものを選べ
- 1.本邦の現行の妊産婦死亡統計は、不慮また は偶発の原因による死亡を含めている。
- 2.2007 年の本邦の妊産婦死亡統計では、妊産 婦死亡数は出生10 万対32 である。
- 3.本邦の妊産婦の推定外因死数は、産科的死 亡数を大幅に上回っている。
- 4.Pregnancy-Associated Death(CDC,AC OG)とは、妊娠中〜妊娠終了後42 日未満の、 外因死を含む全ての原因による死亡をさす。
- 5.Pregnancy-Related Death(WHO)とは、 妊娠中〜妊娠終了後365 日未満の、外因死を 含む全ての原因による死亡をさす。
CORRECT ANSWER! 12月号(vol.45)の正解
広範囲胸部大動脈瘤に対する治療戦略に ついて
問題:胸部大動脈瘤手術に関して正しいのはど れか。
- a. 胸部大動脈瘤の内、紡錘状瘤は瘤径にかか わらず手術適応である。
- b. 急性大動脈解離I 型の血栓閉塞型は自然治癒 例である。
- c. 弓部大動脈瘤手術時、通常懸念すべき合併 症は術後対麻痺である。
- d. 急性大動脈解離IIIb は手術適応はない。
- e. 弓部大動脈瘤手術時、選択的脳灌流が必要 である。
解説:
- a.:間違い。紡錘状瘤は通常瘤径に応じて手術適応が決定する
胸部大動脈瘤では一般的に50mm 以上を手術適応とする。
一方、嚢状瘤は破裂の頻度が高いため、瘤径にかかわらず手術適応である。 - b.:間違い。治癒でなく、偽腔が再開通する例 が多い。
- c. :間違い。脳梗塞に伴う片麻痺である。対麻 痺は通常、胸腹部大動脈手術時の脊髄虚血に 伴う合併症である。
- d.:間違い。急性大動脈解離IIIb の手術適応 は、臓器虚血、破裂等である。
- e.:正しい。臓器保護のために低体温循環停止 に脳灌流を併用する。脳保護の方法として逆 行性脳灌流法と選択的脳灌流があるが、一般 的に選択的脳灌流法が用いられる。
正解 e