第109回沖縄県医師会医学会総会

広報委員 久場 睦夫

第109 回沖縄県医師会医学会総会が、平成 21 年12 月12 日(土)、13 日(日)に開催され ました。第1 日目は冒頭、会頭の大宜見義夫先 生が挨拶されました。その中で不登校の事例を 発達障害という視点で捉えうまくいったとのお 話があり、難しい症例では視点を変えて診るこ とが重要である、と印象深く拝聴しました。
続いて東京大学大学院教育学研究科身体教育 学講座教授・転倒予防医学研究会世話人代 表・武藤芳照先生の特別講演「高齢者の転倒・ 骨折予防の実践と教育」がありました。予防に 勝る治療はない、の大前提のもと適正な運動療 法の重要性を述べられました。一般市民への 「転倒予防7 カ条」で、運動・生活プログラム をより広く解りやすく伝え、楽しく運動・生活 を行っていくことの大切さを具体的に話され、 日常診療ではやや門外漢の小生にもよく理解で きました。冒頭で「難しいことを易しく、易し いことを深く、難しいことを面白く話して聴衆 を居眠りさせない」といわれましたが、講演は まさしくその通りで、あっという間の1 時間で した。最後の方で高齢者の転倒には「介入によ り防ぐことのできる転倒」と「現在の医療水準 に照らして避けられない転倒」の2 種類があ り、医療者を萎縮させないよう後者にあてはま る転倒のある事を医療受給者にもよく理解して もらう事も重要と述べられ、まさに同感であり ました。
その後、第24 回沖縄県医師会医事功労者表 彰式があり、沖縄県知事表彰が3 名、県医師会 会長表彰が37 名の先生方になされました。誠 におめでとうございます。
引き続き、シンポジウム「骨粗鬆症・転倒の 予防〜寝たきりを防ぐために〜」が開かれまし た。座長の琉球大学整形外科教授金谷文則先生 は、人生最後には男性で平均6.3 年、女性で 7.9 年の介護が必要であるが、骨折は脳血管障 害、老衰に次ぐ第3 位の原因であり、骨折予防の大切さを冒頭で述べられました。シンポジウ ム第1 席は、琉球大学整形外科准教授大湾一郎 先生の「骨粗鬆症と骨折の増加〜最近の動向 〜」で、本県の大腿骨近位部骨折は2004 年の 調査で1 年間に男性242 人、女性1,107 人であ り、1987/88 年に比し、男女とも約2 倍に増加 しているとのことでありました。新潟県と鳥取 県に比較すると本県では自力歩行者での骨折が 多いとのことですが、その要因については検討 が必要とのことでした。第2 席は西崎病院副院 長吉川朝昭先生の「骨粗鬆症の治療〜運動療 法・薬物療法〜」で、ビスフォスフォネート製 剤・選択的エストロゲン受容体モジュレーター の使用法さらには活性型ビタミンD、ビタミン K、カルシトニン等との組み合わせについて講 演されました。また運動療法・栄養補充療法に ついても述べられたが、宇宙飛行士が運動とビ スフォスフォネートの効果により自力歩行で帰 還した事を引き合いにした、運動療法と薬剤併 用の重要性の話が印象的でした。第3 席は沖縄 リハビリセンター病院回復期病棟課長宜野座妙 子師長さんの「回復期病棟の転倒・転落防止の 取り込み」と題したリハビリテーション現場で の転倒防止対策についての報告でした。様々な 対策・工夫での転倒防止とともにADL の拡大を計っていくといった難しい課題への取り込み に敬服しました。第4 席は南部病院リハビリテ ーション科長神谷喜一理学療法士さんの「機能 回復・運動療法」で温熱・運動療法、それに自 宅での家屋環境の整備・日常生活でのトレーニ ングなどリハビリの実際を呈示されました。
以上4 席は、骨粗鬆症に関連した大腿骨骨折 の現状、骨粗鬆症の治療、転倒防止対策、リハ ビリテーション、といずれも寝たきりを防ぐた めの大変勉強になる講演でした。総合討論で転 倒・転落の3 大原因は睡眠薬の使用、夜間の排 尿、それに移動、であることから、これらに向 けた対策が重要との議論があり、高齢者の診療 に際しての配慮を喚起させられました。近年、 殆どの科において高齢者の診療が必須です。目 前の疾患のみに捕らわれる事なく、‘転倒・骨 折’が如何に予後に重大な影響を及ぼすか、を 常に念頭においた診療の重要性を改めて感じ入 りました。
武藤先生はアリストテレスの言葉“Life is motion(生きていることは動いていること)” を引用されましたが、その意味を深く考えさせ られる大変有意義な特別講演とシンポジウムで した。
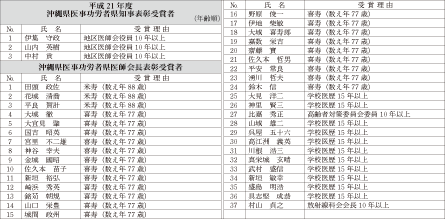
会頭挨拶

第109 回沖縄県医師会医学会総会会頭
大宜見 義夫
このたび、第109 回沖縄県医師会医学会総会 会頭の指名を受けました大宜見義夫でございま す。会頭として一言ご挨拶申し上げます。109 回に及ぶ長い伝統を誇る本学会の会頭の任を賜 り、誠に光栄に存じます。
私は、開業小児科医として22 年になります。 専門の一つとして不登校や心身症など、子ども の心の診療にたずさわっている関係から、県医 師会分科会に属する沖縄心身医学会、沖縄精神 神経学会、日本東洋医学会沖縄支部会の先生方 と交流を深めてまいりました。
具体的なことを申し上げますと、朝起きられ ず登校できないケースについて、原因が、起立 性調節障害による気分不良、気管支喘息やアレ ルギー性鼻炎等による慢性的な不眠や体調不良 によるものであれば、小児科サイドで対処可能 ですが、うつ病性障害、社会不安障害、過敏性 腸症候群などが背景にあると、精神科もしくは 心身医学的なアプローチが必要となります。一 方、身体症状を執拗に訴え、心理療法、薬物療 法が奏功しないケースに対して漢方薬が奏功す る場合があります。
小児科サイドで解決を見ない場合、心身医学 の視点でとらえなおす、それでも解決を見ない 場合、東洋医学の視点でとらえなおす、という 風に視点を変えて病態をとらえなおすコツを3 分科会の先生方から学びました。
かつてこういうケースがありました。腹痛・ 頭痛をくり返し登校できなくなった小学6 年の 女児の母親から受診予約の電話がありました。 当時、母親は、離婚直後の混乱期にあり、家庭 不和が不登校の原因と考え、受診してプライバ シーをさらけ出すことへの抵抗から、当院に向 かう途中受診を断念しました。
それから2 年半、医療機関を転々としカウン セリングや薬物療法を受けるもののよくならず、 中学2 年になって改めて当院を受診しました。
その結果、強度の生理痛に冷えが関与した症 例であることが分かり、漢方薬を服用して3 週 後にはスムーズに登校出来るようになりました。
当院を訪れた不登校のケースは、2,000 例を 超えています。その中のかなりの数において不 登校の要因がはっきりつかめないケースがあり ました。学校で、なぜかよくいじめに遭う、普 通の子とどこか雰囲気が違う、コミュニケーシ ョンやイントネーションが独特、特定なものへ の抜群の記憶力を有しながらこだわりが強く孤 立しているなどなど、これまでユニークで個性 的な子として扱われてきた子らの一群です。
その子たちは、ここ数年発達障害と呼ばれる 子どもたちの一群です。知能は普通並みだが、 社会生活を行う上の能力にばらつきのあるケー スです。
不登校の背景がはっきりつかめないそういう ケースの一群を発達障害という視点でとらえな おすことで、目からうろこの落ちるような体験 をしました。視点を変えてとらえなおすことの 重大さを改めて知りました。
神戸のA 少年の事件以来、これまで理解しが たい少年犯罪がたびたび報道されてきました。 これらの事件も発達の視点でとらえなおし、適 応行動に向けた適切な支援や教育が幼少期から なされておれば悲劇は避けられたのではないか という専門家の意見があります。発達障害への 支援・理解はこれからの社会の大きな責務であ り課題ではなかろうかと思います。
昨年、沖縄で第26 回日本小児心身医学会を 開催しました。学会のテーマは、「診療現場に おける小児心身医療」「小児心身医療における 漢方治療」の2 本立てとしました。狙いのひと つは、心身医療を漢方治療という視点からとら えなおしてほしいという思いがありました。
また、今年11 月沖縄小児保健センターで開 催しました第35 回日本小児東洋医学会のメイ ンテーマは「漢方治療を、視点を変えてとらえ る」としました。漢方医学を西洋医学、心身医 学の視点からとらえなおしてほしいという思い からでした。
109 回を迎える本医学会において専門分野の 違う多くの先生方が年に2 回一堂に会し、討議 討論を重ねることは、学際の場としてまことに ふさわしく意義深いものだと考えております。 沖縄県医師会医学会の更なる発展を祈願する次 第です。
終わりにあたり、本学会の会頭をご指名くだ さいました県医師会会長宮城信雄先生、医学会 会長玉城信光先生、並びに関係者の先生方に深 く感謝申し上げます。ありがとうございました。
特別講演
「高齢者の転倒・骨折予防の実践と教育」

東京大学大学院教育学研究科身体教育学講座教授、
教育学研究科長・教育学部長、
転倒予防医学研究会世話人代表
武藤 芳照
高齢者の転倒をきたす内的要因としては、加 齢、そして日頃の運動不足に伴う身体機能の低 下、身体的・精神的疾患の合併(高脂血症、高 血圧症、糖尿病・抑うつ、認知症等)、薬剤の 服用(「転倒」が副作用として明示されている 薬物や、ベンゾシアゼピン系睡眠薬等の服用あ るいは服用薬剤数の多さ)があげられ、「易転 倒性」(転びやすさ)を生み出す。外的要因と しては、屋外の道路・建物構造、屋内の障害物、段差、足に合わない履物等があげられる。 これらの内的・外的要因が、種々な割合で一瞬 に複合してヒトの転倒が発生する。
その転倒に、「易骨折性」とりわけ基礎疾患 としての骨粗鬆症(骨のもろさ及び骨折しやす さ)が加われば、骨折が生じる。もちろん骨粗 鬆症がなくとも、衝撃が強大であれば骨折が起 こる。一方、重度の骨粗鬆症があれば、転倒が なくとも骨折が起こる。
このような高齢者の転倒・骨折に対して、骨粗 鬆症の早期診断と適切な医学的治療及び運動・生 活指導が必要であることは言うまでもない。それ と共に高齢者の転倒予防のための適正な運動処方 を普及・啓発させることもきわめて重要である。
転倒予防のためには、運動療法を含め、服用 薬剤の点検と指導・調整、建物・構造の点検を はじめとする生活環境への対応等、多面的な介 入・取り組みが必要である。運動プログラムとし ては、バランス訓練及び複合的な運動で特に高 い転倒予防効果が得られることが報告されてお り、運動中の転倒リスクの点を想定して、安全 で楽しい内容と方法に徹することが重要である。
これらのいわば「転ばぬ先の杖と知恵」という ハード面とソフト面への対応を養生訓のような形 で一般市民向けにまとめたものが、下記の「転倒 予防7 カ条」である。一つひとつの言葉の意味・ 内容、それらに込められた運動・生活プログラム を繰り返し伝えていくことも大切と考えている。
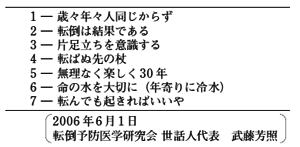
ところで、高齢者の転倒には2 類ある。つま り、「介入により防ぐことのできる転倒」と「現 状の仕組みでは防ぐことのできない転倒」、ある いは「現在の医療水準に照らして避けられない転 倒」である。
高齢者の転倒予防の目指すものは、転倒・骨 折を原因として起こる寝たきりや要介護状態を 低減し、一人ひとりの高齢者の健康と幸福と自 己実現にまで結びつけることである。さらには、 転倒予防を普及・強化することが、医療・介護 の現場で働く専門職の人々の自信と希望につな がることが重要である。
【参考図書】
1.『転倒予防らくらく実践ガイド』武藤芳照 監修、学
習研究社、2009
2.『転倒予防医学百科』武藤芳照総監修、日本医事新報
社、2008.
3.『高齢者指導に役立つ転倒予防の知識と実践プログラ
ム』武藤芳照総監修、日本看護協会出版会、2006.
4.『患者指導のための水と健康ハンドブック−科学的な
飲水から水中運動まで−』武藤芳照、太田美穂、田澤
俊明、永島正紀編、日本医事新報社、2006.
5.『転倒・骨折を防ぐ簡単!運動レシピ』武藤芳照監修、
主婦の友社、2005.
6.『転倒予防教室−転倒予防への医学的対応−』改訂第2
版、武藤芳照、黒柳律雄、上野勝則、太田美穂編、日
本医事新報社、2002.
7.『武藤教授の転ばぬ教室−寝たきりにならないため
に−』武藤芳照、暮しの手帖社、2001.
シンポジウム
「骨粗鬆症・転倒の予防〜寝たきりを防ぐために〜」
座長:琉球大学医学部整形外科教授
(沖縄県リハビリテーション医学会会長) 金谷 文則(1)「骨粗鬆症と骨折の増加 〜最近の動向〜」
琉球大学医学部附属病院整形外科准教授 大湾 一郎(2)「骨粗鬆症の治療 〜運動療法・薬物療法〜」
西崎病院副院長副院長 吉川 朝昭(3)「回復期病棟の転倒・転落防止の取り組み」
沖縄リハビリテーションセンター病院回復期病棟課長 宜野座 妙子(4)「機能回復・運動療法」
南部病院リハビリテーションセンター科長 神谷 喜一
1.骨粗鬆症と骨折の増加 〜最近の動向〜

琉球大学医学部附属病院整形外科准教授
大湾 一郎
高齢化社会を迎え、骨粗鬆症の予防と治療の 重要性はますます高まっている。日本全国では約1 千万人の骨粗鬆症患者が存在し、2007 年 の報告では1 年間で約15 万人(男性3 万人、 女性12 万人)の大腿骨近位部骨折の新規患者 が発生している。
沖縄県における骨折の患者数はどれくらいだ ろうか?我々は本県における骨折患者数の実態 を明らかにするために、2004 年の1 年間に大 腿骨近位部骨折を受傷し、県内の整形外科施設 に入院した50 歳以上の患者を対象に疫学調査 を行った。骨折患者数は男性242 人、女性 1,107 人、計1,349 人で、受傷した方の平均年 齢は男性76.9 歳、女性82.4 歳であった。部位 別には大腿骨頚部骨折が671 人、大腿骨転子部 骨折が654 人(不明24 人)であった。
この骨折患者数は多いのか、少ないのか?ま ず、1987/88 年に我々が行った同様な調査と比 較してみよう。1987/88 年の2 か年間の平均患 者数は男女合わせて469 人で、患者の絶対数は 2.9 倍に増加していた。50 歳以上の人口構成を 同じにして比較してみると、10 万人あたりの 骨折数は1 9 8 7 / 8 8 年が男性7 2 . 8 人、女性 282.0 人、2004 年が男性120.1 人、女性407.6 人で男女とも約2 倍に増加していた。10 歳毎の 年齢階級別の検討でも、すべての年代で骨折発 生率は増加しており、1987/88 年と比べて 2004 年の高齢者は転倒あるいは骨折しやすい ことが考えられた。
同様な全県調査は新潟(2002 年)や鳥取 (1999 年)でも行われており、人口構成を同じ にした10 万人あたりの骨折数を比較してみる と、新潟308 人、鳥取364 人、沖縄355 人 (1987/88 年)・528 人(2004 年)となり、沖 縄県における骨折発生率は比較的高いことが分 かる。
以上の結果より、本県の高齢者は骨粗鬆症の 罹患率が高いと結論付けて良いだろうか?大腿 骨転子部骨折は大腿骨頚部骨折と比べて、より 骨粗鬆症が重度な人に起こりやすい。先の2 県 と大腿骨近位部骨折における転子部骨折の割合 を比較すると、新潟63 %、鳥取59 %、沖縄 49 %となり、本県では転子部骨折の割合が低 いことが分かる。
日本はアジア諸国の中では大腿骨近位部骨折 の発生率は高い方であり、欧米と比較すると低 い方に入る。発生率の地域差は、必ずしも骨粗 鬆症罹患率の差によるものではないと考えられ る。大腿骨近位部骨折の受傷原因は転倒である ことが多く、自立歩行が可能な者に生じやす い。受傷前に自立歩行が可能であった者の割合 は沖縄県では全患者の78 %であり、青森県の 74 %、愛知県の68 %と比較すると高い値であ った。
骨折の発生率を下げるために、今後ますます 骨粗鬆症の治療は重要になると思われるが、な ぜ骨折したのか、なぜ転倒したのかを詳細に検 討することは大切である。転倒には歩行能力以 外にも、筋力やバランス感覚などの個人要因 と、1 人暮らしかバリアフリーかなどの環境要 因が関与している。本県の高齢者ではどの要因 が主に関与し、骨折の発生率が高くなっている のかを明らかにする必要がある。
2.骨粗鬆症の治療〜運動療法・薬物療法〜

西崎病院副院長 吉川 朝昭
原発性性骨粗鬆症の治療について、薬物療法 を中心に、運動療法や栄養補充療法の効果につ いても言及する。
薬物療法
ビスフォスフォネート製剤
破骨細胞の骨吸収作用を抑制する薬剤で、現 在は第三世代までのものが市販化されており、 骨密度増加による椎体および大腿骨頸部骨折の 予防効果を示すエビデンスが得られている。 (エビデンスグレードA) 最近ではコンプライアンスのよい週一回製剤が普及し、使いやすい 薬剤となっている。しかし、骨の代謝回転を抑 制することによって得られた骨量の増加は、正 常にリモデリングされない骨組織の割合が増え ることでもあり、長期使用のもたらす影響につ いては未知数である。また顎骨壊死との関連も 指摘されており、その安全性と有用性の検証が 急務である。
選択的エストロゲン受容体モジュレーター(SERM)
骨に対してはエストロゲン様作用を有し、骨 量の増加、椎体圧迫骨折の抑制効果が認められ ているが(グレードA)、乳房や子宮ではエス トロゲン様作用はなく、ホルモン補充療法 (HRT)に代わるものとして期待されている。 ビス剤よりは骨量増加効果は認められないが、 骨基質の質的改善効果が示唆されている。ビス 剤に較べ、比較的若年層からの使用にも抵抗感 が少ないが、静脈血栓塞栓症や長期臥床状態に ある患者への使用は禁忌であることは留意すべ き点である。
以上の2 剤が薬物療法の主流であるが、その 使い分けや使用開始時期、終了時期について広 くコンセンサスの得られているものはない。本 講演では私なりの使用法について述べさせてい ただく。
他の治療薬としては、活性型ビタミンD 製 剤、ビタミンK、カルシトニン等があるが(い ずれもグレードB)、前述の2 剤の陰に隠れて 過小に評価されているきらいがある。骨粗鬆症 の骨動態による分類や薬剤の組み合わせによる 相乗効果等の検討により再評価の可能性がある ことを指摘しておきたい。
運動療法と栄養補充療法
不動性(臥床安静、麻痺性疾患、廃用症候 群、骨折後等)や栄養性(神経性食思不振症、 吸収不良症候群、胃切除後等)の続発性骨粗鬆 症の場合は、運動療法や栄養補充療法も一定の 効果は期待できると考える。一方、原発性骨粗 鬆症の治療においては、いずれも必要条件とは なり得ても、十分条件とはなり得ないことを明 記しておきたい。しかし骨粗鬆症の予防(若年 期でのカルシュウム摂取はグレードA)や骨量 の維持を考える上では、運動療法や栄養補充療 法は重要なものであり軽視すべきものではない のもまた事実である。本講演では、運動療法や 栄養補充療法の効果やその限界について考察し たい。
3.回復期病棟の転倒・転落防止の取り組み

沖縄リハビリテーションセンター病院回復期病棟課長
宜野座 妙子
はじめに
医療安全に関する指針が出され、全ての医療 機関において安全管理委員会が設置されるよう になり、専従のリスクマネジャーが配置された医 療機関には、診療報酬で点数が加算されるよう になった。そのためほとんどの施設で転倒・転 落対策や医療安全対策への取り組みが実施され、 事故防止対策が行なわれるようになっている。
沖縄県看護協会においても、協会の委員会の 中に特別委員会として、医療安全対策委員会が 設置され、県内の各施設の医療安全担当者が中 心となって委員会活動を行なっている。その活 動内容として、リスクマネージャー交流会を年 2 回開催、情報交換や事例紹介・要因分析等を 行い事故の再発防止に取り組んでいる。また、 県内のリスクマネージャー研修会の開催や看護 協会内に医療安全の相談窓口の設置。会員の安 全やメンタル等の相談等、医療安全への支援を 行い、さらなる事故防止策への取り組みを行っ ている。
沖縄リハビリセンター病院6 階病棟は回復期 の病棟で、平成12 年に開院して以来、入院患 者に占める65 歳以上の割合は増加の傾向にある。また、当病棟は創設時より脳血管疾患や高 次脳機能障害、脊髄損傷患者等のリハビリテー ション患者を多く受け入れており、転倒・転落 は事故報告の第一位を占めている。平成20 年 度のインシデント・アクシデントの件数は178 件中、転倒件数は148 件(83 %)、転落0 件 (0 %)、誤薬16 件(8.9 %)、その他14 件 (7.8 %)の割合を占めている。また、この転 倒・転落事故は患者要因に起因することが大き いため、対策が難しくあとを絶たないことも事 実である。そしてまた、看護者側にも誤薬事故 等に比べ自覚が乏しいといえなくもない。
しかし、一方ではこうした事故発生時の看護 者の責任も免れ得ないものとなっており、その ため必要以上に警戒しADL の拡大を遅らせる 対策を講じるなど、患者のQOL の低下を招く という結果を引き起してしまいがちである。そ こで、いかに転倒・転落を予測し、未然に防ぐ ためのケアを的確に実施していくかが不可欠だ と考える。
病棟において、患者に安全で安心した医療を 提供するために、多忙を極める日々の業務の中 で、どの場面でも転倒・転落をなくそうと努力 している。その甲斐あって、最近では転倒アセ スメントツールや転倒予防マニュアルも改訂を 重ねて充実し、実践活用も見られるようになっ た。しかし、医療者側が必死に努力しているに も関わらず転倒・転落事故はゼロにならないの が現状である。急性期においても、転倒対策は 重要な課題だと思っているが、回復期病棟にお いても、ADL の向上とともに転倒リスクが増 大し対策に苦慮している現状がある。回復期病 棟の特徴として、中枢神経系に問題がある場合 は認知・理解力に影響を与える事がしばしばあ り、治療に対する理解力が乏しくなる。この場 合、当然、患者は看護師を呼ぶという事の説明 の理解ができない。そのような患者が大半を占 める病棟で、さらに、反射機能の問題から転倒 の際に自分の身を守る事ができず、頭部打撲か ら頭蓋内出血、死に至るケースも少なくない。 つまり『転倒=死』を想定して臨まなければな らない病棟である。と一般的に言われている。 このことから、スタッフに患者の行動を予測す るという高度の能力が求められ、転倒による安 全教育と感性教育が必要と考える。
このような現状の中で、当病棟の転倒・転落 対策の紹介をしていきたい。
まず、入院時、外来において主治医から回復 期における転倒・転落リスクの説明を家族に説 明。安全帯使用の同意書の確認がおこなわれる。
病棟では、最初に転倒・転落アセスメントツ ールを用いて患者の危険度の評価を行う。この 場合1)認知・理解力に問題がある場合センサー 設置、部屋の位置、環境調整、2)動作能力に問 題がある場合は手すり、車椅子、歩行器、杖の 配慮、3)転倒外傷の予測される重傷度患者の場 合1)と同様な対策を行い、場合によっては行動 抑制を行なっている。その結果、当病棟におい て平成20 年度は転倒・転落の重大事故は発生 してない。
また、転倒・転落事故はその対策を解除する ときは一時もなく、一職員が頑張るだけでは防 止することができず、職員が一丸となって取り 組まなければならない。さらに転倒の要因分析 をおこない、要因毎の対策・防止策を考えてい く事が重大事故防止に繋がると考える。当病棟 では、リハ・看護・介護の職種が連携を取り転 倒・転落対策に取りくんでいる。特に転倒・転 落に関しては介護福祉士の対応が非常によく教 育されていて、リハスタッフと協同で小道具作 りをして対応し、転倒・転落防止を行なってい る。回復期でADL の拡大と共に転倒は伴って くるが、職種間が連携を取り、転倒・転落防止 をはかり、患者のADL の拡大を積極的に行な い、自宅復帰、社会復帰への支援の実践をして いくことを考える。
今後の課題として
1.高次脳障害患者の予想外の行動変化による転倒・転落への対応
2.転倒・転落事故が予測される患者へ、リハビリを提供し能力を上げていく過程での転倒防止策
3.体幹抑制はしないが行動抑制を行う際の患者の評価
4.機能回復・運動療法

南部病院リハビリテーションセンター科長
神谷 喜一
骨粗鬆症と診断された高齢者は、ちょっとし たことで骨折してしまう場合があります。高齢 者の寝たきりの原因のうち約20 %が骨折とい われており、骨折をきっかけに歩行能力の低下 や認知症の発症、再転倒による新たな骨折を恐 れて外出頻度が減る等といった様々な要因で行 動範囲が狭くなり日常生活に制限を来します。 その影響により心身機能の低下、骨密度の減少 と更なる悪循環に陥ってしまいます。
骨折の治療手段として保存療法と観血療法が あるのですが、長期安静による筋力や心肺機能 の低下といった廃用症候群、認知症等の2 次的 合併症を防ぐために、手術が可能であれば積極 的に観血療法が用いられます。リハビリも出来 るだけ早期より介入し、早期離床を目指してい きます。
大腿骨頸部骨折術後プロトコール
- 術前:持続牽引
- 術後当日〜:リハ開始
- 術後2 日目〜:創部問題なければシャワー可
:全身状態良ければベッドから離床し、立位・歩行開始
- 術後14 日前後:抜糸、退院
急性期リハから回復期リハへ移行していく際 に鍵となるのが病院間の連携です。地域連携パ スに沿って継続したリハビリテーションを実施 していきます。
主なリハビリ内容として
・温熱療法(ホットパック)…疼痛緩和目的
・運動療法
1)筋力維持・増強訓練
…体幹、下肢の筋力を鍛えることにより歩 行能力の回復、再転倒予防目的訓練内 容として、抵抗運動や負荷強度の強い運 動は不適当で、負荷の少ない無理のない 運動を、時間をかけて取り組むことで十 分な効果が得られると言われてます。骨 に直接荷重をかける運動で効果的に骨密 度を増やすことが可能ですが、筋肉を鍛 えることにより間接的な運動負荷でも骨 密度を増加させることも可能といわれて います。
2)バランス訓練
…坐位時、立位時、歩行時における姿勢の 安定性確保、転倒予防目的
3)ストレッチ
…転倒時動作の改善・抑制効果を目的に体 幹、下肢の筋に施行
4)ADL(日常生活動作)訓練
…歩行、移乗動作をはじめ更衣、整容、排 泄、入浴動作時における介助量軽減、自 立獲得を目指します。
その他、自宅復帰を目指して
・家屋環境の整備(段差解消スロープ、手すり 設置等)が重要になってきます。
・福祉用具の選定(ベッド、シャワーチェア ー、四点歩行器、杖等)が必要です。
・自分にあった適度な運動を継続して頂くために 散歩や買い物、家の掃除、洗濯、炊事等の家 事動作をはじめ個々の日常生活に着目し、そ の動作に必要な運動が活かせるよう自主トレ ーニングの促し、指導をしていきます。
・更に社会交流・参加を目的に通所リハビリの 利用や自治区への参加促進が必要です。
退院後の生活を見据えて、心身機能の回復や 生活環境を整える事により、また社会資源を提 供していくことがより良い人生に繋げられると 考えます。