��18 �ꌧ��t������J�u��
��炮���N���������Ȃ�
�`���茒�f�Ń��^�{��I�`

�����@�ʈ�@�C

����͉����p�V�t�B�b�N�z�e�������̊Ԃ� �ς��A����21 �N1 ��31 ���i�y�j���j�̌ߌ�1 ��������J�Â���܂����B����ꏊ���ς���� ���ŁA�Q���l��������̂ł͂Ȃ����Ƃ����s�� ������܂������A���ۂɂ�400 �l���Q���l ���ʼn��͖��ȂƂȂ�lj��̍��Ȃ����đΉ� ����Ƃ�������ł����B����͓��茒�f�J�n�� �N�x�Ƃ������ŁA����̓��茒�f��U��Ԃ��� �����Ă����ۑ���p�l���[�̊F����ɂ��b���� �������A�c�O�Ȃ���ᒲ�ƂȂ�������̓��茒 �f��f���̎��N�x�A�b�v�Ɍ��т��Ă������� �Ƃ����̂��_���ł�����܂����B���ꌧ�Ń��^ �{���b�N�nj�Q�����ƂȂ��Ă��鎖�͘_��� ���Ȃ��Ƃ���ł���܂����A���ꂪ�����t���a �iCKD�j���o�Đl�H���͓����Ɏ����Ă��鎖 ��A�S����̑������Ɍq�����Ă��鎖���͏[�� �ɔF�m����Ă��܂���B����̌������J�u���� �l�X�Ȉ�Ï��̒��������ł����A�h�{ �m��ɂ��h�{�w���⌒�N�^���w���m��ɂ�� �^���Ö@�̎���������܂����B�p�l���[�̊F�� ��̍u���ƃp�l���f�B�X�J�b�V�����̊ԂɌ��N �^���w���m��̊F����ɂ��������܂܂ŏo�� ��v�`�̑��̃R�[�i�[�����胊���N�[�[�V���� �����˂Ĕ��ɍD�]�ł����B���ꌧ�̓��茒�f �͑��{���ɔ�r���Ĕ��Ɉ����ŁA���e�̏[�� �������̍������f���s���Ă���̂������ł��B ����͉��ꌧ��t��ɂ��W���_�ʂ����� ���������ɑ傫���Ǝv���܂��B�ʌ��f�ƏW �c���f�̌��f���e���������x���ŋψꉻ���A�� �i���Ɋւ��Ă�������Ƃ��ē���������s���Ă܂���܂����B���ۂ̉^�c�ɂ������Ă��A ����ɂ�����l�X�Ȗ������ɂ�����A�X�ɍ� ��̉ۑ�̏W�ς��n���ɍs���Ă��܂����B���� ����t��̊����͂��̑��{���ɗނ��݂Ȃ��[�� �������茒�f��ł���b�ɂȂ��Ă���̂� ���B�[���������̍������茒�f�̈ێ��́A���� �͂܂��[���Ȏ�f���Ƃ��Ă͂˕Ԃ��Ă��Ă͂� �܂��A�����ꌧ���ɗ�������Z�����Ă��� �ׂ̕K�v�����ł���ƍl���Ă���܂��B������ ���͂���1 �N�ԓ��茒�f�Ɋւ��A�l�X�ȕ��� �̗l�X�ȕ������̓��茒�f�̉~���ȉ^�c�Ɋ��� �����Ă��������Ă��鎖���ɋ����M���Ȃ�v�� �����Ă���܂����B������[���������茒�f�� �����ɒ��邱�Ƃ��A�����̌��N���ێ����i ������ׂɕK�{�ł���Ɗm�M���Ă���܂��B�S ���Ɍւ��f���炵�����茒�f�W���_��̘g�g �݂�������ƂȂ��A�W�e�@�ւƋ��͂������� ���獡��������Ɏ��̍������茒�f����� ���߂ɓw�͂��Ă��������Ƃ����M���v����V�� �ɂ����������J�u���ł����B
�u���̏��^
���茒�f�́A�����̃��C�t�X�^�C���� �ς����D�ƂȂ�
�`����������얞�A����䂭�l�ނւ̒���`
�Y�Y�����a�@���f�Z���^�[��
�v�c�@�F��Y
���a43�N�@�����w��w����w�ȑ���
���a48�N�@�����w��w��R���ȏ���
���a52�N�@���u�t
���a54�N�@�x�R���ϐ�����a�@����
���a57�N�@�Y�Y�����a�@�A���ȕ����Y�Y�s�ݑ���x���Z���^�[��
�@�@�@�@�@�@�@���A�a�Z���^�[�����o�Č��݂Ɏ���
�w����@���{���Ȋw��F���
�@�@�@�@�@�@�@���{���A�a�w�����
1�D�����������A�����Ė������郁�^�{���b�N �nj�Q
����18 �N�x�������N�E�h�{�����ɂ��A 40 �` 74 �ł݂�ƁA�j����2 �l��1 �l�A���� ��5 �l��1 �l���A���^�{���b�N�nj�Q�܂��͗\ ���Q�ɊY������Ƃ����B�ߍ��Ȏ��R�ƌ����� ���A���X�A���̂Ȃ��ŁA�ǂ̂悤�ɂ��ĐH �āA�����Ăǂ��������тĂ������݂̂��l���Ă����������̑c��ɁA���́u�얞�Љ�̏o ���v�͑z���ł��Ȃ��B
�č��������O�̌����̐ێ�J�����[�͂��悻 �{�y��80 ���ȉ��A�Ƒz����₷���Ђ� �ς��A�������тĂ�����l�����̕��݂������A �S���ғ��{��̍ő�v���ł������B�������A�� ���̐ێ�ʂ͉��ĕ��݂ƂȂ�얞��i���ƂȂ� ���B�����āu����������̐_�b�v�͐Ƃ������� �����B
2�D���茒�f�ł킩�郁�^�{���b�N�nj�Q���� �������邩
���^�{���b�N�nj�Q�̓}�N���I�ɂ݂�ΑS�g �̓����d����10 �N�ȏ㑬���i�s���A�����Ƃ� ��B���Ȃ킿���^�{���b�N�nj�Q�͘V���𑣐i ����̓����J�j�Y���̊��������Ӗ�����B�V�� �́u�זE�̘V���v�����łȂ��u�����̌̂��� ���̘V���v�ł���B���݁A�Ȋw�I�ȍ��������� �Ƃ����Ă���V�����́u�_���X�g���X���v�� ��сu�V����`�q�}���ƒ������i��`�q������ ���v�ł���Ƃ����Ă���B�����������^�{�� �b�N�nj�Q����������Ӌ`�́A�V���Ɏ��~�߂� �����A���Ƃ����������тĂ��A�ӔN��S�؍[ �ǁE�]�����E�������s�S�ƌ��������ĕ�炷�� �ł͂Ȃ��A�����Ă������͌��N�Ȃ܂܂̐l�����y���݂����B�c���ꂽ20 �` 60 �N�Ԃ̐l���� �ǂ����N�ɐ����邩�Ƃ�����_�ɏW���B
3�D���ꌧ�̓��퐶���̕��i�Ɠ��茒�f�ɂ�� �ϊv
�u�ԎЉ�ɂ��̂����Ȃ������v�u���b �̉ߏ�ێ�������炷�g���������v�u�ߏ�Ȓ` �����Ǝ������܂ނƃ`�����v���[�����v�u���� ���E�t�@�[�X�g�t�[�h���{��v�u����^�Љ�� �[�H����H�������H�����v�u���݉���̃C�x ���g�̑����v�u�T�R�`�S������݉����q�g �B�v�u�c�ƎЉ�v�����͂��ׂă��^�{���b�N �nj�Q�ǂ����V���𑣐i������B���̎Љ� ���ǂ��ϊv���邩�H
�ߓx�̗����ɂ������A���y��H�~�Ƃ��� �~�]�������Ƃ��K���ƈʒu�Â������l�ς� ���Ƃł́A��������֒f�̖̎��̖����o���� �l�Ԃ͂�����ȒP�ɑł��̂Ă邱�Ƃ͂ł��� ���B�H�����s���E�g�̊����s���𗥂���ӎ��E ���l�ς̓]�����K�v�B���Ȃ킿�A�V���𑣐i�� ���郁�^�{���b�N�nj�Q�ɂȂ�Ȃ��u�H�v�� �u�g�̊����s���v�̑I��͂����ƁA������ �Ԃ����Ȃ��œ������Ƃ��ł���E����̐� ���ł���B���{�H�����̍ő�̈�Y�́u������ �Ȃ����������v��������Ȃ��B����� �uHARA-HATIBU�v�Ƃ��đS���E�֔��M���� ���������̂�������Ȃ��B
4�D���茒�f���n�܂��Ă��鍡�A�킽�������� �����̓]�����ɐ����Ă���
�n�����g�����ۂɏے������悤�ɑ�ʐ� �Y�A��ʏ���A��ʔp����O��Ƃ���Ή��G�l ���M�[���p�̒n�������^�����͏I���̎���ɓ� �����A�������\�N�ő��z���⎩�R�Ƃ̋����ɂ� ��n�㎑���^�����ֈڍs����Ƃ����B
�������A�n�㎑���^�����ֈڍs�����Ƃ��� ���A���������������Ă���얞�Љ�����ɍ� �������Ƃ͍l���ɂ����B���̌��J�u���͗\�h ��w�̍őO���Ŋ���茴�搶�A���A�a�E�� �^�{���b�N�nj�Q�̗Տ��⌤���̑��l�҂ł� ��c���搶�A�����̂ŏZ���ƌ����������茒�f �𐄐i���Ă���ی��t�̈��搶�A����̐H�� ��������߁A���P�����Ă��錧�h�{�m ��̊Ǘ��h�{�m�̓c��搶�ɂ�錧�����J�u�� �ł���B
�����E�����E�V���������E��@�ӎ����u�m�v ����āA�ӎ���ς��A�����ĐH�s����g�̊��� �s����ς���B�얞��i�����ꂩ��A���^�{�� �b�N�nj�Q�����̓���T��A�S���ɔ��M���� ���B����A�����̌����̊F�l���Q������邱�� ��ؖ]���܂��B
���^�{���疝���t���a�@�����ĐS���a��

��Ö@�l�G����c����@�@��
�c���@�G��
���a62�N�@������w��w����w�ȑ���
����6�N�@������w�����a�@��2 ���ȏ���
����10�N�@���ꌧ���암�a�@���Ȉ㒷
����14�N�@�L���钆���a�@���A�a�E�����K���a�Z���^�[����
����17�N�@�c����@�@��
�얞�҂̊������j���Ƃ��f�g�c�őS����ł� ��킪���̃��^�{���b�N�V���h���[���i���^ �{�j�̕p�x�𖾂炩�ɂ���ړI�Œ������s���� �����B�ΏۂƂȂ����W�c�́A�L���钆���a�@�� �l�ԃh�b�N��2003 �N5 ������2004 �N3 ���܂� �Ɏ�f����30 ����79 �܂ł̒j�����킹�� ��7,000 �l�ł��B
�e���^�{�\���v�f�̗z�����́A��������j�� �ō����A�����얞�A�������A���������b�A���� ���̏��ƂȂ�܂����B���^�{�̕p�x�͏����ł� ����ɔ����ď㏸���܂������A�j���ɂ����Ă� ��N�w���܂ޕ��L���N��w�ō��p�x�ł����B�� �^�{�̕p�x�͑S�̂ŁA�j��3 0 . 2 �� �A���� 10.3 ���ł���A�j���ŗL�ӂɕp�x�������Ƃ������ʂł����B
�܂����̏W�c�Ń��^�{�Ɩ����t���a�iCKD�j �̊֘A�ׂ��Ƃ���A���^�{�\���v�f�̐��� ������ɏ]����CKD �ɂȂ�댯�����㏸���� �����i�}1�j�B����̓��^�{��CKD �����ʂ̊� �Ղ����\�����������܂��B
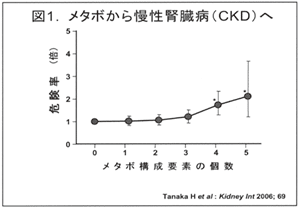
����ɓ��W�c��3 �N�ԒǐՒ��������Ƃ���A ���^�{�̑��݂͏�����1.8 �{�A�j����2.5 �{�S ���a�̗ݐϔ��������㏸�����܂����i�}2�j�B
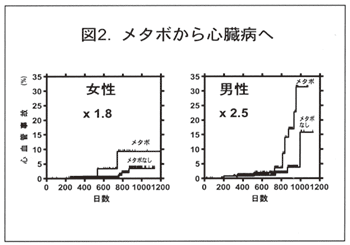
�ȏ�̎�������A�얞���匳�ƂȂ胁�^�{�� CKD ���������A���̌��ʐS���a�Ɏ������Ɛ� �@����܂����B
���݂ł�����́A���N�I�ȍ���҂�S���҂� �������Ƃ��ėL���ł��B�������Ȃ���A����� �͎�N���璆�N�w�Ɏ���܂ō����b�H�ɑ�\�� ��鉢�Č^�̃��C�t�X�^�C�����Z�����Ă���A �얞���Љ���ɂȂ��Ă���̂͊F�l�悭���� �m�̒ʂ�ł��B2005 �N�̓s���{���ʕ��ώ��� �ŁA�����͑S������������܂������A65 �Ζ� ���̎��S���ł͒j��1 �ʁA����5 �ʂƑ������� ���S����ƂȂ��Ă��܂��B���͂⒴����҂̒������ŁA������Ⴂ����̒����X����₢�� ��Ȃ����Ԃƌ����܂��傤�B
����̓��茒�f�̐��ۂ��A���N�������ꕜ���� ���������Ă���Ƃ����Ă��ߌ��ł͂���܂���B
���茒�f�ɂ�郁�^�{�U���@

�ߔe�s��t����K���a���f�Z���^�[������
�茴�@�i�C
���a62�N�@�H�c��w��w����w�ȑ���
�@�@�@�@�@�@�@������w��w���@�]�_�o�O��
����8�N�@�R�y���n�[�Q����w���w
����13�N�@�ߔe�s��t��@�����K���a���f�Z���^�[������
�E���{�]�_�o�O�Ȋw�����
�E���{��t��F��Y�ƈ�
�E���{�l�ԃh�b�N�w�����
��N����S���ŊJ�n�������茒�f�́A���^�{ ���b�N�V���h���[���𐧈����邽�߂̌��N�f�f �ł��B����܂ł̌��N�f�f�Ƒ傫���Ⴄ�_�́A ��f�̍��ڂ��͂��ߌ������ڂ���т��̔���� ����S���œ��ꂵ�����Ƃł��B����Ɍ��ʂ��� �Ƃɕی��w�����Z�b�g�ōs�����ƂŁA�g�E���^ �{�h��ڎw���Ƃ������m�ȖړI�����������N�f �f�ł��B
��ʂɂ́g���^�{�h�C�R�[���g�얞�h�Ǝv�� ��Ă��܂����A���m�ɂ̓��^�{���b�N�V���h�� �[���Ƃ͔얞�������N�����₷���������A���� �ُ�A�����l�ُ�Ȃǂ����łɋN��������Ԃ� �w���܂��B����䂦�A���^�{���b�N�V���h���[ ���̐f�f�́A���N�f�f���瓾����g�̌v���� �����A��������ƌ��t�����̌��ʂ𑍍����ď� �߂ĉ\�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
���茒�f�̖�f���ڂ͑S����22 ���ڂ��� �i�\�j�A�H�K���E�^���K���E�i���E�����E�x�{ �Ɋւ��鐶���K���̎���ł��B����9 �Ԗڂ̎���́A�u20 �̎��̑̏d����10kg �ȏ㑝�� ���Ă��܂����v�A13 �Ԗڂ̎���́A�u����1 �N�Ԃő̏d�̑������} 3kg �ȏ゠��܂��� ���v�Ƃ������̂ł����A����2 �̎���͂� �Ă��d�v�ŁA�ߋ�����ŋ߂̑̏d�̕ω���m �邱�Ƃ��ł��܂��B�܂�A�����̐H���Ő� �悷��G�l���M�[�ƁA�^���Ȃǂŏ����G �l���M�[�̕��ϓI�ȃo�����X���킩��܂��B ���̃o�����X���[���Ȃ�Α̏d�͕ω������A �v���X�Ȃ�얞���A�}�C�i�X�Ȃ猸�ʂ��Ă� ���Ƃ������Ƃł��B���̃G�l���M�[�o�����X �i�J�����[�o�����X�j�̕]���͍ł��d�v�Ȏ� ���ł��B
���^�{���b�N�V���h���[���ɂ�錟���l�� ������P���邽�߂ɂ́A�얞���������Čl �ɍ������̏d���ێ����邱�Ƃ��������܂� ��B�������Ȃ��猸�ʂ���ʂȕ��@��H�ނ� ��������A����H�������Ċ撣��Ƃ����� ���ȒZ���I�Ȃ�肩����I������Ǝ��s���� ���܂��悤�ł��B�ނ��뒷���I�Ȋϓ_�ŁA�� ���̏K���������������Ƃ����l����������t ���邱�Ƃ����������߂ł��B1 ���̐H���ɂ� ��ێ�J�����[������2,000kcal �Ƃ����� ���A���̈ꊄ����200kcal �ł����A���̒��x�� �M�ʂł�1 �N�Ԓ~�ς����7 3 , 0 0 0 k c a l �i200kcal �~ 365 ���j�ƂȂ�A�̎��b1kg �� 7,000kcal �Ȃ̂ŁA�̏d10kg �ɑ�������M�� �ɂȂ�܂��B�܂藝�_��́A�������Ȃ�ʕ� �㕪�ł��\���Ȍ��ʂ���킯�ł��B
���茒�f�ɂ�郁�^�{�U���@�Ƃ��āA�u���� �̐l�����茒�f����f���ă��^�{���b�N�V���h ���[���̗L����]�����邱�Ɓv�A�u���N�f�f�̌� �ʂ����ƂɖڕW�̏d��ݒ肵�A���݂̐H�K���� �^���K���̉��P�̌v��𗧂Ă邱�Ɓv�A�u������ �Ȃ����@�Ŏ��s�E�p�����邱�Ɓv��3 �_������ ���܂��B
���茒�f�����N�x���I���܂������A���ꌧ�� �̌��f��f���͂��Ȃ�Ⴂ���Ƃ��\�z����Ă� �܂��B���ケ�̓��茒�f�Ɍ��������ȏ�ɒ��� ���A��f����S����ɍ��߂�Ȃ�A�g������ ���h�����������̂��̂ƂȂ�ƍl���Ă���܂��B
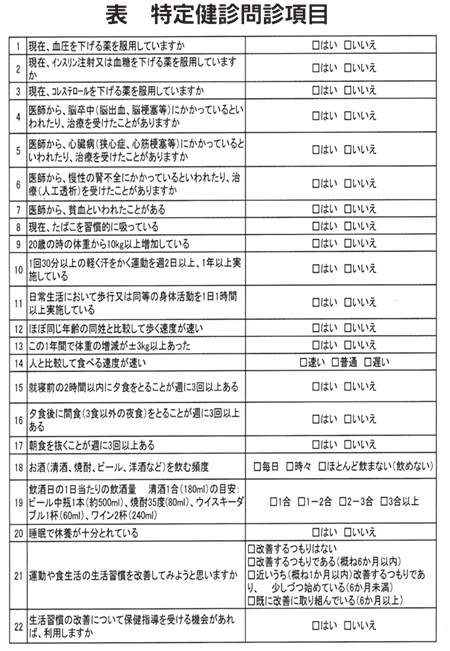
100 �L���J�����[�̐헪�@�`���^�{�͗\�h�ł���`

���ꌧ�h�{�m���@����s�����s�����N�ە��劲
�c��@���q�q
���s�Ɛ��Z����w����
���s�Ɛ��Z����w�h�{��C�ے��C��
�Ǘ��h�{�m�o�^�i���a57 �N�j
���ꌧ�h�{�m����i����12 �N�j
�s����ی��w���t
����ی��w���͐����K����U��Ԃ��D�̃`�����X�ł��B�X�ɉ��������k�����A���N �I�ȐV�����������܂�ς��M�d�Ȏ��Ԃ� ���B����ی��w���̈ē��̂��������͂��Љ�� �֑������^�т��������B�g���P�̃|�C���g�h�� �x�����܂��B
�T�D�얞�����Ń��^�{�\�h
�H�ׂ�Ƃ����{�\�I�ȍs�����A���ɓ������b �̒~�ς������A�l�X�Ȍ����ُ���܂��B ���̃��X�N�̏d�Ȃ�����Ԃ���u��������ƁA �]�����A���A�a�����Ǔ��ɂȂ����Ă��܂��� ���B�������A���̓����͐ێ�G�l���M�[���� �i�얞�j�ɂ���A�����ς��A�i�s��}������ ���Ƃ͉\�ł��B
�U�D�얞�ƌ��ʂ̃V�~�����[�V����
�Ⴆ��1 ����100kcal �]���ɐێ悵������� 1 �N��ǂ��Ȃ�ł��傤�B
���悻5kg �̑̏d�����ɂȂ�܂��B�i�̎� �b1kg ��7,000kcal �ɑ����j
���Ȃ���1 �N��͂ǂ��ł��傤���B3 �N��A 5 �N��͂ǂ��ł��傤�B
�V�D100kcal �̐헪
�얞�͖����̐H�����̐ςݏd�˂������� ���܂��܂��B�ʂƕp�x���ۑ�ł��B
�C�ɂȂ�g�߂ȐH�i�G�l���M�[�ʂɎ��_�� �����A�헪������Ă݂܂��傤�B
�G�l���M�[�������g�̊������d�v�ȃJ �M�ł��B
�W�D�G�l���M�[���x�o�����X�̉��P
�����4 �̍��ڂɂ��Ă̒�Ăł��B
������ꂻ���ȁA���s�ł������ȉ������� �Ƃ����܂��傤�B
- 1�D��H�ێ�ʂ̔c���F�K�ʐێ�
- 2�D�ԐH�K���̉��P�F�悭�H�ׂ�َq�ނ� �G�l���M�[�ʂ̔c��
- 3�D�����K���̉��P�F�A���R�[���̃G�l�� �M�[�ʂ̔c��
- 4�D�����ێ�ʂ̔c���F��ނƃG�l���M�[ �ʁE�����g�p�ʓ�
�X�D�m���ɐg�̂��ς��I
��������s�����N�����Ă݂܂��B�m���� �g�̂ɕω����N����܂��B
2,000 ��ނ����݂���H�i�ɂ͂��ꂼ����� ������A�G�l���M�[�ʂ�h�{�����قȂ�܂��B �������A�悭���ɂ���H�i�͌����Ă��邽 �߁A�C�ɂȂ�H�i���i��A�C�y�Ɂukcal�v���` �F�b�N���Ă݂܂��傤�B�܂��p���o�������Ȃ� �Ƃ������܂��傤�B
�������ɒ~�ς��ꂽ�̎��b���}���Ɍ��炷���� �͊댯�ł���A���o�E���h�̉\���������B�� �ʂ͐H��^���̑��A�X�g���X�̉���������Y ���𐮂��邱�Ƃ��d�v�ł��B
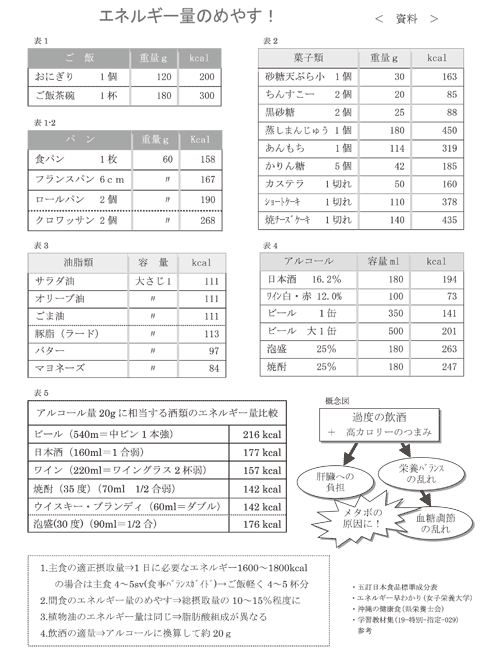
���茒�f����f���Ė����t���a�iCKD�j��\�h���悤
�`���������̏�́A���茒�f�ł��`
���s�ی��t�@���@�D�q
�������N�@���ꌧ���ߔe�Ō�w�Z����
����5�N�@���ʏ鑺����ی��t
����18�N�@���s�����ی��t
1�D���茒�f�́A��f����܂������H
����20 �N�x4 �����A���茒�f����ی��w ���Ƃ����V�������f�V�X�e������������܂� ���B�傫���ω������̂́A
1�j���{��̂���Õی��҂ɂȂ������Ɓi�F���� �̎����Ă���ی��蒠�̎�j�ł��B
2�j���́A����24 �N�x�̎�f���ڕW��65 ���ƌf ���A���ꂪ�B���ł��Ȃ���y�i���e�B���� �����Ɓi��҂̕��S��������d�g�݁j����� ��҈�Â��x����x��������������Ȃ� ��Ȃ�Ȃ��Ȃ�܂��B
���̋߂���s�ɂ����ẮA�������N�� ���ɉ������Ă���40 �` 74 �̏Z�����Ώ� �ɂȂ�܂��B����20 �N12 ��25 �����݁A�� �ێ�8,513 �l�̂������茒�f����f�������� 2,100 �l�Ŏ�f��24.7 ���ł��B
�c��6,413 �l������f�ł��B���Ȃ݂ɓ�� �s��20 �N�x�̖ڕW��35 ���ł��B
2�D���̓��茒�f����f����̂��H
�u�ǂ����ɂ��Ȃ��̂ɁA���т������������� ���̂ɉ��Ŏ�̎��̏���ł���v�u�ɂ��� ������a�@�ɍs����v�Ƃ������t�����ɂ��� ���B�ɂ��Ȃ�����ǏłĂ���ł͑�ς� ���B��Ô�͍��z�ɂȂ�A������������������ ��܂��B���łɁA�t��������������l�H���͂� �Ȃ��Ă��܂����l�̘b���Ă݂܂��Ɓu���� �ŕa�@�ɍs���Ɠ��͂ƌ����ڂ̑O���^���Â� �Ȃ����v�u���f���Ă킩�������� �Ă���悩�����v�ƕK������̌��t�����ɂ� �܂��B���B�͂��������l���o���Ă͂����Ȃ��� ����f�ґ�ɗ͂����Ă��܂��B
�����������͗\�h�\�Ȓi�K�Ŕ��������� �����茒�f�ł��B
���茒�f�́A���^�{���b�N���f�Ƃ����C���[ �W�������Ǝv���܂��B�얞����N����a�C��\�h���邱�Ƃł����A�����ЂƂ��厖�ȍ������� ���Ă��܂��B
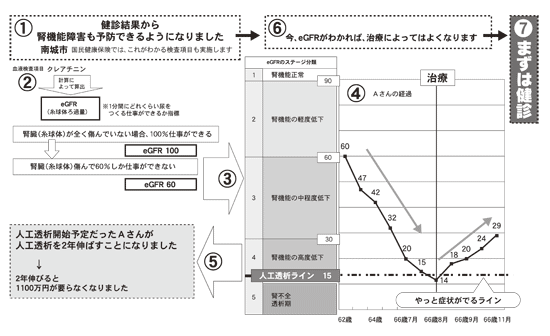
3�D�厖�ȍ��ڂƂ́H
�Ȃ�ƁA�����t���a���ǂ������킩���ł��B
����19 �N2 ��24 ���A��14 �����J�u�� ��炮���N���������Ȃ�u�����t���a�v�`�Ȃ� ��������̐t�s�S�`�̃e�[�}�ōu�����Ă����� ���o���Ă�������Ⴂ�܂����H
����́A���͂��������f��f�����Ⴂ�A���� �������厖�Ƙb���Ă��܂����B
����̓��茒�f�ł͖����t���a������ł��A �ǂ̒i�K����������悤��1 �` 5 �i�K�̃X�e�[ �W�ŕ��ނ���ƂĂ��킩��₷���w�W�ƂȂ��� ���܂��B�X�e�[�W���ނ́A���t�����̍��ڂ̌� ���N���A�`�j���Ɛ��ʁA�N��Ōv�Z����e- GFR�i�������h�ߗʁj�ł���킵�܂��B�t�� �̔\�͂��ǂꂭ�炢���H�܂��A�����\�����ł� ��悤�ɂȂ��Ă��܂��B
���āA���Ȃ��̃X�e�[�W�͂ǂ̒i�K�ł��� ���H���f����f���Ȃ���킩��܂���B
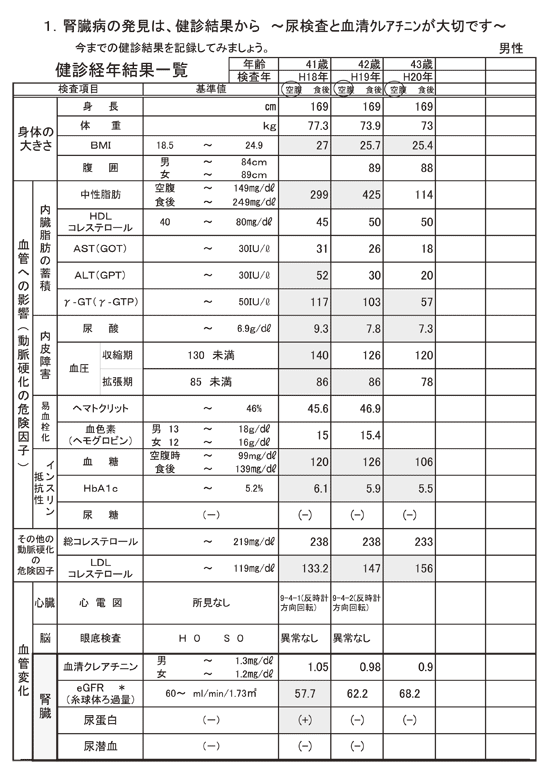
���k��`�������J�u�����I���ā`
���ʈ䗝���@�����̋v�c�搶�B�����̌��J�u �����I���Ă̂����z�����肢�������܂��B
���v�c�����@����̌��J�u���̎�|�́A���� ���f����������̕��ɔF�m���Ă��������āA�� �f���Ă��������Ƃ������̂ł����B
����ł͎�f�������Ȃ����ƂƁA���茒�f�� ��ʂ̕��X�Ɏ��m�O�ꂳ��Ă��Ȃ����߂ɂ�� ���̂ł����B�p�l���X�g�̐搶���̐����͂Ƃ� ���悩������ł����A�u������ɗ����� ���͂�����x�ӎ��̍������Ȃ̂ŁA���Ȃ��l�� �ǂ����邩�����ł��ˁB
�V�����Ŏ��m���Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ǝv����ł� ���E�E�E�B
���c���搶�@�l�͍����͂��܂���茒�f�ɂ� �G��Ȃ��ŁA�Ȃ����^�{�K�v���������A �ԐړI�Ɍ��f�̎�f�����オ���Ă��炦��� �v���Ęb�����܂����B��ꂩ��̎���̒��ɍ� ���ۂɎ�f���Ă���������茒�f����f������ �����ǂ��̂��Ƃ��������Ȏ��₪��������ł� ���A�{���͎�|���猾������Ⴂ�l��a�@�Ɋ| �����ĂȂ��悤�Ȑl�ɐ���s���Ă��炢������ ����ˁB
���茴�搶�@�����́A���^�{�U���@�ɂ��� �b�����܂����B���ꌧ�̃��^�{���b�N�V���h�� �[�����ǂ����邩�Ƃ������Ƃɂ��āA�悸�� ��ԖڂɎ�f�����グ�邱�Ƃ����̍U���ɂȂ� �Ƃ������b�����܂����B��f�҂̃��`�x�[�V�� �����ǂ��グ�邩�Ƃ����_�ɂ��ẮA����� �͊m���Ɍ[�����K�v�ł����A��Ë@�֑��̎�f ���𐮂��邱�Ƃ��d�v���ƍl���܂����B�܂��A�Ⴂ�l�B���ǂ������烁�^�{���b�N�V���h ���[���ɂȂ�Ȃ��悤�ɂ��邩�Ƃ����_�ɂ� �ẮA���w�Z�̍����琶���K���a�͎n�܂�̂� �g�H��h���s���ƂƂ��ɁA�Љ�l��ڑO�ɂ��� ���Z���ɑ��Ă��[���������d�v���Ɗ����Ă� ��܂��B
���c��搶�@�����́A100�L���J�����[�̐헪 �Ƃ����������ł̕������Ă��������܂����B
�h�{�m��̗���Ō��ꃌ�x���̘b�������Ă� ����������ł����A����̓��茒�f�E����ی� �w���͎s���������S�ƂȂ��Ă���Ă���̂ŁA ���̗���Řb��������A�������g���[���ł� �����ȂƎv���܂����B
�����搶�@�����̍u���Ŏ�f������Ɍ��� �Đ����������ȂƎv���܂��B�s�����ō����Ă� �邱�Ƃ́A���Ò��̕������\���邱�Ƃł��B�� �͎��Ò��̐l�������炫����Ǝ�f�����Ȃ��� �Ƃ����Ă��āA�������͂�����Ƃ��������� �����Ȃ��Ă͂����܂���̂ŁA���Ò��̕��ɂ� �Ăт������s���Ă��܂����A�܂����͈�t�哱 �^�Ȃ̂ŁA�搶����u�Ȃ�œ������ڂȂ̂Ɏ� ����́H�v�ƌ���ꂽ����Ȃ��Ƃ������� ������ł����A�茴�搶����قǂ���������� �����������悤�ɁA��Ë@�ւɐ����ɉ�낤�� �v���Ă���܂��B
���c���搶�@��f�����オ��Ȃ��ꍇ�̃y�i ���e�B�̎�������̂Ŗl���������܂����ǁA�{ ���͈�x����������Ƃ������l���̌��������� ����ˁB�����ɂ������g���ė~�����B
�����搶�@�����Ȃ�ł��B���ꂪ�厖�ł��ˁB
���ʈ䗝���@���茒�f�Ɋւ��ẮA�Ⴆ�Ε� �ʂ̐f�Âƈꏏ�ɍs���āA�^�_�Ŏ���� �G�ꍞ�݂Ŏ��ɂ��ւ�炸�A�f�Õ�V���� ��������A���Ȃ������肷��킯�ł��B
���܌��������Ƃ́A����ō�������\���� ����܂��B�����Łu�^�_���Ƃ���������Ȃ� ���v�Ƃ������ƂɂȂ邱�Ƃ��l�����܂��B�� �̕ӂ�������Ɛ蕪���Ȃ��Ƃ����܂���ˁB
���A�F�X�b�����f������ł����A���̃t�� �A����F�X���₪�o�Ă���܂������A����ɂ� ���Ă͂������ł����ł��傤���B
���v�c�����@CKD ����茒�f�A�H���A�^�� �Ö@�Ƃ����Ă��Ȃ��Ȃ�����A�l�I��30 �� �b�����Ă����������邱�Ƃ͓���Ǝv���܂��B
�ŏ��̍��ڂōő�̌��ʂ�������悤�Ȃ� �̂�����Ηǂ��̂ł����A�����A��Ԃ̖��� �얞�ł���A�얞���S�Ă̐����K���a�̓���� �ɂȂ��Ă���̂ŁA�얞�ɂȂ�Ȃ����߂ɂǂ� ����悢���l���Ȃ�������܂���B
�g���茒�f�̎�f����S���i���o�[�����ɂ� �悤�h���L���b�`�t���[�Y�ɂ��邱�Ƃ����� �ǂ����Ƃ��Ǝv���܂��B��������ɂ��Ă݂�� �����茒�f���Ă��炦�Ύ����̓������b�� ���Ă���藝����[�߂�Ǝv���܂��B�Ƃɂ� ����f���������Đ悸���Ԃ�m���Ă��炤���� ����n�߂āA�얞�ɓ����Ă������ق����A�v�� �[�`���₷���Ǝv���܂��B�h�S���i���o�[���� �ɂ��悤�h�Ƃ�������Ȃ�ƂȂ����̋C�ɂȂ� �Ȃ����ȂƂ������������܂��B
�{���̉��̎���͐F�X����܂������A�܂� �܂��A���茒�f�ɂ��Ď��m�O�ꂪ�K�v���Ɗ� ���Ă��܂��B
���ʈ䗝���@�����ł��ˁB�l������͌��܂� �����A��ꂩ��̃��N�G�X�g�̒��ɂ͂����Ǝ� ���₷�����f�ł����Ăق����Ƃ������v�]���� ��������܂����B�u�Љ�ی��̐l�͂ǂ��Ȃ� �Ă���̂��v�Ƃ��A�u�ɂ��������ǎt ���Ă���Ȃ������v�Ƃ��u�ʉ@���Ă��邩��� ���Ȃ��ėǂ��v�ƌ���ꂽ�Ƃ������b������� ���B���̂�����͈�t��܂��͈�Ñ��̎��m�O ����K�v���Ɗ����Ă��܂��B
���v�c�����@���茒�f�ɂ����ĎЉ�ی��̖{ �l��A�}�{�A��}�{�̂����͂ǂ�����̂��Ƃ� �����Ƃ͑S���O�ꂳ��Ă��Ȃ��ł��ˁB���nj� �ۂ��Ɠ��œ����Ă�����͂�����ł����A�� �Ƃ̏ꍇ�ł����茒�f�ŕ⏕���o���Ƃ������ ��A�o���Ȃ��Ƃ���������Ă��̏ꍇ�͍��� �ɍs���ĉ������ƌ����āA��f�҂��ǂ��ɂ� ���Ă������킩��Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�����܂��B
��Ë@�ւł����X�\���ɗ����͂��Ă��Ȃ��� �v���܂��B
�����]�F������
![���]�F������](images/067.jpg)
���f���������Ă��� ���Ƃ��������Ă���� �ŁA���ƌ���t��Ƃ� �A����ɂ����Ęb���� ���A�����|�X�^�[���� �邱�ƂɂȂ�܂����B ������e�f�Ï��ɓ\�� �Ă������������Ǝv���܂��B�܂��A���ꂼ��� ��Ë@�ւ��ł��鍀�ڂ�\������|�X�^�[���� ������̂ł����\�ɓ\���Ē��������Ǝv���� ���B2 �����Ɋe�f�Ï��ɂ����܂��̂ŁA����� �����p����������Η������[�܂�̂ł͂Ȃ��� �Ǝv���܂��̂ŁA��낵�����肢���܂��B
��X�����f�����A�b�v���邽�߂ɂǂ������ �悢���������s���Ă���܂����A���͎��ۂɌ� �f���s���Ă���搶�����������Ă���ł� ��܂��̂ŁA����₷�����f�̎d�g�݂������� �p���t������܂��̂ŁA�������t�ɂ����Ďw �����Ē��������Ǝv���܂��B
����ŕ�����Â炢�Ƃ������Ƃł�����w �E��������������ł��B
���茴�搶�@�ЕۂɊւ���E�ꌒ�f�Ƃ����� �́A�J�����S�q���@�Ŏ��Ǝ傪�J���҂̌��N�Ǘ� �����邱�Ƃ͌��߂��Ă���̂ŁA������x��f ���͗\��������ł����A���͎��c�Ƃł��ˁB ���c�Ǝ҂͎����̎d�����x��ł����Ȃ���� ���܂���̂ŁA�Ȃ�ׂ��Z���ԂŁA���������� ��Ȃǂ𗘗p���āA���ۊ֘A�̎�f�����グ�� �悤�ɂ���Ƃ��������Â��肪�ł���̂ł͂� ���ł��傤���B
���ہA����̃��f���P�[�X�ɂȂ邩�Ǝv���� �����A��X�͐^�a�u�n��̎�����璼�ڗ��� ��āA���f����f���ċA��܂ł̏��p���Ԃ� 30 ���ł�邱�Ƃ��o���܂����B�ߔe�s����50 �l�����ꂼ��30 ���ŏI����ė~�����Ƃ̗v�] ���������̂ł���Ă݂��̂ł����A���ۂɏo�� �܂����B���ꂩ��́A�y�j�̌��f�A���s���� ���Ă����̌��f��A���j���̌��f�ȂǁA�{�� �ɂ����܂Ŏ��v������̂��킩��܂��A�� ������̂ł���A��f�҂̗������l���Ď� �{���Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ƍl���Ă��܂��B
�����搶�@���s���Z���ԂŎ���d �g�݂ɂȂ��Ă��܂��B
���ʈ䗝���@�Z���Ԃœ��茒�f����Ƃ� �����������߂邱�Ƃ͑厖�Ȃ��Ƃ��Ǝv���܂��B
�����A���ۂɎ�f������Ă�����̒��ɂ́A ����͂ɂ��Ȃ�̍�������܂��B
��f�Ɋւ��Ă��A�ЂƂЂƂ����Ă����� ���ƁA����𗝉��ł��Ȃ��������ɑ����B�� �̕��B���E���グ�Ă������ƁA�Ⴆ�Βn��̐f �Ï��������̃`�����l���ɂȂ�Ȃ��Ƃ����Ȃ� �̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
���������Ӗ��ł���t��������Ƃ��Ċe�n ��̐f�Ï����T�|�[�g���Ă������Ƃ����㋁�� ���Ă����Ǝv���܂��B
���{��

��t��S�ʓI�ɋ� �͂���Ƃ������ƂŊe ��Ë@�ւ͎�������� �悤�ɂƍL�Ă��� �܂����B�܂��A���f�� �₷���悤�ɑS�� ������ϑ����ɂȂ��� ���܂��B����͂����ꗿ���������Ȃ������ �܂��A�l���S�𑝂₵������Ƃ����Ď� �f���������邱�Ƃ͖����Ǝv���܂��B�s������ ��͎��ȕ��S��������ƌ��f���������邩��� ���邾�������ݒ肵�Ă���Ƃ̗v�]���������� �Ƃ���A��t������f�����グ�邽�߂ɋ��͂� �Ă��܂������A���́A���f����������ɂ͎� ���̂̔M�ӂ��K�v�ł��B�ł����玩���̂ɂ�� �č�������܂���ˁB
���ʈ䗝���@�l���e�����̂����Ă��Ă��� ���v���̂́A��f�ґ��̔��z�ōl���Ă��邩�� �������Ǝv���܂��B��f�҂����̎�f�������� ���茒�f�𗝉��ł���̂��Ƃ������z������ �āA�p���t����L����s���Ă���̂��A��� �莩���̂ɂ���č�������Ǝv���܂��B�S�Ă� ���ł����A�V�������Ƃ����邽�߂ɂ͎��m�O�� �����邱�Ƃɑ��Ăǂ��������_�Ń��m����� �����d�v���Ǝv���܂��B
�����]�F�������@���͈ȑO�암�����ی��� �ɂ��܂����B�����s�͈�Ԉ�Ô�����āA�� �Ԍ��f�̎�f���������ł��B����ł������ ���Ă܂����B�����ی����������A�s�������� �Ǝ����Ă���邾�낤�Ƃ������ƂŁA���� ����c�̌�30 �������Ԃ��Ƃ��āA���茒�f�� �b�⎅���s�̈�Ô�̘b�Ȃǂ����܂����B
�˂炢�́A���ے������e������ΒS���҂��\ �Z�v�����₷���̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃ���� �����B
���ʈ䗝���@�^�C���X�̕��ǂ���B������ 400 ���قǗ����Ă��v���܂����B���ۉ��� ���炵�Ăǂ̂悤�Ȃ����z���������ł��傤���B
�����lj���^�C���X�ЎЉ��

�ŏ��͓��肪���܂� �ǂ��Ȃ��āA�S�z���� ����ł����A�r������ ��R�͂����Ă��ăC�X ��lj������قǂł����B �Q���҂����ɔM�S�ŁA �e�[�}���炷��Ƃ��� �����Ǝv����ł����A����܂ň�t���s �������g��ł������ʂ��o�Ă���̂ł͂Ȃ� ���Ɗ����Ă���܂��B��N�̓^�C���X�̋L�҂� ���^�{�Z��Ƃ��ă_�C�G�b�g�̘A�ڋL�����f�� ���Ă���܂������A��l�͌����Ƀ��o�E���h�� �Ă���܂����B
�����ڂ̑O�Ō��ĂāA���ɑ�ς��Ɗ����� ����܂����A��͂������͖����A�n���ȓw�� ���K�v���Ǝv���܂����B
����܂ŐF�X���Ă�������ł���܂� ���A�܂��܂��l�I�ɔF�m�x�̍������邩�Ǝv ���܂��̂ō�������͂��Ă��������Ǝv���Ă� ��܂��B
���ʈ䗝���@���茒�f�ɂ��ẮA����� ��Ō��f�������ǂ��Ȃ�킯�ł͖����Ǝv���� �����A���ꂩ����l�X�ȃ`�����l�����g���ė� �������߂�Ƌ��ɁA���m�O������Ď�f���A�b �v�Ɍ��т��Ă��������Ǝv���Ă���܂��B
���{���@�����������ő�̉ۑ�ł��B�{ ���̍u���ő��������S����Ƃ������Ƃ��� �т����肵�Ă���܂����A���̕ӂ��O�ꂵ�� �����ׂ����Ǝv���܂��B���N���������߂��� �Ƃ��ړI�ł��̂ł��̂��߂ɐF��Ȑl�������� ����Ă�����d�g�݂Â��肪�厖����Ȃ��� �Ǝv���܂��B���̂��߂Ɉ�t��Ƃ��Ă��ł��� �����̂��Ƃ͂���Ă��������Ǝv���܂��B
���̂悤�Ȋ��͂����Đi�߂Ă����ׂ����� �v���܂��B
�{���͂��肪�Ƃ��������܂����B
�������z���������������X�̒�����A�����̕��ɃC���^�r���[�������Ă��������܂����̂ŁA���� �����牺�L�̂Ƃ���4 ���̕��̂��ӌ��E�����z���f�ڒv���܂��B
�{��̍L���ɂ����͂��������܂��āA���ɗL��������܂����B
�C���^�r���[1�j�F
�{���̍u����ɎQ������Ă̊��z�����������������B
�@�܂��A����̓��퐶���łǂ̂悤�Ȏ��ɋC�����悤�Ǝv���܂����B
�C���^�r���[2�j�F
��t��ւ̗v�]�����������������B
�i33 �E�����E�Ǘ��h�{�m�j
1�j���E��̕��X����u�������Ƃ��ł��ėǂ������ł��B���^�{�Ǝ����̗v���̃O���t�����킩��₷ ���w�K�ł��܂����B��������L�_�f�^����S�����Ă��܂��B
2�j�u����ɂ��Ă̂��m�点�����W�I�ł��ē����ė~�����B�u���̔N�ԗ\��i�X�P�W���[�����j������� �z�[���y�[�W�Ō��J���ė~�����B
�i30 ��E�����E�a�@�������j
1�j�v�w�ŎQ�����܂����B�v���얞�Ȃ̂ł����S�����ʂ���w�͂������Ȃ��̂ŁA���̐搶���̍u���� �����ď����ł����C�t�X�^�C�����ǂ������������Ă��ꂽ��Ɗ��҂��Ă��܂��B
2�j������A���̂悤�ɓy�E���ɒ���I�Ɍ��J�u�����J�Â��Ă��������Ƃ��肪�����ł��B
�i66 �E�����j
1�j���߂ču����ɎQ�����܂����B���i���猒�N�ɂ͋C�����Ă������ł������A���ȏ�ɊS�������� �撣��Ȃ�������Ȃ��Ǝv���܂����B����̓E�H�[�L���O�𑱂��đ������������Ȃ���Ǝv���܂��B
2�j�����ɂ����炵�āA���낢��A�h�o�C�X���ĉ������B
�i69 �E�j���j
1�j�^���A�H���ɁA���ȏ�ɋC���������B
2�j��҂̃��^�{�i�\���R�j�������Ƃ̂��ƂȂ̂ŁA�E��ł̌��N�f�f�Œ��ӂ���V�X�e���ɗ͂���ꂽ�� �ǂ��Ǝv���B��t��̃A�s�[���Ɋ��҂���B

�v�`�̑�

�h�{�w���R�[�i�[

��ꕗ�i

�^���w���R�[�i�[