九州医師会連合会平成20年度 第2回各種協議会
Ⅲ.医療制度対策協議会(医療政策、地域医療を含む)
副会長 玉城 信光
常任理事 安里 哲好

去る1 月24 日(土)、ホテル日航熊本におい て開催された標記協議会について、以下のとお り報告する。当日は、内田日医常任理事にもご 出席いただき、一部の議題についてコメントを いただいた。
協 議
(1)医療費適正化計画の各県の取り組みと 進捗状況について(福岡県)
<提案要旨>
平成20 年4 月に施行された医療費適正化計 画では、特定健診・保健指導の実施率や平均在 院日数、療養病床数等、平成24 年度までの達 成目標が示されているが、進捗状況をご教示願 う。また、同計画は3 年後の中間評価を経て、 5 年後の計画終了年の翌年に、目標達成状況を 評価し、必要であれば都道府県の診療報酬の特 例を設定することができることになっている が、これに対する医師会としての対策、今後の 進め方等について伺いたい。
(2)医療費適正化計画と関連施策について (佐賀県)
<提案要旨>
下記の点に関する各県の見解と日医の見解を お伺いしたい。
1)医療費適正化計画のペナルティーについて
医療費適正化計画のペナルティーについて は、最終的に地域住民の保険料や医療機関に転 嫁され、このような医療費抑制の仕組みは納得 がいかない。
政府管掌健康保険を運営する協会健保の保険 料率は、現在は全国一律8.2 %であるが、平成 21 年秋までには各都道府県の医療費を反映さ せ保険料率が設定される。
都道府県において保険料率が相違するという ことは極めて不自然で許されるものではない。さ らに、国保を都道府県ごとに一本化すれば、国保の負担が増大し破綻する可能性が危惧される。
2)エビデンスに基づかない特定健診・特定保健 指導制度について
特定健診・保健指導については、予防医学の 立場からは正しいが、住民、受診者には十分理 解されておらず、保険料から巨額の財源を投入 しても成果が懸念される。費用対効果の面から 医療費適正化には結びつかないのではないか。
3)平均在院日数の短縮について
DPC における無制限の平均在院日数の短縮 化が進められ、著明に短くなっているが、再入 院率が高く、患者に必要且つ十分な治療が施さ れているか疑問である。又、平均在院日数の短 縮により、いわゆる救急難民が発生している。 DOC の在り方の検討が必要である。
4)療養病床の転換について
療養病床の転換については、医 療・介護難民が生まれるので、も っとゆるやかな制度改革が必要で はないか。
(8)特定健診・特定保健指導の各 県の実施状況について(福岡県)
<提案要旨>
福岡県の生活習慣病対策検討委 員会において、福岡県内の66 市町 村の特定健診・特定保健指導の実 施状況を調査した結果(平成20 年 8 月末現在)、本年度の受診率見込み27.3 %を 大きく下回っている。
その要因として、制度の問題とシステムの問 題が指摘されており、具体的には、被保険者に 対する広報が十分でないこと、がん検診等との 同時実施が難しいこと、制度が複雑で住民が理 解できていないこと、労働安全衛生法による健 診のデータの受け渡しの問題、代行機関のシス テムトラブルなどがあげられている。
このように受診率が低迷している現況におい ては、制度自体の見直しが必要であると考えら れるが、各県の実施状況を伺いたい。また、制 度自体に対する問題点について日医の考え、取 り組みについてご意見を伺いたい。
協議事項(1)(2)(8)は一括協議。
<各県回答>
医療費適正化計画では特定健診・保健指導受 診率、平均在院日数、療養病床数等、平成24 年度迄の達成目標が示されている。特定健診受 診率に関しては各県ともに、目標値を大きく下 回っている状況で、平均在院日数および療養病 床数の具体的な状況については現在のところ把 握していないのが殆どで、療養病床数について は、次期介護報酬改定を見て対応を検討する会 員が多いと予測される。各県の目標値および実 施状況については下表のとおり。
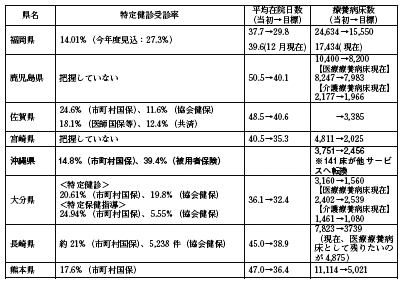
<内田常任理事コメント>
特定健診では、契約が遅れたこと、周知不 足、制度そのものが複雑であること等が原因 で、5 年間での目標達成は非常に難しくなって いる。
特定健診の処理率は、全国で122 万件(国保 分)となっており非常に少ない。また、請求の エラーについては95 %がクリアされている状 況である。
九州地区(12 月処理分)では、福岡県が 28,000 件、佐賀県が2,700 件、長崎県が15,000 件、熊本県が17,000 件、大分県が11,000 件、 宮崎県が6,500 件、鹿児島県が17,000 件、沖縄県が8,600 件という状況である。
特定保健指導はほとんど実施されておらず、 全国で1,715 件のみの処理(国保)の他、エラ ー率も高い。
ワーキングで詰めている段階であるが、課題 が多い。4 月から健康保険局や厚労省で検討会 を開催し詰めていくことになっている。
また、がん対策で予算が確保されているの で、それを活用しモデル事業を行うことを検討 している。
医療費適正化計画のペナルティーについて は、地域格差が生じるため日医も反対してい る。平均在院日数や療養病床数を機械的に抑制 するのは現場的に難しい状況であるので、現場 の意向を主張していくことが重要である。ペナ ルティーによってインセンティブを守るという のはいけない。
<その他の意見>
・適正化は削減ではない。計画の根本的な見直しが必要(福岡)。
・人口・産業構造等が全く違うので、保険料率は全国統一していただきたい(大分)。
(3)臨床研修制度の見直しについて(宮崎県)
<提案要旨>
わが国ではOECD 先進諸国と比較して医師 の絶対数が足りないが、平成16 年度から始ま った臨床研修制度より、医師不足・偏在がより 鮮明となった。特に地方における基幹病院の医 師不足が顕著であり、医療崩壊が現実化しつつ ある。医学部定員増も即効性はなく、現在の臨 床研修制度の見直しは必要と考える。一部のマ スコミでも提言されているが、第三者機関によ る後期研修医の適正配分や専攻科規制など、何 らかの処置が必要ではないか。各県のご意見を お伺いしたい。
<各県回答>
各県ともに、臨床研修制度の見直しや何らか の処置は必要であるとしている。具体的には、 地方地域枠の拡大や受入枠の削減と適正配置、 後期研修における各専門学会の専門医等の適正 化と適正配置、大学病院の機能回復や医局制度 の再構築等があげられた。また、大分県から休 職中の女性医師の活用として、すべての病院に 保育所を義務化(設置・運営費は公費負担)す るべきとの回答があった。
<内田常任理事コメント>
臨床研修問題については、日医のグランドデ ザインへ提言していくこととしている。
その中で、卒前卒後教育の一貫性として卒後 研修の見直し、1) 1 年目は内科・救急、2 年目 は専門研修、2)地域偏在対策として、1 年目は 卒業した大学の地域に残ることを提言したい。
研修期間を2 年から1 年にするのは法改正等 の問題が絡んでくるので難しい。また、適正配 置に関しては、地域医療研修ネットワーク(仮 称)を活かして取り組んでいけるのではないか 検討しているところである。
離島・僻地への義務化・強制に関しては、一 部で奨学金を導入した自治医大方式がスタート しており、一部義務化となっている。
(4)公立病院改革ガイドラインに関する各 県の状況について(長崎県)
<提案要旨>
地方公共団体は、平成20 年度内に公立病院 改革プラン(経営効率化は3 年、再編・ネット ワーク化、経営形態見直しは5 年程度を標準) を策定することとなっている。
経営の効率化や公的病院のみに視点を置いた 再編・ネットワーク化は更なる地域医療の崩壊 に結びつくことも考えられ、医師会としても注 視し、積極的に関わる必要があると考える。
本県では、県による公立病院改革プラン検討 協議会において県全体の状況についての報告書 が作成されたところであるが、各県の状況につ いてお伺いしたい。
また、救急救命センターの立ち上げや運営す る際の意見があれば伺いたい。
<各県回答>
公立病院改革に直接関与している医師会は、 本会と佐賀県医師会のみで、その他の県は、県 や市町村が主体となって、それぞれ改革プラン を作成することになっている。
佐賀県医師会では、医療審議会と別に「公立 病院の今後のあり方を考える会」を設置し、県 全体の医療資源等を踏まえ検討がなされている。
また、本会からは、県立病院事業の厳しい経 営状況等を踏まえ、県立病院の役割、機能並び に運営体制を抜本的に見直し、効率的かつ継続 的な医療提供体制を確保することを目的として、 今年度中に「県立病院のあり方に関する基本構 想」を策定し、県医師会も積極的に関与し地域 医療の確保に努めるとの回答を行った他、救命 救急センターの役割について一次を担うのでは なく二次、三次に特化すべきとの回答を行った。
(5)診療所の新たな病床の設置について (大分県)
<提案要旨>
医療計画では診療所の一般病床についてはこ れまで設置の制限は受けていなかったが、平成 19 年の医療法改正により原則として基準病床 数の範囲内での設置しか認められなくなった。 しかし、以下の場合は特例として認められるこ とになっている。
(1)居宅等における医療の提供の推進のために必要な診療所
ア 社会保険事務局に在宅療養支援診療 所としての届出をしている診療所。
(2)へき地に設置される診療所
ア へき地診療所
イ 無医地区又は準無医地区に新たに開設
される診療所
(3)その他特に必要な診療所
ア 小児科又は小児外科を標榜し、小児科
専門医又は小児外科専門医が常勤する診
療所
イ 産科又は産婦人科を標榜し、分娩を取
り扱う診療所
本県において、在宅療養支援診療所として届 出を行う診療所の病床申請に対し、「基準病床 数がオーバー」、「他県でも認めていない」との 理由で受付が行われず、審議会での協議もされ ていない。
厚労省は有床診療所について「患者の身近に ある」、「患者の生活背景等まで把握してサービ スを提供することが可能」、「夜間、急な医療行 為が必要な場合でも対応可」という利点がある としており、今後の在宅医療を支援する病床と してもその役割は重要である。
先般、県と調整したところ、有床診療所部会 にかけて前向きに検討するという回答を得たの で、今後は認められていくものと考えられる。 それらを踏まえて各県の状況をお伺いしたい。
<各県回答>
各県ともに、病床申請はされていないが基本 的には医療審議会有床診療所部会等で審議され るとの報告があり、鹿児島県および佐賀県につ いては、取扱いを検討中あるいは具体的な手続 きや基準については整理されていない状況であ るとの回答があった。
福岡県では、医療計画部会で審議することに なっており、先般、眼科クリニックから斜視の 早期手術による2 床の病床申請があり、特例で あるとして申請を受理したとの報告があった。
宮崎県においては、病床設置の特例につい て、既に医療審議会において協議され、分娩を 取り扱う有床診療所を新規に開設又は増床する 場合は、届出による病床設置が認められている が、在宅療養支援診療所については、目的どお りベッドが使用されているのか確認することも 難しいとの県の見解もある。また、小児科専門 医又は小児外科専門医が常勤する診療において も、地域によっては、内科と小児科の標榜科目 が同じ診療所が多数あり、何らかの整理が必 要。へき地に設置される診療所は、無医地区の 定義に沿った形で申請があれば医療審議会で協 議されるというように前向きに捉えているので 申請があった場合は柔軟に対応いただくよう県に要望したいとの回答であった。
本会からは、全国有床診療所連絡協議会にお いて、地域における有床診療所の設立に関して は、医療審議会を通せば制限はないといわれて おり、医療審議会に申請があればスムーズに受 理されるよう話し合われているところである。 各県の担当者が誤解をしているので、疑問があ る場合には各県で判断するのではなく厚労省に 問い合わせるようにと回答した。
(6)中小病院、診療所の医療安全対策の取 組みについて(鹿児島県)
<提案要旨>
平成19 年4 月1 日の医療法改正により、医療 機関の医療安全対策が義務化され、これまで診 療報酬上のみで必要であった医療安全対策が、 診療所においても行われなければならない。
本県では、年2 回行う医療安全対策講演会と は別に、平成18 年度から会員医療機関を対象 とした医療安全対策モデル事業を実施し、「イ ンシデントアクシデントレポート」作成や「影 響度レベル」の検討や院内での医療安全対策に おける評価法と対策、防止器具の紹介など中小 病院・診療所でも取り組めるようなモデル事業 を行っているが、十分とは思えない。各県で中 小病院、診療所を対象とした医療安全対策の有 効な取り組みがあればお伺いしたい。
<各県回答>
九州各県ともに、年に2 回の研修会または講 習会を開催している。
福岡県では、平成17 年度から会員はもとよ り会員医療機関の医療安全担当者を対象に、医 療安全推進者講座(8 日間: 40 時間)を毎年 開催している(2 万円の受講料)。
佐賀県では、病院・診療所別に「医療安全 管理体制・院内感染防止対策ガイドライン/マ ニュアル」を作成し、会員医療機関に配布して いる。
宮崎県では、県医師会館を主会場に研修会等 を開催し、テレビ会議システムにより県内8 地 区へ同時放映している。
長崎県では、会員医療機関に研修会等を受講 させ、口伝する形式等の院内研修会を年に2 回 開催している他、日医や厚労省から示された指 針、様式等を基に医師会で作成した資料を会員 医療機関に配布、会員向けホームページへ掲載 している。
熊本県では、医療安全管理マニュアル冊子を 作成し、県内会員医療機関に配布すると共に、 医療安全研修会を年に3 ~ 4 回開催している。 平成20 年度には、法人病院と診療所を区分し て、研修会を開催したとの回答があった。
<内田常任理事コメント>
日医では、医療安全推進講座を実施してお り、平成18 年度からはe-learning を活用し、 認定証を配布している。また、医療従事者のた めのマニュアルを作成し、ホームページからア クセスできるようにしている。今後、各県の事 例等をあげていただき検討していきたい。
(7)新型インフルエンザに対する県医師会 の対応策について(長崎県)
<提案要旨>
新型インフルエンザの発生が懸念されてい る。新型インフルエンザの流行は社会的危機を 招くとされており、医療にも社会的危機の状況 下での対応が求められている。
本会の診療所及び病院における新型インフル エンザ対策の作成は緒に就いたばかりである が、各県の対策の状況をお伺いしたい。
<各県回答>
福岡県、鹿児島県、佐賀県、宮崎県、大分県 では、新型インフルエンザ対策行動計画または 各種対応ガイドラインの検討が進められてお り、フェーズ4 以降の見直しから発熱外来の運 営を含めた訓練等が関係機関と実施されてい る。また、鹿児島県からは、教育委員会と共同 で学校現場でのガイドラインを作成したとの報 告があり、佐賀県からは、公的機関の訓練は既に実施されているので、パンデミック時の一般 県民の行動計画を策定していく必要があるとの 報告があった。
<内田常任理事コメント>
国との新型インフルエンザに関する会議に参 加しているが、そこでは都道府県の対策のとり 方がまちまちなので、都道府県の 情報をしっかりと把握するよう申 し入れている。また、補償の問題 についても取り組まれていないの が現状である。
タミフルの備蓄に関しても、体 制の問題や薬の保存期間の問題等 があるので、しっかり対応してい ただくよう要求しているところで ある。
(9)がん検診について(長崎県)
<提案要旨>
平成19 年に施行されたがん対 策基本法に基づくがん対策推進基 本計画によると、平成23 年まで に市町村で行うがん検診の受診率 を50 %以上とする目標が掲げら れている。
しかしながら、市町村の負担するコストの問 題や消極的な受診勧奨等があり、目標を達成す るのは困難な状況と言わざるをえない。
当県においても、受診率改善の特効薬は、見 出せない状況であるが、いずれにせよ、受診率 の向上には郡市医師会や県医師会が自治体と積 極的に関わっていかざるを得ないものと思われ る。そこで次の点について各県の状況をお伺い したい。
1)貴県医師会におけるがん検診への取り組み状 況や医師会又は、個々の会員による積極的な 受診勧奨を行っているか。
2)受診率向上へ向けて、各自治体と話し合いを 持たれているのか。
3)具体的な受診率向上への例、案をお持ちであ ればご教授いただきたい。
<各県回答>
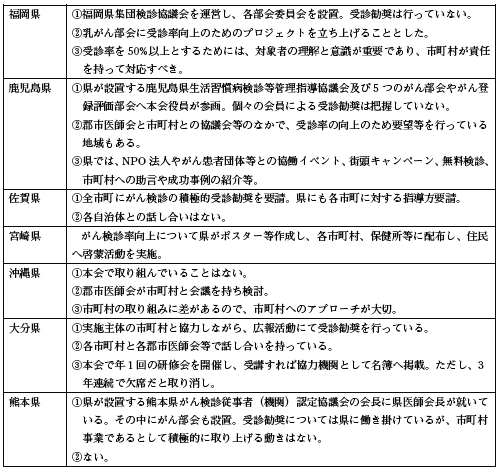
<内田常任理事コメント>
がん対策推進基本計画では、がん検診の受診 率を50 %としているが一番達成の難しそうなの が受診率である。それは受診率の把握が難しい からである。また、がん検診を一般財源化する ことも現在の財政状況では厳しいものがある。
日医としては、がん対策推進委員会で具体的 な取り組みを検討することとしており、がん対 策に関する予算が増えているので、特定健診と 合わせてモデル事業を展開していくなど活用で きないかと考えているところである。
印象記

副会長 玉城 信光
去る1 月24 日(土)、ホテル日航熊本において開催された標記協議会の報告をする。
沖縄から会議に出席すると,いつも開始時間ギリギリの熊本到着である。しかしながら、東京発 の午前の便なのでゆっくりとホテルに入った。前日に日本医師会で医業税制の委員会がもたれた のである。将来の社会保障の財源として消費税の問題を医師会が取り上げなければならないとの 話しがあった。面白い講演であった。
熊本では医療費適正化計画と特定健診・特定保健指導の各県の実施状況について話し合われた。 特定健診受診率がアップしないとペナルティーが課せられると言われる割には、各県とも今年度 の健診受診率は低いままに推移している。また各県とも療養病床の削減が進んでいることが印象 的であった。
臨床研修制度の見直しについて宮崎県から質問がでたが、内田常任理事から1 年目に内科と救 急、2 年目は専門研修にするなどの構想があるといわれた。最近のYahoo ニュースに亀田総合病 院で「明日の臨床研修制度を考えるシンポジウム」が開かれたとある。記事を見る限りひとつの 研修制度ですべてを満足させるシステムはないように思える。初期研修は現在のままで、後期研 修で選択の幅を広くした方が良いのではないかと私は考える。
公立病院改革のガイドラインについて話された中で長崎県では3 つの病院を統合して一つにす るのだが、その中に救命救急センターを立ち上げるといわれた。運営等にアドバイスを頂きたい との話しがあった。沖縄の南部医療センターの例をあげ、二次、三次救急に特化した方が良いの ではないかと話した。コンビニ受診を控えさせる施策を最初から講じるべきであると述べた。ま たYahoo ニュースであるが、鳥取大学で救命救急センターに1 万2,965 名の患者を受け入れて、 入院は約900 名であったと報じられている。コンビニ受診による過労のために教授以下4 名の医 師が退職し救命救急センターが閉鎖になったと記事がある。沖縄県には患者のたらい回しがない と誇らしげに言われるが、早晩同様の事態がおこることも予測される。
診療所の新たな病床の設置について大分県から提案があったが、全国有床診療所連絡協議会の 常任理事会では各県の医療審議会にあがれば、ほとんど認可されることになっているとの説明が ある。疑義があれば厚労省に問い合わせるように言われている。そのようにしてほしい旨を報告 した。その他も話されたが、別紙報告を参照してほしい。
熊本出張はあと1 回である。馬刺、辛子レンコンと別れる日も近くなった。
印象記

常任理事 安里 哲好
医療費適正化計画において、特定健診・保健指導の実施率や平均在院日数、療養病床数等の平 成24 年度までの達成目標が示され、達成状況に応じて都道府県の診療報酬の減額や保険者が拠出 する後期高齢者支援金の増額が策定される主旨に対する医師会の対策と今後の進め方についての 提案があった。特定健診受診率の低さはどの県も頭の痛いところだ。ところが、当県の平均在院 日数とその達成目標値は幾らだったのかと、思い出せなかった。それにしても、目標値が高い壁 として感じており、もっとゆっくり時間をかけて実施されるよう願いたいものだ。
卒後医師臨床研修制度が医師の診療科及び地域偏在を招き、医療崩壊へと導く大きな要因とな っていると指摘し、その制度の見直しが必要で、また、第三機関による後期研修医の適正配分や 専攻科規制など、何らかの処置が必要ではと言う提案があった。2 年間の研修を短縮することは 制度上困難であろうから、研修内容を替えて、実質的に2 年目より指導医のダブルチェックなし (必要に応じてダブルチェック)で診療ができる体制は可能だろうか。これからは、大学と地域の 医療機関が連携し、大学の機能を活かした地域に根ざした医師の循環システムを構築することが 医師不足を解決する近道ではないかと考える。その循環システムの後期研修期間において、離島 診療に従事するシステムが作り出されることは重要と思われる。
公立病院改革ガイドラインに関する各県における状況については、8 県の内、医師会が積極的 に関わっているのは佐賀県と沖縄県のみであった。佐賀県は、医療審議会とは別に県行政におい て「公立病院の今後のあり方を考える会」が設置され、会長がそれに参画しており、またシンポ ジウムを1 回開いたようだ。当県のように、熱く燃え、日々新聞紙上を賑わしている状況にはま だ至って無い感がした。
中小病院、診療所の医療安全対策の取組みは、年2 回の講習会のみならず積極的に8 日間・40 時間の講座等を行っているところが3 県、2 回の講演会プラスαが2 県、2 回の講演会が3 県であ った。当会は、年2 回の講演会の現状について述べ、各県の取組みを参考にし充実させて行きた いと回答をした。
新型インフルエンザに対する県医師会の対応策について、九州各県では当県が遅れている印象 を受けた。その中で、大分県の郡市医師会感染症対策担当理事連絡協議会と県との連携下に、対 策がスムーズに進んでいる感がした。当県はアジアからの観光客を中心とした航空便や船舶が多 く、また、近隣諸国旅行ツアーよりの帰沖の際等、国外から持ち込まれる可能性の高い地域と考 えられる。そのような背景の中、完全で無くてもよいから、模擬訓練等を行うことは大きな進歩 であろうと考える。県行政と県医師会、郡市医師会とで連携し、発熱外来、感染防護具や治療薬 の備蓄支援、迅速な診断システム、ワクチン接種時期の決定、医療従事者の補償制度の問題等、 早急な対策の構築が望まれる。
懇親の場で、他県の素晴らしい地域医療実践活動を拝聴するため、色々な意見交流をすると、 ある県は医師会活動の拠点の場(県医師会館)もまだ予定がたっていず、その土地の購入や建物 を建てる蓄財も無いという。土地を確保し、会館を建てるための蓄財をしていただいた当会の諸 先輩方に、改めて感謝の念が心よりこみ上げてきた。新会館を拠点とし、次年度は当県の地域医 療活動の諸課題を検討し、一歩でも前進したいものだと心に記し、熊本の美酒と滋味深くそれで いて後悔の念を抱かせる馬肉を味わった。