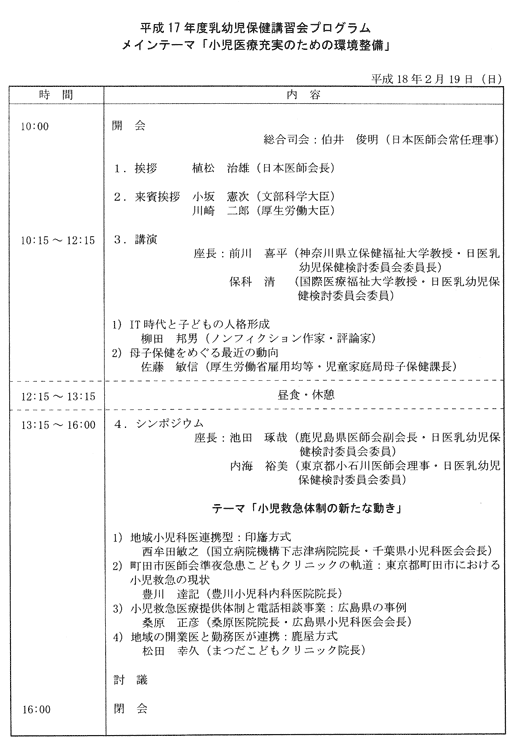平成17年度乳幼児保健講習会報告及び印象記

母子保健担当理事 野原 薫
平成17年度の乳幼児保健講習会が去った2月 19日(日)に日本医師会館大講堂で開催されま した。この講習会の趣旨は「少子化が進展する 現状を踏まえ、地域医療の一環として行う乳幼 児保健活動を円滑に実践するために必要な知識 を習得する」ことです。参加者は全国から約500 名と盛会でした。メインテーマは「小児医療充 実のための環境整備」で、下記にプログラムを 示します。詳細は日本医師会雑誌8月号に載る 予定ですので、簡単に要旨を報告いたします。
午前10 時から日本医師会長の挨拶に続き、 文部科学大臣、厚生労働大臣の来賓挨拶があり ました。
講演の一番目はノンフィクション作家で、評 論家の柳田邦男先生で、「IT時代と人格形成」 という演題でした。講演の基本的内容は「IT社 会が子どもの心の形成にゆがみをもたらすおそ れがある」ということで、佐世保の小学6年生 の同級生殺人事件を分析して述べていました。 この加害女児の人格特性として、①自分を見つ め、言語化することが苦手である、②基本的な 安心感が希薄で、他者への愛着が形成しにく い、③文脈をとらえて理解する力が未熟であ る、④表現回避か攻撃への両極端の走る傾向が あるとしています。このような傾向は最近の保 育園児や小学低学年ではよく見られる光景であ ると多くの保育園、学校関係者が述べているそ うです。メディアによる情報環境が大きく変わ り、親と子の接触のしかたが変わってしまい、 生身のコミュニケーションが失われたためだと 講演では分析し、このことから「アタッチメント」の大切さ、愛着関係の形成の重要性を説い ていました。また、アメリカの小児科学会、日 本小児科医会などでは2歳までは、子どもにテ レビを見させないように勧告していることも紹 介がありました。
次の講演は厚生労働省雇用均等・児童家庭局 母子保健課長の佐藤敏信先生で、「母子保健を めぐる最近の動向」の演題でした。全医師数は 平成8年と比較して、平成16年は11.5%増加し ているが、小児科医は6.5%しか増加せず、産 科医にいたっては2.1%減少しているとの報告 がありました。更に、小児科医、産科医は女医 がそれぞれ31%、22%を占めており、30歳未 満では男女比は逆転しているとのことでした。 因みに、20年後には医師数は人口10万人あた り500となり、世界でも有数の医師過剰状態が 予測されています。小児科医不足、産科医不足 に対して考えられる対応、行政としての対応を 幾つか述べられていましたが、特に目新しいも のはありませんでした。
午後は「小児救急体制の新たな動き」と題し てのシンポジウムが開催されました。千葉県印 旛医療圏では、1カ所の小児急病診療所に小児 科標榜医師が参加し、4カ所の二次輪番病院体 制をひくシステムです。東京都町田市では午後 7時から10時までの小児準夜急患センターを運 営するシステムです。広島県からは電話相談事 業の紹介がありました。鹿児島県大隈地区では 一次救急は内科系、外科医系の当番医が行い、 必要な場合に小児科医のいる二時救急の医療セ ンターに紹介するシステムです。それぞれのシステムに長所、短所があり、地域の医療事情に 合わせて救急システムを構築していくしかな く、患者教育の必要性、行政の協力が必要不可 欠だと感じました。また、改めて沖縄県の小児 救急体制の素晴らしさを再確認しました。