平成18年第1回医療に関する県民との懇談会報告

ふれあい広報担当理事 玉井 修

会場風景
5月25日(木)午後7時より、沖縄ハーバー ビューホテルにおいて県民との懇談会が開催さ れました。医療に関わる諸問題を県民の代表の 方たちと率直に語り合い、医療に対する理解を 深めて頂くことを目的としております。今回は 新たな委員の選出もあり、会の冒頭に小渡副会 長より各委員へ委嘱状の交付と改めて自己紹介 をしていただきました。開会にあたり小渡副会 長より、医療を取り巻く状況は年々厳しさを増 しており、この様な折、医療側と県民側の相互 理解を深めていくことにより良い医療の醸成に 寄与できる懇談会に発展させるためにも、是非 とも忌憚のない意見、ご叱責をお寄せ下さるよ うお願いを含めたご挨拶がありました。
その後、私の司会で懇談に移りましたが、今 回のテーマは「福島県立大野病院産婦人科医師 逮捕の件」という大変重いテーマを取り上げま した。このテーマに関しては、ふれあい広報委 員会議においても、かなりナイーブな問題でも あり、扱いを慎重にするように様々なご意見を 頂戴しておりましたので、事件性の有無に関し ての議論は限られた情報しか得られない現状で は無理があることを再確認し、プレゼンテーシ ョンには細心の注意を払う事と致しました。
まず私から今回の事件の概要を話し、金城忠 雄理事より前置胎盤、癒着胎盤が非常に危険性 の高いレアケースであること、村田謙二理事よ り大量出血時の麻酔対応の困難さを、更に永山 孝南部地区医師会長よりこの逮捕がもたらした 医療界への反響の大きさに関して、更に阿波連 光弁護士からは証拠隠滅や逃亡の恐れのない被 疑者を事件後1年以上を経過して突然逮捕拘留 したことに対し抗議文を提出した旨ご報告があ りました。
この様な事件に対し、医療側から充分な意見 の表明ができなければ、いたずらに医療不信を あおるだけで誰の利にもなりません。県民側の 委員からも、今回の様な話を聞くまでは一方的 に医療ミスという認識しかできず、様々な方向 から見ることの大切さを再認識したとのご意見 を頂戴致しました。
最後に小渡副会長から、今回の懇談会におい てマスコミ報道だけでは伝わってこない様々な 考えのあることをご認識頂き、そして最終的に ご判断頂くのは良識ある県民の皆様ご自身であ る事をお話頂き、会をまとめて頂きました。
私は担当理事として、県民との懇談会は今後 県民の皆様が活発に医療側への意見を述べて頂 けるアクティビティーの高いものへ発展して行 けるものと期待しております。
○玉井(医師会)
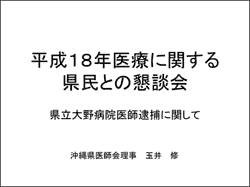
スライド1)
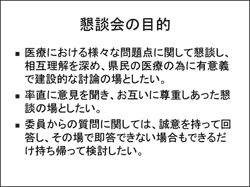
スライド2)
それでは早速、懇談に移らせていただきます。
本日は、今年の2月に福島県の県立大野病院 で起こった、産婦人科医師逮捕にかかわる問題 を取り上げさせていただいております。
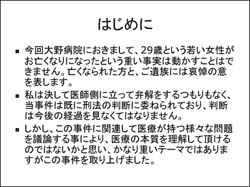
スライド3)
今回、大野病院におきまして29歳という若い 女性ですね。妊婦の方がお亡くなりになったと いうこの重い事実はどうしても動かすことはで きないとというふうに思っております。
亡くなられた方とご遺族の方々には哀悼の意 を表させていただきます。
この事件はすでに刑法の判断に委ねられてお りまして、様々な証拠物件もすでに押収されて おります。それについて個々の状況において事 実関係を云々をしても始まらない部分もござい ますが、この事件の経過において、いくつか問 題点がございますので、それに関連して我々は ここで議論をし、できるだけ医療の本質を理解 していただけるような会にしたいと思って、こ のテーマを取り上げました。
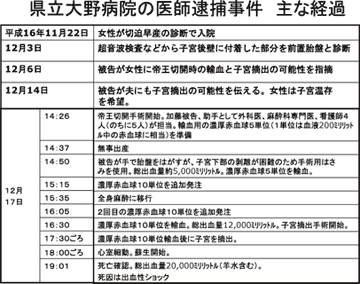
スライド4)
県立大野病院の医師逮捕事件の主な経過をこ ちらに書いてあります。
この事件は、まず平成16年ですので1年半前 です。平成16年11月22日に29歳の女性が切迫早産ということで入院されております。
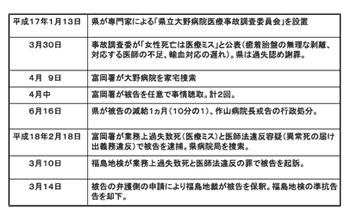
スライド5)
同年の12月3日に前置胎盤。前置胎盤につい ては、あとで金城先生のほうからお話がありま すけれども、要するに非常に危険な状態である ということがわかったということですね。
12月6日に、これは普通には出産はできない だろうということで帝王切開の状況であるとい うことと、場合によっては子宮を摘出するかも しれませんということをお話してあります。
12月14日、被告と書いてありますけれども、 この被告というのが産婦人科の医師でございま す。要するに子宮を摘出する可能性があります よというふうにお伝えをしておりますけれど も、お若いですので子宮温存を希望というのは 当たり前という気がいたします。
12月17日に実際に帝王切開手術は開始され ます。2時26分に開始です。助手として外科医 がついております。この外科医は熟練した外科 医です。助手として外科医がついた状態で被告 が執刀をしております。麻酔科専門医がついて おります。看護師4人、のちに5人に増えます が、濃厚赤血球5単位、このあたりはあとで村 田理事のほうから説明していただきますけれど も、輸血の準備もしっかりやっております。
14時37分に無事、お子様は帝王切開でご出産 されております。この間、麻酔は腰椎麻酔です。
あとで金城先生からお話があるかと思います が、一般的に胎児の帝王切開に関しては腰椎麻 酔でするのが一般的だということですので、ここ までは何の特殊な状況ではないということです。
14時50分、ここあたりから少々事態が急変 してまいります。被告が前置胎盤を剥がそうとしておりますけれども、これがなかなか剥げな い。剥離ができないということで、手術用はさ み、クーパーと言いますが、それを使って剥離 操作を行っております。
総出血量5,000ミリリットルですね。村田先 生、人間は血液は何リットルあるんでしょう か。簡単に教えていただけたらと思います。
○村田(医師会) あとで私のスライドでお見 せするんですが、5,000というと大ざっぱに言 うと、人間の体の中にある全部の血液が一度に 出てしまった量というふうに考えていただけれ ば大体イメージがわくと思います。
○玉井(医師会) 要するに体にある血液はこ の時点ですべて出きってしまっているというぐ らいの大量出血の状況に、この時点でなってお ります。この事態に対しまして麻酔科のドクタ ーは、すぐに濃厚赤血球10 単位を追加発注。 さらにここから全身麻酔に移行しています。
ということは金城先生、全身麻酔に移行する ということは、ここあたりから子宮摘出の可能 性を考えているということですか。
○金城(医師会) そうですね。帝王切開で も3,000ミリリットル以上も出血するのであれ ば、子宮摘出の適応を考慮したほうがいいとい うことになります。
○玉井(医師会) わかりました。というこ とはここで全身麻酔に移行したということで、 これも麻酔科の一般的な判断ということでは間 違いないわけですね。
○村田(医師会) 全身麻酔に移行したとい う理由を少し詳しく追加したいんですけど。
一つは腰椎麻酔でなぜ最初にやるかというの は、これは赤ちゃんを守るためなんですね。全 身麻酔を最初からやると赤ちゃんも麻酔がかか ってしまうものですから、赤ちゃんというのは 母体の中にいる間はお母さんから酸素とか栄養 をしっかりもらっていますから安全ですけど、 出てきた瞬間から自分で呼吸をしないといけな い。そういうところに麻酔がかかって出てきま すと、スリーピングベビーと言いますけど、酸 素を十分、自分の肺で呼吸できない。非常に危機的な状況になるので、腰椎麻酔であれば使う 薬もほんのわずかですから、赤ちゃんが全く正 常な分娩と同じような状態で出てくるという意 味で、赤ちゃんを守るために腰椎麻酔をするん ですね。
全身麻酔というのは、気管に管を入れまして、 麻酔科医が人工的に呼吸して酸素をあげるもの ですから、自分が呼吸に使うエネルギーがほと んどゼロで済むのですね。そういう負担をとっ てあげるということが、ひとつ患者さんの危機 的状況を守るという意味で必要なんですね。
ところが、先ほど申しましたように、血圧自 体は非常に下げてしまうもので、必ずしもいい ことばかりではない。非常に怖いことなんです けれども、そういう意味ではやむを得ない措置 だということが言えると思います。以上です。
○玉井(医師会) ありがとうございます。
赤ちゃんを守り、お母様の状態を危機的状況 から救うために全身麻酔に移行しているという ことです。その後、赤血球10単位を追加して輸 血した後に子宮摘出手術が16時30分から開始 されます。その間、総出血量は1万2,000、12 リットルです。
人の血液が2回以上入れ替わったということ になります。17時30分に子宮は無事摘出されま した。しかし、その後、この心室細動、蘇生開 始。これはもうショック状態というでしょうか。
○金城(医師会) そうですね。ショック以 上に心臓が止まる寸前の状態を心室細動と言い ます。
○玉井(医師会) はい、ありがとうござい ます。
18時頃ショック状態。さらに危機的状態。蘇 生を開始いたしましたが、19時01分に死亡を 確認。残念ながら救命できなかったということ です。
2万ミリリットル、20リットルの出血でござ います。
被告の医師はその後もお仕事をされておりま す。結局、その後ももちろん本人のお話では全 力は尽くしたと。しかし、救命できなかったということで、そのままお仕事は続けていらっし ゃいます。この県立大野病院で産婦人科のドク ターはこの先生1人だけだったんですね。
平成17年1月13日、県が専門家による「県立 大野病院医療事故調査委員会」を設置。3月30 日に、これは医療ミスだという公表をしており ます。その指摘は癒着胎盤の無理な剥離、対応 する医師の不足、輸血対応が遅れているという ことでございました。県は過失を認めて謝罪。
4月9日、富岡署が家宅捜索に入りまして、4 月中に被告を任意で事情聴取。
6 月16 日に県の行政処分が下されておりま す。減給1カ月、行政処分を行っております。
その後は、特に大きな動きもなかったんです が、平成18年2月18日に、富岡署が業務上過失 致死と医師法違反容疑(異状死を届けなかった) ということで被告を逮捕し、同病院局を捜索。
3月10日に起訴いたしまして、3月14日は保 釈ということです。その間は留置場に入られて いるということで、その間は産婦人科の医者は いなかったということであります。今も自宅に いらっしゃるということで、産婦人科のいない 状態が続いております。
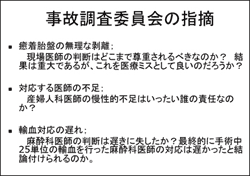
スライド6)
ここで事故調査委員会の指摘の三つの点につ いて私なりに書いてみました。
「癒着胎盤の無理な剥離」ということです が、現場医師の判断はどこまで尊重されるべき なんだろうか。その結果は重大ではありますけ れども、癒着胎盤の無理な剥離というのは、ど こまでこれを医療ミスとしてよいのだろうかということですね。
「対応医師の不足」ということですけれど も、ベテランの外科医が助手に入っております し、今はどこの病院さんも産婦人科の医師は慢 性的に不足です。それについて行政処分をす る、またはこれについて医療ミスとする理由に なるのだろうかというところもあります。
「輸血対応の遅れ」ということですけれど も、麻酔科医師の判断は遅きに失したのでしょ うか。術中に25単位の輸血を行い、一連の麻 酔科対応をしているにもかかわらず、これが麻 酔科医の対応が遅れたといえるのだろうかとい う疑問があります。
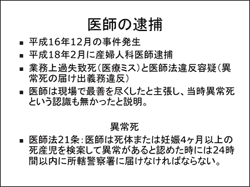
スライド7)
医師の逮捕ということですけれども、平成16 年12月に事件が発生して、逮捕するのが平成 18年2月です。その間、1年半ぐらいあるんで すね。その間、医師は普通に仕事をしておりま す。ここでなぜいきなり逮捕という形になって しまうのか、これがちょっと解せないところが あります。
業務上過失致死と医師法違反容疑ということ ですけれども、医師は現場で最善を尽くしたと 主張しており、当時、異状死という認識もなか ったと説明しております。そもそも異状死とい うものが、定義的にはこういうふうに書いてい るんですけれども、曖昧であるということであ ります。
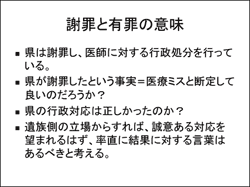
スライド8)
謝罪と有罪ということですけれども、県は謝 罪して行政処分を行っております。謝罪したと いうことが医療ミスということで、どうしても 論調はそういうふうになってしまいます。そう いうことになってしまうというのが果たして正 しいのだろうか。県の行政対応がこれでよかっ たのかどうなのか。
遺族側の立場からすれば、誠意ある対応を望 まれるとは思います。率直に結果に対する言葉 はあってもいいとは思いますが、行政対応がす ぐに行政処分をしてしまって、これがマスコミ の論調をかなり有罪側に向けてしまったのかな という感じもいたします。
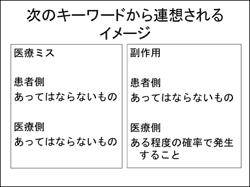
スライド9)
医療側はある程度の確率で1本の注射を打て ば副作用というのは起きてしまいます。手術を すれば、またそれも副作用は伴っております。 これもまた医療の現実でございます。
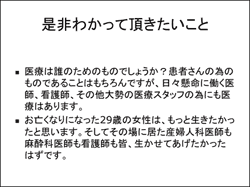
スライド10)
ぜひ委員の皆様にもわかっていただきたいの です。医療はだれのためのものでしょうかとい うことを、よく私も問われます。患者さんのた めのものでもあります。しかし、我々医療スタ ッフも日夜頑張っております。ぜひ、その医療 スタッフのためにも医療があるということもご 理解いただきたいと思います。亡くなられた29 歳の女性は、もっと生きたかったというふうに 思います。しかし、そこに居合わせた産婦人科 の医師も麻酔科医師も看護師もまた生かせてあ げたかったと思っていたはずです。それをぜひ わかっていただきたいと思っております。
では次に、金城先生、産婦人科の立場から前 置胎盤、癒着胎盤、一体どういうものなのか、 改めてご説明いただきたいと思います。
○金城(医師会)

今、詳しく玉井先生から話がありましたが、 話の順序として手術の経過の概略、それから前 置胎盤とはどういう状態なのか。それから、癒 着胎盤とはどういうことなのか。日本産婦人科学会、日本産婦人科医会が抗議文とその内容、 考え方について発表していますから、それにつ いて話をしたいと思います。
参考として母体の死亡の推移と、それから母 体死亡の原因について話をしたいと思います。
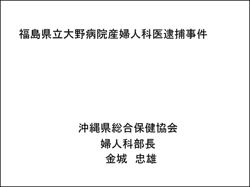
スライド1)
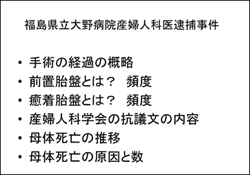
スライド2)
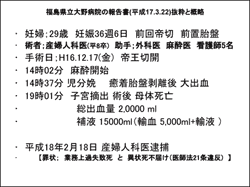
スライド3)
今、経過を詳しく話してもらったんですけれ ども、大まかなことをこの1枚のスライドにま とめました。
午後2時2分に麻酔開始。37分にはもう赤ち ゃんは出ています。そして、胎盤を剥離しようと思ったら癒着胎盤で大出血を起こしたと。そ して、19時1分に癒着胎盤のため子宮摘出をし たんですけど、残念ながら母体は亡くなってし まった。
総出血量が2万cc。入った血液が5,000と輸 液ということで母体を失ってしまった。
そして、1年2カ月ぐらい経ってから、平成 18 年2 月18日に産婦人科医は業務上過失致死 と、それから異状死したけれども届け出がない ということで逮捕されております。これが大ま かな流れです。
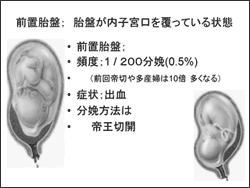
スライド4)
前置胎盤とはどういうことかと言いますと、 子宮がありまして、この赤いのが胎盤です。こ れは子宮の入り口ですね。この子宮の入り口を 胎盤がふさいでいるものですから、分娩の方法 は帝王切開しかないです。200分娩に1人ぐら い0.5%、200人に1人ぐらいは前置胎盤で子宮 の入り口を塞いでしまう。
症状は、そのまま放っておいたら、大出血し ます。それで37週に入ったら分娩の方法は帝王 切開しかありません。
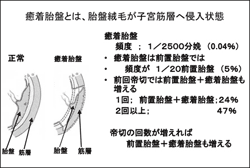
スライド5)
癒着胎盤とはどういうことかと言いますと、 胎盤が筋層内に入り込んでしまう。普通、正常 ですと、これは子宮の筋層ですね。そして内膜 があって、その上に胎盤が付いていて胎児は胎 盤からお母さんの血液を受けて、その血液の中 から栄養分を吸収、あるいは老廃物を胎盤に流 し込んでお母さんが処置してくれるというのが 正常の形です。胎盤と筋層。癒着胎盤とは筋層 内に胎盤が入り込んでしまう。
それで癒着胎盤の頻度は、2,500分娩に1人。 0.04%です。
癒着胎盤は前置胎盤では多くなります。20前 置胎盤に対して1例。5%の割合。前置胎盤は 20名に1人は癒着胎盤ですよということです。
1回帝王切開をすると、前置胎盤と癒着胎盤 は増えてきます。帝王切開の回数が増えれば前 置胎盤、癒着胎盤は増えます。
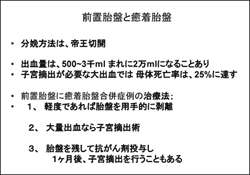
スライド6)
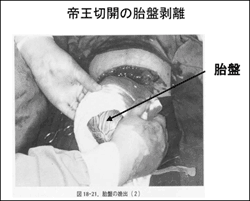
スライド7)
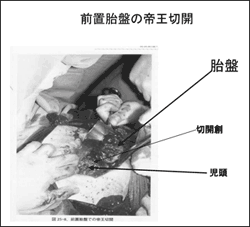
スライド8)
前置胎盤と癒着胎盤、分娩方法はもう帝王切 開しかありません。陣痛がくるのを待っていた ら大出血をして、お母さんも失うし、もちろん ベビーも失います。それで症状が出る前、37週 に入ったら帝王切開しなさいというのが産婦人 科の考え方です。
出血量は軽いものですと500ぐらい。3,000、 あるいは今回のように2万ぐらい出血すること はあります。
そして、子宮摘出、3,000cc出血したら子宮 摘出したほうがいいだろうというふうに考えま す。子宮摘出をしなければならないほど大出血 のあるのは母体の死亡率が25%、4分の1ぐら い。皆さんのテキストには母体の死亡率が25% と書いてあるかもしれませんけど、子宮摘出し なければならないほどの大出血ですと25%ぐら いということです。
前置胎盤に癒着胎盤があるのは軽いのであれ ば、用手的に剥離できます。3,000cc以上出血 するのであれば、子宮を取る。
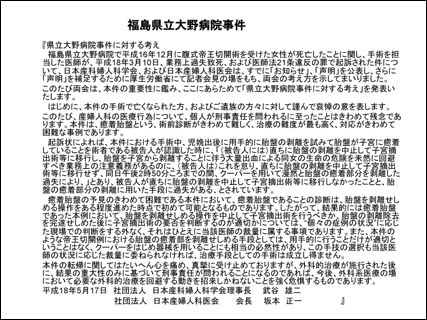
スライド9)
福島県立大野病院事件ということで、2月に逮捕されたものですから、そのあとにすぐ産婦人科医 会と、それから産婦人科学会が、沖縄県もそうです。それから千葉県、茨城県なんかも抗議声明を出 しています。産婦人科をはじめ医師会、沖縄県も出しています。
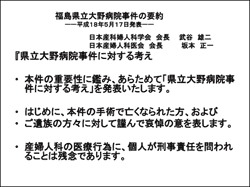
スライド10)
私なりにまとめてみました。これは産婦人科 学会と学術団体で大学を中心とした先生方、産 婦人科医会は臨床医、開業の先生方とか、病院 に勤めている先生方。一般的にはもちろん産婦 人科医は両方に入っています。代表する会長が、 5月17日に改めてその考え方について声明を出 しております。細々としたものは読めないもの ですから、私なりにまとめてみました。
本件の重要性に鑑み、あらためて県立大野病 院の事件に対する考え方を発表します。
はじめに本件の手術で亡くなられた方、及び ご遺族の方々に対しては謹んで哀悼の意を表し ます。産婦人科の医療行為に個人が刑事責任を 問われることは非常に残念であります。
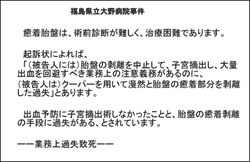
スライド11)
癒着胎盤は術前診断が難しくて、治療が非常 に困難です。
起訴状によりますと、被告人は、胎盤の剥離 を中止して、子宮摘出し、大量出血を回避すべ き業務上の注意義務があるのに、クーパー(は さみ)を用いて漫然と胎盤の癒着部分を剥離し て、こういうミスをした過失があります。出血予防に子宮摘出しなかったことと、胎盤の癒着 剥離の手段に過失があると伝えていますと。こ れが業務上の過失致死の理由になっております。
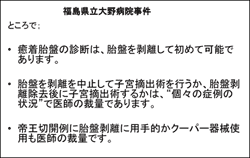
スライド12)
ところで、この癒着胎盤の診断は、胎盤を剥 離して初めてわかるものです。
胎盤を剥離を中止して子宮摘出を行うか、胎 盤剥離除去後に子宮摘出術するかは、個々の症 例の状況で医師の裁量権にあります。
それから、帝王切開の例に胎盤剥離に手でも って剥離をするか、あるいはクーパー(はさ み)でもって剥離するか、これも医者の裁量権 です。
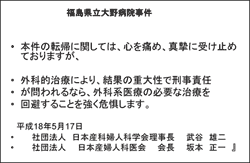
スライド13)
本件の転帰に関しては、心を痛め、真摯に受 け止めておりますが、外科的治療により、結果 の重大性で刑事責任を問われるなら、外科系の 医療の必要な治療を回避することを強く危惧し ます。
これは不可抗力であって、決して犯罪ではな いということを産婦人科学会、あるいは産婦人 科医会が報告している文書です。
大まかにこのようにまとめておきました。
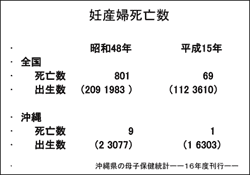
スライド14)
これは参考なんですけれども、妊産婦死亡は どのぐらいあるかと言いますと、昭和48年と平 成15年を比べてみました。
日本全国で昭和48年ですと801名亡くなって おります。平成15年は69名。そのときに分娩 数は昭和48年ですと209万人ぐらい生まれてい ます。平成15年は112万人。こういう全国的な 統計と、それから沖縄県の統計ですが、昭和48 年は沖縄でも9名失っております。平成15年は 1人。最近は毎年1人ぐらいはやっぱり亡くな っています。
昭和48 年は復帰の翌年です。出生数が2 万 3,000人ぐらい。現在は随分減って1万6,000人 ぐらい生まれています。こういう大ざっぱに見 て沖縄でも毎年1人ぐらいは失っている。日本 全国では70名前後、妊産婦を失っております。
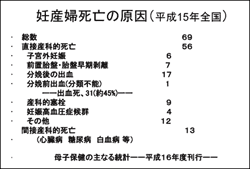
スライド15)
ではどういうことで亡くなっているかという と、総数69名のうち直接、産科的死亡が56名、 子宮外妊娠で6名、前置胎盤、胎盤早期剥離が 7名。分娩後の出血で17名、分娩不能の分娩前出血が1人。出血で亡くなったのが大体45%、 半分ぐらいは出血で亡くなっている。あとは、 羊水塞栓とか言いますけれども、産科的塞栓で 9名、妊娠中毒症、今は妊娠中毒症という言葉 はなくなりまして、妊娠高血圧症候群という言 葉になりました。それが4名。その他が12名。 そして、間接産科的死亡、これは心臓病とか糖 尿病、白血病、そういう分娩は関係ないところ で亡くなっているのが13名ということで、大体 出血で亡くなるのが70名のうち半分ぐらいとい うことになります。
私からの説明はこれで終わります。
○玉井(医師会) どうもありがとうござい ました。
続きまして、麻酔科医の対応も今回、事故調 査委員会では指摘されております。
麻酔科医の立場から村田理事、ご説明よろし くお願いします。
○村田(医師会)

スライドお願いいたします。
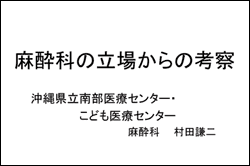
スライド1)
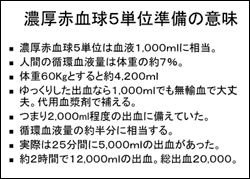
スライド2)
これは先ほどもちょっと述べましたけれど も、まず血液の準備状態がどうであったかとい うことは非常に重大な問題ですので、これをま ず押さえておきたいと思います。
記録によりますと、濃厚赤血球5単位という んですけれども、これは人体の血液に戻すと 1,000ミリリットルに相当します。この1,000ミ リリットルというのは一体人間の血液量のどの ぐらいにあたるのかということを知る必要があ りますけれども、人間の循環血液量は大体体重 の7%ぐらい、大目に見積もる人は8%という 数字が出ます。
女性が大体50kgとしますと、妊婦さんとい うのは子供が生まれる前には大体10kgぐらい 体重が増加すると言われますから、体重50kg の女性が妊婦さんになっていよいよ子供を産む ときに60kgとすると、4,200ミリリットルです ね。そうすると約4分の1ぐらいの出血、その 準備をしていたと。ですけれども人間はゆっく り出血する場合は、代用血漿剤といって、これ は赤血球を含んでいませんから実際は酸素を運 ぶという効率は非常に悪いんですけれども、そ れでも血液が減るよりはいいというぐらいの、 あくまでも代用なんですが、これだと1,000ミ リリットルぐらいでも輸血をしないで何とか切 り抜けられるんですね。ということは、つまり ゆっくりであれば1,000ミリリットルはなくて も大丈夫。さらに1,000ミリリットルを用意し ていたということは、つまり2,000ミリリット ルぐらいの出血には備えていた計算になる。その2,000ミリリットルというのは、つまり大ざ っぱに言うと、この人の循環血液量、全部の血 液の約半分ぐらいは失われても大丈夫だろうと いう想定をしていたということなんですね。
実際に、どれぐらい出血したら人間は体に悪 いかというと、約3分の1ぐらい出血するとシ ョックに陥ると言われていますから、それには 明らかに備えていたということができます。
ところが実際にはあの記録によりますと、た った25分の間に5,000ミリリットルということ は、この人の循環血液量をやや上回るぐらい、 ほとんどがたった30分ぐらいの間に全部出てし まったということで、対応が非常に難しかった と。2時間では12,000、この人の約3倍ぐらい ですかね。総出血量がこの人の血液の約4倍ぐ らいが実際には出てしまったということになり ます。
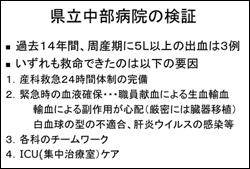
スライド3)
この事件がありまして、県立中部病院が非常 に印象的な検証を行いまして、我々、麻酔科医 は年に2回、お互いの症例を持ち合ってお互い に知識を共有しようという学会をやっているん ですけれども、おそらく県立中部病院というの は、沖縄県内では一番、今まで一番帝王切開が 多い病院ではないかなと思うんですけど、過去 14年間ずーっと記録をさかのぼりまして、この 人のように周産期に5リットル以上、つまり循 環血液量がほとんど出てしまった症例を調べて みると、14年間に3例、4年間にいっぺんぐら いはこういうケースがあるんだということがわ かりました。ですけれども、いずれも救うことが出来たというのは、以下の要因があったから だというふうに中部病院の麻酔科医の先生方は 結論づけています。
一つは、産科救急24時間体制の完備。産婦 人科医の数の確保と、それから麻酔科医がいつ でも当直していますから、すぐに手術に臨むと いう体制が完備されている。
それからもう一つは、これが非常に特徴的な んですけれども、緊急時の血液確保。これはど うしているかというと、先ほどの準備血液で明 らかに足りないというときには、中部病院では 職員全員に呼びかけまして、同じ患者さんの血 液型を持っている人を呼び出して、これは医者 だけではなくて看護師、それから事務系の職員 の方も全部総動員して助けるというシステムを つくっているんですね。
ところが、これは非常にある意味では緊急避 難的なことでありまして、学問的に考えると非 常に怖い治療法でもあるんですね。簡単に申し ますと、輸血による副作用が非常に心配だとい うことです。
肝炎ウイルス、特にC型肝炎の感染者という のは慢性に肝炎を起こして10年、20年後には 確実に肝硬変から肝がんになると言われていま すけれども、この肝炎ウイルスを持っている人 は、実際には自分が末期的な症状になるまでは 自覚がないんですね。よっぽど健康に気をつけ て日頃から検査をして、自分はこういうウイル スを持っている。ですから輸血をしてはいけな いという人ならばともかく、実際にはそういう 人はほとんどいませんから、善意であげたつも りが、実際には自分の血液の中にあった微量な ウイルスを与えてしまうということで、この危 険性というのはかなり、いわゆる赤十字が用意 する血液に比べてかなり頻度が高くなるんです ね。そういう危険を冒してでも、とにかくとり あえず命を救おうという治療法がこれなんで す。ですからこれに関しては非常に賛否両論あ りまして、厳密に輸血の副作用というのを深刻 に考える人にとっては、こういうのは非常に野 戦病院的な治療法だという指摘もあります。
それから、各科のチームワークですね。産婦 人科医だけで足りない場合には外科医もしっか り中部病院では何人も当直していますので、そ ういうチームワークがとれると。
それから、状態が悪くなった患者さんを集中 治療でずっとみていくことができる。こういう ことができるからこそ、4年にいっぺんぐらい の3例ですけれども、一応今まで助けることが できたというのが中部病院の検証です。
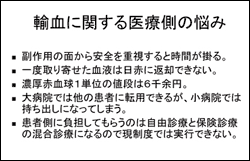
スライド4)
輸血に関する医療側の悩みというのをぜひ皆 さんにお知らせしておきたいんですけれども、 日赤に要請した場合には、最低でも近い病院で も大体30分。ちょっと遠いと1時間とか2時間 かかってしまう。それから、その血液がその患 者さんに合うかどうかというクロスマッチとい う交差試験というのがありますけど、それをや ると実際に注文してから手元に届くまでに早く とも1時間、遅い場合には2時間かかってしま うんです。そうすると先ほどの出血にとても間 に合わないということがあります。
それからもう一つは、一度取り寄せた血液と いうのは、日赤に返却できない制度になってい ます。
濃厚赤血球1単位の値段はどれぐらいかと言 いますと、血液の代金だけで6,000円余りです。 先ほどのは5単位ですから、つまり1,000ミリリ ットル用意すると、3万円以上かかる。それに運 送賃、緊急で搬送してもらうと、またさらにお 金がかかる。このお金はもし使わなかった場合 には、病院のまるまるの持ち出しになります。
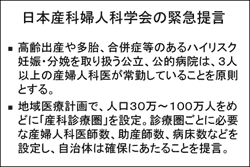
スライド5)
日本産科婦人科学会の緊急提言というのがあ りまして、高齢出産や双子とか三つ子とか、合 併症であるハイリスクの妊娠分娩を取り扱う公 的病院は、3人以上の産婦人科医が常勤してい ることを原則とするというふうに緊急提言をし ています。
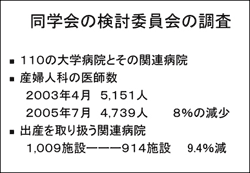
スライド6)
実際に、この学会の検討委員会が110の大学 にアンケートを出して、その関連病院を調べま した。そうすると実に驚くことは産婦人科の医 師数というのは約3年前には5,000人いたのが 8%減少していると。それから、出産を取り扱 う関連病院というのが1,000あったのが900ち ょっとになって、約10%近く減少しているとい うことなんですね。これはある意味では沖縄で も北部病院の問題がこれにあたりますけれど も、全国的にもやっぱり起こっているというこ とですね。
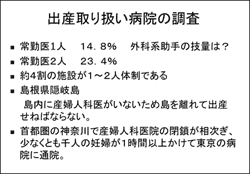
スライド7)
それで、出産取り扱いの病院を調査したら、 何と常勤医1人、これが福島県の大野病院の状 態ですけど、約15%はこういう状態なんです。
常勤医2人をとってみても、約4分の1ぐらい がこれだと。つまりこの二つを合わせると約4 割の手術が日本全国でいうと1人から2人体制 で、つまり産婦人科学会が推奨する施設ではな いという事態に陥るわけです。
それから、首都圏の神奈川で産婦人科医のあ の事件のあと、そんなリスクを抱えてまで自分 はもう仕事ができないというので閉鎖が相次い でいる。少なくとも1,000人の妊婦が1時間以 上かけて東京の病院に通院しているということ が、これはなんとアメリカの新聞に報道された 記事だということなんですね。それほど日本の 母体は今問題になっているということです。以 上です。
○玉井(医師会) どうもありがとうござい ました。
社会的にかなり大きな問題になってきており ます。
続きまして、南部地区医師会会長の永山先生 に産婦人科医療が抱える社会的問題と背景につ いてご発言いただきたいと思います。よろしく お願いいたします。
○永山(医師会)

私は、糸満で1人で開業をしています。あえ て1人でということを強調しておきたいと思い ます。
私は、医者になって36年になりますけれど も、開業する前は広島大学、それから帰ってき まして旧与儀の琉大の保健学部の産婦人科に勤 めておりました。自分で開業いたしまして24年 になります。分娩には今まで1万5,000例以上 立ち会ってきました。
先ほどの金城先生の説明がございましたとお り、実のところを申しますと、起訴・逮捕され た理由が、先生の場合は乱暴の手術をしたとい うのと、それから十分な診断をしなかったという ようなことでございますけれども、はたして癒着 胎盤をどれぐらい認識しまして、いろんな検査 をして、これで本当に診断ができたかどうか。 MRIとか、最新の医療機器がございますけど、 それでも癒着胎盤というのは非常に診断が困難 な場合が多うございます。
最初、共同通信社が全国に流した新聞記事の 最初の報道が、「帝王切開ミス」ということで 大きな題目で出まして、先生がいかにも帝王切 開などの経験がないような先生の見出し、そう いうような論調になっていたということは、私、 産婦人科医としては非常に不満でございます。 ただし、記事をちゃんと読んでみれば、先生は その年40例の帝王切開をしています。
それから、先ほどから言いますように、この 癒着胎盤という診断が非常に難しいと。それから頻度がものすごく少なかったというようなこ とを踏まえますと、やっぱりおかしいんじゃな いかなと、現場の産婦人科の医者としては思い ます。
それから、我々医者というのはやっぱり患者 さんのためを一番大事に考えます。できるだけ 子宮は取らないでおこうというようなことにな るのは、それは当然です。いろんな理由で手術 の途中で子宮を取らなければいけないという、 そういう考え方を、手術の途中で、どの時点で 子宮を取りますよと、そういうような余裕はな かったはずです。たまたま産婦人科の医者が1 人しかいなかったと。そういうような連絡役と か、いろんなものが不備じゃなかったかという ような理由でこういうように逮捕され、それか ら起訴されるというようなことになるようでし たら、外科系の医者として、特に私みたいに1 人で産婦人科を扱っているというような診療所 では、到底何もできないわけですね。
最近言われていますけれども、分娩に安全な 分娩があるかと。分娩が終了するまでそういう ことを自信を持って絶対大丈夫だというような ことを言える産婦人科の医者がいるかというよ うなことが話題になっています。大学の教授で もそんなことは言えないというのが、産婦人科 の学会の正式な発表でございます。
この症例は、結果的には不幸なことになりま したけど、その結果でもって全部を遅かったと か、粗放な操作があったんじゃないかとか、そ ういうことを言われますと、非常に産婦人科の 現場としては何もできないということじゃない かなと私は思います。もちろん患者さんを最重 点で考えまして、私たちは患者さんが一番何を 望んでいるか、できればそういう方向に叶えて あげようというのが医者でございまして、何も そういう医療事故を起こそうと思って起こして いるわけではございません。
だから、私の結論は、今回の大野病院の事故 は、絶対医療過誤ではないと自信をもって私は 言いたいと思います。以上でございます。
○玉井(医師会) 永山先生、ありがとうご ざいました。
引き続きまして、これは司法の立場から阿波 連光先生にお話しいただきたいと思います。
○阿波連弁護士(医師会)

私はこういう仕事をやっているからというこ とではなくて、何人かで勉強会みたいなものを しているんですけれども、その仲間と、この事 件に関しては、福島地検のほうに抗議文を出し ています。どうして抗議文を出したかという と、過失があったとか、なかったとかという中 身の問題ではないんですね。なぜ抗議をしたか と言うと、それは逮捕したからなんです。
逮捕というのは何のためにするかというと、 僕らの世界では本人が逃げたり、それから証拠 を隠滅する可能性があるから逮捕するんです よ。では本当にこの事件でお医者さんが逃げる 可能性があったのかと。それから、証拠を隠滅 する可能性があったのか。そこをきちんと検証 しないまま逮捕している可能性があります。と 言うよりも、おそらく必要はなかったでしょ う。もうカルテも全部差し押さえしています し、お医者さんは逃げずにずっと勤務をしてい たわけですからね。なぜそういう人の身柄をと る必要があったのかと。
今回の事件のもう一つの大きな問題点は、こ のお医者さんは医療過疎の地域で1人で頑張っ ていた産婦人科医なんですね。彼を逮捕すると いうことは、当然ほかの患者さんにものすごく 迷惑をかけるわけですよ。今まで、もうすぐお産になるという人たちはそのお医者さんを頼っ てずっとここまで病院に通っていたわけですか らね。それが突然、その人の身柄をとってほか の人たちの医療の機会を奪ってしまうと。だか らそこにまず、いい・悪いの過失があったか・ なかったかという問題に入る前の問題として、 まずそこに問題があったんじゃないんでしょう かというのが僕らの意見だったんです。
医療過誤というのは刑法の中でいうと、どう いう位置づけになるかというと、犯罪というの は悪いことをすると当然処罰されるんですけ ど、大きく分けると「故意犯」というのと、 「過失犯」というのに分かれるんですね。要す るに「故意犯」というのはわざとやったもの。 「過失犯」というのは誤ってやったもの。犯罪 の中の9割以上は故意犯というやつなんです。 きわめて例外的に処罰される場合というのが過 失犯。ここに書いてある「業務上過失致死傷 罪」というのは過失犯の代表的な例です。交通 事故もこの業務上過失致死罪によって処罰され ています。
では交通事故の場合に、死亡事故を起こした 場合に、その犯人を警察は全部逮捕しているん ですかというと、実はそうじゃないんです。ほ とんどのケースは逮捕はしていません。実際は 事故が起こって本人も怪我したりいろいろして いますから、裁判は家から通ってきてください と。事故の現場というのは警察が全部保全して いますから、本人が逃げる可能性がないような 事件に関しては全部裁判所に通って裁判をする んですね。
ですから、当然医療事故に関しても身柄をと らなくたって裁判はできるわけです。ですから 当然ミスをしたドクターを処罰するなというこ とは私たちは考えていませんし、当然そういう ドクターは処罰されるべきだとは思っています けれども、何でもかんでも身柄をとってやるこ とが本当に必要だったのかと。特に今回のケー スみたいに中身の問題としても過失があったか なかったかというのは、非常に難しいケースな んです。そういうケースについて、まず身柄をとってしまって、それから捜査して起訴しよう としたというところにかなり無理があったんで すね。
それから、もう1点、過失の中身の問題を少 しお話ししますと、実は医療過誤事件といいま すけれども、刑法典には一つの条文しかないん ですね。「業務上必要な注意を怠って人を死に 至らせた人はどうする」と、こう書いてあるわ けです。業務上必要な注意を怠ったということ しか法律には書いてないんですよ。この一つの 条文で交通事故も医療事故もいろんな事故をす べて処理しているわけです。ですから、法律に はどこからがアウトで、どこまでがセーフかと いうのが書いてないんですね。だから警察の側 も基準がないし、裁判所側のほうも基準がな い。だから非常に難しい事件の一つなんです。
この事件について刑事上処罰すべきかどうか という判例があるかというと、ないんです。こ れは実際上も個別個別の事件が起こったとき に、裁判所で審理する中で裁判所が基準を立て ていくということになると思います。
ただ、民事の分野では、かなりこの過失の議 論というのはいろんなケースで煮詰まっていま すので、それから類推して考えることはできる んですね。
ただ、刑事というのは人を処罰する過失です から、民事でいう過失よりも当然重い過失なん ですね。
民事の過失はどうやって決めているかという と、基本的にはさっきから出ている医療水準と いう問題になるんです。要するにそのお医者さ んが水準を満たした治療をしているのか、して いないのかと。水準以下であれば基本的には過 失があります。水準を越えていれば、それは結 果が悪かったのはもうやむを得ないねというの が裁判所の考え方です。
この医療水準というのも結局、解釈によって 決まるものですから、そこがまた難しい話なん です。それがさらにもっと難しくなるのは、医 療水準というのは、日本全国北から南まで同じ かというと違うんです。なぜかというと、東京の大学病院と例えば、沖縄の離島の病院とで、 同じ医療水準かというと当然違うわけです。人 も違うし施設も違うし。ですから当然裁判所の 一般的な基準として、それは地域とか、それか ら例えば大学病院であるとかクリニックである とか。そういう施設の規模とか、地域とか、そ の置かれている状況によって細かく考えていき ましょうというのが民事における過失の考え方 なんですね。ですからそれからたどって刑事の 過失というのはどういうものかというのを考え るとなると、もう少しハードルは高くなる。も っと難しい過失になるだろうというふうには思 います。全体としてそういうふうに思っていま して、中身の問題を一つ置くとしても、今回は 身柄をとったということから始まったところ に、非常に大きな問題があったのではないかと いうふうには思っております。以上です。
○玉井(医師会) 阿波連先生、ありがとう ございました。
ここまで県立大野病院の問題について、いろ いろと多方面からご発言、またはご意見を伺っ てまいりました。ここで委員の皆様、何かご質 問等ありますでしょうか。どの先生にこういう ことを聞いてみようということがございました ら、この問題に関してご議論、ご発言いただき たいと思います。何かございますでしょうか。
もしよろしかったら挙手。よろしくお願いし ます。
○上原委員(琉球新報)

新聞の切り抜き資料などを見ても医療過誤、医療訴訟などの専門的で社会的にインパクトの ある事案については、報道する側の責任という か、姿勢というのも試されているなというのを 実感しましたけれども、そういうことを私たち も考えなければいけないと思っているんですが。
今のお話の中でちょっと疑問点は、帝王切開 した後に、胎盤剥離を止めて後日、子宮摘出を するとか、そういう選択というのはまるで考え なかったのかということ。平成15年の統計で69 件の死亡例があるということでしたけど、そう いう中で医療訴訟というのが起こっているの か。そういうふうにして医者が罪に問われたよ うなケースがあるのかというのがわかればお願 いしたいと思います。
○玉井(医師会) 金城先生。永山先生、い かがですか。
そうですね、胎盤を残して後日ということが できるかどうかですね。
○永山(医師会) 全く開始しなかったら手術 をストップしまして、そういう例もできたかも しれませんけれども、手術の途中で、剥離をス トップして後日これをやるというようなことは 多分不可能だっただろうと思います。
そして、この福島大学の佐藤教授からの報告 を私は持っていますけれども、もう最後の最後 でこれは剥離できなかったというようなことだ ったようです。そういう状態ではもう早く子宮 を取ろうというような状況に進んだだろうとい うことが予想されます。
○金城(医師会) 69例の内訳はよくわかりま せん。それから、医療について逮捕されるかど うかと、これはおそらく刑事事件での逮捕はこ れまでないと思うんですけど、民事については あるんですよね。警察が入ったからということ で今大騒ぎになっているのであって。民事につ いてはいろいろあります。
○玉井(医師会) 69例の中には民事的に そういう訴訟になっていることはあるというこ とですね。
○金城(医師会) そうですね。ほとんどは 民事で解決しているんですがね。
今度の特異なところは、逮捕された、おそらく不可抗力だろうというものを逮捕したというのが大きな問題なんです。
○玉井(医師会) よろしいでしょうか。何か、またほかにご質 問等ありますでしょうか。
○銘苅委員(沖縄タイムス)

今、皆さんの説明を聞きまして、今回のケー スは不可抗力、あるいは避けられない医療のケ ースだったということが改めてわかってくるん ですけれども、ちょっと一つわからない点があ ります。今、全体の流れを見ますと、県の事故 調査委員会が、今回過失と認めているわけです よね。これが3月30日、それを受けて捜査当局 が慌しく動いているという形。4月9日、約10 日以内で動いているわけですけれども、そこの 流れを見るとやっぱり県の調査委員会の決定 が、今回の逮捕という結果につながっているん じゃないかなと考えられるんですけれども。
例えば、産婦人科医の皆さんが、それぞれ今 回の場合は不可抗力という話をしている中で、 この事故調査委員会の中で医師側の立場を主張 する人がいなかったのか。あるいはメンバーが どういう形だったのか、そこの皆さんの今の話 に納得というか、説得力があればここまでの事 態に至ったのかというのが非常にあるんです。 この結果がなければそこまで逮捕ということに はいかなかったんじゃないかと思います。
○永山(医師会) これは私から知っている 限りのことをご報告したいと存じます。
実は、医療訴訟の問題、慰謝料の問題が背景 にあると言われています。
それからもう一つ、県立病院の事故調査委員 会は、実はある福島の県立病院の産婦人科の部 長が1人加わっています。3名ですけど、お1人 は産婦人科の医者ではございません。確か外 科、どこかの病院長か、あるいは病院の部長だ ったと思います。それから、お1人は福島県立 医科大学の講師が入っています。講師の先生は これは絶対、医事紛争になるようなものではな いということで反対されたそうです。これは医 療行為であって、医療行為の結果で不幸な状況 になったということですけど、医療過誤、医者 側に責任があるということは認めていません。 それで3名で2対1で、結局、有責にしようとい うような結果になったそうです。そうでなけれ ば、結局は遺族の方にお金がおりないというよ うな状況だったようです。これははっきりとし た、こういうような報告を私は持っています。
○玉井(医師会) この有責にしなければ補 償がおりないということについて、稲田先生、何 かご発言ありますか。
○稲田(医師会)

今の保険制度では医師に何らかの非がなけれ ば、当然、保険という制度上、患者さんに損害 の慰謝料、賠償がおりないというのがあって、 今、医師会でも問題にしているのは、過失があ ろうがなかろうが、そこで起きた事故に対して はちゃんと補償がされるような制度にして、も っと率直に医療者も患者さんもこういう問題に向き合えるように制度を変えるべきではないか と。「無過失賠償責保険制度」というのが今検 討中であります。ただし、大変な困難があっ て、お金の問題なんですね。だから今、日本医 師会としてはこれに対していろいろ検討中であ ります。
進捗状況としては、現時点では産婦人科の問 題なんですが、脳性麻痺という非常に確率的に も大変避けがたい子供の誕生に対して、それに までドクターの責任を問われて大変な訴訟があ ったりしますので、そこに限定した形で、これ は諸外国でもいくつかそういう保険があるもの ですから、それを真似て日本でもこういう、こ の部分に関して脳性麻痺の子供の訴訟に関して 過失を問わず保険をあげようじゃないかとい う、こういう動きが日本医師会で検討中であり ます。今の話はそれであります。
もう一つ、先ほどの銘苅委員のことに関連し ますが、県立大野病院報告書はこれがすべてで す。これを私はある人からいただいたんです が、呆気にとられたと言っています。というの は、ただこれだけなんですよ。これだけ重大な 事件である報告書がほんの何ページかで結論を 出しているということで、これだけの重大な事 件に対して、このような報告書しかないと。こ のような報告書に基づいて事が突っ走ったとい うか、そういうような印象すら受けます。
○国吉委員(沖縄いのちの電話)

今、お聞きしまして、保険の問題も非常に重 大だなと思いますし、そうすると医者側、病院の側では患者の立場を考えると、医療ミスを認 めないといけないような感じにもなりますし、 そしてまた沖縄からも反論を送ったということ ですが、その調査委員会は、あるいは全国から きたかもしれませんけれども、そういうことに 対しても報告書だけで終わっている状態なの か、その後どうなっているのかちょっとお聞き したいです。
○玉井(医師会) その後の状況はどうでし ょうか。
永山先生、ご発言できますか。
○永山(医師会) 日本医師会と、それから 先ほど金城先生からご報告がありました、日本 産婦人科学会、それから日本産婦人科医会、い わゆる産婦人科の開業医が必ず入らなければい けないというような医会、その3カ所で現在、 こういうような事件に対しまして、第三者、直 接関係しない方々に集まってもらいまして、こ の大野病院の件だけではなくて、今後は第三者 に判断してもらうような会をつくるということ で、厚生労働省と約束して、厚生労働省もそう いうふうに認めております。
それから、日本医師会も先ほど話しましたよ うに、早目に第三者機関をつくって、先ほどの 異状死の問題もありますし、医者の医療行為が 刑事罰、そういうような犯罪にどういうような 医療行為というのがあたるかどうかというのを 早目に定義していただきたいと、そういうよう な会を早目に立ち上げるということが日本医師 会とも国は約束したという報告がございます。
○玉井(医師会) 金城先生、今回の資料をつ くるにあたって、様々手を尽くして、資料を集 めたということですけど、ほとんど資料は集ま らなかったですよね、先生。
○金城(医師会) 4月に産婦人科学会があっ たものですから、もっと詳しいことを知りたい という福島県立医大の教授にお願いしたら、カ ルテはすべて警察に押収されてしまって、そこ にあるのはさっき稲田先生から報告された報告 書だけで、詳しいことはこれ以上はもう手に入 らないそうです。すべて警察にいっているものですから。
○玉井(医師会) 薄っぺらなあの報告書だ けなんですね、今、我々が議論できるのは。
何かほかにありますでしょうか。
○金城(医師会) 裁判は6月に始まるそうな ので、6月になったらわかるだろうということ を言っていました。
○山内委員(沖縄県社会福祉協議会)

ちょっと話の方向を変えるようで恐縮なんで すが。
最初の玉井先生のレジュメの中で大変共感と いいますか、特に質問というわけではなくて感 想としてお聞きいただければと思うんですが。
私ども福祉の領域の場面でも介護過誤といい ますか、介護に関する事項はかなり多くて、そ の中で玉井先生のレジュメの4ページで「謝罪 と有罪の意味」というところに目を引かれたん ですが、やはり私どもはよく耳にするときに介 護現場での事故が起こったときに、そこでどう 対応するか、まず最初に謝罪をすべきなのか、 それとも責任はないという姿勢を貫くべきなの かということが大変問題になります。この件に 関して、例えば保険会社さんなどを招きまして 講演をすると、「いや、謝ってはいけない」と か、弁護士さんをお招きすると「最初に謝った ほうがいい」と、いろんな意見があるんです が、やはりこちらの中で玉井先生がお書きにな った、率直に結果に対する言葉はあるべきであ るということは原理原則だろうというふうに感 じながら読ませていただきました。
私ども最初に謝る、謝らないでそのあとの責 任の取りように影響するということがあっては いけないと。ただ、今回の事件の中では、県の 謝罪というものが、その頃のマスコミの論調の 中で、いかにも責任を認めたというふうなとこ ろに傾いていったんじゃないかというご指摘も ありましたが、私どもはそのへんを心しなが ら、そういう直後の対応ということには誠意を 尽くしていかなければいけないんだなというこ とを感じさせられました。以上です。
○玉井(医師会) 謝罪について阿波連先生、 いかがでしょうか。謝ったほうがいいんでしょ うか、謝らないほうがいいんじょうか、我々は。
○阿波連弁護士(医師会) このへんは人生 観の問題にかかわってくるかもしれませんけれ ども、私が思っているのは、まず事実をきちん と把握することが先なんだろうと思います。事 実の経過をきちんと説明して、お互いに共通の 理解のうえで、そこに落ち度があれば当然謝る べきだと思います。
ところが、事態も把握しないで、何か結果が 起こったことからすぐ「ごめんなさい」という 話をすると、当然謝られた側というのは、次に また賠償に対する期待というのを持ってしまい ます。とにかく僕がよく言っていることは、ま ずきちんと事実を整理して、お互いに共通の理 解に立って、本当にそこに落ち度があるのであ ればちゃんと謝ってくださいと。だけど、そう いうこともしないですぐ伏せようとして謝った りすると、お互いにもっと不幸なことになると いうふうには言ったりします。
それから、もう一つ。裁判というのは、自白 と否認というのがあって、それはこれとは別の 意味なんですけれども、今回の大野病院の事件 で、逮捕したもう一つの理由は、自白をとるた めだった可能性はあるんですよね。要するに、 この裁判は非常に難しい裁判なものですから、 証拠の王様と言われているのは自白なんです よ。そのドクターが認めてしまえば基本的には 裁判はすごく楽になるんです。そのためにどう するかというと、よくあるのがとにかく身柄をとってしまう。当然、お医者さんは拘置所に身 柄を拘置、勾留されたこともないでしょうし、 1週間も10日も勾留すると、大体、僕らはよく 事件でそういう人たちに会いますからわかるん ですけれども、最初の3日ぐらいは元気なんで すよね。だけど、だんだん疲れてくるんです よ。「もう自分はもう早く出たい」と。「出られ るんだったら認めてもいい」と。「先生、この 事件で自分が刑務所に行くことはないんでしょ う」と。業務上過失致死でなかなか刑務所まで 行きませんので、裁判の結果としては普通、重 くても執行猶予の判決なんです。そういう結論 をある程度知ってしまうと、自分が牢屋に行か ないんだったら、もう早く認めて1日も早く保 釈で出たいという、こういう構造になりがちな んですね。そういうところも見て、身柄の確保 に踏み切った可能性はあるなとは思っておりま す。本音のところです。
○玉井(医師会) かなりシビアなことがわか ってまいりました。
それ以外に何かご質問等ありましたら、いか がでしょうか。
○国吉委員(沖縄いのちの電話) 質問では ないんですが、今思い出したんですが、実は私 の友人の子供が小学生のときにアメリカ軍人に 轢かれて亡くなったんですよね。そのときに新 聞も非常に大騒ぎしました。そのアメリカ軍人 は謝らなかったんです。日本では道義的にま ず謝るというのがあるんだけど謝りもしない。 それで、あとでわかったことはアメリカの法律 では、謝らないんだと。向こうは裁判のあとで しか、裁判の結果が出る前に謝るといけないと いう考え。日本の道義的な考えと、何か難しい ような感じで、今回の福島の事件、病院は本当 に過ちとして謝ったのかどうか、ちょっと今で も疑問に残るような感じがするんですけれども。 そういうことです。
○玉井(医師会) 謝っている写真が新聞に 報道されております。かなり深々と頭を下げた 写真が報道されております。見た感じも悪いこ とをしたんだなというふうに見えたのも当たり前かなというふうにも思います。
他に何かご質問ありますでしょうか。
○金城委員(沖縄県土地改良事業団連合会)

質問というわけではないんですが、先ほどの 話と関連して私のまわりでこういったことが今 度テーマになるということで、ちょっと2、3、 お話ししたんですね。そうしましたら、うちの 職場とかまわりの人というのは、直接医療にか かわりのない人ばかりなので、情報を得るもの がほとんどローカル紙です。沖縄タイムスであ ったり琉球新報であったり。そうすると、今回 送られてきたような細かいこととか、今のお話 で知ったようなこととかというのが入ってこな いので、皆さんやっぱり「こういうことがあっ たら怖いよね」とか、それからやはり帝王切開 とかいう手術になると、患者対医者、密室とい うか外部には全然わからないわけだから、やっ ぱりこういったようなことがあったらとても心 配だよねという、こういったものが先に立って 話が進んだんですね。今話を聞いていて、なる ほどな、こういうことがあったのかとか、謝っ たのはそういった賠償問題とか、そういったも のもあるのかと、裏側がいろいろわかってきた んですけれども。本当にこの委員会に参加して 常々思うことなんですけれど、やっぱりコミュ ニケーションというか、情報発信というか、そ ういったのを正確に、本当にリアルタイムで伝 えていかないとやっぱり誤解を招くのかなとつ くづく思っております。
ですから、病院なり、お医者さんの皆さんなり、個人レベルでの情報発信でもいいですし、 組織としてぼんぼん発信するのも大いに歓迎で すし、そういったことの情報提供は常時やって いただけたらなと思います。
○玉井(医師会) ありがとうございます。
これに対して何かご回答いただけますか。
稲田先生。
○稲田(医師会) 大変貴重なご指摘だと思 います。と言いますのは、この事故にかかわら ず様々な医療分野での医療事故というものの紛 争の間に立って患者さん側のお話を伺ったり、 病院側と話をしたりとか、委員会を開いたりと いう、紛争処理の仕事をやっておりますと、例 えば患者さん本人、あるいはご遺族と個別に面 談をさせていただくときに、やっぱり説明して ほしい。何でこんなことが起こったのか、詳し く知りたい。どの方もそういうことをおっしゃ います。どこらへんを求めているかというとこ ろで、その説明、プロセスを何回も繰り返す中 で事実もちゃんと相互理解をつかんでいただい て、それからどうしようかという、進んでいく んですね。その意味では、我々の側がちゃんと 説明をしていくという、いろんな時間がないと か、医療業務の中で大変な疲労があるというこ とを乗り越えても説明というのは患者さん、国 民の側が求めておられることだろうというふう に思います。確かにお互いのコミュニケーショ ンが必要なんだと感じます。
思い出しますのは、あるマスコミの方々たち との座談会で、私が医療事故の構造とか、今の 医療業界の話を相当長くさせてもらったことが あるんですが、あるマスコミの方が「あなたの 言うことはわかるんだけど、所詮医者の言い訳 にしか聞こえない」と一言で切って捨てられ て、がくっときまして、しかし、このがっくり きた感覚をまた受け止めながらコミュニケーシ ョンを図らないといけないなと思いながら、一 生懸命話をさせてもらった記憶があります。
だから、そこのマスコミの方のご指摘という のは、大きな医療側と患者さん側との間の壁を マスコミの人は代表して述べられたんだろうというふうに思いますし、そういう感想でござい ます。
○玉井(医師会) 他に何かご発言、ござい ますか。
○上里委員(沖縄県中小企業団体中央会)

医療の過誤ということで考えると、自分が間 違えたかどうかというのは本人が一番よくわか るばすですよね、医者にとっては。ミスをした か、しなかったかというのは一番はっきりとわ かると思うんですね。
先ほどの弁護士の先生の話では、はっきりす るまでは謝るなというふうな雰囲気で話されて いましたけれども、それは僕はおかしいと思う んですね。間違ったなと思ったら率直に謝らな いといけないと思うんです。間違ったか・間違 っていなかったか判断ができないようだと、こ れは医者としておかしいのではないかというふ うに思います。
ですから、いろいろとここにも書いてありま すけれども、この新聞の記事を全部読んで比べ てみますと、明らかに無理矢理に剥がしたとか、 いろんなことが書かれておりますし、だれがど の記事のほうが正しいのかよくわからないんで すけれども。一番、本人がよく知っていると思 うんです。そういうことを言いたかったです。
○玉井(医師会) 医者が自分での判断をし てくださいということですけれども、何かご発 言できる方いらっしゃいますか。
小渡先生。これはやはり先生に話していただ かないと。
○小渡(医師会)

非常に明解で、ごもっともなんですよ。そう いうものに関してはほとんどの医者は端的に謝 っていると思いますよ。ほとんどのケースがそ ういう単純なものはあまりないです。というの は、ほとんどのケースは「予見義務違反」とい う形でくるんですよね。「業務上過失致死」とい う形でくるわけですね。ということは、医療ミ スをしようと思っている人はいないわけですね。
それから予見義務違反というのは、例えば精 神科の世界でやりますと、入院させたと。この 人を入院させたということは、例えば自殺の可 能性があると。家で見ると危ないですよと、家 族も危ないので入院させましょうと。入院させ たときには当然、病院側としてもこれは自殺癖 とかあるんだということをある程度予見できる んですよ。だけどその中で気をつけて見ていて も自殺される場合があるんですね。だけど、さ れたら最後ですね。訴えられると、医者として は「予見義務違反ですよ」と言われるだけです よね。だからそういうことになっていた場合 に、その医者としてはこれはやっぱり医療ミス なのかなということで悩むケースもたくさんあ るんですね。
例えば単純に外科の手術で切ってはいけない 血管を切ってしまったら、こんな簡単なものだ ったらこれはすぐ謝ると思うんですね。そうじ ゃないケースが非常に多いんですね。そこがま た複雑なんですね。そういうことも一つ理解し ていただきたいなと。
それから、先ほど金城委員からのご意見で非常にそうだなと思うんですよね。仲間で話して も、そういう新聞を見て、これは怖いよねとい う話をする。だけど、こういうところに来てい ろんな情報を得ると、一概にこれだけの情報で は判断できないんだなということがわかると思 うんです。それをどうすればいいかということ なんですけれども、これは私は市民の意識と か、レベルとかが上がってもらわないといけな いと思います。何に対してかというと、マスコ ミに対して。要するにマスコミが書いているの を鵜呑みにしてはいかんと思うんですね。それ は別に医療界の問題だけじゃないです。どの業 界の問題もいっぱいあるわけですよね。環境問 題もあるでしょうし、廃棄物の問題もあるでし ょうし。あるいは最近では姉歯の建築の問題も あるだろうし、これが出たときに、あ、そうだ なとすぐ真に受けないようにするぐらいの市民 のレベルがないといけないと思うんですね。あ、 こういう見方を新聞はしているのかと。だけ ど、これがすべて真実かなという疑問を持てる ような社会にならないといけないと思うんです よ。元来はマスコミもそのことを考えて仕事を していると思いますね。だけど、マスコミはマ スコミの立場で同じようなことがあるんです ね。例えば新聞が売れなければ潰れるわけです から。その意味ではどのようにして書けばいい かということになるわけですよね。
先ほど、有責だと言った場合に、僕らが無責 だと言ったら保険料は出ないわけですよね。そ れと似ている部分もたくさんあるんですね。こ れは社会矛盾かもしれませんけれども。
ある意味では、市民そのものもいろんなもの を見たときに、一面的ではいかんのではないか という感覚を持てればいいんじゃないかと。あ る意味では、反対の意見のいろんなマスコミが あっていいと思うんですよね。それを市民が選 択できればいいんだけど、なかなかそういう時 代にはなっていないと。それは少し残念ですけ れども。そういうことを少しでもできるように なればいいなということで、こういう懇親会を やっているという意味もあるんじゃないかなという具合に思っております。
○又吉委員(沖縄県経済同友会)

時間が随分押しているのですが、一つだけ教 えてください。
玉井先生が書か説明された中で、「是非わか って頂きたいこと」ということで、非常に簡単 に「医療はだれのためにあるのか」ということ で、最後のところに「その他大勢の医療スタッ フのためにも医療はあります」というふうに、 お話しがあったんですけれども、すみません、 具体的にどういうことですか。
○玉井(医師会) 医療というのは患者さん側 が受ける側、我々が提供する側という一方的な ものではなくて、お互いに協力し合えるものじ ゃないかなと僕は思っております。
そういう形で、我々が理解を深めていって協 力できるようになれば、いろんな問題だとか、 いろんな誤解だとかということが解けるんじゃ ないかなというふうに思っております。答えに なっているかどうかちょっとわかりませんけれ ども、いかがでしょうか。
○銘苅委員(沖縄タイムス) 先ほど、小渡 さんのほうからいろいろマスコミには耳の痛い 言葉があったんですけれども、新聞社側から言 いますと、世の中にはいろんな見方がありまし て、今は県医師会の立場、あるいは遺族の立場 とか、世の中にはいろいろな見方があると思う んですよ。その中でやっぱり新聞社、あるいは 報道機関というのは、いろんな見方をみながら 一つの事実を追いかけていこうというのが私たちの立場でして、常にその努力は怠っていない つもりでやっております。確かに、事実は事実 なんですが、真実はまた別のところがあると。 そういう意味では読者のすべての方に満足いた だける立場にはないんですけれども、そういう 事実の観点を追いかけているという点は理解し てもらいたいと思っております。
と同時に、そういう意味では必ずしも一つの 見方ではなくて、新聞でもなくて、テレビでも なくて、直接いろんな方々の意見を聞いて、物 事の一つの見方をするということもこれからは 必要な時代ではないかなと思っております。そ れは同じです。そういう意味では、こういう機 会の場は有益な形になると思います。
今回の福島県のケースに限らず感じること は、医療過誤という点については、この十何年 やっと市民のレベルでも意識として芽生えてき ているんじゃないでしょうか。どうしても患者 さんの立場からすると、まだ弱い立場なんです よ。医療過誤ということは一般市民にはまだま だ十分いきとおってないんじゃないかと。
今回の福島のケースもそれが医者の皆さんに とっては、今回のケースは不本意だと思うんで すけれども、こういう形で、僕らが知らない部 分を教えていただいて、いい方向にもっていけ ればなと思っております。

会場風景
○玉井(医師会) 他に何かご意見あります でしょうか。
○永山(医師会) 私から、二つばかり申し 上げたいと思います。
実は数年前にやっぱり妊婦さんが麻酔事故で 亡くなりまして、実際は起こった場所は那覇だ ったんですよね。それが南部のある産婦人科で ということで、タイトルが社会面に出まして、 南部といいますと産婦人科が二つございまし て、南風原に一つあります。そこに集中しまし て、先生のところではないですよねということ の電話がございました。ちゃんと考えてもらっ て報道していただきたいと。
それから、その話は別にいたしまして、今回 の事件で一番大事なのは家族の悲しみですよ ね。それを我々医者は真っ向から受け止めまし て、担当の先生、あるいは病院も大変つらい立 場ではあっただろうと思います。それをそうし ながら、でもやっぱり家族の悲しみというのを 真っ向から受け止めまして、お気持ちが安らぐ ときを待つべきだと思います。
そして、県立病院側、あるいは福島県は賠償 の問題とか、いろんなことを、こういうような 悲しみの状態のときに、こういう話を持ち出す というのは当然気持ちとして受け入れることは できないだろうと思います。
それが今後、医者側と病院側と、それから患 者さん側が共感できるような状況を早くつくっ てもらいたいと。一開業医といたしまして、そ れを望まずにはおられないという気持ちが本当のところでございます。

会場風景
○玉井(医師会) 時間が過ぎております。 このへんで今回の会はお開きとさせていただき ます。
各委員からのご質問に関しては、持ち帰らせ ていただきまして、当ふれあい広報委員でご回 答させていただきたいと思います。
それでは最後に当会副会長の小渡先生にしめ ていただこうと思います。よろしくお願いします。
○小渡(医師会) 委員の皆様方、大変長時 間にわたって貴重なご意見をいただきまして誠 にありがとうございます。
本来、この会は皆様の意見をたくさん聞きた いんですね。そういうことを趣旨としています けれども、たまたま今回のケースはどうしても 説明がないと理解ができないという、ちょっと 専門的な分野がありましたものですから、ちょ っとこちらからの説明が長時間にのぼって大変 申しわけないなという具合に思っております。
ただし、この事件に関して、我々は別に言い 訳がしたいとか、そうは思っていません。た だ、この事件の事実関係がどうだったのかとい うことの説明をしたいということなのです。そ のことを少しでも県民の方々に理解してもらえ ればいいんじゃないかなと。それも皆さんが評 価することであって、我々の説明を聞いたか ら、「ああ、そうだ、そうだ」と思う必要はな いと思います。こういう考え方もあったんだな ということでもいいと思うんです。我々として は事実は事実として、きちっと県民が評価でき るような、評価するのはそちら側ですから、 我々は評価を受ける側ですから、そういう意味 ではきちっと正しい評価が受けられるように、 我々も当懇談会等を通して今後とも努力を続け ていきたいと考えております。本日は、長時間 ありがとうございました。
注釈:話し言葉で議論されているものを、発 言者の内容趣旨を重んじながら、簡素 化してまとめさせていただきました。
広報委員会