娞墛偺恌抐偲僂僀儖僗儅乕僇乕
僴乕僩儔僀僼昦堾徚壔婍撪壢丂嵅媣愳丂淎
亂梫丂巪亃
娞墛僂僀儖僗偼媫惈娞墛偍傛傃枬惈娞幘姵偺庡梫側尨場偲側傞丅杮朚偱尒傜傟傞 僂僀儖僗惈媫惈娞墛偼庡偵A丄B丄C宆偱偁傝丄偦傟偧傟丄IgM-HA峈懱丄IgM-HBc 峈懱丄HCV-RNA掕惈偱恌抐偡傞丅傑偨丄嵟嬤偵側偭偰E宆娞墛偺崙撪敪徢椺偺曬 崘偑憹偊偰偍傝丄媫惈娞墛偺恌椕偵偁偨偭偰偼擮摢偵偍偔昁梫偑偁傞丅枬惈娞幘姵 偼柍徢忬偺偙偲偑懡偄偑丄娞峝曄傗娞娻偵恑峴偡傞徢椺偑偁傝丄梫拲堄偱偁傞丅柍 徢忬偺娞婡擻堎忢幰偑棃堾偟偨応崌丄愭偢HBs峈尨偲HCV峈懱偱僗僋儕乕僯儞僌 偡傞丅偙傟傜偺専嵏偑梲惈側傜丄僂僀儖僗検傪應掕偟丄昦懺偺昡壙傗帯椕曽恓偺寛 掕傪峴偆丅HBV検偺應掕偼PCR朄丄TMA朄偑桪傟偰偄傞丅HCV検偺應掕偼丄HCV 僐傾峈尨偑姶搙偍傛傃應掕儗儞僕偵偍偄偰枮懌偺偄偔専嵏朄偱偁傞丅
偼偠傔偵
娞墛偼僩儔儞僗傾儈僫乕僛乮GOT丄GPT乯 偺忋徃傪摿挜偲偡傞偑丄娞峺慺偺忋徃偼條乆側 尨場偵傛偭偰婲偙傝丄偦偺恌抐偼堦斒偵梕堈偱 側偄丅娞墛偺拞偱傕丄娞墛僂僀儖僗偵傛偭偰婲 偙傞応崌偼丄寑徢娞墛傗娞峝曄丄娞娻偲偄偭偨 廳撃側幘姵傪棃偨偡偙偲偑偁傝丄揑妋側恌抐偲 帯椕偑媮傔傜傟偰偄傞丅嬤擭丄娞墛僂僀儖僗偵 娭偡傞尋媶偑媫懍側恑曕傪偲偘丄娞墛偺恌抐偲 帯椕偵娭偡傞懡偔偺怴偟偄抦尒偑摼傜傟偰偄 傞丅杮榑暥偱偼丄娞墛偺恌抐偵娭偟偰丄僂僀儖 僗惈娞墛傪拞怱偵丄嵟嬤偺抦尒傪岎偊側偑傜夝 愢偟偨偄丅
嘥丂媫惈偲枬惈偺堘偄
娞墛偼戝偒偔丄媫惈偺昦婥偲枬惈偺昦婥偵暘 偗傞昁梫偑偁傞丅堦斒偵媫惈娞墛偼徢忬傪桳 偟丄枬惈偺幘姵偼恑峴偟偨徢椺傪彍偄偰柍徢忬 偱偁傞丅娞憻偺愱栧壠偼娞墛偲偄偆昦柤偼梡偄 側偄丅昁偢媫惈偐枬惈偐傪嬫暿偟偰昞尰偡傞丅 媫惈偲枬惈偱偼丄摨偠傛偆偵娞墛僂僀儖僗偵傛 偭偰婲偙偭偰傕丄傑偭偨偔暿偺幘姵偲尵偭偰傛 偄傎偳昦懺偑堎側傞丅
嘦丂媫惈娞墛
娞墛僂僀儖僗偼A乣E傑偱5偮偵暘椶偝傟傞 偑丄偦偺奺乆偼媫惈娞墛偺尨場偵側傞乮恾1乯丅 擔杮偱憳嬾偡傞偺偼A丄B丄C宆偺3庬椶偺僂僀 儖僗偵傛傞媫惈娞墛偱丄偲傝偁偊偢丄偙傟傜偺 僂僀儖僗偺姶愼偺桳柍傪傒傞昁梫偑偁傞丅媫惈 娞墛偺姵幰偝傫偑庴恌偟偨応崌偵専嵏偡傞崁栚 偼IgM-HA峈懱丄IgM-HBc峈懱丄HCV-RNA掕 惈偺3偮偑廳梫偱偁傞丅偙傟偩偗偱偩偄偨偄偺 応崌偼懌傝傞丅偙傟偵HBs峈尨偲HCV峈懱傪 壛偊偰丄5偮偺専嵏傪峴偊偽丄ABC偺3偮偵僂 僀儖僗偵傛傞媫惈娞墛傪恌抐丄偁傞偄偼偙傟傜 偑堿惈偺応崌彍奜偡傞偙偲偑偱偒傞丅埲壓偵偦 傟偧傟偺専嵏偵偮偄偰娙扨偵夝愢偡傞丅
乮1乯A宆偺恌抐
A 宆娞墛僂僀儖僗偼暢岥姶愼偡傞僂僀儖僗 偱丄堦夁惈偵姶愼偟丄擇搙滊姵偡傞偙偲偼側偄 偲尵傢傟偰偄傞丅A宆娞墛僂僀儖僗偵懳偡傞専嵏偼HA峈懱偲IgM-HA峈懱偑偁傞偑丄媫惈娞 墛傪恌抐偡傞応崌丄IgM-HA峈懱偩偗偱廫暘偱 偁傝丄HA峈懱乮偙偺応崌丄庡偵IgG僋儔僗偺 峈懱傪應掕乯偼昁梫側偄丅HA峈懱偺専嵏偼偳 偺傛偆側偲偒偵昁梫偐偲偄偆偲丄椺偊偽丄搶撿 傾僕傾側偳偺A宆娞墛僂僀儖僗偑枲墑乮悈宯偵 揱攄乯偟偰偄傞抧堟偵巇帠偱弌偐偗傞恖偵偮偄 偰A宆偺姶愼偺婛墲偺桳柍傪僠僃僢僋偡傞応崌 側偳偱偁傞丅HA峈懱偑梲惈偱偁傟偽丄姶愼偺 婛墲偲嫟偵姶愼杊屼峈懱傪桳偟偰偄傞偲峫偊偰 傛偄丅
乮2乯B宆偺恌抐
B宆偺娞墛僂僀儖僗儅乕僇乕偼幚偵懡庬椶懚 嵼偡傞偑丄偦偺拞偱IgM-HBc峈懱偺傒偑媫惈 娞墛偺恌抐偵桳梡偱偁傞丅弶姶愼偱偁傟偽丄傎 傏娫堘偄側偔IgM-HBc峈懱偑梲惈偱偁傞偑丄B 宆偺応崌柍徢岓惈僉儍儕傾偐傜偺媫惈敪徢傕媫 惈娞墛偲傎傏摨條偺昦懺傪掓偡傞偨傔丄HBs峈 尨傕暪偣偰應掕偟偨曽偑朷傑偟偄丅
乮3乯C宆偺恌抐
C 宆娞墛偺弶姶愼椺傪恌傞偙偲偼婬偵側偭 偨丅C宆媫惈娞墛偺応崌丄HCV峈懱偑弌尰偡傞 傑偱偵帪娫傪梫偡傞偙偲偑偁傝丄HCV峈懱偺 應掕偺傒偩偲尒摝偡壜擻惈傕崅偄丅C宆媫惈娞 墛偺恌抐偺偨傔偵偼HCV-RNA偺掕惈専嵏傪峴 偆昁梫偑偁傞偑丄曐尟恌椕偲偟偰擣傔傜傟側偄 壜擻惈傕偁傞丅曐尟恌椕偱應掕偡傞応崌丄昦忬 偵懳偡傞僐儊儞僩偑昁梫偵側傞丅
乮4乯E宆娞墛
偙傟傑偱丄擔杮崙撪偱姶愼偡傞壜擻惈偺偁傞 娞墛僂僀儖僗偼A丄B丄C偺3庬椶偲尵傢傟偰偄偨偑丄2000擭埲崀丄杒奀摴傗搶杒傪拞怱偵E宆 娞墛偺崙撪姶愼椺偑懡悢曬崘偝傟傞傛偆偵側偭 偨丅偦偺敪惗昿搙偼C宆媫惈娞墛傛傝傕崅偔側 偭偰偄傞丅E 宆娞墛偼恖抺嫟捠姶愼徢 乮Zoonosis乯偱丄恖傊偺庡側姶愼宱楬偼丄撠丄 僀僲僔僔丄幁側偳偺擏乮摿偵儗僶乕偲儂儖儌 儞乯傪惗傗惗偵嬤偄忬懺偱愛怘偡傞偙偲偲偝傟 偰偄傞1乯丅壂撽偱傕寛偟偰婬偱偼側偔丄2003擭 傛傝丄枅擭1椺偺姶愼椺偑妋擣偝傟偰偄傞丅E 宆娞墛偺恌抐偼IgM-HE峈懱偐HEV-RNA傪應 掕偡傞昁梫偑偁傞偑丄巆擮側偑傜崱偺偲偙傠曐 尟揔墳偵側偭偰偄側偄丅
昞1偵僂僀儖僗惈媫惈娞墛偺恌抐偵偍偗傞奺 庬娞墛僂僀儖僗儅乕僇乕偺桳梡惈偲曐尟揔梡偵 偮偄偰傑偲傔偨丅
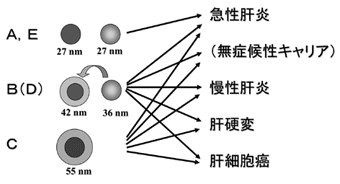
恾1丏娞墛僂僀儖僗偲娞幘姵偲偺娭楢
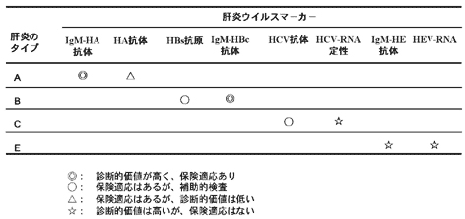
昞1丏媫惈娞墛偺娪暿恌抐偲曐尟揔墳
嘨丂枬惈娞墛
枬惈娞墛偼堦斒偵柍徢忬偱偁傝丄専恌傗專寣 摍偱嬼慠偵敪尒偝傟傞偙偲偑懡偄丅専恌摍偱娞 婡擻堎忢傪巜揈偝傟偨偙偲傪偒偭偐偗偵庴恌偟 偨姵幰偵懳偟偰偼丄堎忢偺尨場傪惛嵏偡傞偙偲 偑廳梫偵側傞丅偡側傢偪丄娞峝曄偵恑峴偡傞昦 婥偐偳偆偐傪恌抐偡傞昁梫偑偁傞丅娞峝曄偵恑 峴偡傞戙昞揑側幘姵偑僂僀儖僗惈枬惈娞墛偱偁 傞丅A乣E偺娞墛僂僀儖僗偺拞偱帩懕姶愼偡傞偺 偼B偲C偱偁傞丅D宆傕帩懕姶愼偡傞偑丄偙偺応 崌偼B宆偺帩懕姶愼傪敽偭偰偍傝丄庢傝姼偊偢丄 B偲C傪挷傋傟偽廫暘偱偁傞丅偟偨偑偭偰丄柍徢 忬偺GPT堎忢幰偑棃堾偟偨応崌丄傑偢HBs峈尨 偲HCV峈懱傪挷傋傞丅摉柺偼偙傟偩偗偱廫暘偱 偁傞丅偙偺2偮偺専嵏偺偆偪偄偢傟偐偑梲惈偱偁 傟偽丄B宆偁傞偄偼C宆枬惈娞墛傪媈偄丄偝傜偵専嵏傪恑傔偰偄偔昁梫偑偁傞丅
乮1乯B宆偺恌抐
HBs峈尨偑梲惈偱偁傟偽丄B宆枬惈娞墛偺媈 偄偑嫮偔側傞丅偙偺応崌丄B 宆娞墛僂僀儖僗 乮HBV乯憹怋偟偰偄傞偐偳偆偐傪昡壙偡傞偙偲 偑廳梫偵側傞丅B宆枬惈娞墛偱偁傟偽丄椺奜側 偔HBV偑憹怋偟偰偄傞丅HBV偺憹怋偺桳柍傪 昡壙偡傞専嵏偲偟偰埲慜偐傜斏梡偝傟偰偄傞偺 偑丄HBe峈尨偲HBe峈懱偱偁傞丅慜幰偑梲惈 偱偁傟偽丄HBV偺憹怋傪堄枴偟丄屻幰偼HBV 偺憹怋偺掆巭傪堄枴偡傞丅HBe峈尨偼HBV偺 峔憿抈敀偱偼側偔丄HBV偑憹怋偡傞嵺偵嶻惗 偝傟偰丄寣塼拞偵暘斿偡傞抈敀偱偁傞丅嫲傜 偔丄HBV偑懠偺屄懱偵姶愼偡傞嵺偵僸僩偺柶 塽墳摎偐傜HBV杮懱傪庣傞偨傔偺僇儌僼儔乕 僕儏偺栶栚傪壥偨偟偰偄傞偲巚傢傟傞丅HBe峈 尨偑梲惈偱偁傟偽丄傎傏椺奜側偔丄HBV偑憹 怋偟偰偄傞丅HBV偑僸僩偺嵶朎彎奞惈T儕儞僷 媴偺峌寕傪庴偗傞偲丄HBe峈尨傪嶻惗偱偒側偄 曄堎宆偺僂僀儖僗偵曄壔偡傞丅曄堎傪婲偙偡偲 HBe峈懱傊僙儘僐儞僶乕僕儑儞偡傞偲嫟偵僂僀 儖僗偺憹怋傕掆巭偡傞偑丄堦晹偺徢椺偱僙儘僐 儞僶乕僕儑儞屻傕憹怋偑尒傜傟傞丅偄偢傟偵偟 傠丄HBe峈尨/峈懱偼HBV偺憹怋傪娫愙揑偵昡 壙偡傞傕偺偱偁傝丄尰嵼偱偼寣塼拞偺HBV検 傪捈愙應傞曽朄偑庡棳偵側偭偰偄傞丅
寣拞偺HBV検傪應掕偡傞曽朄偼20擭埲忋慜 偐傜偁偭偨偑丄姶搙偑撦偔丄椪彴揑偵偼偦傟掱 斏梡偝傟側偐偭偨丅嵟嬤偵側偭偰丄僂僀儖僗偺 妀巁傪憹暆偡傞曽朄傪棙梡偟偰丄傛傝崅姶搙偺 HBV検偺應掕朄偑奐敪偝傟偰偒偰偄傞丅尰嵼 曐尟恌椕偱擣傔傜傟偰偄傞HBV検偺應掕朄偼4 庬椶偁傞偑丄偙傟傜偺拞偱HBV-DNA億儕儊儔 乕僛偲HBV-DNA僾儘乕僽朄偼姶搙偑埆偔丄椪 彴偱偼傎偲傫偳巊梡偝傟側偔側偭偨丅嵟嬤偼丄 TMA朄偲PCR朄偺2庬椶偺HBV検偺應掕朄偑 巊梡偝傟傞偙偲偑懡偄偑丄PCR朄偑傛傝巊偄傗 偡偄偲巚傢傟傞丅偄偢傟偺曽朄傕僂僀儖僗検偼 懳悢偱昞偝傟偰偍傝丄偦偺應掕儗儞僕偼丄 TMA朄偑3.7乣8.7LGE/ml丄偡側傢偪1ml拞偺 HBV検偑5,000乮103.7乯乣500,000,000乮108.7乯 屄偱丄PCR朄偑2.6乣7.6LC/ml乮摨條偵1ml拞 偺HBV検偑400乣40,000,000屄乯偲側偭偰偄傞 乮偪側傒偵丄LGE丗logarithm genome equivalent; LC丗 log. copies偱偦偺堄枴偡傞偲偙傠 偼堦弿偱偁傞乯丅偄偢傟傕偦偺應掕儗儞僕偼 5Log.偺暆偱偁傞偑丄PCR偺朄偑傛傝彮側偄僂 僀儖僗検傪専弌偱偒傞丅HBs峈尨梲惈幰偺戝晹 暘乮90亾埲忋乯偑HBe峈懱梲惈偱偁傝丄HBV 検偼彮側偄偙偲偑懡偄丅偟偐偟側偑傜丄HBe峈 尨梲惈偲敾偭偰偄傟偽丄TMA朄偱應掕偟偨曽 偑傛偄丅
埲慜偺姶搙偺埆偄曽朄偱應掕偟偨応崌偼丄 HBV偑専弌偝傟傟偽丄僂僀儖僗偺憹怋偁傝偲敾掕偟偰傛偐偭偨偑丄TMA朄傗PCR朄偺応崌丄 旝検側HBV偱傕應掕偱偒傞偨傔丄専弌偝傟傞 偙偲偑昁偢偟傕憹怋傪昞偡偙偲偵偼側傜側偄丅 HBV偑専弌偝傟偰傕丄偦偺寣惔拞偺擹搙偑105 僐僺乕/ml枹枮偱偁傟偽娞墛傪婲偙偡偙偲偼婬 偱偁傞丅堦曽丄107僐僺乕/ml埲忋偱偁傟偽丄僂 僀儖僗偵懳偡傞柶塽墳摎偺偁傞僸僩偱偼椺奜側 偔娞墛傪庝婲偡傞2乯乮恾2乯丅HBs峈尨偑梲惈偱 偁偭偰傕偦偺僂僀儖僗検偑105僐僺乕/ml枹枮 偱偁傟偽丄娞忈奞偺婡彉偲偟偰丄B宆埲奜偺尨 場傪峫偊傞昁梫偑偁傞丅
B宆娞墛僂僀儖僗儅乕僇乕偲偦偺椪彴揑側堄 媊傪昞2偵傑偲傔偨丅枬惈娞墛偺応崌丄姶愼杊 屼峈懱偱偁傞HBs峈懱偑梲惈偱偁傞偙偲偼嬌傔 偰婬乮傕偟梲惈側傜姶愼杊屼峈懱偱側偔丄HBs 峈尨棻巕偺堦晹偲偺傒斀墳偡傞旕拞榓峈懱偲峫 偊傞傋偒偱偁傞乯偱偁傝丄應掕偡傞昁梫偼側偄 偲巚傢傟傞丅傑偨丄HBV傊偺朶業傪堄枴偡傞 HBc峈懱傕姼偊偰應掕偡傞昁梫偼側偄偑丄帩懕 姶愼忬懺偱偁傞偙偲傪妋偐傔偨偄偲偒偵偦偺峈 懱壙傪應掕偡傞偙偲偼堄枴偑偁傞丅HBc峈懱偺 應掕偼専嵏儊乕僇乕偵僆乕僟乕偟偨応崌CLIA 朄乮chemiluminescent immunoassay乯偱應 掕偝傟傞丅偙傟傑偱應掕偝傟偰偄偨RIA朄偺応 崌丄帩懕姶愼傪昞偡崅椡壙偺敾掕偼200攞婓庍 偱慾奞棪偑90亾埲忋偲偝傟偰偄偨偑丄CLIA朄 偵傛傞崅椡壙偺敾掕偼10S/CO乮sample/cutoff乯 埲忋偲側偭偰偄傞丅
HBc峈懱偵偮偄偰嵟嬤傢偐偭偨偙偲偼丄偙偺 峈懱偑梲惈側傜椺偊HBs峈尨堿惈偁傞偄偼姶愼 杊屼峈懱偱偁傞HBs峈懱偑梲惈偱偁偭偰傕娞憻 偺拞偵B 宆娞墛僂僀儖僗偑懚嵼偡傞偙偲偱偁 傞丅HBc峈懱偑梲惈偱偁偭偰傕HBs峈尨堿惈 側傜娞墛傪婲偙偡偙偲偼側偄偑丄嫮椡側柶塽梷 惂嵻傪巊梡偡傞応崌偼丄娞憻偱柊偭偰偄偨僂僀 儖僗偑憹怋偟丄娞墛傪堷偒婲偙偡偙偲偑偁傞丅 椺偊偽丄寣塼幘姵偱嫮椡側壔妛椕朄傪庴偗傞姵 幰偺応崌偼丄昁偢HBc峈懱傪専嵏偟丄梲惈偺寢 壥偑弌偨応崌偼丄娞墛偺憹怋偺桳柍傪掕婜揑偵 僠僃僢僋偡傞昁梫偑偁傞丅偙偺応崌傕曐尟偺怰 嵏偑栤戣偲側傞偺偱丄昦忬偺愢柧傪偒偪傫偲婰 嵹偡傞昁梫偑偁傞丅
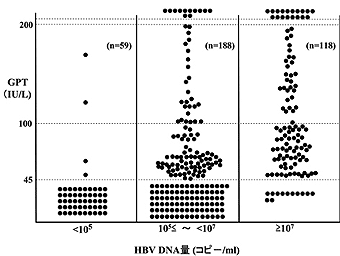
恾2丏HBe峈尨堿惈偺HBV帩懕姶愼幰偵偍偗傞僂僀儖僗検偲娞墛偲偺娭楢
105僐僺乕/ml埲壓偺応崌丄GPT忋徃傪帵偡偙偲偼婬偱偁傞丅堦曽丄107僐僺乕/ml埲
忋偱偁傟偽丄傎偲傫偳偺徢椺偱GPT忋徃傪帵偡丅105乣107僐僺乕/ml偱偼丄娞墛傪婲
偙偡徢椺偲偦偆偱側偄徢椺偑崿嵼偡傞丅
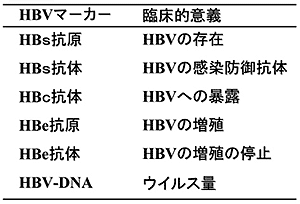
昞2丏HBV儅乕僇乕偲偦偺椪彴揑堄媊
乮2乯C宆偺恌抐
C宆枬惈娞墛偺応崌昁偢HCV峈懱偑梲惈偱 偁傞丅偟偐偟側偑傜丄HCV峈懱梲惈偱偁偭偰 傕昁偢偟傕C宆偲尵偊側偄丅HCV峈懱偼B宆娞 墛僂僀儖僗儅乕僇乕偵摉偰偼傔傞偲HBc峈懱偲 堦抳偡傞丅偟偨偑偭偰丄HCV峈懱偑梲惈偱偁 傟偽丄C宆娞墛僂僀儖僗偵朶業偝傟偨偙偲傪堄 枴偡傞丅偙偺応崌丄帩懕姶愼忬懺偺偙偲偑懡偄 偑丄姶愼偺婛墲傪昞偡偙偲傕偁傞丅HCV峈懱 偑梲惈偲敾柧偟偨傜丄僂僀儖僗偺懚嵼傪妋擣偡 傞昁梫偑偁傞丅HCV峈懱傪應掕偟偨応崌丄捠 忢偼梲惈丄堿惈偺敾掕偩偗偱偼側偔丄峈懱壙偑 僇僢僩僆僼僀儞僨僢僋僗偱昞帵偝傟偰偄傞丅 HCV 偺帩懕姶愼忬懺偺応崌丄B 宆偵偍偗傞 HBc峈懱偲摨條偵丄HCV峈懱壙偑崅偄丅偡側 傢偪峈懱壙偱偁傞掱搙僂僀儖僗偺懚嵼傪悇應偡 傞偙偲偑壜擻偱偁傞丅
HCV峈懱壙偲偦偺昡壙朄偵偮偄偰昞3偵娙扨 偵帵偟偨丅峈懱壙偑5埲壓偺応崌偼丄傑偢僂僀 儖僗偑懚嵼偟偰偄側偄偲峫偊偰傛偄丅偙偺応崌婛墲姶愼傛傝傕婾梲惈偺壜擻惈偑崅偄丅HCV 峈懱偺婾梲惈斀墳偼偦傟掱婬偱側偔丄1,000恖 拞1恖偔傜偄偺妋棪偱弌尰偡傞丅婾梲惈斀墳偲 婛墲姶愼偺娪暿偼RIBA朄偱壜擻偱偁傞偑丄擔 忢椪彴偱姼偊偰娪暿偡傞昁梫偼側偄丅僂僀儖僗 偑懚嵼偡傞偐偳偆偐偑栤戣偲側傞丅
HCV偺懚嵼偼HCV-RNA掕惈専嵏偱妋擣偡 傞偙偲偵側傞偑丄僂僀儖僗偑懚嵼偡傟偽丄椺偊 GPT偑惓忢偱偁偭偰傕C宆枬惈娞墛偺壜擻惈偑 崅偄丅懡偔偺巤愝偱梡偄傜傟偰偄傞GPT偺惓忢 忋尷偼40IU/L 偱偁傞偑丄摿偵彈惈偺応崌丄 30IU/L傪挻偊傟偽娞墛傪桳偡傞偙偲偑懡偄丅
B宆偺応崌丄僂僀儖僗検偲娞墛偺嫮偝偲偺娫 偵偼柧椖側憡娭偑偁傞偑丄C宆偺応崌偼偦偺傛 偆側娭楢偼側偄丅偟偨偑偭偰丄宱夁娤嶡偺偨傔 偵HCV検傪應掕偡傞堄媊偼朢偟偄偑丄僀儞僞 乕僼僃儘儞偱帯椕偡傞応崌偼丄HCV検偺應掕 偑旕忢偵廳梫偵側傞丅偲偄偆偺偼丄偁傞検傪嫬 偵僀儞僞乕僼僃儘儞偺帯椕岠壥偑桳堄偵堘偭偰 偔傞偐傜偱偁傞丅
HCV検偺應掕朄偼偄傠偄傠奐敪偝傟偰偄傞 偑丄尰嵼堦斒恌椕偱梡偄傜傟偰偄傞偺偼DNA 僾儘乕僽朄丄傾儞僾儕僐傾掕検乮僴僀儗儞僕 朄乯偲HCV僐傾峈尨偱偁傞丅偦傟偧傟偵姶搙 偲應掕儗儞僕偑堎側傞丅偙傟傜偺3庬偺曽朄偼 偦偺扨埵偑堎側傞偺偱愱栧奜偺恖偺偨傔偵傢偐 傝傗偡偔夝愢偡傞丅
嵟弶偵奐敪偝傟偨偺偑丄DNA僾儘乕僽朄偱 偁傞丅偦偺扨埵偼Meq/ml乮Mega-equiva-lent/ml乯偱丄1Meq/ml偼1ml拞偵C宆娞墛僂 僀儖僗偑106僐僺乕乮儊僈偼100枩偺堄枴乯偄傞 偙偲傪堄枴偡傞丅HCV検偑1Meq/ml埲忋偺徢 椺偱偼僀儞僞乕僼僃儘儞偺帯椕惉愌偑埆偔丄 1Meq/ml 枹枮偺徢椺偱偼丄挊岠棪偑崅偄丅 DNA僾儘乕僽朄偼掕検惈偵桪傟偨應掕朄偱偁 傞偑丄偦偺應掕尷奅偑105.5僐僺乕/ml偱丄姶搙 偑掅偔丄C宆枬惈娞墛姵幰偺栺30亾偑姶搙埲壓 偲敾掕偝傟傞丅師偵搊応偟偨偺偑丄傾儞僾儕僐 傾掕検朄偱偁傞丅偙偺曽朄偼丄PCR朄傪墳梡偟 偨傕偺偱丄姶搙偼0.5K僐僺乕乮栺300僐僺乕乯 偱偁傝丄僾儘乕僽朄偲斾妑偡傞偲丄偦偺姶搙偼 悢抜桪傟偰偄傞丅傾儞僾儕僐傾朄偺100K僐僺 乕/ml偼僾儘乕僽朄偺1Meq/ml偵憡摉偡傞丅 100K僐僺乕/ml偼105僐僺乕/ml乮K僐僺乕偼 1,000僐僺乕偺堄枴乯偱偁傝丄應掕朄偵傛偭偰 僂僀儖僗検偑堦寘傕堘偆偲偄偆偙偲偵側傞丅偳 偪傜偺専嵏偑僂僀儖僗偺愨懳検傪昞偟偰偄傞偐 偼傛偔敾偭偰偄側偄偑丄恾3偱偼傾儞僾儕僐傾 朄偺應掕検傪尦偵應掕儗儞僕傪斾妑偟偰偄傞丅 傾儞僾儕僐傾朄偺拞偱嵟弶偵弌偨僆儕僕僫儖朄 偼應掕儗儞僕偑嫹偔丄崅僂僀儖僗検偺徢椺傪惓 妋偵掕検偡傞偙偲偑弌棃側偐偭偨丅偦偺屻丄傛 傝崅僂僀儖僗検偺應掕偑壜擻側僴僀儗儞僕朄偵 堏峴偟偰偍傝丄専嵏儊乕僇乕偵埾戸偡傞応崌丄 僴僀儗儞僕朄偱偺寢壥偑曉偭偰偔傞丅偙偙偱懡 彮栤戣偲側傞偺偑丄僴僀儗儞僕朄偺100K僐僺 乕/ml乮幚嵺偵偼KIU/ml偲昞帵偝傟偰偄傞乯 偑僆儕僕僫儖朄偺100K僐僺乕/ml偵昁偢偟傕 堦抳偟側偄偙偲偱偁傞丅戝懱僴僀儗儞僕朄偺 160K僐僺乕/ml偑僆儕僕僫儖朄偺100K僐僺乕 /ml偵憡摉偡傞偲峫偊偰傛偄丅
HCV僐傾峈尨偼擔杮偱奐敪偝傟偨HCV検偺 應掕朄偱丄埲慜偼應掕儗儞僕偑嫹偔丄偁傑傝梡 偄傜傟側偐偭偨丅嵟嬤偵側偭偰姶搙丄應掕儗儞 僕偲傕偵夵椙偝傟丄椪彴偱巊偄傗偡偔側偭偨丅 HCV僐傾峈尨偵傛傞崅椡壙/掅椡壙偺嫬栚偑 1,000fmol/L偱偁傝丄傾儞僾儕僐傾偺1K僐僺乕 /ml偑10fmol/L偵憡摉偡傞偨傔僂僀儖僗検偺夝 庍偑埲慜傛傝傕梕堈偵側偭偨丅HCV僐傾峈尨 偼丄曐尟揰悢偑傾儞僾儕僐傾偺栺1/3偱偁傝丄姵幰偺晧扴傕傛傝寉尭偱偒傞偲偄偆棙揰傕偁傞丅
恾4偵柍徢忬偺GPT堎忢幰傪尒偮偗偨応崌偺 娪暿偺恑傔曽偵偮偄偰娙扨偵婰嵹偟偨丅
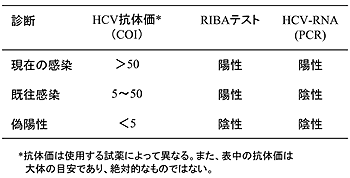
昞3丏HCV峈懱梲惈幰偺娪暿
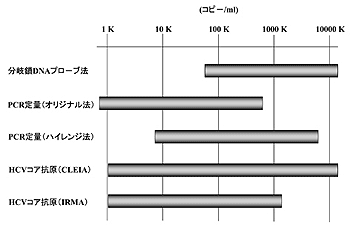
恾3丏奺庬偺HCV掕検朄偲偦偺應掕儗儞僕
HCV僐傾峈尨偼姶搙丄應掕儗儞僕偲傕偵桪傟偨専嵏朄偱偁傞丅
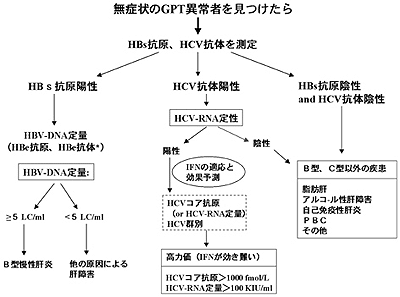
恾4丏柍徢忬偺GPT堎忢幰偺娪暿恌抐
HBe峈尨丄峈懱偺應掕寢壥偼帯椕曽恓偺寛掕偺嵺偵嶲峫偵
IFN丄丗僀儞僞乕僼僃儘儞
傑偲傔
媫惈偲枬惈偵暘偗偰娞墛偺恌抐偵偍偗傞僂僀 儖僗儅乕僇乕偺桳梡惈偲椪彴揑堄媊偵偮偄偰弎 傋偨丅僂僀儖僗惈媫惈娞墛偺娪暿偺偨傔偵偼 IgM-HA峈懱丄IgM-HBc峈懱丄HCV-RNA掕惈 偺3偮偺専嵏偑廳梫偱偁傝丄偙傟偵HBs峈尨偲 HCV峈懱傪娷傔偨5崁栚偺専嵏偱廫暘偱偁傞丅 堦曽丄枬惈偺幘姵偺応崌偼丄HBs峈尨偲HCV 峈懱偱僗僋儕乕僯儞僌傪峴偄丅偙傟傜偑梲惈偱 偁傟偽丄僂僀儖僗検傪應掕偟丄昦懺偺昡壙傗帯 椕揔墳偺敾掕傪峴偆丅
僂僀儖僗惈媫惈娞墛偼堦斒偵梊屻椙岲側幘姵 偱偁傞偑丄帪偵廳徢壔偟丄巰偵帄傞偙偲傕偁 傞丅傑偨丄枬惈娞墛偼抦傜偢抦傜偢偺偆偪偵娞 峝曄傗娞娻偵恑峴偟丄庤抶傟偵側傞偙偲傕偁 傞丅偟偨偑偭偰丄僂僀儖僗惈偺娞幘姵偑媈傢傟 偨傜丄愱栧堛偵憡択偟丄揑妋側恌抐偺尦偵帯椕 曽恓傪寛掕偡傋偒偲巚傢傟傞丅
嶲峫暥專
1乯嵅媣愳丂淎丄懠丗D宆丄E宆娞墛丅擔撪夛帍93丗2351-2356
2乯Sakugawa H, et al 丗 Correlation between serum
transaminase activity and virus load among patients
with chronic liver disease type B, Hepatol Res, 21丗 159-
168, 2001
挊丂幰丂徯丂夘

僴乕僩儔僀僼昦堾撪壢丂嵅媣愳丂淎
惗擭寧擔丗徍榓30擭11寧12擔
弌恎抧丗撨攅巗
弌恎戝妛丗怴妰戝妛堛妛晹 徍榓56擭懖
棯丂楌
徍榓56擭丂棶媴戝妛戞堦撪壢擖嬊
徍榓60擭丂摨忋丂彆庤
暯惉尦擭丂棶媴戝妛堛妛晹晬懏昦堾桝寣晹島巘
暯惉18擭丂僴乕僩儔僀僼昦堾
愱峌丒恌椕椞堟丗徚壔婍撪壢丄娞憻
偦偺懠丒庯枴摍丂庯枴丗撉彂丄嫞攏
Q U E S T I O N 両
師偺栤戣偵懳偟丄僴僈僉乮杮姫枛捲偠乯偱偛夞摎偄偨偩偄偨曽偵丄擔堛惗奤嫵堢島嵗 5 扨埵傪晅梌偄偨偟傑偡丅
栤戣丗娞墛僂僀儖僗儅乕僇乕偵偮偒惓偟偄偺偼偳傟偐丄1偮慖傋丅
a丏HCV峈懱偼C宆娞墛僂僀儖僗偺姶愼杊屼峈懱偱偁傞丅
b丏HBs峈懱梲惈偱偁傟偽B宆娞墛僂僀儖僗偑懚嵼偡傞偲峫偊偰傛偄丅
c丏HA峈懱偼A宆媫惈娞墛偺恌抐偵桳梡偱偁傞丅
d丏HBV-DNA検偑105僐僺乕/ml埲壓偱偁傟偽堦斒偵娞墛偼惗偠偵偔偄丅
e丏HBe峈懱偑梲惈側傜B宆娞墛僂僀儖僗偑憹怋偡傞偙偲偼側偄丅